旅籠屋日記アーカイブ
- diary archive -
旅籠屋日記アーカイブ
- 2021.09.17 最後の日記
-
7月29日に公表した通り、本日午後に開催される定時株主総会をもって、私は取締役を退任し、完全に会社から離れます。
日本にもアメリカのMOTELのような宿泊施設を展開し、自由で自立した旅を提案するとともに、新しい働き方を実現しようと思い立ってから30年近くが過ぎました。
志を曲げることなく、思い描いた夢の一部を実現できたという達成感があります。
多少は感傷的になるかと案じていましたが、年初に「創業理念」をまとめ直し、ここまでの出来事や思いを「旅籠屋物語」と題した動画に残したこともあり、やりきった感じ、すがすがしい気持ちに包まれています。そして、意欲あふれる後継者に恵まれたことは、何よりの幸運でした。
少ない貯金をはたいて、房総に中古の一戸建てを破格値で購入したので、明日からは晴耕雨読の生活、老母を支えながら愛犬たちとのんびり穏やかに暮らしたいと考えています。
コロナ禍で会社がたいへんな時期に会社を離れることについて、「無責任ではないか」との批判を受けました。
リタイアは何年も前から考えていたことで、自分に鞭打ちながら会社を支えてきた自負があるので、その批判は甚だ心外です。
コロナの影響など一時的なものです。私が退いても確実に業績は回復し、その後安定して継続発展していく事業だと確信しているからこその決断です。
また、それなりの役員退職慰労金をいただくことについて、株主の方から「良心を疑う」と叱責されました。
30年近く金銭的な報いを後回しにし人生の大部分を会社につぎ込み、他の人にはわからないストレスを背負ってきたのですから、何の後ろめたさもありません。
平時なら倍額以上であっても良心の痛みなど微塵もありません。世の中に新しい価値を提案し、具体化してきたことを軽く評価されるのは残念です。
とはいえ、これまで、多くの方々や取引先の皆さんの厚情に支えられてきました。間違いなく幸運にも恵まれてきました。
しかし、それは不断の努力と誠実な姿勢を守り抜いてきたからだと、密かに自負しているところです。
私利私欲のために、周囲を利用したり欺いたことなどありません。達成感やすがすがしい気持ちは、その結果です。
そして、最大の幸運は、この30年間、まがりなりにも平和な時代が続いたということです。
コロナ禍による行動自粛は人生自粛だと嘆いている人がいました。同感です。
感染防止に努めながらも、ひとりひとりが自由に旅し、生きて行くことが大切にされることを心から願っています。
ただし、わがままで短気な性格のせいで、周囲の人たちに向かって声を荒げたことが数多くありました。一生懸命だったからという言い訳もありますが、傷つけてしまったことは間違いありません。今更ですが、この場を借りて、お詫びします。ごめんなさい。
去年と同様、株主総会は平穏無事には終わらないかもしれません。可能な範囲で誠実に対応したいと考えています。
それでは、いよいよ最後。
お付き合いいただいたすべての皆さんに心からお礼申し上げます。
皆さんが健康で心豊かな生活を送られることを心から祈ります。
どうぞ、これからも旅籠屋をよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。そして、さようなら。
間違いなく 充実した仕事人生でした。
- 2021.07.28 臆病な日本人
-
6月末が決算日の旅籠屋は、決算作業の真っ最中。
今月に入って監査法人による会計監査が始まり、今日ようやくほぼ終了した。
前期は最後の4ヶ月ほどがコロナ禍の影響を受け11期ぶりの赤字になってしまったが、今期は通年なので赤字の大幅拡大は避けられない見通しだ。
前々期は年間稼働率が初めて70%を超え、売上高も黒字額も過去最高だったので、あまりの落差に落胆は大きい。
しかし、こんな1年間においても稼働率が50%を超えたことに勇気づけられる。だから売上高はピークだった前々期の3/4ほどをキープしているのだが、固定費の比率が高いビジネスなので利益額は大幅に下振れしてしまう。
売上高に比べ固定的な人件費と店舗オーナーに支払う地代家賃がそれぞれ4割、つまり全体の8割以上を占めているのでこういう結果になってしまう。宿泊業全般に共通する特徴である。
そのため人員削減を含め給与の引き下げや家賃の減免を行う同業者が少なくないようだが、当社は検討すらしてこなかった。何より大切にしてきた信頼関係は守らなければならない。
常々500年も1000年も続ける価値のある事業だと言ってきたが、だとすればいずれ収束するに違いないコロナ禍に惑わされるべきではない。明治維新や関東大震災や太平洋戦争の災禍に比べてみればよい。
金融機関に求められたこともあって向こう3年間の事業計画書を作成したが、コロナ禍の影響は来年2022年いっぱい続くと予想した。それでも再来期には、売上高・利益とも過去最高となる可能性がある。
それにしても、新型コロナウィルスを恐れ委縮してしまっている日本人のなんと多いことか。テレビや新聞などマスメディアは1年以上も恐怖を煽り続けている。
いきなり個人的な話しになってしまうが、先日ランニングのために何年も通っているスポーツジムから警告書が送られてきた。マスクの着用ルールに従わなかったからだ。運営会社の考え方もスタッフの立場も理解できるから、何も反論せず退会手続きを行った。
端的に言うが、陽性者が日本よりはるかに多いイギリスにおいて、ワクチン接種が進み重症者や死亡者が大幅に減少していることを理由に規制解除に踏み切ったジョンソン首相の決断に私は拍手を送っている。
こういうことを書くと批判が殺到しかねないが、いずれコロナ禍は収束し、しばしの沈黙の後、世論は反転するに違いない。毎日毎日「感染者数」を数えて一喜一憂していたあの時の騒ぎは何だったのか、季節性のインフルエンザと大差なかったのではないかとワイドショーのコメンテーターは言い始めるだろう。
こういう時には国民性や個人の価値観の違いが顕著に見えてくる。個人と社会の関係、リスクのとらえ方。
同調圧力を感じながら、議論を避けて表面的な平穏を求める、心の中の違和感に蓋をして考えることをやめてしまう。
そんな人が多いのが日本人の特徴のように思う。
話しは飛躍するが、社内で指示を出す時「してもらえませんか?」という疑問形で話すのはやめるべきだ、と昔から何度も何度も注意してきた。それは、印象は柔らかくなるが相手に判断を委ねることで、こちらの意図や立場を曖昧にしてしまう。
テレビを見ていても、「~と思います」という言い方をせず、「とは思います」とか「~し、」でダラダラと話をつなぎ、最後の動詞を鮮明にしない話し方が増える一方だ。
優しい日本人? 曖昧にすることによって表面的なぬるい雰囲気を守り、傷つくことから逃げ、考える手間も省く。
卑怯でずるくないか?
臆病な日本人、自分の中にそういう面があるからこそ、そうなりたくないと自戒してきた。
高校卒業以来50年、私はこれを守り続けてここまで来たのだけれど。
- 2021.05.04 上を向いて歩こう
-
コロナ禍などで右往左往しているうちに、5月になってしまった。気がついたら、なんとこの日記も今年初めてだ。
去年の今頃は「未知の疫病」で世界中が不安になり、SFの世界の言葉のように思っていた「パンデミック」が現実のものになり、あれこれ考えることによって努めて冷静になろうとしていた。
会社の業績は、3月から4月(第1波)、7月から9月(第1波)、12月から1月(第1波)、
そして4月からの第4波と何度も重いパンチを受け、消耗戦で苦しみ続けている。
前期は11年ぶりの赤字、今期も赤字でとうとう債務超過が現実のものになってしまったが、借入のうち数億円は資本とみなされる劣後ローンなので、資金調達は安泰である。長年蓄積した信用と将来性が評価されたのだと思う。
ある銀行からは、「リーマンショックや東日本大震災を乗り越えて堅実に事業を継続してきた旅籠屋さんのような企業はしっかり支える方針です」というありがたい言葉をいただいている。
旅籠屋は500年も1000年も続けられる、そしてそれだけの価値のある事業だと信じている。
これからも、大災害や戦争やパンデミックなどの災禍に直面することがあるに違いない。
うろたえず、長期的な志を失わず、平常心で歩んでいけば良いのだ。これくらいの逆境は、過去何度もあったし、これからも繰り返されることだ。
それにつけても、ついこの間まで企業の内部留保が批判されていたけれど、まったく聞かれなくなった。
資金繰りに不安がなく、将来性が豊かでも、貸借対照表上の数字で金融機関の姿勢が違ってくるのだから、今後は繰越利益剰余金を厚くしておくしかない。コロナ禍の教訓のひとつはこの点だろう。
さぁ、上を向いて歩こう。前を向いて、未来に向けて進んでいこう。
個人的なことだが、来週末はバイクでのキャンプツーリング。野宿したことはあるが、ソロテントでの野営は初めて。
さんざん迷って購入したのは、こちら 。
とっても楽しみ!
- 2020.12.29 仕事納め
-
きのうは、2020年の仕事納め。
年末年始に待望の本社スタッフが増えるため、朝から机移動、席替え、荷物移動とてんやわんや。
コロナ禍を含め最悪の年だったので、これで厄払い、人心一新となるかどうか。
一夜明けて、今日は休みの初日。 でも、何人かは出勤して仕事をしている。
店舗運営管理部長は、年末年始、自ら店舗の除雪応援に出かけるとのこと。
もちろん、店舗の支配人は休み無しで、応援を引き受けてくれる代行支配人も複数いる。
こうして、年中無休で宿を支えているのに、GoToトラベル停止によって稼働率は半分以下。
もったいない、悔しい。
何十年も、何百年(!)も続けていれば、こんな時もある。腐らずに、平常心でやり続けていくしかない。
さて、仕事を離れ、個人的な今年1年を振り返ってみる。
いろんな事があって、なんだか遠い昔のような気がするが、2月に念願の「ナイル川クルーズ」に出かけたことが一番の楽しい思い出。
コロナ騒ぎの直前だったので、ほんとうに幸運だった。
あと、おそらく一生忘れられないのは、7年ぶりに年間1,000km走りきったこと。
日常的に走り始めたのは2008年の後半からで、毎月100km以上、 フルマラソンも10回以上完走した。
でも、いろんなことがあって、7年前からは月間50kmに目標を下げて無理しないことにした。
なのに 、おととし結果的に年間900kmを超えて欲が出て、もう一度だけ年間1,000kmを走ってみようと考えるようになった。
ところが、昨年は950kmにとどまり、今年こそは、と年初に心に誓った。
その矢先1月に捻挫してしまい、1ヶ月近く走れなかったので、ここまで来るのはほんとうに大変だった。
前から何度も書いている通り、走りたいと思ったことなど1回もない。
寒い日、暑い日、仕事で心身ともに疲れ切った夜、だらだらしたい休日に、葛藤に打ち勝って走りに出る。
それを1年間続ける。
一緒に付き合ってくれる社内のラン友の存在がなければ、絶対に出来なかった。
もちろんお互い様だけど、ほんとうありがとう。
最後は、土曜の午後に皇居のまわりを2周してジャスト1,000km!
珍しく飲んだ乾杯のビールが、じんわりとおいしかった。
そんなラン友に誘われて、今年は30年ぶりくらいにキャンプに行くようになった。
楽しかった。薪が燃える火を見ていると心が落ち着く。
来年も時々行きたい!

もうひとつ、私の心を支えてくれたのは、愛犬たちの存在。
年明けには6歳になるが、いつまでも元気でいてほしいと心の底から祈ってしまう。

そして、最後は、相変わらず乗っているバイク。
思い切って、3年ぶりにサーキットを走った。
不思議なもので、走り出すと、心も体も熱くなってきて楽しくなる。
来年は、もっとたくさん走ろう!

というわけで8月、9月に発売される話題の車を予約してしまった。
久々の250ccの4気筒バイク。
人気が高く、何か月も納車待ちだったが、なんと大晦日12月31日に受け取れることになった。
考えてみたら、そろそろ免許返納の時期も考え始めなければならない歳だが数少ない「好きなこと」だし、この気持ちが燃え残っている間は、心を温めてもらおうと思う。

あと3日で元日、数えで70歳。古稀だ。
仕事では、自分にしかできないこと、やっておかなきゃならないことを、鞭打ってやり遂げる。
プライベートでは、熱があるうちに、やり残したことに飛び込んでいきたいと思う。
まだまだ、人生はこれからだ!
来年も、よろしくお付き合いください。
- 2020.11.20 コロナパニックに惑わされず、平常心で、営業中です
-
11月も下旬に入った。
10月は 売上が前年比90%以上まで戻り、順調に回復していたが、今月は第3波が騒がれ始めて予約に急ブレーキがかかってしまい、頭打ちになってしまった。悩ましい。
ところで、今年も 「月刊 ホテル旅館」(柴田書店発行)の1月号に寄稿させていただく機会をいただいた。その原稿を以下に転記します。
年頭所感 「2021年の展望と課題」 コロナ禍を生き残る施策とポストコロナを見据えた施策
当社は6月が期末のため、コロナ禍は前期決算に大きな影響を与えました。売上は創業から25年目にして初の前年割れ、11期ぶりの赤字に終わりました。
3月から業績悪化が顕著になってキャンセルが殺到しゴールデンウィークは壊滅的でした。先行きの資金繰りに不安を感じ、借入れを増やしたのはこの頃です。
4月に緊急事態宣言が発出されてからは移動自粛ムードが強まり、役所から休業要請を受けたり、近隣から「営業を停止すべきだ」という抗議の電話を受ける店舗も複数ありました。
支配人も感染リスクを恐れ不安を感じていたに違いないのですが、「休業はしない、感染が明らかでない限りすべての方を受け入れる」という指示を出し、通常営業を続けてきました。宿泊者ゼロが続いている店舗の場合、休業して「雇用調整助成金」の支給を受けた方が得、という判断もありえたのですが、「車社会のインフラ施設」を自認し、誰もが気軽に泊まれることを大切にしてきたのですから、営業を続けることが使命だと考えたわけです。風評に惑わされず、他の施設で敬遠されるような方々もけっして差別しないというポリシーが試されることになりました。
自宅に帰ることが難しくなっていた病院関係者を数多く受け入れ、明らかに自主隔離で泊まられる方も拒みませんでした。テレワークの需要に応え、デイユースもスタートさせました。
その後、第1波がおさまり6月には予約が戻り始めましたが、7月に入って第2波が騒がれるようになり夏休みも取り返しのつかない状況に終わりました。
そんな中で、7月22日から「GoToトラベル」キャンペーンが始まりました。料金が安いため、効果は限定的だと予想されましたが、参加しない選択肢はありませんでした。その結果、この数か月間、対応に膨大な手間を強いられ、振り回されています。現場を知らない官邸主導で強引にスタートした緊急対策ですから朝令暮改は当たり前、事務局に問い合わせても要領を得ず、割引を期待して予約されるお客さまとの間でストレスばかりが増えていきます。予約商売のため、早めに制度の詳細が決まらないために混乱が生じるのです。加えて、10月からは「地域共通クーポン」の配布も義務付けられ、数日前になっても券が届かないなど、綱渡りの状況がピークに達しました。
当社の場合、直予約が多いため、今も先々の予算枠が決まらないことで気をもんでいます。割引分の入金は先になるため、資金繰りの面でも不都合が生じます。これは予約サイト企業を優遇して中小の宿泊施設を淘汰し、キャッシュレスを促進するという隠れた意図があるのではないかとも感じています。利用者をさもしくし、旅の価値を変質させている、これは行うべきではなかったというのが個人の感想です。
9月からは回復基調となり、10月にはようやくほぼ例年の9割前後まで戻ってきましたが、第3波の不安が広がって先行きは不透明なままです。
冷静にデータを見ると、新型コロナによる死亡者は例年のインフルエンザを下回っています。しかも、60歳以下の死亡率はほぼゼロのようです。検査の陽性者を感染者と呼び、不安心理を掻き立てる。これこそ、恐怖心に駆られたパニックというべき状況ではないでしょうか。
数年後、あの騒ぎは何だったのだろう、という日が来るかもしれません。その日が一日も早く訪れることを祈ります。
リーマンショックや東日本大震災の時と同様、「ファミリーロッジ旅籠屋」は平常心で営業を続けます。移動する自由を支え続ける、宿泊業の価値は目先の損得ではなく、世の中の圧力に同調することでもなく、もっと根源的なものだと信じているからです。
- 2020.09.22 名誉棄損
-
先週の金曜日は、年に一度の定時株主総会だった。
コロナ禍で、どれくらいの方にご参加いただけるかと案じていたが、
例年通り、一般株主も10名近く、業績悪化に対する厳しい質問もあり、1時間以上の長時間総会となった。
もともとシャンシャン総会を良しとしているわけではないから、何時間かかっても問題ない。
過去、貴重な提案をいただいたこともあり、こうした緊張感を与えられることは、経営者に必要なことだ。
ただ、残念だったのは、ある株主から、私からすると、言いがかりのような不信感をぶつけられたことだ。
彼の主張の要点は、以下のようなことだった。
1.業績の急激な悪化により、数か月後には債務超過(負債が資産より大きくなる)になり、金融機関の奴隷のようになってしまう。
2.今回の業績悪化は、それ以前の放漫経営のつけであり、これは社長の経営のやり方に根本的な原因がある。
3.放漫経営の例としては、以下のようなことがある。
① 初期に比べ、新店舗の家賃が大きく上がっており、その支払いが収益性を損ねている。
その原因は、社長と常務だけで勘に頼って決めている、社長が大和ハウスのおべんちゃらに乗せられていること等である
② 経費の付け替えなどの粉飾決算を行っていた。
③ 私が様々な提案を行っても、不機嫌そうな顔をするばかりで、採用しようとしなかった。
そう、この株主は3年前まで、本社スタッフだった人間だ。
在職期間は約5年半。入社時は、すぐにでも役員になってもらい、次代を担ってほしいと期待した人だった。
その彼が今、「私は、会社の内情を知っている人間ですから、株主の皆さんはだまされてはいけません」と、
出席者に対し、同調を求めている。社外の株主には説得力があるに違いない。
そして、最後に、私に次のふたつの選択を提案してきた。
A. 過去の誤りを認め、即時退任する。そうすれば、新しい経営者のもとで、良い会社になる。
B. このまま職にとどまれば、株主代表訴訟により、個人財産のすべてを失うことになる。
15分くらいだったろうか、彼の演説が終わるまで、黙って聞いていたが、
主張の1については、理解できなかったので、銀行出身である監査役にその場で尋ねてみた。
監査役の答えは「たとえ債務超過の状態に陥っても即座に返済を求められることはなく、隷属することにはならない」だった。
私の理解もまったく同じだ。まったく心配していない。業績の回復に時間がかかることは、みんな承知の上のことだ。
主張3の中の粉飾決算という指摘については聞き捨てならないことで、思い当たることがないので、具体例を挙げるよう求めたが、明確な回答は得られなかった。
間違いなく彼は株主代表訴訟とやらを起こすだろうから、裁判所でひとつひとつ反論していけば良い。
しかし、自他ともに誇ってきた「公正で、隠し事をもたない透明な経営」を、このように否定されたことは、何より腹立たしく怒りを感じた。
総会には、当社を担当する監査法人や税理士法人の方も同席していたが、やましいことは何もないので、かえって好都合だ。
今気づいたことなのだが、本社には密室となっている「会議室」というものがない。
打合せテーブルは1階と3階にあるのだが、どちらにもスタッフの机があり、人払いすることはない。
無防備というか、非常識と言われるかもしれないが、隠し事があるように思われることすらイヤなのだ。
過去26年間の私の経営が、放漫経営だったのかどうか。
私は、まったくそうではなかったと自負しているのだが、考え方の違いにより、賛同する人もいるのだろう。
例えば、
・「誰もが気軽に利用できる宿を全国に整備する」という創業理念にもとづき、高い収益の見込めない地域に出店することもある。
・同様に、たとえ収益性が低い店舗でも、安易に撤退せず、営業を継続していく。
・今回のコロナ禍のように急激な業績の悪化があっても、信用を重視し、可能な限りオーナーに対して家賃の減額を求めない。
・学歴職歴などに恵まれない多様な方たちを雇用し、リスクを引き受けながら、その生活を守るため、休業も減給も行わない。
こうしたやり方を放漫経営というのだろうか。でも、これは経営方針の問題であり、会社の理念の問題である。
社員の意見を経営者が採用しなかったからといって、それを放漫経営と決めつけられても困る。
余談だが、私は、取引先からの中元歳暮の類は一切受け取っていない。
「儀礼はやめましょう」と常々お願いしているが それでも会社に届くわずかな品々は本社スタッフ全員で、じゃんけんして分配している。
同様に、取引先との飲食は、「各自の自腹で」と強くお願いしている。
逆に、こちらから儀礼の品を送ることはないし、年賀状も出していない。
とにかく、私利私欲につながる、あるいはそのように見られる役得は厳しく排除しよう、というのが、私の強い思いである。
これは、毎年、大量に届く中元歳暮に対し、ひとつひとつ同額の返礼を送り続けていた父の姿勢と、
かつて勤務した住宅メーカーで体験した苦い記憶があるからだ。
小さな接待や貸し借りがしがらみを生み、癒着となり、社内外の信頼関係を損ね、公正な判断を難しくしていくからだ。
あらためて説明する機会はほとんどないのだが、社会経験の乏しい若い社員には伝わっているだろうか。
私が、大和ハウスの方たちのおべんちゃらに乗せられて、高い家賃を受け入れている?笑うしかない。
このように見られていたなんて、びっくりしてしまった。
デリケートな面があるので、あまり触れられないことだが、
会社の経営者にとっての一番のストレスは、自分の思いを曲解し、妨げようとする一部の社員との関係ではないかと思う。
これは、信じている目的の方向に皆を引っ張っていこうとするリーダーなら避けて通れない永遠の悩みなのだと思う。
サラリーマン経営者であれば、出来上がった組織に「処理」を任せて他人事にするだろう。
皆を引っ張っていく気持ちを持たない管理者なら、「変わった人だね」と、笑って放置するだろう。
突き付けられたふたつの選択肢、もちろん私は、ここで退任するつもりはないと即座に答えた。
基本、今までの方針を変えるべきだとも考えていない。
何度も言ってきたとおり、26年前、私は個人の利益や名声に憧れてこの会社を起ち上げたわけではない。
もし、そうなら、まったく割に合わない26年間だった。
メディアに対しても、こちらから自分を売り込むことなど、性に合わないことだ。
年々つもっていくストレスから解放され、気ままに余生を楽しみたい。これが正直な願いである。
こんな、社長にあるまじきつぶやきを聞いた人は少なくないはずだ。
だから、私利私欲のために、今の立場にしがみつきたいなんて、まったく思っていない。
ただ、ずっと願い、わずかでも実現してきたと自負している「社会的企業」としての「旅籠屋」の灯を、
消えることなく、揺らぐことなく、次代に引き継いでいきたい、その思いだけで、自分に鞭を打っているだけだ。
信じてくれている人も、たくさんいると思うのだが、裸の王様になっているのなら、いつでも放り出します。
- 2020.09.16 事実
-
猛暑の夏休みが終わり、ようやく過ごしやすくなってきたが、コロナ禍の影響はだらだらと続いている。
1か月前に書いたとおり、5月後半からの回復傾向が、陽性者数の再増加や自粛ムードによって急ブレーキがかかり、
最大の稼ぎ時である8月も、7月以上に低迷してしまった。
10日ほど前、国立感染症研究所が致死率を改めて推計した結果が発表されていた。
全年齢 50歳未満 70歳以上
第1波(1/16〜5月)の致死率 5.8% 0.2% 24.5%
第2波(6月〜8/19)の致死率 0.9% 0.0% 8.7%
第1波と第2波を比べると、検査拡大で無症状や軽症の陽性者が多く報告されたことや治療法の改善が指摘されている。
それにしても、PCR検査で陽性と判定された50歳未満の人たちの致死率は0.0%(ゼロではなく、0.05%未満ということでしょう)。
これが、事実です。
この自粛ムードは、冷静な判断を離れたコロナパニックだと言えるのではないでしょうか。
- 2020.08.14 ディストピア
-
監査法人による会計監査や税理士法人による税金計算が終わり、昨夕、決算速報をリリースした。
3月決算の企業と異なり、コロナパニックの影響を4ヶ月以上受けたこともあり、2億円近くの赤字決算になってしまった。
固定費の高い商売なので、売上の上下が利益の増減を大きく左右してしまう。
赤字になるのは11期ぶり、売上が前年を下回るのは創業以来初めてのことである。
こうした決算は致し方がないとして、悩ましいのは5月後半からの回復傾向が、陽性者数の再増加や自粛ムードによって
再びブレーキがかかってきたことである。
7月の売上は前年同月の62%にとどまり、8月も同程度になりそうだ。
一番の稼ぎ時である夏休みの低迷はつらい。
9月以降の行楽シーズンに向けて、自粛ムードが鎮まり、旅行需要が大きく回復していくことを祈るばかりである。
それにしても、世の中の異様な雰囲気は、どうしたことか。
電車の中はともかく、街を歩くほぼすべての人がマスクをしている。
まるで、以前どこかで観た未来のディストピア世界を描いたSF映画のようである。
皆が表情を隠し、他人を警戒し、同調しない者を探し出してにらみつけようとしているようだ。
あー恐ろしい、不気味で怖くなる。
私個人は、電車や人ごみの中以外はノーマスクである。
先日、いつも通っているスポーツジムで走っていたら、珍しく出勤していたスタッフにマスクの着用を求められた。
フロアに居たのは私一人だったし、マシンは1台ずつシートでさえぎられているし、何よりマスクしながら走りたくない。
その日は たまたま持参していなかったので、そのように訴えたが、結果として追い出されてしまった。
ジムでクラスターが発生したニュースは知っているし、企業防衛上もスタッフはそのような対応を強く指示されているのだろう。
理由も立場もよくわかる。 されど、怒りがおさまらない。
まるで、書類の不備だけで冷たくはねつけられたり、外見だけで排除されるような感じ、本能がこれは違うと叫んでいる。
あー息苦しい。
こんなことを書くと、「それはあなたのわがまま、みんな我慢しているのだから」という「もっともらしい正論」が聞こえてくる。
感染拡大を抑えることによってかけがえのない命を守る、もちろんその目的はわかっている。
しかし、ウィルス曝露者数>PCR検査陽性者数>感染者数>発症者数><要入院治療者数>死亡者数、と分解して考えれば、
事態は明らかにPCR検査陽性者数ばかりにおびえて集団パニック状態に陥り、「正しく恐れる」とは到底言えないと思う。
はっきり言って、騒ぎ過ぎ、おそるるに足らず、と私は考えている。
それにしても、みんなはこういう状況に違和感や怒りや不気味さを感じないのだろうか。
それとも、すっかり慣れてしまっているのだろうか。
リスクを怖れ、無難に逃げ込み、同調圧力に結果として加担する。
こういう感性や行動パターンが、さまざまな差別や争いや不公正を生んできたと感じたりしないのか。
当社は、ひとりひとりの自由を大切にするために、多様性を尊重することを重要なポリシーとしている。
パンフレットにもこう書いている。
「いろいろな個性や違いを受け入れ、少しずつ寛容になることが自由を支えているのだ」。
決算の話しに戻る。
驚かれる人も多いと思うが、当社の役員報酬は、私を含め年間1000万円に届かない。
あとは利益連動の役員賞与や配当金が加算されるわけだが、今年は両方ともゼロ。
収入が1/3以上も減ってしまうのだから、正直言ってつらい。
楽しみにしていたクルーズも中止、海外旅行にもいけない。
気持ちの支えは、普段のまま何も変わらない愛犬たちと、購入予約したこのバイクだ。
数か月先になるらしいけれど、早く乗りたい。

- 2020.06.02 たどり着いた結論
-
6月に入った。
数か月で 約10億円の資金調達を果たし、平常心で事業を継続できる基本が確保できた。
先が見えなかった利用者の減少もGW頃に底を打ち、回復傾向が明らかになってきた。
壊滅的な影響を受けている宿泊業界で、すぐれて堅実な状況にあると言えると思う。
とりあえずは一安心である。
創業から25年、バブル崩壊や リーマンショックや東日本大震災など、大きな災禍をしのいできたが、今回もしぶとく乗り越えられそうな気がしてきている。
500年、1000年企業を目指しているのだから、この程度の逆風で吹き飛ばされるわけにはいかない。
そのためにも、ピンチはチャンス。
絶好の成長機会として活かしていこうと、業務の見直しに取り掛かっている。
さて、先日来考え続けているコロナの問題。
先日もあるテレビ番組を見て、なんとなく腑に落ちる考えにたどり着くことができた。
そのきっかけは、日本人の哲学者が紹介していたドイツのメルケル首相の3月18日のテレビ演説で語られた以下の言葉だ。
日常生活における制約は、
渡航や移動の自由が苦難の末に勝ち取られてきた権利であるという経験をしてきた私のような人間にとり、
絶対的な必要性がなければ正当化し得えないものなのです。
民主主義においては決して安易に決めてはならず、決められるのであればあくまで一時的なものにとどめるべきです。
しかし、今は命を救うためには避けられないことなのです。
言うまでもなく 、この言葉の背景には東ドイツで生まれ育った彼女の切実な経験と歴史認識がある。
そして 、そこから導き出された人間の営みの根本についての哲学がある。
ドイツの人々はうらやましいなと思った。日本のリーダーにもこうした「哲学」を語ってほしいと思った。
間違いなく私の感性や考え方の根底には「個人の自由を大切にしたい、するべきだ」という強い思いがある。
「自由」といってもいろいろある。
日本国憲法の中だけでも、思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、集会の自由、結社の自由、表現の自由など
さまざまな「自由」が明記されている。
ただ、こうした自由の中でも、もっとも基本的で重要なものが「移動の自由」だ、と私も思う。
再び日本国憲法に戻れば、それは居住移動の自由、外国移住の自由、国籍離脱の自由などを含む。
以前にも紹介したが、旅籠屋の「総合ガイド」の冒頭に「気兼ねなく、好きな時に、好きな所に行ける自由」のことを掲げている。
つまり、宿泊施設、少なくとも「ファミリーロッジ旅籠屋」がもっとも大切にすべきことは、その自由を守ることだという信念がある。
そのために、分け隔てなく気軽に泊まれる、すなわち多様性を受け入れるというポリシーがある。
抽象的なきれいごとではない。
ファミリー・カップル・ビジネス・ペット連れなど目的や構成の違い、
年齢・性別・人種、身なりなどの外見や身体的な違い、
言語や文化的習慣などコミュニケーションに関わる違い、
非常識でわがままなクレーマーを含め、性格や考え方の違い、
いわゆる障害と呼ばれる差異を含むすべてに関わる多様性。
いずれも、予断・偏見・先入観にとらわれず多様性を受け入れるということは、それなりのリスクを引き受ける覚悟を持つということだ。
ひるがえって、今回の外出自粛要請。
新型コロナウィルス感染の恐怖が強調されるが、少なくとも日本における感染状況を見る限り、
絶対的な必要性があるとは、到底思えない。
命か経済かではなく、感染拡大のリスクを抑えるために人間社会の根本を支える「移動の自由」を制限すべきかどうかという問題ではないか。
ゼロリスクを求めるのなら、そもそもインフラを支えるサービス業など成立しない。
戦争中にも行われなかったほどの移動制限を行う必要性を、この数か月の状況の中で、私は認めることができない。
そんな風潮や風評に流されることこそ、いさめるべきことだという反骨心が湧いてくる。
「自粛警察」の感情的糾弾を甘受し、「ファミリーロッジ旅籠屋」は平常通り営業を続ける。
他県ナンバーだからと石を投げられる人にも宿を提供し続ける。
そのリスクをとりたくないのなら、病院や交通機関や宿泊施設で働く人々は転職を考えるべきだ。
職業選択の自由は、もちろんある。
- 2020.05.12 示唆に富む言葉たち
-
嫌いなのに、半ば義務感で何十年も目を通し続けている朝日新聞、毎日毎日30分近くを費やしているので膨大な時間をとられているわけですが、
新型コロナに関する以下のようなインタビュー記事に出会うと嬉しくなります。
〈社会を覆う「正しさ」〉(5月8日、磯野 真穂さん)、〈私の人生、不要不急?〉(5月12日、養老 孟司さん)。
とても示唆に富んだ内容なのでぜひ一読いただきたいのですが、有料記事なのであえて要約させていただくと、およそ次のようなことが述べられています。
医療人類学者の磯野さんは、ゼロリスクを目指す「道徳的な正しさ」は、遠くの人にはエールを送りながら近くの人を排除する矛盾を生んでおり、
同時に 「安全な人や集団」と「危険な人や集団」を分ける「村八分」を招いていることを指摘し、リスクとの寛容な付き合い方を提言されています。
解剖学者の養老さんは、感染拡大抑止のなかで、「不要不急」かどうかということが判断基準として言われているが、人生は本来、不要不急ではないのか。
ヒトとウィルスは共生していくしかないことを含め、要は各人の問題であり一元的な価値基準で善悪が断じられることへの疑問を遠回しに述べられています。
緊急事態宣言が発出されて以降の自粛が功を奏し、ようやく感染拡大の勢いが弱まり、宣言解除や自粛要請の段階的縮小のニュースが増えてきました。
「旅籠屋」 は、手洗いの励行、マスクの着用、換気の徹底、消毒薬の常備、フロントへのスクリーンの設置など
感染防止に努めながら全店営業を継続してきましたが、4月・5月とも売上高は前年に比べて7割減、6月末の決算では、創業25年目にして初めての減収、
11年ぶりの赤字は免れない状況となっています(詳しくは、先日発表した「第3四半期報告書」や「決算短信」をご覧ください)。
休業しないことについては、「こんな時に営業を続けているのはけしからん!」という抗議の電話をいただくこともあったのですが、
その悔しさや迷いや矜持について、旅館経営者からの視点で率直な思いを述べられているエッセイに出会い、勇気づけられたりしました。
〈コロナで揺らぐ、宿泊施設の存在意義〉(4月28日、永山 久徳さん)
「旅籠屋」は、帰宅困難な医療関係者などの宿泊に活用いただいたり、テレワークのためにデイユース利用を受け入れたりして喜ばれているのですが、
事の本質は目先の社会的要請に合致して世の中の役に立っているかどうかではないように思うのです。
そうでなければ、パチンコ店やライブハウスなどの施設や、仕事以外で旅に出る人は自分勝手と責められ一方的に切り捨てられることになります。
新型コロナウィルスのリスクばかりが強調されますが、身の回りに感染症はいくつもありますし、ゼロリスクを言うなら車のような人殺しの道具には乗れないし、
「得体のしれない」他人と共存したり、文化も風習も異なる知らない土地への旅行などすべて排除すべきことになってしまいます。
世の中のムードにあわせていれば無難ですし、被害者としての立場に徹していれば気楽ですが、それは違うだろうという気がしてなりません。
自らの利益だけを考えるわがままを許すつもりは微塵もありませんし、感染拡大抑止に努めることは当然ですが、
そこから先は、一定のリスクを引き受けながら、互いに寛容な姿勢で、通常通りの生活や事業を続けていく、人間の社会はそんなものだと思うのです。
言い換えれば、多様性を受け入れることによってそれぞれの自由を守り通すということです。
もう少し、考えます。
- 2020.05.08 論点整理
-
「ファミリーロッジ旅籠屋」の「総合ガイド」の冒頭に、「旅は、自由。」と題して、以下のような文章を載せています。
気兼ねなく、好きな時に、好きな所に行ける。
当たり前のことのようですが、今世界中で、こんな自由に恵まれた人々がどれだけいるのでしょう。ほんの一部に違いありません。
心と体の健康、ある程度の経済的ゆとり、車社会のインフラ、個人を大切にする平和で安全な社会。
これらの条件がそろわないと得られないことだからです。
50年前はどうだったのでしょう。50年後はどうなるのでしょう。
長い長い歴史の中で、無数の人たちがあこがれ、願い、ようやく手にした夢のような時代と場所に私たちは生きています。
当社では、新入社員研修の中で、必ずこの文章を読み上げながら会社のポリシーを説明します。
しかし、「50年前はどうだったのでしょう。50年後はどうなるのでしょう」という問いかけに対し、つい数か月前までは「?」という反応が通常でした。
今あるものは昔から当たり前にあり、これからも続いていくはずだ、そのように考えてしまう人が多いのです。
過去を振り返ってみても、誰もが気軽に海外旅行に出かけられるようになったのは、つい数十年くらい前からのことなのです。
例えば、査証(ビザ)、つまり入国許可証。
ご存知の通り、本来、他の国へ渡航する際、その国が発行するビザの発給を事前に受けなければなりません。
これを省略してパスポートだけで他国に入国できるのは、ビザ免除の取り決めがなされている場合だけなのです。
私が初めてアメリカに行ったのは1987年12月のことでしたが、その時は、事前にアメリカ領事館にビザ発給の申請を行った記憶があります。
調べてみたら、日本人に対して90日以内の観光や商用旅行についてビザ免除が認められたのは、ちょうど1年後の1998年12月からのことだったようです。
ちなみに、1年ほど前、日本のパスポートが世界一強くなった、つまり、日本がビザなしで最も多くの国(約190か国)へ渡航できる国になった
というニュースが報じられていました。
そして、現在と未来についてです。
数か月前には想像もできなかったことですが、今、世界中の国々が鎖国状態で、原則他の国へ旅行することができなくなっています。
加えて、 国内でも県をまたぐ不要不急な旅行は自粛することが要請されいます。
「50年後」どころか、数か月も経たないうちに「気兼ねなく、好きな時に、好きな所に行ける」自由は失われてしまいました。
この不自由な状況については既視感があります。 1973年の第1次オイルショックの時のことです。
イスラエルとアラブ諸国による第4次中東戦争の影響で原油価格が急騰し、世界中がパニックになりました。
日本ではトイレットペーパーの買い占め騒ぎが有名ですが、それ以外にも以下のような出来事がありました。
- テレビ深夜放送の休止。
- デパートのエスカレーター運転中止。
- 地下鉄照明の間引き。
- ネオンサインの早期消灯。
- 野球のナイターの開始時間の繰り上げ これらは、節電による石油消費量の減少を直接ねらったことですが、あわせて、不要不急な娯楽は控えるべきだというキャンペーンがはられました。
- ガソリンスタンドの日曜日休業。
- 自動車メーカーによるモータースポーツからの撤退。
その結果、起こったのが、以下のようなことです。
当時、大学生であった私は、こういう感情的な同調圧力に強い違和感を感じたことを覚えています。
このような状況がいつまで続いたのか、よく覚えていませんが、オイルショックが与えた影響はきわめて大きく、
経済は戦後初めてのマイナス成長となって高度経済成長が終焉、省エネ意識が高まっていきました。
すでに1960年代から公害問題など経済成長のひずみが顕著になり、「モーレツからビューティフルへ」というテレビCMが話題になったりしていたのですが、
多くの人の意識において楽天的な未来志向が冷め、根底から価値観が変化していったのはこのオイルショックが契機だったように思います。
話しは変わりますが、最近、高齢者がとかく否定的に語られることがあります。
自分たちの目先の利益ばかり考えて問題の解決を先延ばしにしてきた。そのツケを若い世代に背負わせている。
しかし、長く生きてきたことの財産もあります。それは、世の中のさまざまな様子を実際に体験してきたことです。
私は戦後生まれですが、それでも傷痍軍人や防空壕など、戦争の臭いを鮮明に覚えています。
そして、ほんとうに皆が貧しく、生きて行くのに必死だった様子。そのせいもあって公衆道徳に欠け、列を守らず、タバコやゴミを捨てる人が多かったこと。
国産品は粗悪で世界でバカにされていたこと、日本人は粗野で醜悪な「イエローモンキー」だと軽蔑されていたこと。
いっぽう、デモや騒乱が頻発し、先日の香港のような状況もあったこと、けっして政治や社会に無関心な時代ばかりではなかったのです。
中国人観光客の爆買いや東南アジア諸国のエネルギーあふれる様子は、 「エコノミックアニマル」と揶揄されていたかつての日本の姿です。
感染症の流行については、衛生状態がずっと劣悪だったし、情報も限られていたため、今回のコロナ禍ほどの騒ぎは記憶にありませんが、
小児麻痺(ポリオ)は身近でしたし、日本脳炎への警報もよく耳にしました。
あとは、1968年から1969年にかけて流行した香港風邪。調べてみたら、死者は世界で50〜100万人、日本でも2千人を超えたそうです。
未知のウィルスによるパンデミックですから、今回の新型コロナウィルスとまったく同じですが、死亡者は数倍も多かったわけです。
私を含め、 高齢者はこのように様々なことを体験しています。
ですから、新しい出来事に対しても耐性を持っているはずで、パニックにならず、冷静に判断して経験を活かさなければなりません。
若い人以上に感情的になったり、逆に個人的な達観に逃げ込んで無関心を装う人もいるようですが、それではいけません。
こんな時こそ、落ち着いて状況を俯瞰し、知恵を出すべきだと思うのです。
話しが本題から離れてしまいました。
考えなければならないのは、コロナ禍の中で、どう生きていくべきか、何を判断の基準にすべきかということでした。
生命の安全と個人の自由の選択を迫られれば誰でも前者を選ぶ、と誰かが言っていました。
ほんとうにそうでしょうか。
そもそも、こんな二者択一の設問に対して答えを求めることに問題があるように思います。
生きている限り病気や事故のリスクはあるし、社会生活を営む以上完全な個人の自由などというものもありません。
考えるべきことは、以下のことを短期と長期に分けて整理してみることではないかと思います。
1.感染拡大抑制の目的は、医療崩壊の防止なのか、感染者を少なくすることなのか、死亡者を最小限にすることなのか。
2.経済的なダメージを最小化するために最適な方法とは何か。
3.従業員(施設の運営者)と、お客様(宿泊者)の感染リスクはどう異なるのか。
4.会社を存続させ、ダメージを最小化する方法とは何か。
5.そもそも宿泊施設が存在する社会的意義とは何か。
すっかり回り道してしまいましたが、まだまだ考えます。
- 2020.05.06 コロナ対策の基本戦略
-
じつに様々なニュースが飛び交っていますが、私が一番なるほどと思ったのは、感染医の高山義浩さんがfacebookに投稿していたこの分析です。
1番目は、都市封鎖を含めて徹底的に感染を限られた場所や地域に抑え込んで蔓延を防ぐ「封じ込め路線」、
その例として、中国、韓国、台湾、ベトナム、タイ、マレーシア、シンガポール、ニュージーランド、オーストラリア、アイスランド、ハワイ州が挙げられています。
2番目は、感染者が急増して医療崩壊が起きない程度に感染拡大のスピードを抑える「コントロール路線」、
その例として、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、イタリア、日本が挙げられています。
3番目は、集団免疫による終息を信じ、最小限の感染抑制策しかとらずに感染拡大を容認する「拡大許容路線」、
その例は、スウェーデン、ブラジル、(方針変更前の)イギリスとオランダ。そしてアフリカなどの発展途上国もやむを得ずこの路線を採りつつあるようです。
経済活動の抑制、すなわちダメージの大きさで見れば、1番>2番>3番、
予測される死亡者の数で見れば、逆に、3番>2番>1番ということになるようです。
これは、すっかり有名になったジョンズ・ホプキンス大学によるシミュレーションでも示されていました。
もちろん、これら3つの路線=戦略には、以下のような前提条件があります。
ひとつは、感染者の大部分が無症状あるいは軽症で、致命率(致死率)が1.5〜3%以下にとどまること。
エボラ出血熱のように、致死率が50%を超えるような感染症の場合、3番目の路線を採ることは許容されないでしょう。
ふたつ目は、感染者は必ず抗体を持つようになり、その後は一定期間再感染することも、他の人へ感染させることもないだろうということ。
この点が未だ明確になっていないことが問題を複雑にしています。 3番目はもちろん、2番目の路線も、こういう期待を前提にしているのですから。
みっつ目は、いずれ、ワクチンや特効薬が開発されるに違いないと考えられていることです。
この期待が早期に実現しないとすれば、1番目の「封じ込め路線」は、いつまでも規制を緩めたり、鎖国を解くことが出来ず、
感染者が少ないだけに終息にもっとも長い期間を要し、経済的にも狭い範囲の内需に頼るしかなくダメージも大きくなります。
逆に、3番目は医療崩壊を甘受するわけですから際限なく死者が増え続け、社会全体が崩壊してしまうことになります。
PCR検査の数や規制の程度など、断片的な意見や批判が目立ちますが、こうして全体的な戦略を整理して眺めてみると、
医療体制の基礎体力、貿易依存度や内需経済の大きさ、国や自治体などの統治能力、人々の死生観や価値観など、
それぞれの国や地域で対応が異なるのは当然で、答えは一つではないことがわかります。
日本の場合、医療体制は充実しているものの、ICU病床や感染症対応力には脆弱な面があるようです。
経済面でいえば、もちろん貿易依存度は低くないのですが、一定の内需があり、ある程度は鎖国状態に耐えられるのかもしれません。
そうしてみると、2番目の「コントロール路線」を採っていることは、最適な選択だったように思えてきます。
しかし、これも、「集団免疫」の効果が発揮され、ワクチンや特効薬の開発が近い将来実現しないとジリ貧になってしまいます。
もちろん、そうでなければ、1番目の「封じ込め路線」も、3番目の「拡大許容路線」も結果は同じになってしまいます。
このように、現時点では、終息への道筋が見えないため、路線の優劣の判定もできませんし、 政府や自治体からの要請に対する対応も決めにくいのです。
しかし、個人としても、会社としても、今この時の方針を定めないわけにはいきません。
ところで、以上のこととは別の次元の判断基準はないのでしょうか。
その一つが、個人の自由を尊重するかどうかという問題です。
その面で考えると、、3番>2番>1番ということになります。
いきなり、感覚的な話しになりますが、私個人は、ここで紹介されているパリ在住の哲学者の心情に共感を覚えます。
でも、個人的な感覚ではいけません。
さらに考えてみます。
- 2020.05.05 考えるチャンス
-
前回の日記から1か月近くが経った。
4月7日に緊急事態宣言が発出され、感染者は累計で15,000人を、死亡者も500人を超えた。
珍しく毎日欠かさずテレビのニュースを見て、ネットでさまざまな人の意見に触れている。
きょうも、NHKのBS1で、世界を代表する3人の有識者の提言を聞き、武漢のレポートを見た。
それぞれに一理あって、考えれば考えるほど迷ってしまう。
ひとりでも多くの命を救うのか、経済活動を維持してすべての人たちの生活を守るのか。
グローバリズムの機能停止と国家の復権は進歩なのか、後退なのか。
公共の秩序か、個人の自由か。独裁と民主主義は二者択一なのか。
これほど根源的な問いを突き付けられる状況は数十年ぶりのこと。
自分なりに考えを整理しないと、経営者として明確な方針を責任を持って示せない。
なぜ、店舗の営業を自粛しないのか。あえて社内懇話会を開催するのか。
というわけで、数日間、深く考え抜いてみようと思う。
というのも、先月は資金繰りの準備に努めて、10億円近くの資金確保の目途が立ち、心の余裕が生まれたからなのだ。
ここで思考停止に陥ってはいけない。
- 2020.04.12 自粛と事業継続の狭間
-
新型コロナウィルスの感染拡大がなかなか収まらない。
数理分析にもとづく予想どおりであり、少なくとも数か月は自粛を緩める状況にはならないと覚悟している。
毎月の客室稼働率を公開しているが、2月後半から影響が顕著になり、3月は約1/3減少、4月は半減する見込みである。
昨年12月に老母を連れてドイツのクリスマスマーケットを訪ね、2月中旬にはエジプトのナイル川クルーズに出かけた。
今はすべて催行中止になってしまっている。
ぎりぎりのタイミングで幸運に恵まれたわけだが、半年前、世界中の国々が鎖国状態になるなんて、誰が想像したことだろう。
最近は国内旅行も自粛ムードで、私も15年来続けてきた「ハーモニカ教室」の合宿旅行が中止になり、楽しみにしていたバイクツーリングも延期した。
本社でも在宅勤務を認めているため、オフィスは閑散としている。
電車通勤の社員が集まる職場は、もっともクラスターになりやすい場所に違いない。
ただ、日本国内に限って言えば、新型コロナウィルスの感染者は現時点で累計7,000人足らず、死亡者数は100人を超えていない。
検査を絞っているため、実際の感染者はずっと多いに違いないが、
厚生労働省発表によれば、通常のインフルエンザの感染者(毎年10,000,000人)と死亡者数毎年(約10,000人)と比べてきわめて少ない。
こうしてみると、騒ぎ過ぎ、恐れ過ぎ、ここまで経済を委縮させることの合理性に疑問を感じてしまう、というのが私の率直な印象である。
予防法も治療法も確立されていない未知の病気であり、外国の状況を見ると、こうした見方は無責任な楽観論なのかもしれないが、
批判されることを承知で言えば、このままの状況が数か月も続けば、中小企業や自営業者の多くは倒れてしまう。
「病を治して病人を殺す」、それで良いのか。
とはいえ、経営者の務めとして、リスクに備えるため少しでも現預金を増やしておこうと金融機関に対し、積極的に融資の申し入れを行っている。
先々の心配とはいえ、資金繰りのことを考えるなんて、十数年ぶりのことだ。でも、「備えあれば憂いなし」である。
20年前、旅籠屋にお金を貸してくれる銀行なんてなかった。
堅実経営が評価され、少しずつ信用力が増し、7年前からは代表者保証もなく、今では年0.5%未満の固定金利で融資いただけるようになっている。
ありがたいことだ。
とにかく、従業員の生活を守り、地域を支え、たくさんの利用者の必要に応え続けなければならない。
幸いなことに、店舗の支配人を含め、社内で感染者が出たという報告はない。
でも、みんな不安を抱え、心配している。
そんな中、今週は「長者原SA店」のオープン準備に皆で出かける。
そして、引き続き、東北各店の支配人を集め、恒例の「社内懇話会」を開催する。
延期してはどうか、との意見もあったが、ウィルスとの戦いは長期化し、常態化することを考えれば、重要な通常活動は維持継続するべきだと決断した。
マスクや手洗いはもちろん、室内でのミーティングは窓を開け放して行い、食事会も屋外で行う。
リスクを最小限に抑える努力をしながら、やるべき大切なことはやり続けるべきだと考えた。
結果としてこの判断が誤りであれば、経営者の責任が問われることになる。当然のことだ。
テレビも新聞もコロナの話ばかり。
いつのまにか、気が滅入って「コロナうつ」にかかりそうになる。
だから、昨日も今日も、いつものように隅田川テラスをひとりで走った。
先週から、ジョギングする人の数が目立って増えている。
こんな時こそ、体を動かし、汗をかいて、心の元気を保つ。
何百年も続く東京の老舗企業は、明治維新も、関東大震災も、戦争も乗り越えて今に至っている。
もっとも恐れるべきことは、いつも「心の中」にある。
- 2020.03.02 新型コロナウィルスの大騒ぎ
-
新型コロナウィルスのニュースで、連日大騒ぎである。
海外からの宿泊者が2%前後ときわめて少ないため、直接の影響は小さいのだが、それでも国内旅行を控える動きも顕著になっており、全国の店舗でキャンセルが相次いでいる。
昨年夏に毎週のように襲来した台風の影響に加え、こうした外的な要因による旅行客の減少は悩ましい。
しかし、これは、我々にはどうしようもないことであり、一喜一憂することなく、いつもと同じように客室を整え、全てのお客様を笑顔でお迎えすればよいと割り切っている。
それにしても、日本人は、横並びの自粛に走る人が多いような印象を受ける。
26年前、旅籠屋の創業を計画していた時に受けたアドバイスを思い出す。
「アメリカのMOTELのような宿泊施設を日本に? たしかに、アメリカにはあんなにたくさんあるのに、日本にはありませんよね。喜ぶ人はいるかもしれませんね。
でも、ビジネスとしては、うまくいかないかもしれませんよ。だって、ガソリンスタンド、コンビニ、ファーストフード、ファミリーレストラン、ショッピングセンターなど、
ロードサイドで誕生したビジネスはすべて日本に導入され、これだけ巨大になったでしょ。うまくいくなら、どこかの企業が、とっくに始めているはずだと思いませんか?」
日本人的な発想である。みんながやってるなら安心、誰もやっていないならやめとこう。 乱暴に言えば、アメリカ人は反対かもしれない。
誰もやっていないなら、やってみよう。みんなやってるなら、やめとこう。
政府は一斉に学校の休校や規模の大きなイベントの自粛を求めている。これに対する反対意見も多いようだが、オリンピックの中止や延期を避けるという目的もあるのだろうし、これについてここで批判するつもりはない。
私が違和感を持つのは、個人個人が風評に惑わされ、半ば恐怖に駆られて判断力を失って感情的になっていることだ。
店頭からは マスクや消毒薬だけでなく、ティッシュペーパーやトイレットペーパーや紙おむつまでもが消えている。再びの光景である。
自粛を求めるのは禁止する法的な根拠がないからなのだが、これに従う自治体や企業、そして個人が相次いでいる。
みんな、「何かあったらどうするんですか? 責任をとれるのですか?」と言われるのを恐れているのである。
正論を言っているつもりかもしれないが、本音はそこにある。反論を封じ、異論を避ける。
考えてみたら、そんな言い方は無茶苦茶である。卑怯である。
生きている限り、何らかのリスクを負って生きている。大勢の人間がひしめき合って生きている現代社会はリスクの上にしか成り立たない。
いや、現代社会に限らない。古今東西、生きるということはそういうことだ。
昔放映されていた損害保険会社のテレビCMを思い出す。YOUTUBEに残っていた。これである。
新型コロナウィルスは、感染力が低くないようだ。でも、重症化する可能性も低そうだ。
かつて流行した新型インフルエンザと比較しても、過度に危険視する必要はないのではないか、それが、現時点での客観的かつ科学的な見方のように思う。
自主的に通勤や通学を控えたり、用品を備蓄したりすることを否定しない。自己判断でどうぞというだけだ。
私の場合、睡眠と休養をとるように心掛け、できるだけ人ごみを避けたりするだけで、あとは日常どおり。
ただし、宿泊業を営む立場としては、一般の人以上のリスクを引き受けてでも、ぎりぎりまで店舗の通常営業を維持し続けるよう覚悟を決めている。
医療関係者や自治体関係者など公益性のある仕事に従事している人間はもちろん、誰だって自分の持ち場を守る、
社会人としての責任やプライドって、こういう時のためにあるんじゃないか、と私は思う。
その意味で、勝浦の「ホテル三日月」の人たちには心からの敬意を抱いている。
いろいろ批判されている「ダイヤモンド・プリンセス」のスタッフに対しても同じだ。もちろん、船長は最後まで船にとどまったはずだ。
当然のことを行うことは、なかなか難しい。みんな、ヒステリックに魔女狩りしている。自分第一なのはわかるけど、人のせいにばかりするのはやめないか。
自分たちの身を守ることを冷静に考え、静かに行動すれば良いのだ。
さぁ、必要以上に、ワイドショーやニュースを見ないようにしましょう。
治療法がない以上、検査だって、受けたって仕方ない。
無用な心配をせずに、心を落ち着けて体調を整えるように心がければいいんです。
- 2019.12.26 ラグビーから学んだこと
-
12月に入ったと思ったら、今年もあと数日。ほんとうに師走の時の流れははやい。
今年も「月刊 ホテル旅館」(柴田書店発行)の1月号に寄稿させていただく機会をいただいた。その原稿を以下に転記します。
年頭所感 「2020年の展望と課題」 ラグビーから学んだこと
毎年同じ書き出しになりますが、日本にもアメリカのMOTELのような車旅行者が誰でも気軽に利用できる宿泊施設をと願い「ファミリーロッジ旅籠屋」を誕生させて25年、全国各地70ヶ所以上に直営店を展開するに至りました。春には4番目の高速道路内店舗も実現する予定です。日本初で唯一のMOTELチェーンとして、少しずつ実績を築いてこれたことはとても嬉しく誇らしいことです。
昨年の本欄で、「流れにもムードにも乗りません」と題して、そのユニークな特徴を紹介させていただきました。- 1.リピーターが60%以上。
- 2.予約サイトへの依存率は15%未満。
- 3.支払いはあえて現金のみ。
- 4.出店は需要の小さなエリア中心。
- 5.海外居住者がわずか1〜2%。
- 6.人間性本位で支配人ペアを採用。
- 7.収益や効率の最大化を追求しない。
これらは、創業時から掲げている「シンプルで自由な、旅と暮らしをサポートする」というモットーにしたがって歩んできた結果と言えます。
昨年の秋、ラグビーワールドカップが開催され日本中が熱狂しました。
日本代表の快進撃やゲームの面白さだけではなく、背後にある基本的精神に心動かされた面があったように思います。
清々しい風が吹き抜けた気分になりましたが、ラグビー憲章というものがあり「品位、情熱、結束、規律、尊重」という言葉がうたわれていることを知って納得しました。普遍性のある理念や哲学が明確に示され、試合以外の部分でも一貫して体現される、だからこそ多くの人に伝わったのでしょう。翻って当社の場合、創業前から掲げている理念は以下のようなものです。
●2つの事業目的。
1.旅行者が、気軽に安心して泊まれる自由で経済的な宿泊施設の提供
2.地域に調和する資産活用事業の創出と堅実で自立した生活基盤の確保
●4つのコンセプト
1.素泊まり・・・宿泊特化の宿
2.街道沿い・・・ドライブに便利な宿
3.小規模運営・・・家族運営の宿
4.チェーン展開・・・どこでも安心の宿
●4つのポリシー
1.求められないサービスはしないのがサービスと割り切る。
2.快適にお泊りいただくという基本は譲らない。
3.あらゆる面でシンプルであることの合理性を追求する。
4.周囲への調和と環境負荷の低減を図る。
これらは、創業前にアメリカを旅しながら感じたMOTELの本質と日本で展開することの社会的意義を考え抜いて導き出したことです。その後、数多くの困難があり、分かれ道があり、迷いもありましたが、根底にある強い願いと掲げた言葉により、ぶれずに進んでくることができたように思います。コンセプトやポリシーに一定の耐久性が、言い換えれば普遍性があったということだと自負しています。
しかし、事業を続けながら気づかされたこと、新たに考えなければならなくなったことはたくさんあります。
- 車社会のインフラとして全国展開を進めれば需要の小さい地方への出店が増えてくる。また、建築費の高騰により土地活用の利回りが低下しており、出店が困難になる可能性がある。こうした収益性の問題をどう考えるか。
- 店舗が増えるに伴い、質を標準化し、維持していくことが困難になる。また、多様な支配人社員に運営を委ねることによるリスクも高くなる。こうした人的な問題をどう解決していくのか。
- 少子高齢化と車離れもあり国内のマイカー旅行は減少する見通しであり、不安定なインバウンド客に依存せず安定的に宿泊施設を維持継続していくことは可能か。
- オーバーツーリズムの問題を含め、そもそも地域社会の維持と観光はどのように調和するべきか、「世界観光倫理憲章」で提起されている課題を含め何を指針とすべきなのか。
- 残念ながら、日本では当社と同様の業態のMOTEL事業を担う会社が存在しない。切磋琢磨して事業を深化させ、広く社会に問題提起していくには同業他社の存在が欠かせないと思うが、その欠落をどう埋めていくのか
- シンプルで自由な旅をサポートするMOTELのような宿泊施設は500年も1000年も続けていく価値と可能性があると考えるが、事業の承継や継続性をどのように実現していくのか。
ラグビーワールドカップを見ながら、あらためて普遍性のある理念や哲学とこれを共有し体現していくことの重要性を再認識しました。
お気づきかもしれませんが、先に紹介した当社の理念は、切り口も次元もまちまちで断片の羅列という面を否定できません。
創業から25周年を迎え、今一度深く考えて見直しを図り、「旅籠屋憲章」とでもいうべき言葉を明確に示さなければと考えているところです。
- 2019.10.18 ラグビーWカップ
-
9月20日に開幕した「第9回 ラグビーワールドカップ」の熱戦が続いている。
日本戦に限らず、テレビで放映される試合をすべて観戦し、自分でも驚くほど盛り上がっている。
昔々、高校に入ってすぐ、私は数か月間だけラグビー部に所属していたことがある。
ところが、根性主義の時代のこと、試合はもちろんミニゲームにも参加できず ただ走らされるばかりの練習に嫌気がさして退部したので、細かいルールもわからないまま、トップリーグも見に行ったことがない。
いわゆる 「にわかファン」のひとりである。
でも、ラグビーには私の心を震わせる何かがあって、昔、国立競技場をにぎわせた早明戦や早慶戦を見に行って大声をあげたり、その後も日本代表の「善戦」に心躍らせたり、4年前のイングランド大会で南アフリカを破った「スポーツ史上最大の番狂わせ」は中継を見ながら泣きそうなほど感動した。
だから、今回の大会はとても楽しみにしていたのだが、まさか日本が予選リーグを全勝で勝ち抜けるななんて想像もしていなかった。
開幕のロシア戦、アイルランド戦、サモア戦、スコットランド戦、どれもこのまま離されて負けるのかなぁ、逆転されるのかなぁ、半分腰を引いて応援していたのだが、こんな結果になるなんて、嬉しすぎる。
しかし、各国の試合や関連のニュースを見ながら、こみあげてくる感動の源泉は、日本代表の活躍だけではなく、このスポーツが本質的に持っている別の部分にあることに気づかされた。
ルールであるとはいえ、不利な判定に対し感情的になるプレイヤーがいないのはなぜ?
一方的な負け試合なのに、最後の最後までふてくされることなく全力でプレイするのはなぜ?
ノーサイドの直後、さっきまで格闘していた相手と笑顔で称えあうことができるのはなぜ?
試合後、なぜ相手チームのロッカーまで出向いてラフプレイを詫びにいき、それに拍手で応えるのはなぜ?
試合が中止になったのに、現地に残り、ボランティア活動に参加するのはなぜ?
何年も苦しい練習を続けてきたのに「自然災害の現実に比べれば、ラグビーなんてささいなこと」と言えるのはなぜ?
応援しているファンが相手チームの国歌を歌い、試合後、穏やかに相手の試合ぶりをほめることができるのはなぜ?
今回は解説にまわっている五郎丸選手が4年前の南アフリカ戦を振り返り、次のようなことを話していた。
「あの劇的な勝利の後、我々は歓喜のあまり選手同士で喜びを爆発させていました。
しかし、すぐに南アフリカの選手が近づいてきて、勝利をたたえてくれたのです。
その瞬間、ラグビーが実現しようとしていること、求めていることは別のところにあることに気づかされ恥ずかしくなりました。」
ラグビー憲章 を読んで、すべてのことが腑に落ちた。
そこには、 このスポーツの根底にある理念や哲学、大切にすべき精神が、次の5つの言葉に集約されて明記されている。
品位(Integrity)。
情熱(Passion)。
結束(Solidarity)。
規律(Discipline)。
尊重(Respect)。
もちろん、ウルグアイ選手の泥酔暴行事件や、スコットランド協会の「日本戦を中止すれば法的手段に訴える」という、残念な例外もあった。
ちなみに、後者については、ヨーロッパの人たちは、台風や地震や津波の恐ろしさを経験したことがないのだな、と思った。
つくづく、日本に住む我々は、大昔からこうした自然の脅威にさらされ、耐えることによって、生きてきたのだなぁ、と思った。
こんなラグビーの世界に惹かれていると、ついついサッカーと比べてしまう。
審判を欺くこともテクニックのうちと考え、大げさに倒れたり、演技したりする選手。
試合中も試合後もレフェリングに文句を言う、選手や監督。
相手をののしり、軽蔑を隠そうとしないサポーターの言動。
ラグビーは上流階級の恵まれた人たちのスポーツで、サッカーは庶民のスポーツだから、という説明を聞いたことがある。
でも、きれいごとであれ、「人間、捨てたもんじゃないなぁ」と思わせてくれる世界を引きずり下ろす必要はない。
こんな理念や精神が浸透していけば、世の中はもっと美しく生きる価値のある世界になっていくかもしれないと夢想するのを冷笑する必要もない。
私は、こんなやせ我慢や理想主義が好きだ。
この1週間、風邪気味で微熱が続いている。
でも、なんとしても、この週末、準決勝の4試合を全力で観戦する。
こんな素晴らしい機会を見逃すわけにはいかない。
日本、頑張れ。そして、どの国の選手もみんな頑張れ。
そして、気高い人間の心を見せてくれ。
- 2019.08.12 イギリス、バイクツーリング 8日目
-
●8日目・・・6月26日
飛行機の便は夕方なので、昼過ぎまで自由時間。
大好きな街歩きの時間。
まずは、ホテル近くのパディントン駅へ。
入口脇の壁に大きな絵が何枚も飾られている。
犬連れの家族がイギリス各地を旅してまわっているシーンが描かれているが、とても可愛くてほっこりしてしまった。
行かれる方は、ぜひ見てください。


駅の構内、ホームの横に、有名なパディントンベアーの像や絵がさりげなく飾られている。
前に来た時に見かけたのだが、今回もこれを探して構内をうろうろ。
改札口がないので、自由に列車の脇まで行ったり来たり出来る。


続いて、駅の北東方向に歩いて有名なアビーロードの横断歩道へ。
途中迷ってしまい1時間以上かかってしまった。
途中で黒人のお兄ちゃんに尋ねたら親切に教えてくれた。
彼が笑いながら言ってたとおり、周囲には観光客がいっぱい。
50年も経つのに世界中から人を引き付けるなんて、ビートルズはすごい。

ホテルに戻る途中、ロンドンでもっとも美しいと言われているリージェントパークへ。
ここも2度目だが、広々とした緑の空間は、人もまばらで素晴らしい雰囲気。
町中の喧騒から離れ、車の音もなく、くつろげる。
犬がリードなしで散歩したり自由に走り回ったりしている。
私が住んでいる浅草界隈にも、こんな公園があったら、どんなにいいだろう。
上野公園も人が多すぎるし、犬を遊ばせるなんて無理。


最後に、無料公開という案内に魅かれ、貴族の館へ。
Wallace Collection。
外観やアプローチの雰囲気は、大英博物館に似てるような。
館内には、集められた武具や絵画、陶磁器などが、あふれんばかりに展示されている。
大英帝国の栄華と富の蓄積にあらためて驚かされる。
絵画の中には、レンブラントの自画像もさりげなく飾られていた。
ものすごい値がつくだろうにと、下世話なことを考えてしまった。


以上で、今回の旅は、ほぼ終了。
あれから1ヶ月半も経ってしまったが、やはりバイクの旅は、一般的な観光旅行よりもはるかに思い出が濃い。
歳も歳だし、気力体力のあるうちにと思って半ば衝動的に申し込んだが、行って良かった。
何よりも、日本とはまったく異なるイングランドの地形や風景を感じることができた。
同じ島国で、面積は日本の方がずっと広いけれど、使える土地の広さは逆だと思った。
2,000km以上も走ったが、トンネルは一度もくぐらなかったような気がする。
それだけ、高低差がなかったということだ。
日本の自然の変化の豊かさをあらためて感じた。
高速道路を作る費用と手間と技術、おそらく日本は世界一ではないだろうか。
そして、田舎町の景色の違い。
どこへ行っても、石造りの素敵な建物とセンスの良い庭が並んでいて、 無秩序な日本の街並みが情けなく思える。
でも、何日も同じような風景を見ていると、単調な気がしてくる。
新しいものに飛びつかない頑固さと、それを許さない無言の圧力のようなものもあるのかもしれない。
それに比べ、雑多ではあるけれど、日本の地方の街や村は無邪気なスッピン。
もう少し統一的な美的感覚を持ってほしいと思うが、見られることなど意識していない無防備な正直さにあふれている。
好きではないが、これもありなのかもしれないと、少しだけ思った。
それにしても、歴史や伝統を重んじる性向は、間違いなく文化的な雰囲気を醸成する。
厳然と継承されている貴族階級の存在が、保守的な安定を支えているのかもしれない。
それは一種のプライドなのか、排他的なアイデンティティなのか。
EUからの離脱問題のニュースが騒がしいが、現地ではなんの兆候も感じられなかった。
古い歴史を持つ島国という意味では似ている日本とイギリス。
でも、両者の国民性は対極にあるようで、イギリスには独特なこだわりを捨てないでほしいと思う。
前のめりのグローバリズムのスピードの方が異常なのだ。
一言でいうと、さりげなくもとことん人間くさいイギリス、住みたくはないけれど、気に入りました。
また、訪ねる機会はあるのだろうか。
- 2019.08.05 イギリス、バイクツーリング 7日目
-
●7日目・・・6月26日
きょうは、バイクツーリング最終日。
レンタルバイクの店まで戻るのだが、途中、街並みの美しさで有名なコッツウォルズ地方を抜けていく楽しみなコース。
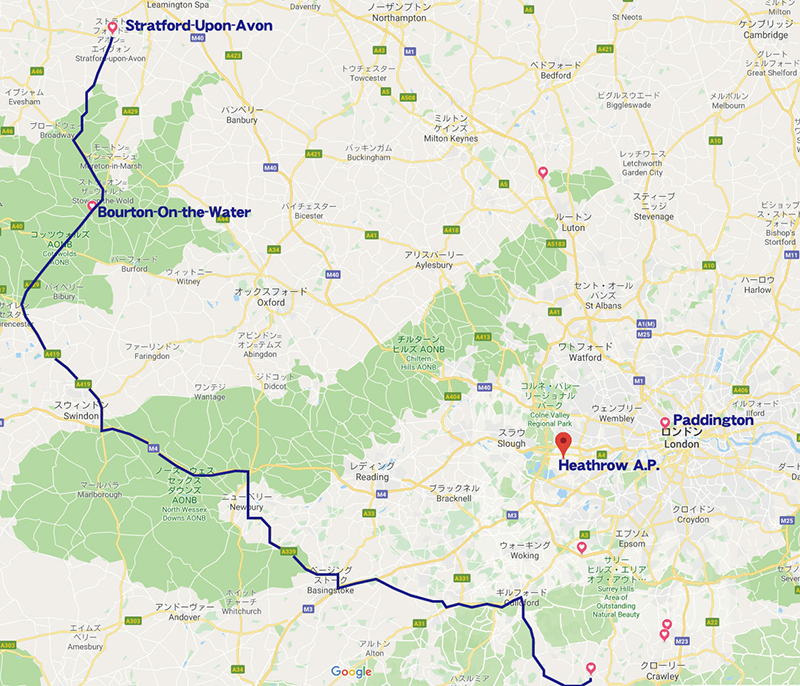
古くから羊毛の交易で栄えた地域らしいが、時代の波に取り残され、原風景が残ったということ。
日本でも同じ。
昔「妻籠」に行った時、宿の人に「見捨てられた場所だから残っただけですよ」と言われたことがある。
都会人のノスタルジーと地元の人たちの視点は違う。
そんなことはともかく、丘を抜けていくと、蜂蜜色の石造りの建物が目立ってくる。やさしい外観。
最初に立ち寄ったのは、Chipping Campden。
素晴らしい天気で、お伽の国のよう。
茅葺の家もある。

細かく手が入れられているけれど、人工的ではなく自然な雰囲気。
いわゆるイングリッシュガーデンと呼ばれる家々の庭を眺めながら、街中を散策。
壁を飾るハンギングバスケットの植え込みも、ほんとうに上手で美しい。
日本と異なる地形や気候、自然や緑との付き合い方のベースにある感覚が明らかに違うのだろう。
こういうものはひとつの文化だし、うわべだけ真似てもダメ。
日本で時々見かけるプラスチックの鉢をそのまま見せている家など皆無だ。



続いて、Bourton-On-the-Water という街に立ち寄る。
ここは、以前にも来たことがあるが、その時は雨が降っていて寒かった。
今回は、最高の青空が迎えてくれた。

街中を流れるソ水深の浅い、人工の水路。
以前、ニュージーランドのクライストチャーチという街に行った時、底の浅い船で水路を巡ったことを思い出した。
たしか、パンティングとか言う舟遊び。
水鳥がゆっくり泳いでいて素晴らしい雰囲気。



1時間ほど散策した後、ロンドン方面に進み、午後には郊外のレンタルバイク屋さんにバイクを戻す。
結局、今回のは6日間で3回も立ちコケしてしまい、バイクを傷つけてしまったので、修理代がどれくらい請求されるかと心配。
でも、金額は、じっくりチェックして後日連絡が来ることになった。
なんだか気が重くなるが、仕方ない。
アメリカのツーリングの時のように、全額保証の保険があったらよいのにと思う。
とにもかくにも、怪我もなく無事戻ってこれたし、ずっとさわやかな晴天に恵まれたことに感謝。
店主に「なにとぞ、よろしく」という気持ちを込めて握手し、タクシーに分乗して、Gatwick空港へ。
直通の電車に乗り替えて、ロンドンのPaddingtonへ。

ホテルは駅の近くの建物。 ここもエレベーター無し。もう慣れてきた。
下は、ホテルのすぐ近くのビル。
壁一面に花を植えたバスケットが飾られているが、水やりはどうするのだろう?

夕食は添乗員さんお勧めのワインバーへ。
店内の雰囲気も料理もとてもよかった。
大陸は40℃を超える熱波が来ているらしいが、ロンドンの夜は肌寒いくらいだった。

- 2019.08.05 イギリス、バイクツーリング 6日目
-
●6日目・・・6月26日
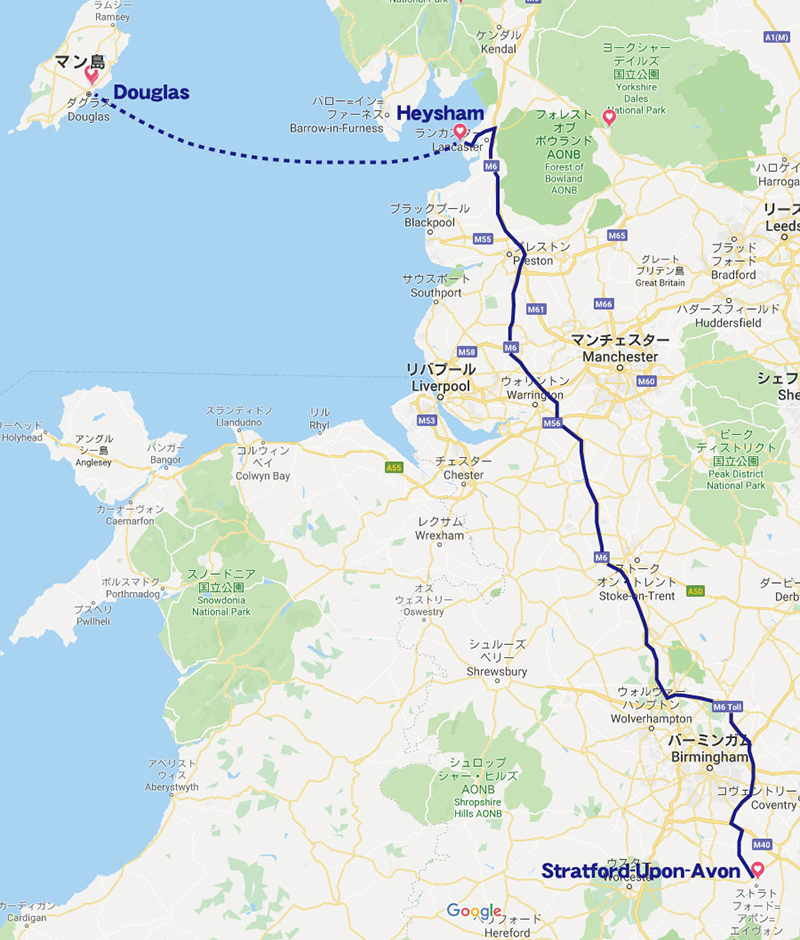
旅も後半。
きょうは早起きしてブリテン島に戻り、ひたすら高速道路を南下し、シェイクスピアの生誕地で有名な街へ。

フェリーはすいていて、船内でゆっくり昼食をとる。
海を見ると、海の中に無数の風力発電。
これが良いのか悪いのかはともかく、知らないうちに世界は変化しているのだなぁと思う。
我々がメディアを通して得ている情報なんてほんの一部。
来てみないと気づかないことがいっぱいある。

途中で立ち寄ったSA、ここにもMOTEL。
「Travelodge」も「DaysInn」も、アメリカ中にあるチェーンだが、前者はイギリスに500軒、後者は40軒ほどあるらしい。
SA内といっても、広い芝生の中に建っていて、なかなか良い雰囲気。

昼過ぎからずっと高速道路を走り続け、夕方6時過ぎに、Stratford-Upon-Avonに到着。
ここは、世界一の店舗数を誇るMotelチェーン「Best Western」を名乗っているが、元々は古くからある宿なのだろう。
集客のために、チェーンに加盟しているのに違いない。

歩いて数分のところに、シェイクスピアの生家。 500年以上も残っているのがすごい。
残念ながら見学時間は終わっており、内部は見られなかった。

道の反対側の写真。左側手前が生家。
500年前はどんな通りだったのだろう。
もちろん、電柱も電線もない。

2時間ほど、街中を散歩したが、旧市街地は観光客向けのこぎれいなショップばかり。
ここは、ピーターラビットのお店。閉店前に来たかった。
世界中、有名な観光地は、どこも観光客向けのお店が軒を連ねている。
自然なことだし、かわいらしくて期待通りなのだが、作られた虚像のような感じもして、少ししらける。
オーバーツーリズムの問題にもつながる、難しい自問自答。
散歩の途中、裏通りで日本食の食堂を発見。
たこ焼きとラーメンを注文したが、ラーメンはひどかった。
日本人がやっている店ではないらしいので仕方ないが、これが日本料理と思われるのは残念。
近くのテーブルでは、白人カップルが寿司を食べていたが、3ダースくらいの握りをひとりで平らげていた。
うーん、質より量のこの感じにも違和感。
- 2019.08.04 イギリス、バイクツーリング 5日目
-
●5日目・・・6月25日
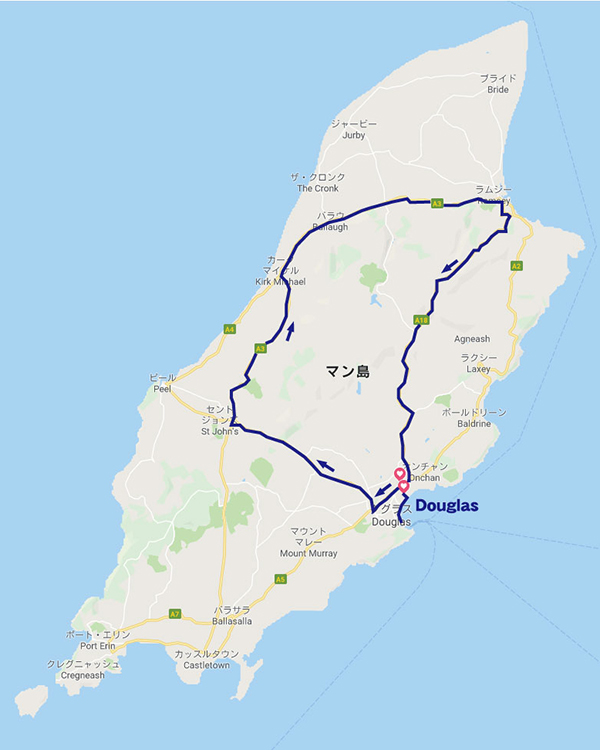
今日は、終日マン島に滞在。
全員自由行動だが、4台は添乗員に先導してもらいながら、TTレースのコースを一周。
ホテルから少し斜面を上がった地点が、スタート・ゴールのメインスタンドのある場所。

すぐ右を走る一般道路と並行して、ここだけ専用のピットレーンのようになっている。
表彰台の上から撮影した動画はこちら。うまく再生できるだろうか。
オートバイやレースに興味のない人も、「マン島TTレース」という言葉を耳にしたことがあるかもしれない。
終戦から10年も経たない1954年、当時世界的にはまだ無名だったホンダの本田宗一郎が、ヨーロッパ視察の途中にこのレースを観戦し、
帰国後、まったく無謀な「出場宣言」を発表し、数年後に優勝したことは伝説的なエピソードだ。
この経緯については、こちらをご覧ください。当時の日本人と日本企業の志の高さと強さを感じることができます。
ごく簡単に紹介すると、このレースのスタートは100年以上も昔の1907年。
以来、レギュレーションやコースが変更されながら今も続き、今年も5月、1週間にわたり開催された。
特徴は、専用のサーキットではなく、島内の一般道路がコースになっていることで、これまでに観客を含め300人近くの事故死が発生している。
戦後始まった2輪の世界選手権においても、主要なレースの一つになっていたが、このようにあまりに危険だということもあって、
メーカーやトップライダーは参加を忌避するようになり、1976年以降は独自の単独レースとして、特異な存在であり続けている。
詳しくはこちらをご覧ください。
ただし、言葉や文章では伝わらない。
ぜひとも、こちらの映像をご覧ください。 上の写真の場所も出てきます。6分あまりの記録映像です。
ご安心ください。事故のシーンはでてきません。

コースの途中の集落。
1周、約60kmのコースの2/3くらいはこのような普通の民家の間を走る。
ここを200km/h以上のスピードで競争するなんて、正気の沙汰ではない。
もうしばらく走るとコースは市街地を抜けて、ゆるやか丘へ。
少し暗くなり、雲行きが怪しくなってきた。

丘のコースに入ってくると、濃い霧。 前のバイクのテールランプを頼りに、走る。
途中、もっとも標高が高いあたりのコース脇に立てられた、伝説のライダージョイ・ダンロップの銅像を見に行く。
マン島TTレースの最多勝利を誇る彼は、2000年、エストニアでの公道レースで事故死。享年48歳。
その後、彼の弟や息子たちがマン島TTレースに参戦している。
ホンダのレーシングマシンにまたがりコースを見下ろしている彼の表情は、やさしく微笑んでいる。
深刻な表情でないのが、いい。
ちなみに、この像の建立費用を負担したのは、彼にヘルメットを提供していた日本のARAI。
粋なことをしたものだ。

なんとか、コースを一周して、ダグラスの街へ戻る。
ゆっくり2時間近くかけて走ったが、レースでは60kmを20分以内で1周するらしい。
もう1周する他のメンバーと別れ、ホテルに戻り、午後は、ゆっくり街中を散策。
公式Tシャツを製造販売している店のここが本店。
名前も「TT SHIRTS」、シャレている。
お約束のお土産を購入。

街の中心部はこんな感じ。ここでも、電柱や電線は見えない。
TTレースの旗やバイクが飾られていて、レースが観光イベントの中心になっていることが伺える。
2〜3時間ぶらぶら散歩して、早めに就寝。
あすから、 旅も後半だ。
- 2019.07.31 イギリス、バイクツーリング 4日目
-
●4日目・・・6月24日

今日はいよいよマン島へ渡る日。
少し遅めにウィンダミアのホテルを発って、Heyshamという港町のフェリー乗り場へ。
有名な三本足のマークが出迎えてくれる。
このマークを見て、NHKの大河ドラマ「いだてん」を思い出す人もいるかもしれない。
私は「いだてん」の放映開始の時から、「あれっ? これってマン島のマークじゃないの?」と不思議に思ってました。
なにか関係があるのでしょうか?

それはともかく、マン島の複雑な歴史と立場については、Wikipediaをご覧ください。
島内でしか通用しない独自の通貨があったりして、中央集権が進んでいる我々日本人には、驚きです。

駐車場で乗船待ちをしていたら、1926年製のベントレー。
もうじき100歳! 現役で走ってるのがすごい。
こういう所も、イギリスの懐の深さ、乗り物文化の確かさ。
なんだか、素敵だなぁ。
マン島へは4時間弱の船旅。
ほぼ満席で団体客がうるさいし、退屈。
上のデッキに出てみたら、すぐ目の前をカモメが並走していて、その大きさにびっくり。
下に戻ったら、ペット連れ優先室があって、犬が何匹も足元に寝ていた。
我が愛犬と同じゴールデンリトリーバーも居て、思わず手を振ってしまった。
お店でも列車でも見かけることが多く、犬連れで旅行することが広く受け入れられているのがとてもうらやましい。
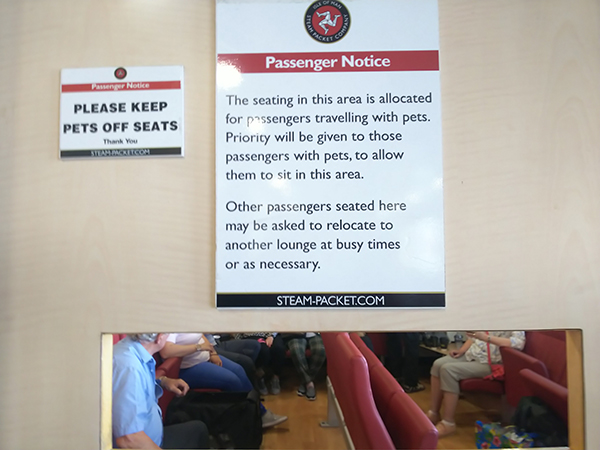
揺れることもなく、19時頃、無事にマン島の中心地Douglasのホテルに到着。
空堀に面した地階があって、間口の狭い建物。
イギリスの市街地で一般的なつくりだ。
それなりに古いのだろう。難点はエレベーターがないところ。
ここは、客室が4階だったので、狭く急な階段を使っての荷物の上げ下ろしがほんとうに大変だった。

夕食は、今夜もフィッシュ&チップス。
十分においしかったけれど、一皿をふたりで、ちょうどよい。

- 2019.07.19 イギリス、バイクツーリング 3日目
-
●3日目・・・6月23日
じつは、 バイクツーリングの初日、ガソリンスタンドの近くで、さっそく立ちコケしてしまった。
走っている時は何の問題もないのだが、停止して足を着こうとした時につま先立ちになってしまい、バランスを崩して車重を支えきれなくなってしまう。
後ろのシートにカミさんを乗せていたので、怖い思いをさせてしまった。
身長の低さを嘆きたくなるが、スムースな減速と停止やシートから降りての取り回しの下手さ加減は私のせいだ。情けない。
結局、きょうから彼女は添乗する4輪の伴走車に同乗させてもらうことにした。申し訳ない。
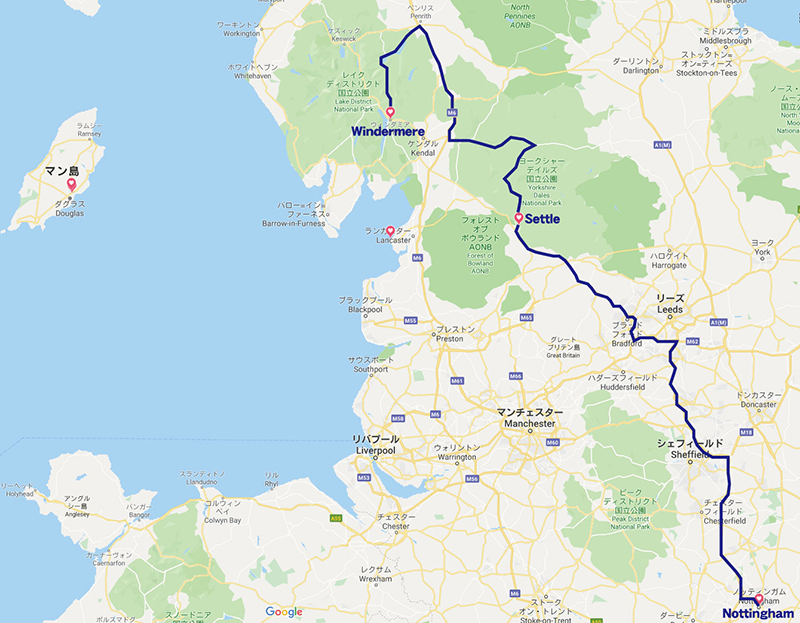
今日は、前半は高速道路を北上し、後半は一般道路を走って、イングランド北部の景勝地「湖水地方」を巡る。
ロンドンの環状高速を離れてからリーズという町までは、ずっとM1という高速道路。
1号という名前が付いているので、日本の東名高速のような最大の幹線道路なのだろう。
通行量が多いが、 片側3〜4車線と広く、走りやすい。制限速度は70マイル=112km。ほとんどの車は100〜130kmで淡々と走っている感じ。
割り込みやあおり運転はなく、マナーは良い。1/4〜1/3は日本車、嬉しい。
おもしろいのは市街地が近くなって渋滞が発生するようなエリアになると、時間と区間を限定して路肩の走行を認めていること。
日本でも、渋滞時に限って2輪の路肩走行を認めるようにしようというアイデアがあるが、ぜひ実現してほしい。
最初に立ち寄ったSAには、もちろん宿泊施設。

走りやすいが単調な高速道路を降りて、ようやく一般道路に入る。
すぐに、SETTLEという町の小さな鉄道の駅に立ち寄る。
あまりの美しさ、かわいらしさに感動してしまった。
飾られている草花を含め、心を込めて大切にしていることが伝わってくる。



ご承知の通り、イギリスは鉄道発祥の地。車に押されて衰退しているのは日本と同じだろうが、鉄道マニアがボランティアで走らせている路線も多いらしい。
鉄道が、輸送という機能だけでなく文化として受け継がれ、大切にされ、定着している。
このあたりに、イギリスの文化的な深さや成熟した味を感じる。
日本では、経済的合理性だけで、線路や道や建物が捨てられていくことが多い。
やりきれない。うらやましい。あこがれてしまう。見習いたい。

田舎道を走り、いくつもの小さな町や村を過ぎると次第に家が少なくなり、荒涼とした風景がひろがってくる。
ヨークシャーデイルと呼ばれる地域だそうだ。
ここまで500km以上イングランドを南北に縦断してきたわけだが、島国とはいえ、日本とは景色が大きく異なる。
高い山がなく、見渡す限りなだらかな丘が続く。部分的に残る林を除くと牧草地。そこでは羊や牛や馬がのんびり草を食んでいる。
水田がないため、ゆるやかな斜面ばかりだ。


ヨークシャーデイルを過ぎると、湖水地方。
この辺りは明らかに氷河が作り出した地形に違いない。谷間には細長い湖が点在している。
ツーリングを楽しむ数多くのバイクとすれ違い、追い抜かれる。 人気の観光地らしい。
30分ほど待ってもひとりが集合場所に到着しないが、残りのメンバーで、今日の宿泊場所 Windermereのホテルに向かう。

ここは、湖水地方の中心地。たくさんの観光客でにぎわっている。
まだ外は明るいので、街を散策。
遅れていたメンバーは迷子になっていたらしく、無事に到着。良かった。


どの街もそうだが、電柱や電線が目に入らない。
地下に埋設されていない場合も、電線は建物の裏側に目立たないように通っている。
このあたりの美意識も見習いたいところ。
さぁ、あしたは憧れのマン島に渡る。
- 2019.07.18 イギリス、バイクツーリング 1〜2日目
-
「木更津港店」や「大阪枚方店」のオープン準備、決算手続きなどに追われている時期だが、半年以上前に予約したこともあり、6月下旬、10日近くも休みをとり、強引にイギリスに行ってきた。「イングランド北部 湖水地方とマン島 9日間」というバイクツーリングである。
海外でのバイクツーリングは2度目。前回は、ちょうど3年前の6月中旬に行った「アメリカ大西部周遊とルート66 8日間」。
40年以上バイクに乗り続けているし何とかなるだろうと甘く考えて申し込んだのだが、ハーレーに乗るのは初めてで、乗車姿勢も操作方法も違うし、何より車重が400kgもあり、初日から立ちコケしてしまった。恐怖心さえ感じてしまい、グループから離れ、出発地のラスベガスでみんなが帰ってくるのを待つことにしようかと本気で考えたくらいなのだが、なんとか気を取り直し一日一日必死で旅を続け、1,700kmの行程を走りきることができた。
毎日40℃を超える気候で、後ろに乗るカミさんも大変だったと思うが、ギラギラ照り付ける太陽を感じ、乾いた風を受けながら雄大な風景に包まれる感覚は、観光バスツアーではけっして味わえないもの。何より、自分でアクセルを開け続けない限り進んでいかないのだから、能動的な意志を問われる旅であり、バイクツーリングならではの深みを生む。苦楽を共にする仲間とも、運命共同体のような心のつながりが生まれ、忘れられない色濃い思い出となった。
今回のイギリスツーリングも、3年前の記憶が後押しして決めたこと。気力体力があるうちにと思って決断した。ロンドンには過去2回行ったことがあるが、映画などで見るイギリスの田舎の風景を体感してみたいと思った。昔から関心のあったマン島TTレースの舞台を訪ねられるというのも魅力だった。
ところが、出発の40日前の5月11日、ひさしぶりにぎっくり腰になってしまい、無理に山歩きをして悪化させてしまったこともあり、完治しないまま当日を迎えることになった。 何とかなるだろう。
以下、私なりに感じたことを中心に、旅のあれこれをまとめてみるので、よろしかったらお付き合いください。
全体の行程は、以下の通り。7泊9日の旅である。
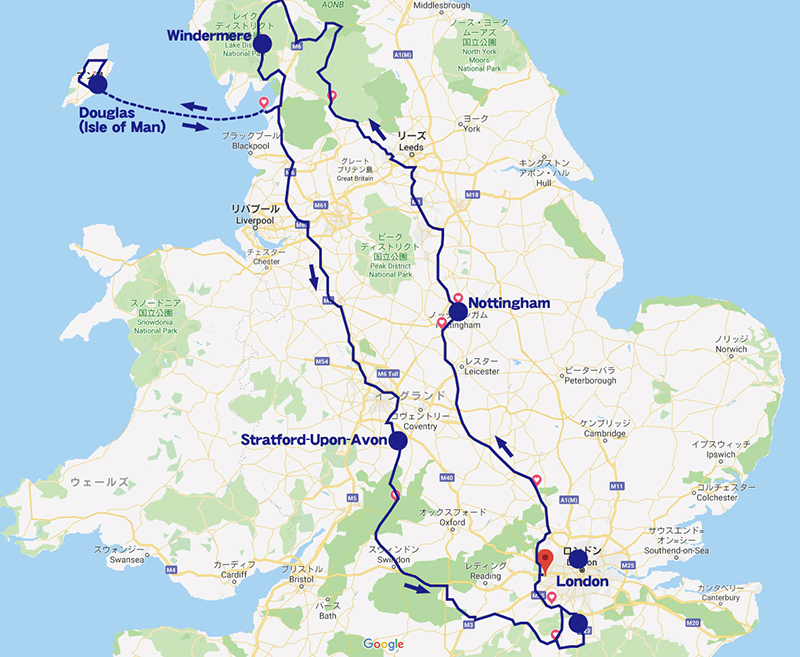
●1日目・・・6月21日
早朝に成田空港に集合。添乗員を含め、総勢9名。バイクは6台。自分が最年長に違いないと想像していたが、なんと70歳以上が3人もいる。
まわりから見ると老人ツアーである。
飛行機は大韓航空なので、ソウル郊外の仁川空港で乗り継いでロンドンに向かう。
この空港は、東アジア有数のハブ空港らしく、さすがに規模が大きく、施設も立派。
空港内では、昔の武人のような装束の人たちが剣舞などを演じて回っている。なかなか見ごたえがあり、しばらく見入ってしまった。
国の表玄関で自国の歴史や文化を紹介するこうした試みはアリだと感じた。余裕があれば、日本でも、全国の空港でデモンストレーションをやってみれば良いのに、と思った。そういえば、ハワイに行くと、フラダンスで迎えてくれる。
日本人は積極的にアピールすることが苦手なのか、必要ないと思っているのか、こんな所で負けていると感じた。

仁川空港からロンドンのヒースロー空港までは11時間以上。
入国審査に時間をとられると心配していたが、最近自動化されたようで、申請書類もなく、機械にパスポートをかざして写真を撮られて終わり。
列に並んでいた時間を含め、15分程度で完了した。
ところが、そのあと、迎えの車が遅れ、宿に到着したのは午後9時近く。
ロンドン郊外にあるもうひとつの空港、Gatwick空港そばの小さなホテル、ちょうど夏至の頃なので、この時間でも外は明るい。

●2日目・・・6月22日
時差の関係で早朝に目覚めたら、快晴の青空。
先週は雨が続いていたので案じていたが、晴れると湿度も低く、空気がさわやか。
下の写真はホテル前の街並み。緑が多く、鳥たちが飛び交い、あちこちからさえずりが聞こえる。街は静かでいい感じ。
そうか、今日は土曜日なんだ。

タクシーに分乗して30分以上走り、レンタルバイクのお店に到着。
トライアンフ2台、BMW2台、モトグッチ1台、私は手前に写っているホンダCBF600。
もっともシート高が低いことを期待しての選択だったが、またがってみるとつま先立ちに近い。4気筒で重量があり、これが悲劇を繰り返すことになる。

なんとか走り出して、しばらくは伴走する4輪に続いて田舎道を走る。
左側通行なので走りやすいが、日本のような信号のある交差点が少なく、ほとんどがRoundaboutと呼ばれるロータリー。
さっそく高速道路に乗るロータリーで車列が分断され、最後尾を走っていた私ともう1台は、先行する人たちを見失ってしまった。
M24というロンドン環状高速を西へ向かうはずが、どうも逆の東に走っているらしい。
路側帯に停車して添乗員に電話したところ、次の集合場所であるSAで待っているから、どこかでUターンしてきてくれとのこと。
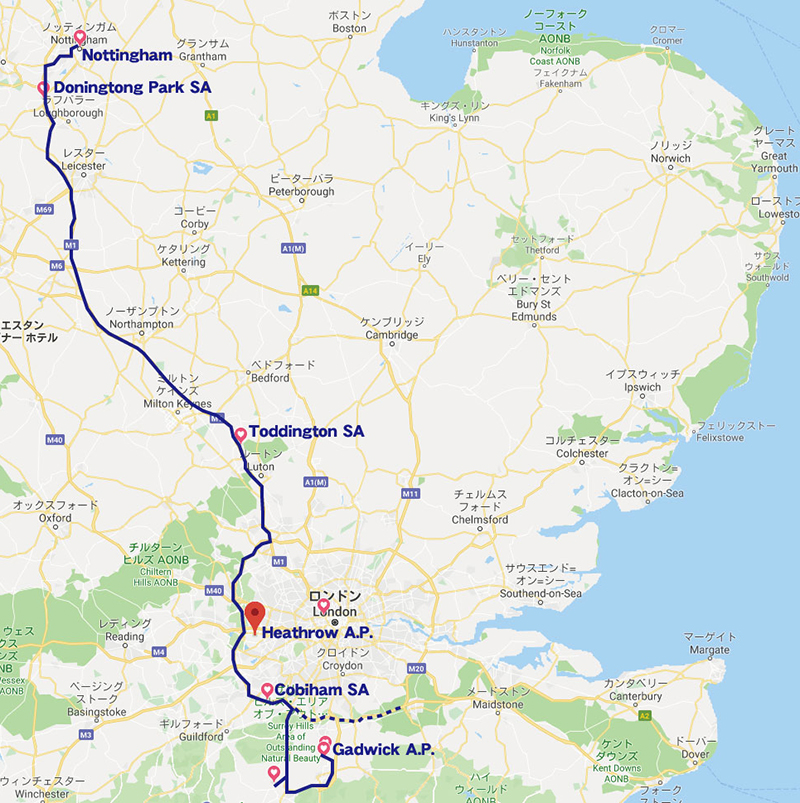
ここで説明しておかなければならないのだが、イギリスの高速道路は大部分が無料。アメリカと同じだ。知らなかった。
ただ、アメリカの高速は、市街地を離れると信号はないものの一般道路とあまり区別がつかない感じで、気軽に出入りすることができるが、イギリスの場合は日本と同じく閉鎖された空間になっており、インターで一般幹線道路に乗り換えるジャンクションがあるだけで、いわゆる出口というものが見当たらない。
この違い、うまく伝わるだろうか。
日本のように出口を見つけて外に出て入り直せば逆方向に走れると思ったが、それが出来ず延々と逆方向に走り続けてしまった。
ようやく状況を理解し、ジャンクションから一般道路に出て、ロータリーを使って逆向きに高速に入り直すのに30分以上かかってしまった。
上のマップの点線が無駄に往復した部分だ。
というわけで、集合場所のSAに着いたら、みんなは待ちきれずに出発した後。交代でトイレを済ませ、ちょっとだけ施設を覗いてみた。

ここでまたアメリカとの違い。
同じ無料でも、アメリカの高速には、トイレやベンチだけ設けてあるRest Areaはあるが、日本のような飲食物販やガソリンスタンドがそろっているService Areaに該当する施設にお目にかかったことはない。私の知る限りの話なので、まったくないとは断言できないが、あったとしてもごく一部だけなのではないかと思う。
要するに、食事をとったり、買い物をしたり、給油したければ、気軽に高速を出て、一般道路脇の施設を利用すれば事足りるという感じだ。宿泊施設も同様、MOTELは無数にある。
ところが、イギリスの高速は厳格に閉じているので、日本と同じような施設がある。サービスエリアという名前ではなく、Serviceseという名前で道路脇に表示が出ている。
上の写真は最初に立ち寄ったCobihamというSAの施設内の写真。日本とよく似ている。しかし、決定的に違うのは、必ず宿泊施設があること。
今回の旅行中、数か所のSAに立ち寄ったが、例外なくMOTELかHOTELがあった。
下は、最初にCobihamというSA内にあったDays Inn。アメリカ中にある有名なMOTELチェーンだ。パンフレットを見たら、イギリスだけでなんと600軒以上もある。

イギリスの高速道路はMotor Wayと呼ばれ、M1とかM25のように番号が付いている。一般道路はAという記号と数字が付いている。
ちなみに、 日本やアメリカの場合、高速道路関連の表示は緑色に統一されているが、イギリスでは白地の看板で他との区別がつきにくく、慣れないと見過ごしてしまいがち。ロータリーの標識もそうだが、アルファベットだけで書かれている内容を一瞬で読み取るのは難しい。
漢字を使う日本のありがたみを痛感する。
下は、バイクのレースで有名なドニントンパークに隣接するSAにあったTravelodge。これもアメリカ中にある有名なMOTELだ。
途中、シルバーストーンやミルトンキーンズなどの地名標識が目に入る。イングランドはモータースポーツファンにはワクワクするような場所なのだ。

そんなこんなで300km以上を走り、夕方6時頃に今日の宿泊地、ノッティンガムに到着。
歴史のある街のようで、お城を中心に赤レンガの建物が連なる落ち着いた品の良い雰囲気。

早めに着いたので、街中を散歩し、イングランドで一番古い(1189年開業、元はInn)というパブで夕食。
店の名前がすごい。「エルサレムへの道」。十字軍の宿だったのか?
みんなは地ビール、飲食に興味のない私はコーラにフィッシュ&チップス。
意外においしかった。

- 2019.06.20 「キャッシュレス化」について
-
また、半年も空いてしまった。あと10日で決算日、今期も終わりだ。
ところで、先日5月18日の朝日新聞に以下のような拙文が掲載された。
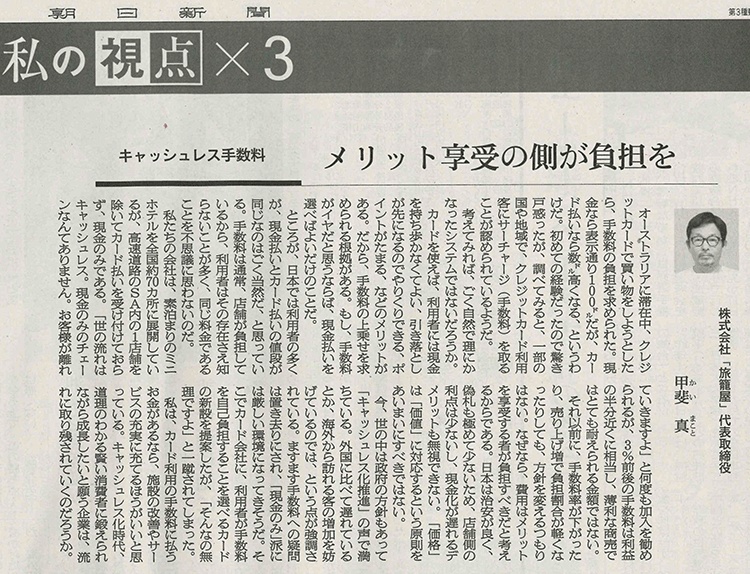
3年前、「民泊」についての意見が掲載されたことがあり、その後、「旅館業法」の改正に当社からの要望が反映される成果につなかった。
しかし、今回は何の反応もない。
「キャッシュレス化」の狙いのひとつは、地下経済の資金洗浄や脱税の防止にあるようだが、この点はあまり語られない。メディアもほとんど伝えない。
お金の使い方というプライバシー情報のかたまりが可視化されることへの気味悪さも問題視されることは少ない。
「自分は、人に知られて困ることはない。神経質になっているのはやましいことがある人でしょ?」なんて無邪気に構えている人ばかりなのか。
最初の原稿では、そんなことにも触れていたが、スペースの関係で削られてしまった。
みんな、なんとなく流されるだけで、ほんとにいいんですか?
- 2018.12.27 流れにもムードにも乗りません
-
2011年から寄稿している「月刊 ホテル旅館」の年頭所感、9年目となる今回は、以下のような原稿を寄せました。
年頭所感 「2019年の展望と課題」 流れにもムードにも乗りません
毎年同じような書き出しになりますが、日本にも、アメリカのMOTELのような車旅行者が誰でも気軽に利用できる宿泊施設をと願い、「ファミリーロッジ旅籠屋」をスタートさせてから24年、全国各地約70ヶ所で直営店を展開するに至りました。
昨夏は、西日本豪雨や台風の襲来、記録的猛暑や北海道地震などの影響で苦戦しましたが、秋以降は好調です。利用者も累計で延400万人を超え、日本初で唯一のMOTELチェーンとして少しずつ認知されるようになり、役所や業界の方とお会いする機会も増えてきました。その中で「ファミリーロッジ旅籠屋」の特徴やこだわりが鮮明になることがあります。
1番目は、リピーターの多さです。
60%以上が再利用なのですが、これは異常に高い数字のようです。お客様に気に入っていただいている証しなので、たいへん嬉しく誇らしく思うと同時に、日本におけるMOTELの潜在需要の大きさや確かさを示している数字だと受け止めています。すなわち、短期的な業績や社会の流れやムードに左右される必要はないし、そうすべきでもないということです。
2番目は、予約サイトへの依存率が15%未満ときわめて低いことです。
85%以上が直接予約なのです。10年ほど前、創業時からの「一物一価」のポリシーを曲げ、過渡的な措置としてOTAへの登録に踏み切りましたが、あえて手数料分を料金に上乗せしています。売上増ではなく、存在を知っていただくための広告と割り切っているからです。
3番目は、カードなどによる支払いを受付けず現金のみとしていることです。
チェーンホテルでは、とても珍しいことではないでしょうか。カード会社からは再三提案を受けますし、キャッシュレス社会の促進という政府の方針もあるようですが、変更の予定はありません。薄利な商売のため手数料によって利益の半分近くを失ってしまうという事情もありますが、そもそもこれは利便性を享受する利用者が負担すべきであり、店舗側が負担する契約に納得がいかないからです。日本では疑問視する人が少ないようですが、利用者負担としている国もあります。価値と価格の一致、サービスは有料という感覚を啓蒙普及させたいのです。2番目と同じです。
4番目は、需要の小さな地方の郊外への出店が多いことです。
これは12〜14室という規模だから可能なのですが、車社会のインフラ施設として全国に展開していくという目的実現のためには当然果たすべき社会的役割です。地域振興や地方創生が叫ばれて久しいのですが、一過性ではない活性化のためには、地元に根付く宿泊施設が必須です。赤字が続く店舗も複数ありますが、撤退するつもりはまったくありません。最近、地方の自治体からの出店要請が増えており、優先的に取り組んでいますが、これも嬉しく誇らしいことです。
5番目は、海外居住者の利用が1〜2%ととても少ないことです。
数年来、政府の方針もあってインバウンド客が急増し、これを狙って新しい施設を増やしたりサービスを強化することが業界の大きな流れになっていますが、当社はまったく消極的です。お客様を選ばないというのが当社のポリシーですから避けたりお断りすることはありませんが、海外向けの集客は行っていません。二人だけで運営しているため言葉が通じると誤解されては困ります。世界中で親しまれているMOTELですから、気軽にご利用いただく外国人も少なくないのですが、積極的に増やす考えはありません。インバウンドは社会情勢に大きく左右されるため安定経営には大きなリスクになりますし、そもそも急激な観光客の増加と依存は地域の文化や生活を破壊する恐れがあり、無条件に歓迎すべきことではないという問題意識があります。
6番目は、国籍・年齢・性別などの形式や学歴・職歴などにとらわれず、人間性本位で人生のパートナーのペアを支配人として採用し続けているということです。
これは、けっしてきれいごとではなく、容易なことでもありませんが、日本社会や日本人の「常識」に対する大きな挑戦です。
7番目は、収益性や効率の最大化を追求していないことです。
「シンプルで自由な、旅と暮らしをサポートする」というモットーに従い、お客様からの断片的な要望に引きづられてポリシーを曲げることはしません。売上高や利益優先ではなく、公正で透明で堅実な経営を大切にしたいのです。
創業以来ずっと不合理な規制や偏見に苦しめられ闘い続けてきました。要領よく許認可を得るのではなく、審議会の開催を求め、時には審査請求を行い、正面から議論を重ねてきました。その結果、旅館業法の改正に当社の主張が反映され、ある自治体では条例の見直しが行われました。こうした姿勢を失わないことこそ、ベンチャー企業の存在意義だと信じています。
2019年、当社は世の中の流れにもムードにも乗りません。
「社会的企業」の良き先例になることが、変わらぬ願いであり、覚悟です。
- 2018.12.06 自立から自律へ、自由への道
-
5か月も空いてしまった。
相変わらず、日々の仕事に追われて、気がついたら師走を迎えていたという感じ。
そんな中で、3つの雑誌から寄稿の依頼を受けた。
ありがたく、光栄なことだ。
以下に、そのひとつを転載させていただく。
公益社団法人日本道路協会が発行している月刊誌『道路』の「道」というテーマでの随想。
会社設立の頃からの歩みを「道」という言葉に託して振り返ってみた。
1月号に掲載される予定。
この雑誌には、2008年8月号の特集「高速道路における多様な展開」に 「ハイウェイホテルの存在意義とSA・PAの役割」というタイトルで寄稿させていただいたことがある。
ちょうど、「壇之浦PA店」と「佐野SA店」が実現した年。10年前のことだ。
その後、高速道路内には「宮島SA店」が加わったのみ。
全国のSA・PAに増やしていきたいのに、なかなかままならない。
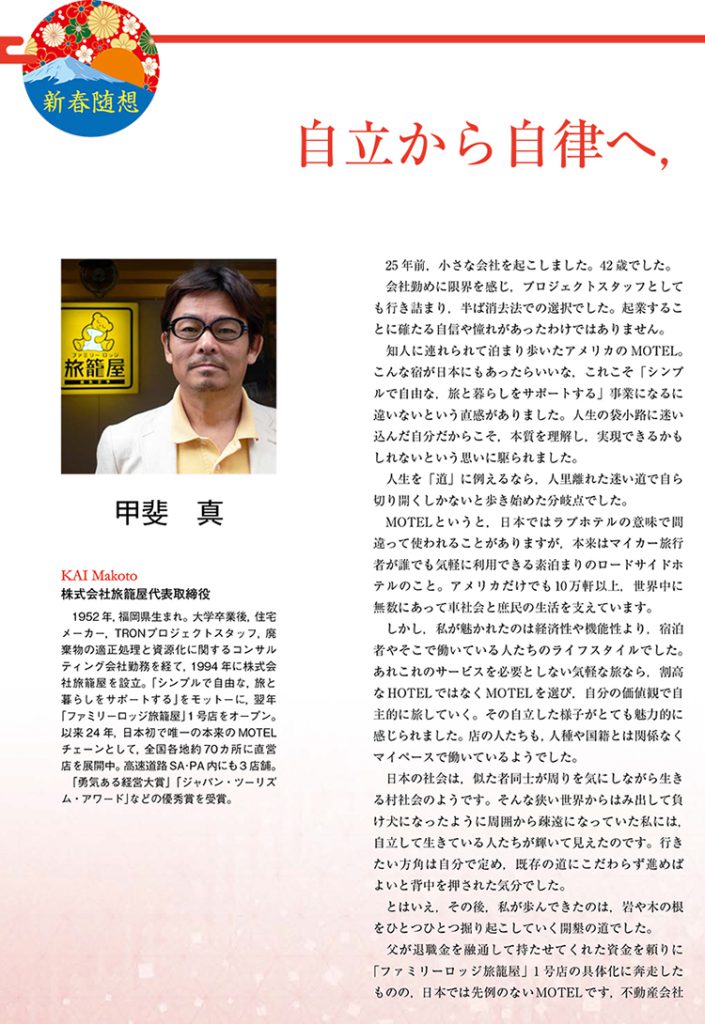
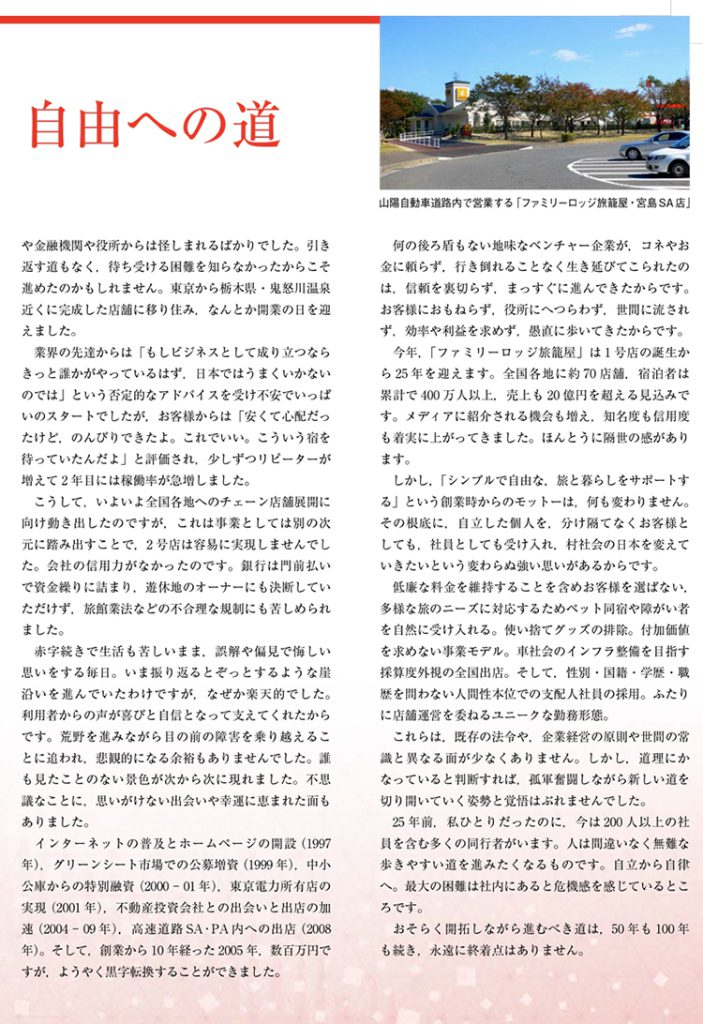
- 2018.07.15 観光客として、いつも思うこと
-
「井原店」と「函館店」のオープン準備にはさまれた今週、一足早い夏休みをとってクルーズ旅行に出かけた。
こんな忙しい時に、と自分でもいら立つが、去年申し込んだ時にはこんなタイミングになるとは思っていなかった。
キャンセルしようかという迷いもあったが、目的地が滅多に行けない小笠原なので、振り切った。

東京から1000kmも離れた絶海の孤島、世界自然遺産に指定された独特な生態系、白人などが先に住み着いたという特異な成り立ち、戦争、占領、返還を経てきた歴史。
好奇心が刺激され、一度はその場所に立って、自分なりに感じてみたいと思った。
あらかじめ情報処理されていない生の空気、バーチャルではけっして得られない。
五感のアンテナを伸ばし、感性で自らの心の反応を探る。これこそが旅の楽しみだ。

滞在は2日間。オプショナルツアーに参加して父島の森や浜辺を散策、固有の生物やその進化を解説してもらう。
青い海と常緑の山々の素晴らしい眺め、人間の身勝手と自然の深みを実感できて暑さを忘れた。
ところが、いつものことながら、ここで暮らすガイドさんへの興味の方がどんどん強くなる。
父島に住む彼女は、20年前にダイビングが好きで島に移り住み、ふたりの子供を育て、上のお嬢さんはこの春北九州の大学に進学したそうだ。
常々言っていることだが、日本の社会はレンジが狭くて、「普通」に生きていくことへの同調圧力が強い。
それが人一倍嫌いなくせに、同じように相手の「普通」からの距離を測って、納得しようとする俗物の自分がいる。
どうやって生計を立てているの? 「普通」の人生から外れることへの迷いや抵抗はなかったの? ご主人は? いつか島を離れて本土に戻るの?
根掘り葉掘り聞きたくなるが、それは彼女のプライベートなことで、観光客がそんな質問をするのは失礼だという良識は持ち合わせている。
でも、もし尋ねたとしても、すらすら答えてくれるか、話す必要のないことでしょときっぱり断るような毅然とした雰囲気が彼女にはあった。
海外のあちこちを訪ねるといつも、故郷を遠く離れて生きるガイドさんたちの人生を覗いてみたくなる。
訊かれることも多いのだろう。自分から面白おかしく話してくれる人もいる。
共通しているのは、そんな彼らがとても魅力的なことだ。
多分、日本人としての「普通」と違う生き方をしてきたことへの迷いや悩みが彼らを自覚的にし、人生を選び取っている意思や意志がそこにあるからだと思う。
私は、そういう人間にとても強いシンパシーを感じる。
仲間内のなれ合いに安住しようとする人を好きになれない。日本人にはそういう人が多すぎる。どんどん増えて劣化しているような気がする。
「旅籠屋」を起ち上げた思いの半分は、この辺りにある。
ところで、こんな仕事をしているが、私は旅マニアでも、旅の達人でもまったくない。
恵まれたことに、毎年のように数日は海外に出かけているが、ほとんどはガイドさんに頼る。
説明を聞かないと気づかないままに終わってしまうからだ。
もう一度若い頃に戻れたら、留学して、言葉を覚えて、暮らしてひとりひとりとコミュニケーションしたいと思うが、さすがにもう遅い。
だから、ある意味上っ面の観光旅行なのだが、それでも感じることは多い。
毎回のように気になるのは、ルームメイクに携わる人たちに出稼ぎや移民と思われる人々が多いこと。
なんとなく、嫌な感じがする。
人種差別の国に行って、自分が「名誉白人」として遇されているような居心地の悪さ。
チップを渡すのも、上から目線みたいで、気が引ける。
先進国だとその確率が高い。アメリカも、イギリスも、フランスも、ドイツも。
北欧にいくと違っていてほっとする。
浅草の近くに引っ越してきて、もう20年以上になるが、最近、どんどん外国人が増えている。
犬の散歩をしていてすれ違う人の半分以上は、日本人じゃない。誇張ではない。
この1年で、家の周りにインバウンド客向けのホステル、簡易宿所が3軒もオープンした。
東横INNやアパホテルから出てくる人も大きなスーツケースを引いている外国人が多い。
世界中の人たちが、自由に行き来できる平和で豊かな世の中は素晴らしい。
私も、もっともっと未知の国々に行ってみたい。
多少なりとも異文化体験と相互理解が深まることは、無知による誤解や恐怖のプロバガンダに抗する貴重なことだと思う。
でも、私は、度を越した、無遠慮な異邦人の襲来はけっして健全なことだと思わない。
そこに暮らしている人がマジョリティで、観光客はあくまでマイノリティであるべきだと思う。
ちょっとお邪魔します、という謙虚さとリスペクトが失われたら、観光は生活や文化やアイデンティティを破壊する。
これは、国内においても同じことだ。
こんな仕事をしていながら、私はいつもこんなバランス感覚にこだわっている。
インバウンドの波に乗ってひと稼ぎ、空き家になったワンルームマンションを民泊に活用、なんていう感覚は好きになれない。
ナイーブ過ぎると言われるかもしれないが、こんな感覚を失いたくない。
この数か月間、「カンブリア宮殿」というテレビ番組の取材を受けた。
数日後に放映される。ありがたいことだ。
だが、先日予告編を見たら、嫌な予感。
上に書いたようなことをたくさん話したのだが、またぞろ「ユニークで格安な宿」という紹介に終始するかもしれない。
そうでないことを願っている。
「旅籠屋」に込めた思いが、少しでも伝わればよいのだけれど。
- 2018.01.10 日本で唯一のMOTELチェーンとして
-
先日に続き、雑誌へ寄稿した文章の転載です。
週刊ホテルレストラン1/5〜12号に掲載されています。内容が一部かぶります。
顔写真が余計ですが、黒塗りするのもわざとらしいので恥ずかしながらそのまま。

- 2018.01.05 MOTELの社会的意義とは
-
年末年始の休みも終わり、本社はきょうから平常勤務。
店舗も順調に増え、おかげさまで稼働率も堅調(こちらのページで公開しています) だが、さすがに、役員を含め本社スタッフ15名では、人手不足。
昨年から、求人募集していますので、「我こそは」という方は、ぜひ会社説明会にいらしてください。数名採用の予定です。
さて、今年最初の日記は、「月刊 ホテル旅館」(柴田書店発行)に例年寄稿している原稿の転載です。
あらためて、日本における「MOTEL」ビジネスの意味について、考えてみました。
年頭所感 「2018年の展望と課題」 MOTELの社会的意義とは
日本にも、アメリカのMOTELのような車旅行者が誰でも気軽に利用できる宿泊施設をと願い、「ファミリーロッジ旅籠屋」をスタートさせてから23年、全国各地60ヶ所以上に直営店を展開できるようになりました。ここで、日本においてMOTELを普及展開することの意義について、あらためて振り返ってみたいと思います。
まず1番目に挙げられるのは、「車社会を支えるインフラ施設の整備」ということです。
気兼ねなく、好きな時に、好きな場所に行ける、これこそ車社会の価値なのですが、未だに宿泊施設は駅前や観光地に偏在しており、ロードサイドに目立つのはビジネスホテルばかりです。全国1000ヶ所以上に増えた「道の駅」にも宿泊施設は稀です。意外なことに、日本の車社会には必要不可欠のインフラ施設が欠落しており、車本来の利便性が発揮されていないのです。
ちなみに「ファミリーロッジ旅籠屋」のうち3店舗は高速道路のSA・PA内にあるのですが、その意味は小さくありません。途中で泊まることによって安心して長距離離ドライブを楽しめるようになりますし、これまで早く目的地に着くための通過路に過ぎなかった高速道路が地域への結節点として機能できるようになります。
意義の2番目は、「周辺地域への貢献」です。
MOTELは基本的に宿泊特化ですから、宿泊客は周辺で食事・買い物・観光を楽しんだり、仕事をしたりします。つまり、宿以外でお金を使います。
また、宿に付加価値がないため、集客のためには地域の魅力を自力で宣伝することになります。放置されていた土地が活用され、長期間安定した利益を生む存在に変わるという面もあります。
地域振興や地方創生が叫ばれて久しいのですが、一過性ではない活性化のためには、地元に根付く宿泊施設が必須なのです。「ファミリーロッジ旅籠屋」は12〜14室と小規模のため、需要の小さな町や村にも出店できます。目立って増えている自治体からのお誘いに優先的に応えていきたいと考えています。
3番目はちょっと抽象的なのですが、MOTELは「自由で自立した旅を提案する」存在であるということです。
我々日本人は周囲の評価に流されたり、事前の計画をなぞるだけの旅をする傾向があります。自分なりに時間を楽しみ、価値と価格を賢く選択する旅、アメリカのMOTELで痛感するのはそうした自由で自立した感覚です。
日本にMOTELが普及していくことは、素泊まりで何のサービスもない安価な宿が増えるという表面的なことではありません。自由で自立した旅を楽しむ感性や価値観を提案し、サポートし、醸成していくことに隠れた意味があると思います。
4番目は、「日本では珍しいユニークな就労機会を提供する」存在であるということです。
MOTELは一般庶民の宿であり、そこで働く人たちも上昇志向にとらわれたエリートではありません。田舎の寂れたMOTELでマイペースで暮らしを営むたくさんの人たちの姿に都会とは違うアメリカを見ました。
現在、当社には200人を超える社員がいます。そのほとんどは全国に散在する店舗の支配人たちです。ふたり一組の正社員に運営業務のすべてを任せます。分け隔てなく多様なお客様を受け入れるというのと同様、社員も国籍・年齢・性別などの形式、あるいは学歴・職歴など過去にとらわれず、採用してきました。別姓やLGBTの方々も同様です。これは、けっしてきれいごとではなく、容易なことでもありません、日本社会や日本人の「常識」に対する大きな挑戦なのです。
5番目は、MOTELが日本では先例のない業態のビジネスだということに起因するのですが、「不合理な規制などへの問題提起を行わざるを得ない存在」であるということです。
ここ数年、「民泊」の急増と合法化が注目を集めていますが、旅館業法やラブホテル抑制条例の過剰規制は放置されたままです。当社では業界団体を通して要望書を提出したり、厚生労働省・生活衛生課を訪ねて直接意見交換を行ったりしました。こうした営業規制だけでなく、市街化調整区域で宿泊施設が建てられないなどの建築規制や、就労形態に関する問題もあります。時代遅れで不合理な規制は、事なかれ主義・先例主義、業界に対する予断偏見を含め、改めていかなければなりません。ベンチャービジネスを切り拓く者は、直面する障害から逃げず、正面からチャレンジし続ける点にこそ存在意義があるはずです。
宿泊業界は、インバウンド客の増加で沸いていますが、構造不況業種として苦しんだ歴史を繰り返さないか大きな不安を感じています。観光客に過度に依存することが健全なことなのかという根本的な疑問もあります。「ファミリーロッジ旅籠屋」の場合、海外在住者の割合は1%にも達しません。そんなものに頼らずとも、宿泊施設の果たすべき役割はもっと本質的で、可能性は大きいと考えるのですが、いかがでしょうか。
- 2017.12.27 ネットで出会った言葉たち その4 (偉人たちの残した言葉)
-
1年ぶりに日記が更新されたら、今度は立て続け、と言われてしまったが、4日連続できょうも。
「ネットで出会った言葉たち」の最後は、有名人の残した言葉です。
クラーク博士の別れの言葉
Bots, be ambitious Like this old man! Be ambitious not for money or for selfish aggrandizement, not for that evanescent thing which men call fame, Be ambicious for the attainment of all a man ought to be.
少年よ、この老人のように大志を抱け!
金や私欲のためではなく、名声などと呼ばれる空しいものでもなく、人間として当然持つべきもののために大志を抱け。
「少年よ、大志を抱け!」という言葉は、広く知られているが、 これは明治9年に札幌農学校(現在の北海道大学の前身) に教頭として招かれた
クラーク博士が9ヶ月間の滞在を終えてアメリカに帰国する際に残した言葉とされている。
「大志を抱け!」に続く言葉があったらしいということで、紹介してみました。
なんにせよ、当時は教える人間にも、教わる人間たちにも、熱い思いがあったのですね。
こういうの、大好きです。
吉田茂の防衛大一期生卒業式での訓辞
君達は自衛隊在職中、決して国民から感謝されたり、歓迎されることなく自衛隊を終わるかもしれない。
きっと非難とか叱咤ばかりの一生かもしれない。御苦労だと思う。
しかし、自衛隊が国民から歓迎されちやほやされる事態とは、外国から攻撃されて国家存亡の時とか、災害派遣の時とか、国民が困窮し国家が混乱に直面している時だけなのだ。
言葉を換えれば、君達が日陰者である時のほうが、国民や日本は幸せなのだ。
どうか、耐えてもらいたい。
若い人たちのためにあえて解説するが、吉田茂は、昭和20年代の首相であり、敗戦後の日本の針路を定めた人物としてあまりにも有名な人物だ。
ちなみに元首相で現財務大臣の麻生太郎は孫にあたる。
1957年(昭和32年)2月、卒業式での訓示として知られていますが、実際は、一部の卒業生を自宅に招いて語った言葉というのが事実のようです。
いずれにしても、含蓄のある、リーダーらしい言葉として、心に響きました。
田中正造の言葉
いにしえの治水は地勢による。
あたかも山水の画を見るごとし。
しかるに今の治水はこれに反し、定規をもって経(たて)の筋を引くごとし。
山にも岡にもとんちゃくなく、真直に直角につくる。
治水は造るものにあらず。
我々はただ山を愛し、川を愛するのみ。
いわんや人類をや。
これ治水の大要なり。
真の文明は山を荒さず、川を荒さず、村を破らず、人を殺さざるべし。
田中正造は足尾銅山からの鉱毒に苦しむ人々を守るために命がけの活動を行った明治時代の政治家。
明治天皇へ直訴したことでも有名。
彼のすばらしい言葉です。
- 2017.12.26 ネットで出会った言葉たち その3 (差別と多様性について)
-
何度も書いてきたことですが、私は「BLUES」が好きです。
中学生の頃、ビートルズにはまってロック少年になり、そこからルーツであるブルースに出会ったという流れです。
メロディやリズムも、それまで耳にしていた西洋音楽とは何もかもが異質でショックを受けました。
大げさに言うと、それまでの常識が根底からひっくり返されたような衝撃でした。
正直言って背伸びする感覚もあったのですが、本物のリアリティがあるような気がしました。
しかし、そんな付随的なことはともかく感性に響くものがあったわけで、今も「BLUES」が聞こえてくると心が震えてきます。
そんな音楽に出会えたことは幸せなことです。
残念なことですが、あの頃から50年が経って、もはや狭い意味での「BLUES」は現役の音楽ではなくなってしまいました。
しかし、ごく一部の民俗音楽や伝統音楽を除いて、世界中の音楽のほとんどが「BLUES」の洗礼を受けているように感じます。
もちろん、「BLUES」という音楽は、アメリカの黒人たちの生活の中から生まれたものです。
アフリカから奴隷として拉致され、アメリカの田舎にバラバラに連れて来られた黒人たちが、他の色々な音楽に触れる中でなんとなく生まれてきた音階やリズムや形式が、わずか100年前後で世界中に影響を与える存在になったとは、驚くべきことです。
そんなこんなで、私は、「BLUES」を通して、アメリカの黒人たちに興味を抱き、
驚いたり、あこがれたり、尊敬したり、軽蔑したり、あきれたりしてきました。
ですから、こんな書き込みには反応してしまいます。
続・ももクロとラッツ&スターに捧ぐ:黒人であることが何を意味するか (引用元)
それが意味するのは……いつも目立ってしまうこと(異質だから)。
自分の価値を証明し続けなければならないこと。
個人なのに、黒人という民族全体の代表例と見なされること。
良い部分は喰い物にされ、悪い部分が少しでもあれば貶められること。
誤解されること、信用されないこと。
対等には扱われないこと。
生命が軽視されること。
この日本人ミュージシャンの意図は理解できるが、それでも無礼で無神経だ。
いかに黒人が搾取されるか、いかに他人種が黒人の功績から不当な利益を得るか、の一例に過ぎない。
かつては、白人が顔を黒塗りし、黒人を題材に笑いを取るショーをやっていた。
こうしたショーは、黒人に対する差別や先入観を助長し、ネガティブな黒人像を残した。
そのステレオタイプは、今も健在だ。
黒人文化は、いつもビュッフェのように扱われる。
まるで、気に入ったものだけアップして、残りは無視していいかのように。
黒人には、他人種が信じているようなステレオタイプ以外のあり方が許されないかのように。
件の日本人アーティストがやっていることは、我々への賞賛に見えるかもしれない。
しかし実際には黒人の人間性を奪うものだ。
商品化され、パッケージとして売られる黒人文化。それは悪である。
それによって、我々黒人の存在自体は軽んじられるのだから。
ミンストレルショーのことですね。
「黒人音楽に対する敬意を表しているのだから問題視するほうがおかしい」という意見もあるようですが、それは「差別される人たち」への想像力に欠けているというしかないと思います。
メガネをかけ、出っ歯で、ニヤニヤ笑っている小柄な人間が、カメラを提げて登場するシーンを何度も見たことがあります。
金髪のカツラをかぶり、顔を白く塗った人たちが笑いをとるシーンを見たことはありません。
さらに、率直かつ具体的に述べられているのが、以下の文章です。
在日黒人男性から日本人へのオープンレター (引用元)
日本人の方々へ
私達に暖かく、優しく接してくださり感謝しています。礼儀正しく、自制に重きを置く日本の文化を、私達は尊敬しています。
おバカ、無神経、ナルシスト、イヤな奴…などなど、欠点も少なくない我々外国人男性ですが、私達にも不平不満はあります。
あなた方が自分の行動の影響に無知だと知っているからこそ言わなかったり、あなた方との友情を壊したくないから言えなかったりすることです。
これは、私達黒人が経験するいらだちや不平を並べたリストです。
もちろんあなた達がわざと、悪い意図を持って行っている行為ではないと分かっていますが、極力避けてほしいことです。
1. 人と違うことや、友人とくらべて個性的でありたいがために黒人と友達になったり、恋人関係にならないこと。
2. 英語を教わるために黒人と友達になったり恋人関係にならないこと。仕事として「学校」という場所で英語を教えているプロもいるのです。
3. オバマやボビー、その他あなたが片手で数えられる位しか知らない黒人有名人に似ていると言わないこと。似ていない場合がほとんどです。
4. 黒人が大好きだと訴えてこないこと。黒人の行動や見た目が好きなだけで、黒人自身を好きな訳ではないのでしょう。
不快な気持ちになります。あなたの目の前に立っている人と、その人の性格と向き合ってください。皆それぞれ違うんだから。
5. 黒人だから良い体型だねとか、強いと言わないこと。この体を作り上げた私の甚大な努力を無碍(むげ)にしないでください。
あなたも努力したら、違う発言になるかもしれませんよ。
6. 褒めるときに「黒人/外国人だから」と付け足さないこと。説明する程のことでしょうか?
7. 私がマリファナや他の違法ドラッグを好きか、あるいは所持しているか聞かないこと。
黒人が違法ドラッグを所持していたり、他の違法行為に及んでいると決めつけるのは人種差別です。
母国でも、白人の子供や警察、セキュリティガード達に同じ質問をされますが、かなり不名誉でストレスが貯まる経験です。
何千マイルも離れたこの地で同じことを経験するとは!
8. 黒人になりたいと言わないこと。褒め言葉ではありません。
あなたは黒人ではないし、黒人には一生なれないし、しかも黒人になりたい理由がおバカで子供っぽいことが多い。
黒人は、内なるリズムやスピリチュアリティを持って生まれた特別な人間ではありません。お願いですから自分のことを愛してください。
9. 自分の人種をおとしめて黒人を褒めないこと。
10. 聞く前から私達の髪の毛をさわらないこと。私達は動物ではありません。
11. 自分の人種をけなしながら黒人男性や女性の体を褒めないこと。気持ち悪いです。自分のことを愛してください。
12. 黒人を魅了するために黒人の女性をマネしないこと。黒人の女性が好みだったら、そもそもあなたを選びません。
13. ラップできると決めつけないこと。黒人皆に同じ才能がある訳ではありません。
14. バスケットボールがうまいと決めつけないこと。理由は上記。
15. ダンスがうまいと決めつけないこと。理由は上記。
16. 黒人や黒人の体のフェチにならないこと。それはモノ扱いだし、人種差別です。黒人はモノではなく、人です。
17. あなた方が「ブラックカルチャー」や「B系」と呼ぶものは、黒人文化のごく一部です。他の名前をつけた方がいいかもしれませんね。
世界中の黒人の過半数は、それらと関わりがない生活を送っています。
18. 友達にいいよと言われても、ニガーと言わないこと。ダメなものはダメ。ある日、大変なことになりますよ。
19. 黒人の見た目や肌の色で国籍を決めつけないこと(アメリカ、ジャマイカ、アフリカしか知らないようですが)。
黒人は世界中どこにでもいます。
20. 好みのタイプが黒人は皆同じだと決めつけないこと。
21. 黒人は貧乏だと決めつけないこと。あなたが無知なだけ。テレビを消して。
22. アフリカ人は皆飢餓で苦しみ、救いを求めていると決めつけないこと。あなたが無知なだけ。
23. 黒人は全員、異性愛者だと決めつけないこと。
24. 黒人はセックス好きと決めつけないこと。テレビを消して。
25. 黒人は強姦魔と決めつけないこと。テレビを消してください。
26. 他の人とくらべて黒人はHIVや他の性感染症や病気を持っている可能性が高いと決めつけないこと。
本当にお願いだからテレビを消してくれ!
27. 公共浴場で黒人のペニスをジロジロ見ないでください。何も見るものはありません。
28. 黒人は皆ペニスが大きいと決めつけないこと。ガッカリしますよ。
29. 「試してみたい」「どんな感じか知りたい」ために黒人と付き合わないこと。
流行ファッションみたいに、飽きたらポイっと捨てて新しいモノへ走るのはわかっています。
30. アフリカを国とみなしたり、アフリカ大陸と国との対比をしないこと(例:アフリカと日本の対比など)。
アフリカ大陸には54ヵ国と2000以上の民族と言語が存在します。あなたが無知なだけ。
31. 黒人と繋がるために「Dope(ドープ)」「Swag(スワグ)」「Gangsta(ギャングスタ)」等の言葉を使わないこと。
黒人全員がその言葉を理解するわけでも、同じ言葉を喋るわけではありません。
32. 音楽の趣味を決めつけないこと。黒人全員がヒップホップ、R&Bやレゲエを好きなわけではありません。
33. 単一的な「黒人」の見た目はありません。肌の色も体の部位も多様です。
34. あなたが黒人に似せるためにブレイズをしたり、アフロやスパイラルにしたり、頭におしゃれな布を巻いたりしても、
黒人に似ているとは思いません。
35. 黒人の唇、肌の色、髪の毛やその他 黒人の体の部位をネタにして笑わないでこと。
失礼だし、究極にガキです。しかも、あなたがどれだけ世界のことに無知か知らしめているだけですよ。
36. 黒人の肌の色をチョコレートやその他の黒っぽいモノに例えないこと。 ?
これは攻撃ではなく、あなた方と私達がもっとお互いを理解し、友情を深めるための情報です。
私達が過剰に反応しているのではなく、これは、黒人がずっと否定されてきた部分を尊重してもらうためのものなのです。
私達の多くは、これらを経験して気分を害しても、これが普通だと受け入れるしかないのです。
上記の多く(そしてもっと酷い場合も多い)は、黒人が少数派である国や人種差別がはびこる国でも同じように経験されているものです。
日本の方々、この情報を黒人の知人がいる人や、「ブラックカルチャー」に没頭している友人にシェアしてください。
「アプリシエーション(感謝)」と「アプロプリエーション(私有化)」の違い、「愛」と「フェチ」の違いを理解してください。
ダイバーシティとか、多様性ということが言われます。
耳ざわりの良い言葉かもしれませんが、立ち止まって、自分の心の中をじっくりと覗いてみる必要があります。
自分と違う人に対して違和感や警戒心を抱くのは自然な反応です。誰でも、アイデンティティを保てなければ、心のバランスを失ってしまいます。
それを防いでいるのが、ある種の共通の価値観を持つ集団に帰属しているという安心感なのだと思います。
ですから、我々は排他的な感情から逃れられません。差別意識を持たない人などいない、私はそう考えています。
でも一方で、差別されるのもイヤだし、差別する人間でもいたくないと心底思います。
こうした矛盾をどう消化すれば良いのか。そんな時に出会ったのが、以下の文章です。
ある質問に対する答えとしてネット上に書き込まれたものです。心を打たれました。
弱者を抹殺する。 (引用元)
不謹慎な質問ですが、疑問に思ったのでお答え頂ければと思います。
自然界では弱肉強食という単語通り、弱い者が強い者に捕食される。でも人間の社会では何故それが行われないのでしょうか?
文明が開かれた頃は、種族同士の争いが行われ、弱い者は殺されて行きました。
ですが、今日の社会では弱者を税金だのなんだので、生かしてます。
優れた遺伝子が生き残るのが自然の摂理ではないのですか。今の人間社会は理に適ってないのではないでしょうか。
人権などの話を出すのは今回はお控え頂ければと思います。
え〜っと、、、よくある勘違いなんですが、自然界は「弱肉強食」ではありません。
弱いからといって喰われるとは限らないし、強いからといって食えるとも限りません。
虎は兎より掛け値なしに強いですが、兎は世界中で繁栄し、虎は絶滅の危機に瀕しています。自然界の掟は、個体レベルでは「全肉全食」で、種レベルでは「適者生存」です。
個体レベルでは、最終的に全ての個体が「喰われ」ます。全ての個体は、多少の寿命の差こそあれ、必ず死にます。
個体間の寿命の違いは、自然界全体で観れば意味はありません。
ある犬が2年生き、別の犬が10年生きたとしても、それはほとんど大した違いは無く、どっちでもいいことです。
種レベルでは「適者生存」です。
この言葉は誤解されて広まってますが、決して「弱肉強食」の意味ではありません。
「強い者」が残るのではなく、「適した者」が残るんです(「残る」という意味が、「個体が生き延びる」という意味で無く「遺伝子が次世代に受け継がれる」の意味であることに注意)。
そして自然というものの特徴は、「無限と言っていいほどの環境適応のやり方がある」ということです。
必ずしも活発なものが残るとは限らず、ナマケモノや深海生物のように極端に代謝を落とした生存戦略もあります。
多産なもの少産なもの、速いもの遅いもの、強いもの弱いもの、大きいもの小さいもの、、、、
あらゆる形態の生物が存在することは御存じの通り。「適応」してさえいれば、強かろうが弱かろうが関係無いんです。
そして「適者生存」の意味が、「個体が生き延びる」という意味で無く「遺伝子が次世代に受け継がれる」の意味である以上、ある特定の個体が外敵に喰われようがどうしようが関係ないんです。
10年生き延びて子を1匹しか生まなかった個体と、1年しか生きられなかったが子を10匹生んだ個体とでは、後者の方がより「適者」として「生存」したことになります。
「生存」が「子孫を残すこと」であり、「適応」の仕方が無数に可能性のあるものである以上、どのように「適応」するかはその生物の生存戦略次第ということになります。
人間の生存戦略は、、、、「社会性」。
高度に機能的な社会を作り、その互助作用でもって個体を保護する。
個別的には長期の生存が不可能な個体(=つまり、質問主さんがおっしゃる”弱者”です)も生き延びさせることで、子孫の繁栄の可能性を最大化する、、、、という戦略です。
どれだけの個体が生き延びられるか、どの程度の”弱者”を生かすことが出来るかは、その社会の持つ力に比例します。
人類は文明を発展させることで、前時代では生かすことが出来なかった個体も生かすことができるようになりました。
生物の生存戦略としては大成功でしょう。
(生物が子孫を増やすのは本源的なものであり、そのこと自体の価値を問うてもそれは無意味です。「こんなに数を増やす必要があるのか?」という疑問は、自然界に立脚して論ずる限り意味を成しません)
「優秀な遺伝子」ってものは無いんですよ。
あるのは「ある特定の環境において、有効であるかもしれない遺伝子」です。遺伝子によって発現されるどういう”形質”が、どういう環境で生存に有利に働くかは計算不可能です。
例えば、現代社会の人類にとって「障害」としかみなされない形質も、将来は「有効な形質」になってるかもしれません。
だから、可能であるならばできる限り多くのパターンの「障害(=つまるところ形質的イレギュラーですが)」を抱えておく方が、生存戦略上の「保険」となるんです。
(「生まれつき目が見えないことが、どういう状況で有利になるのか?」という質問をしないでくださいね。それこそ誰にも読めないことなんです。
自然とは、無数の可能性の塊であって、全てを計算しきるのは神ならぬ人間には不可能ですから)
アマゾンのジャングルに一人で放置されて生き延びられる現代人はいませんね。
ということは、「社会」というものが無い生の自然状態に置かれるなら、人間は全員「弱者」だということです。
その「弱者」たちが集まって、出来るだけ多くの「弱者」を生かすようにしたのが人間の生存戦略なんです。
だから社会科学では、「闘争」も「協働」も人間社会の構成要素だが、どちらがより「人間社会」の本質かといえば「協働」である、
と答えるんです。
「闘争」がどれほど活発化しようが、最後は「協働」しないと人間は生き延びられないからです。
我々全員が「弱者」であり、「弱者」を生かすのがホモ・サピエンスの生存戦略だということです。- 2017.12.25 ネットで出会った言葉たち その2 (人間関係について)
-
「犬」から一転して、仕事がらみで目に留まった言葉をいくつかご紹介します。
ビジネス本にあふれているような、なんともベタな文章ですが、日頃気にしていることなので見過ごせなかったのです。
すれ違う部下と上司 (引用元)
部下のせいにする上司、上司のせいにする部下
わかってくれていると思う上司、わかって欲しいと思う部下
任せていると考える上司、押しつけられたと捉える部下
自分で考えて欲しい上司、具体的に教えて欲しい部下
叱っているつもりの上司、怒られているつもりの部下
うまくいっていると満足な上司、不満がたまっている部下
相手を責めても何も変わらない、どちらが先でもいいから歩み寄る
ボスとリーダーの違い (引用元)・ボスは部下を追い立てる。
・ボスは権威に頼る。
・ボスは恐怖を吹き込む。
・ボスは私という。
・ボスは時間通りに来いと言う。
・ボスは失敗の責任を負わせる。
・ボスはやり方を胸に秘める。
・ボスは仕事を苦役に変える。
・ボスはやれと言う。→ リーダーは人を導く。
→ リーダーは志、善意に頼る。
→ リーダーは熱意を吹き込む。
→ リーダーはわれわれという。
→ リーダーは時間前にやってくる。
→ リーダーは黙って失敗を処理する。
→ リーダーはやり方を具体的に教える。
→ リーダーは仕事をゲームに変える。
→ リーダーはやろうと言う。
山本 五十六 の言葉
やって見せ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば、人は動かじ
話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず
やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず
元は江戸時代の米沢藩藩主・上杉鷹山の言葉をを改変したものらしいと付記されていました。
以上、いずれの文章も、上司だからといって、頭ごなしに命令したり、怒鳴ったりしてはダメだということを言っているわけですが、「新聞でよく見かけるきれいごとの正論だよ」という気もします。
当事者意識の低い、自分で考えない指示待ちの人間に対して、いつも我慢強く、待ち続けるというわけにもいきません。時には無性に苛立ってしまうのです。 そんなジレンマを抱えている時に見かけたのが、次の言葉です。
あるところに、すぐに怒り出してしまう少年がいました。
父親は彼に釘の入った袋を渡し、怒りが爆発するたびに柵の裏側に釘を打ち付けるように言いました。
初日の終わりには、少年は37本の釘を柵に打ち付けていました。
それから数週間、少年は自分が怒る瞬間を気に留めるようになり、打ち付ける釘の数は少なくなっていきました。
やがて少年は、柵に釘を打ち付けるよりも怒りを制御する方が簡単だということに気付きます。
そしてついに、少年が一度も怒らなかった日がやってきました。
そのことを父親に告げると、これからは怒り出さないよう自分を無事制御できた日に釘を引き抜いていってはどうかと言われました。
月日が経ち、ある日少年は釘を全部抜いたことを父親に伝えました。
父親は息子の手を引いて柵に連れて行きました。
父親は言いました。
よくやった。でも、柵に空いた穴を見てごらん。柵はもう二度と元通りにはならない。
憎しみに溢れた言葉を使うと、その言葉はこんな風に傷を残す。
相手の心を刃で突き刺して、引き抜くようなものなんだ。
どんなに謝ったって、その傷は消えない。
言葉には力がある。覚えておきなさい。
何かを言ってしまったとき、それは許されるかもしれない。
でも、忘れられはしない。
これは、仕事に限らず、すべての人間関係でも言えることかもしれません。反省。
最後に、「働かされる側?」からの言葉。
アメリカにおけるファストフードの位置づけと、そこで働く人たちの心情が率直に表現されており、なるほど、と思いました。
マクドナルドで4年間働いてわかったこと (引用元)
18歳から22歳までの4年間、私はマクドナルドで働いた。
もっといい仕事を見つけられなかったので、パートタイムとフルタイムで働き続けた。昇進もせずマネージャーにもならなかった。
大きなことを成し遂げたりもしなかった。
基本的に、私は典型的な怠け者のマクドナルド労働者だった。いいかげんで、愚かで、自発的に働こうなんて考えもしなかった。
マクドナルドで働いている人は怠け者、と世の中の人たちも思っていることも実感した。
マクドナルドで働いているんだと伝えると、両親や友達はがっかりした。「まだ、マクドナルドで働いているの?」「私だったら、絶対にあんな所で働かない」といった遠回しな批判や、「今日は仕事に行くのやめなよ(そんなの本物の仕事じゃないじゃない)!」といった彼らなりの励ましから、その事がわかった。
私自身も心の中で同じ様に思っていた。私はひどい労働者だった。動きは遅いし、不器用だし、自分の置かれた状況に腹を立てていた。マクドナルドで働くには、自分は優秀すぎると密かに思っていた。「こんな仕事、本当にくだらない! お金のために仕方なくやっているだけ」といつも自分を正当化していた。読書好きで優秀、知的な会話を楽しむ学生の私は、こんな意味のない肉体労働には向いてないと思っていた。
仕事は一向に上達しなかった。上達したくもなかった。
自分にとって何の意味をない仕事を、わざわざ努力して上達する必要なんてないでしょう?
でも数年が過ぎた頃、私の態度は変わり始めた。
自分の仕事にプライドを持ち始めたのだ。
マクドナルドの仕事は最悪でうんざりする。でも私自身や、友達、家族がマクドナルドで働くことに屈辱を感じていたのは、ハンバーガーを作るのが原因ではなかった。そうじゃなくて、それよりもっといい仕事に就けたはずだったから。
こう自問自答した。マクドナルドと他の仕事は何が違うのだろう? 自分の仕事はなぜ他の仕事よりずっと哀れに思われるんだろう?
大企業だから? そうじゃない。もしそうだったらスターバックスや(ディスカウント百貨店の)ターゲットで働くのだって恥ずかしいはず。
悪質企業っていわれているから? だけどH&MやGapも奴隷労働を批判されているでしょ。
ファストフードだから? でもチポトレ(メキシコ料理のファストフード・チェーン)の仕事には悪い印象はない。
知的な仕事じゃないから? いやいや、小売や受付の仕事は問題ないでしょ。
そして私は気が付いた。
マクドナルドは、他に何もできない人にとっての仕事なんだ。初心者レベルの仕事の採用ですら、私がマクドナルドで一緒に働いてきたような人たちを雇っていない。
マクドナルドでは、障害を持った人、太り過ぎの人、生まれつき魅力的とはいえないような人、英語をあまり喋れない人、十代初めの人、それに多様な人種の人たちが働いていた。彼らがマクドナルドを支えており、最も仕事ができる労働者として尊敬されていた。
これがスターバックスだったら、大半の労働者が私のような人だろう。20代前半の白人、そこそこ魅力的、スリムで英語を話す。
これが、私と私の周りにいる人たちがマクドナルドに対して持っていた偏見だった。
アパレルの仕事をすれば「良い」仕事に就いていることになる。
きちんとした環境で育った人は、努力しても仕事ができないような人たちとマクドナルドで一緒に働いたりはしない。
もしあなたが20代前半の白人女性だったら、マクドナルドで働いたら馬鹿にされる。でも障害を持った人や移民の中年女性にも同じことが当てはまるとは思えない。友達から「いつになったら、本当の仕事に就くの?」なんて笑われたりしない。マクドナルドこそが、彼らにとっての仕事だと私たちは思っているから。
マクドナルドの仕事は最悪でうんざりする。でも私自身や、友達、家族がマクドナルドで働くことに屈辱を感じていたのは、ハンバーガーを作るのが原因ではなかった。そうじゃなくて、それよりもっといい仕事に就けたはずだったから。マクドナルドで一緒に働いていた人たちより、もっと知的で、一生懸命働き、有能なはずだったからだ。「私にはもっとふさわしい仕事がある」。恵まれた環境で育った私は、そんな思い上がった気持ちを持っていた。
小売店で働いたり、受付係としてファイルを整理しているから、自分はマクドナルドで働いている人たちより優秀だと考えているなら、それは間違いだ。
そして私は気が付いた。こんな態度はフライドポテトをすくうよりも最悪だ。私はマクドナルドで働いている人たちより優秀じゃない。
確かに私は、彼らとは違うスキルを持っているかもしれない。私は筋力があるほうではないし、プレッシャーを感じると慌てることもある。だから肉体労働よりデスクワークの方が力を発揮できる。だからといって、マクドナルドの凄い従業員たちより、知的でスキルがあって価値があるということにはならない。
世の中には色々な仕事がある。社会で過小評価されている人たちが就いている仕事は、価値がないものに見られがちだけれど、それは違う。
真夜中にハンバーガーを買いにくるお客さんのために、時には20時間働く同僚ほど私はハードワーカーではない。
マネージャーからエンジニアにも早変わりする同僚ほど賢くもない。全ての機械の修理の仕方を学んだ彼は、壊れても修理を呼ばずに自分で直してしまう。
一週間に何千人のお客さんが来るかを予測して、材料を注文する人たちほどの計画性もない。もし失敗すれば上司から大目玉を食らうだけでは済まないということを、彼らは知っている。
ケチャップがないというだけで大声を上げたり、ドリンクを投げつけたり、人種差別的な中傷をするお客さんたちもいる。そんな人たちに対処できるほど忍耐強くもない。
これら全てが仕事のスキルなのだ。
小売店で働いたり、受付係としてファイルを整理しているから、自分はマクドナルドで働いている人たちより優秀だと考えているなら、それは間違いだ。
私にとって、マクドナルドで過ごした時間はとても貴重なものだった。
またフライドポテトをすくったり、ハンバーガーを作りたいとは全く思わない。でもそれ以上に大切な何かを学んだ。自分の横柄さを少しずつ減らし始めた。就いている仕事で人の善し悪しを判断することに疑問を持ち始めた。不愉快な大企業で働いているからといって、そこで働く労働者たちにも嫌悪感を抱くのを止めた。そして他人にもっと共感できるようになった。
マクドナルドで働いたことが履歴書の汚点になる?
私はそうは思わない。
- 2017.12.22 ネットで出会った言葉たち その1 (犬について)
-
私は、新聞を読む人である。
7年前にも書いたことだが、皆さん、「新聞を読もう!」
そんな私でも、半分はネット中毒で、暇さえあれば、その世界をウロウロしている。
所詮、刹那的な好奇心を満たすだけの行為で、断片的なガラクタ情報なのだが、時にはハッとするような珠玉の言葉や文章に出会うこともある。
何回かに分けて、そのいくつかを紹介させていただこうと思います。
まったくもって、私の感性が裸にされてしまうようで恥ずかしかったりしますが、ご賞味ください。
まずは、私が愛してやまない「犬」に関するアレコレから。
大好きなジェシーへ (引用元)
君と家族になった日、僕は「永遠に生きてくれ」と言った。
その後も僕は、君がいなくなってしまうことが怖くて長年この言葉を囁いていたね。
僕の体は、今でも君を散歩に連れていきたくて仕方ないんだ。
玄関に置いてある君のリードも、「散歩に行こうよ!」って語りかけてくる。
今週は雨がずっと降っていたけど、雨が降りやむとつい君の散歩の時間を確認してしまったよ。
それに、クラッカーやポテトチップスを食べる度に、もういない君を探してしまうんだ。
とても静かで、穏やかな性格…。君は、僕にとって最高の犬だった。
変なところにオシッコしたり、誰かに噛みついたことは一度もなかったよね。
普段はまったく吠えないから、たまに吠えると自分の声にビックリするのは面白かったよ。
君は、僕が幸せな時もつらい時もずっと一緒にいてくれた。僕のことをいつも信頼してくれていた。
僕の体重が90kgになってダイエットに励んでいた時も、傍で尻尾を振ってくれていたね。
君は大人しいから、子どもたちがいる場所でも安心できたよ。
老犬になって白髪が増えると、子どもたちから「おばあちゃん」って呼ばれてたよね。
固い食べ物が食べられなくなって、オモチャで遊ぶことができなくなっても、僕は君が大好きだった。
君は最後の瞬間まで、こんな僕を心から信頼してくれたね。
「ごめんよ、永遠になんて生きなくていい。もう楽になってもいいんだよ」って言った僕の言葉にも頷いてくれた。
なんだか、僕の心も君の命と一緒にどこかへ行ってしまった気分だ。
ジェシー、本当に大好きだよ。僕がいつか君のもとへ行く時まで、空の上で待っていてね。
18年間一緒だった愛犬に先立たれた悲しみをつづった手紙だそうです。
私も3年半ほど前に愛犬を失ったので(2014年5月6日 「埋められない穴」、ふたたび)、彼の気持ちは胸が苦しくなるほどわかります。
次は、以下で紹介する短編フィルム中の言葉です。
もし僕が話すことができたら…
あなたと話すことができたらいいな。
(伝えることができなくても)知って欲しいんだ。僕を助けてくれてありがとう。僕を愛してくれてありがとう。
僕たちが一緒に過ごした時間にしたすべてのことを忘れないよ。
僕にしてくれたすべてのことに感謝しているよ。
楽しいことがたくさんあった。
あなたが恋をした瞬間も見て、家族ができた。
いろんな冒険を一緒にしたね。
今でもあの晴れた日のことは覚えているよ。
永遠に走り続けられるような気がした。そして、一緒に天国(空)を見上げたよね。
降り注ぐような星空の下、ずっと眺めたよね。
でも僕は歳を取った。疲れちゃったし、身体のあちこちが痛い。
お別れの時が来たみたいだね。
一緒にいてくれてありがとう。僕は怖くないよ。
僕、あなたが耳をこちょこちょしてくれるのが大好き。
何もかもうまくいくよ。大丈夫。
僕のために悲しんでくれているんだね。あなたと話すことができたらなぁ。
そしたら、伝えることができるのに。ありがとう。僕にしてくれたすべてのことに。
あなたと過ごした日々は、素晴らしい時間だったよ。
まるで最初に紹介した文章へのアンサーメッセージみたいです。
最後は、安楽死のシーンで、胸が詰まります。外国では一般的に行われているようですが、私にはとてもできません。
犬の十戒・・・犬からご主人への10のお願い
1.私の寿命は、10年。長ければ15年。何があっても最後まで、あなたのそばにおいてもらえますか。
私を飼う前に、どうかそのことをよく考えてください。
2.あなたが私に望んでいることを、ちゃんと分かるようになるまで少し時間をください。
3.私を信頼して下さい......それが何より嬉しいのです。
4.私のことをずっと叱り続けたり、罰として閉じ込めたりしないで下さい。
あなたには仕事や楽しみもあるし、友達もいるけれど私には....あなたしかいないのです。
5.時には私に話しかけて下さい。
たとえ、あなたの話す言葉はわからなくても、あなたの声を聞けば、私に何を言ってくれているのか、分かるのです。
6. 私のことをいつもどんな風に扱っているか、考えてみてください。
あなたがしてくれたことを、私は決して忘れません。
7.私を叩く前に思い出して下さい。
私には、あなたの手の骨など簡単に噛み砕ける歯があるけれど、決してあなたを噛まないようにしているということを。
8. 言うことをきかないとか、手におえないとか、怠け者だと叱る前にそうさせてしまった原因が無かったか、思い起こしてください。
ちゃんとした食事をさせてもらっていたでしょうか。太陽が照りつけている中に、長い間放っておかれたことはなかったでしょうか。
老いた私の心臓が弱っているせいで、動けないのかもしれません。
9.私が年老いても、どうか世話をして下さい。私達はお互いに、同じように歳をとるのです。
10. 最期のお別れの時には、どうか私のそばにいてください。
「つらくて見ていられない」とか「立ち会いたくない」とか、そんなこと、言わないでほしい。
あなたがそばにいてくれるなら、私は、どんなことも安らかに受け入れます。
そして、どうぞ忘れないで。私がいつまでもあなたを愛していることを。
あちこちで、色々な訳文が見かけますが、原典はノルウェーのブリーダーが犬の買い手に渡しているものなのだそうです。
最後に、あわせて紹介されていた、犬に関する名言をふたつ。まったく同感です。
一匹の動物も愛したことがなければ、人の魂は眠ったままである
アナ—トル・フランス(詩人、小説家、批評家、ノーベル文学賞受賞者)
もし、天国に犬がいないなら、僕は死んだら、彼らが行ったところに行きたい
ウィル・ロジャース(カウボーイ、コメディアン、作家、社会評論家)
- 2017.12.08 入院していたわけではありません
-
なんと、1年ぶりの日記になってしまった。
最近、複数の方から「ブログ(正確にはブログじゃないのですが…)、最近、まったく更新されませんね。」と言われた。
ありがたいことである。
「病気で入院でもされてるんですか?」という声も間接的に聞こえてきた。
さすがに、これじゃイカンと思い、近況をお知らせしておきたいと思います
更新が滞ってしまった最大の原因は、仕事に追いまくられて、心の余裕がない状態が慢性的に続いているからである。
事業そのものは、相変わらず堅実、着実、順調で、実績や信用は増し、環境は劇的に変わった。
でも、姿勢は20年前と基本何も変えず、ひたすら我が道を行くである。
信頼関係にこだわり、ガラス張りで、時流には乗らず、何も盛らない。
創業以来、私が直接担当していた広報宣伝関連の業務については待望の担当者が決まり、実務は大幅に減った。
そのかわり、経営者としての本来業務に取り組めるようになったのだが、これは魂を削る仕事である。
それに、根が心配性で、理想を追い求める性格なので、限度というものがない。満足するということがない。
そんな中で、かろうじて心を病まないでいられるのは、愛犬たちの存在があるからに違いない。

伸び伸びと生きて欲しいと願い、しつけもしないままだが、ますます甘えん坊になり、いつもこちらを見つめ、そばに寄ってきてくれる。
やんちゃやわがままを含めいつも正直で、裏というものがない。一途である。
もうひとつの救い、それは今も継続しているランニング。
走り始めて10年、月間100kmペースで、フルマラソンにも参加し続けていたが、負担に耐えられなくなりペースダウン。
でも、ここ2年は、月間50km以上のノルマを守っている。
前にも書いたが、走りたくて走ったことは一度もないが、走り終わって後悔したこともない。
人によって走る理由は違うが、私の場合、難しい言い方になるが「自己肯定感を味わうこと」で間違いない。
仲間を誘ったり、近所のジムに入ったり、だましだましである。
なんとかキロ6分ペースで走れるレベルまで戻し、1月のハーフマラソンに備えているところである。
趣味と言えるのはバイク。
還暦祝いに自分にプレゼントしたW800(かおる君)だが、今年初めに発売されたTriumph Bonneville Bobber(カール君)に一目ぼれしてしまい、5年でチェンジ。人生最後の愛車なんて、まったくのウソでした。

40年以上乗ってきて初めての外国製、1200ccもあるけど、とても乗りやすい。
もう一台のNinja250(カエルちゃん)は、サーキット走行用だが、今年は一度しか行けなかった。

もう5年ほど前から吹かなくなったハーモニカ、教室の裏方は続けているが、どんどん上手になっていく皆の演奏を横から見るばかり。
こんな動画を見ると、無性に吹きたくなる。
なんとか折り合いをつけて、そろそろ再開したいと思っている。
12月に入って、めっきり寒くなってきた。
喉が弱いせいか、タバコを吸い続けているせいか、気温が下がってくると昔はすぐに扁桃腺が腫れ、慢性的な微熱に悩まされていた。
ところが、走るようになってから、その悩みからほぼ解放された。
ひざの痛みも消えてしまったし、ジョギングはお勧めです。
でも眠っている間に顔に降りてくる乾いた冷気は大敵。
そこで、最近はこんなグッズで武装しています。



どれも、お気に入り。お勧めできます。
というわけで、病気にもならず、入院もしていません。
もうしばらくは老害と陰口されようが、自分なりの責任を果たすべく、ベストを尽くす所存です。
- 2016.12.26 旅館業法の改正についての、当社の関わり方
-
ニュースでも報道されていたのでご存知の方もいるかもしれないが、12月6日、内閣府の諮問機関である「規制改革推進会議」より「旅館業規制の見直しに関する意見」が政府に提出された。
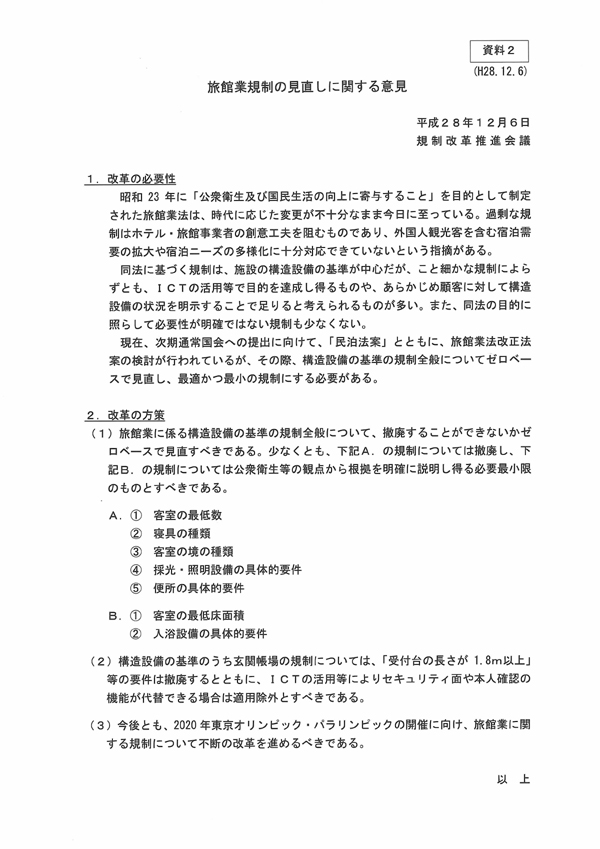
この内容の多くは、当社が(財)宿泊施設活性化機構に対して提出した資料や問題提起をベースとしてまとめられている。
その提出資料は、以下のとおり。
● 160714民泊新法に関する提言 ・・・ 7月14日に当社より宿泊施設活性化機構へ提出
● 161117不合理な規制の実例 ・・・ 11月17日に当社より宿泊施設活性化機構へ提出
● 161125旅館業法に関連する規制の実例 ・・・ 11月25日に当社より宿泊施設活性化機構へ提出
当社は、21年前にオープンした「日光鬼怒川店」以降、常に「旅館業法」などの規制に直面してきた。
>
これらの法令は、当初の目的であった公衆衛生上の観点に加え、1980年代に乱立したラブホテルを抑制するための細かな規制が加えられている。
ところが、「車で移動する人たちのための郊外の素泊まりの宿」という点で、本来のMOTELと「ラブホテル」に表面的な類似性があり、結果的に抵触する部分が少なくないという問題に悩まされてきた。
法令が制定された時点では、「ファミリーロッジ旅籠屋」のような本来のMOTELが想定されていなかったため、時代遅れで不合理な部分がたくさんあるのだ。
そもそも「ラブホテル」を白眼視することがどうなのかという問題もあるが、こうした規制が日本における本来のMOTELの普及を妨げ、「ファミリーロッジ旅籠屋」出店における大きな障壁となってきた。
「このままでは許可できない」と指摘されるたびに、法令の趣旨に照らして合理性があることを主張し、規制の枝葉末節に従うのでなく、手間ひまをかけて理解を求め、道を開いてきた。
つい先日も、四国のある市役所で、「特定ホテル建築規制条例」というものが定められており、一人用客室の数が全客室の3分の1未満であったり、ラウンジの面積が50㎡以上でなければ「ラブホテル」とみなす、と言われた。
「専ら異性を同伴する客の宿泊又は休憩に利用させることを目的とするもの」という前提条件があるのだから、当社の施設は該当しないと主張したのだが、それを判断するのは別途開催する審議会であり、それに諮るかどうかは我々担当部署が決める、という。
これから、求められるままに資料を提出し、既存店を案内したりして、審議会の開催をお願いし続けなくてはならない。
これをクリアーしなければ建築確認の申請も受け付けられないのだから、少なくとも2〜3ヶ月の時間が余計にかかる。
我々は、こんな誤解と煩雑な手続きで悩まされているのに、いっぽうで、非合法な「民泊」が増え、政府主導で「合法化」を急ぐ動きが顕著になっている。
過剰な規制で苦しんでいる状況が続いているなか、もぐりで横行する「空き室活用のためだけの金儲け」がなし崩し的に規制緩和されるのはおかしい。これを機に、既存の法令も抜本的に改正すべきではないか、このような問題意識から、今年2月に新聞に投稿を行った。
その内容については3月31日の「旅籠屋日記」に転記したので、ご覧ください。
その後、この投稿を機に、(財)宿泊施設活性化機構から、「民泊の合法化に関し、政府に対して既存法令の問題点について政策提言を行いたい。ついては、具体的なご意見を」との連絡があり、3回にわたって来社され、資料を提出し、提案を行ったいう次第である。
当社は、単に格安な宿泊施設を作って新しいビジネスを始めよう、という目的でスタートしたのではない。
このようなスタイルの宿泊施設を車社会のインフラとして整備することによって自由な旅やライフスタイルを守り育てていきたいという願いと使命感を持って歩んできた。
加えて、その過程で直面する不合理には、目を背けたり逃げたりせず風穴を開けようという姿勢を大切にしてきた。
今回のことも、そういう考えの中で力を尽くしてきたことである。来年1月から始まる通常国会で審議されるようだが、我々の経験や提案が反映されることを心から願っている。
- 2016.12.06 支配人の仕事
-
去年の後半から兆しはあったのだが、今年に入って店舗の支配人不足が顕著になった。
コンスタントに続いていた応募がなぜか途切れがちになっていたところに、新店舗のオープン(今年は7店)と病気・介護・定年による退職者の増加が重なった。
かといって、9割以上が予約によるお客様なので、店を閉めるわけにはいかない。かわりに本社スタッフが「代行支配人」として店舗に赴くが、次第にその頻度が高くなり、ここ数ヶ月は、常に本社社員の過半が出張中という状況が続いた。全員が顔を揃える日は月に1度くらいで、重要な打ち合わせもままならない。
9月からは役員も交代で店舗に泊り込むことになり、私も2回、十数年ぶりに「支配人」を務めた。客室を掃除し、予約を受け、フロントに立ってお客様をお迎えする。20年前の1号店支配人としての3年間が思い出される。
朝食の準備を終えると、チェックアウトされた客室をまわり、窓を開けて換気し、リネンやゴミを回収し、バスタブや便器を洗い、ベッドを作り、掃除機をかける。10室を超えると午後3時のチェックイン開始時刻に追われながら数時間の作業になる。予約の電話対応やメールチェックも並行して続く。乱れた部屋が整っていく達成感はあるものの、正直言って、決して楽しい作業とは言い難い。そんな気分を久しぶりに味わった。
素泊まりの宿の日常業務は地味で単調である。おいしい料理や美しい飾りなど、お客様を驚かせる「華」がない。マイナスをゼロにする作業で、プラスを演出する喜びを感じることが少ない。
これは、ベーシックなインフラ施設を維持する仕事に共通する宿命かもしれない。電気・水道・ガス・通信、道路・鉄道・物流、滞りなく流れていて当たり前、清潔に整っていて当たり前。
立場を忘れて言うが、私は黙々と職責を果たしている支配人に敬意を抱いている。仕事なんだから当たり前、という見方もあるだろうが、義務感だけで続けられる仕事ではない。3年間、ほぼ休みなく務めた私の実感である。
社内でいつも言っていることだが、建物内外の清掃やグリーンのメンテは、目に映る姿の背後に人の心が透けて見える。店舗を訪ね、気持ちよく整えられた雰囲気に接したときに浮かんでくるのは、経営者としての満足感ではなく、人間として頭が下がる思い、嬉しくなるような共感である。
もちろん、逆の場合もある。しかし、一方的に責める気にはなれない。延々と続く日常はとても重い。鬱屈した思いが伝わってくる。閉塞感に苦しむ気持ちもわかる。
日々のストレスを軽減する配慮ができないか、少しでも改善する手立てはないかと考えるが、ひとりひとりの性格や人生観もからむので、単純な対策で解決できるわけではない。人間は機械ではない。
お客様のかけがえのない旅の時間を支えているという自覚や、たまに寄せられる感謝の声を自分自身の喜びとして、と言うのは容易だが、人生経験から得られる心の余裕やある種の達観がなければ難しいことのように思う。
「ファミリーロッジ旅籠屋」はすべて直営であり、支配人はすべて当社の正社員である。人生を共にするふたりが店舗に住み込み、文字通り力を合わせて運営業務を行っている。最初に2週間ほどの研修を受けた後、半年から1年の間、支配人が休暇の際の「代行支配人」として、全国各地の店舗を回る。この期間は移動も多く、数日おきに勤務地が変わるため、気苦労も多い。しかし、その経験が支配人になるための貴重な財産になる。これは、お互いに適性を見極める期間でもある。以上、詳しくはこちらをご覧ください。
いっぽう、「代行支配人」専門の人たちも十数組いる。前の職場を定年で退職した中高年の夫婦が中心だが、最近では旅籠屋支配人の経験者も加わるようになって来た。
山あり谷ありの人生を共に歩んできた二人だからこその気負いのない雰囲気、人生の達人と呼びたいような素敵なカップルが多い。
初めて積極的な求人広告を行った効果もあり、おかげさまでたくさんのご応募をいただいた。年明けには人手不足がほぼ解消される見通しだ。
しかし、本社スタッフによる「代行勤務」は、来年も続けていく予定である。店舗の実際の状況を感じ、支配人の気持ちを理解することが、すべての基本である。
支配人たちの笑顔が消えたら、私たちの会社が存在する意味の半分はない。
- 2016.03.31 「民泊」について
-
あと3ヶ月で会社設立から満22年になる。その頃の話し。
登記手続きを終えてすぐに1号店オープンに向けて、用地(借地)探し、建物の設計と建築確認申請、建設業者探しと見積もり依頼などを進めた。
並行して、宿泊営業の許可をとるための準備に着手したが、これがたいへんな作業で難航した。
長く住宅メーカーに勤務していたので建物を作ることに関しては想定内だったが、宿泊業の経験は皆無、申請先が保健所であることすら知らなかった。
担当者の方は真面目な女性で、旅館業法や関連する条例の細かい規定をひとつひとつあげて、これでは到底許可できないと譲らない。
当時の私がそうであったように、一般の人がその規制の細かさや厳しさを目にすることはない。旅館業法の施行令には、客室の広さはもちろん、フロントの位置、カウンターの高さや長さ、外部の共同用トイレについても定めがある。
そもそもアメリカのMOTELのような車で移動する人々のためのオープンで気軽な宿泊施設が想定されていない。逆に、車で乗り付けて利用するラブホテルとの表面的な類似性が足かせになって、駐車場から客室にはフロントを通らなければならず直接の行き来は認められないという。
人生のすべてを賭けた事業はすでに後戻りできない段階まで進んでおり、こちらも必死である。何ひとつやましい所はない。これからの日本に必要な施設であるという強い自負もある。法令の枝葉末節の解釈というレベルで妥協するつもりはないし、規制との食い違いはそんなことでクリアーできる範囲を超えている。
「法律が想定していない業態の施設なのだから、機械的に細かな条文との整合性だけを議論しても意味がありません。旅館業法の第1条に書かれている目的にかなった施設です。判断ができないというのなら、県の保健衛生局なり、県警本部なりの責任者を交えて議論しましょう」と訴える。
「旅籠屋さんが、ラブホテルとは違う宿泊施設を目指しているのは理解しました。でも、結果的にそうなってしまう可能性を否定できますか。ここはアメリカではなく、日本ですよ。」と担当者も譲らない。行政官としては恣意的に許認可の判断を行ってはいけないのだから当然である。
こうしたやり取りが何回繰り返されただろうか。不安で眠れない日が続いたのを覚えている。
後日談だが、数年後、2号店となる「那須店」を具体化する際に地元の保健所を訪ねたところ、あの同じ女性担当者が現れた。たまたま那須に異動していたのだ。お互い苦笑いしてしまったが、「旅籠屋さん、目指したとおり、ラブホテルではなく、色々な人たちに利用される宿になりましたね」と言われた。
彼女の不安を払拭し、ぎりぎりの決断に応えられたことが嬉しく誇らしかった。
あれから約20年、旅館業法やラブホテル抑制のための条例との戦いはほんとうに大変だったし、現在も進行中である。
そうした経験から言うと、 無許可で増えている「民泊」や、政治主導で進められている規制緩和は腹立たしくてならない。自宅の空き室を活用するのならまだしも、ワンルームマンションを借りて転用するなど目先の金儲けにかられているだけで、観光促進や地域創生などの志とは無縁のものだ。
そんな思いが抑えきれず、2月に新聞に投書した。
幸い、掲載された(電子版にも同じ内容で掲載されたので、こちらをご覧ください)が、文章はかなり変更されてしまったので、原文を以下に紹介します。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
私の視点「民泊」の合法化 急ごしらえでなく、法令の総合的な見直しを
株式会社 旅籠屋 代表取締役 甲斐 真
最近にわかに注目を集めている「民泊」。トラブルの増加にともない、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業である限り、旅館業法による許可を受けなければならないはずだ。これを機に関連法令を整備すべき」という議論がようやく活発になってきた。
全国で増え続ける空き家を活用し、急増する外国人観光客などの需要に応えるべきではないかという意見がある。他方、法令を無視した「もぐり営業、フライング営業」は、看過すべきことではないという指摘がある。
既存の宿泊業界からは、法令にしたがって許可申請を行う「正直者」が規制を受け、無視する者は黙認されるような状況は「法の下の平等」に反するという意見もある。いずれも理にかなった当然の主張である。
当社はアメリカを中心に無数に存在するシンプルな汎用ロードサイドホテルを日本で初めて実現し、この二十年余りで全国各地に展開してきた。しかし、法律が想定していない業態であるため、さまざまな規制の壁に直面してきた。例えば、旅館業法施行令はホテルの共同用トイレに男女別の区分を求めている。客室にトイレがない古い施設を想定しての規定なのだが、車椅子で利用できる「誰でもトイレ」を自主的に設置する場合にも男女別が求められることがある。
また、旅館業法に関連して、多くの自治体で「ラブホテル規制条例」が設けられているが、その中には「シングルルームが一定割合以上、あるいは幅1.4m以上のベッドを設ける客室が一定割合未満でなければラブホテルとみなす」というような定めがあり、許可を得るのに複雑な手続きを要することが少なくない。同様の例は他にもたくさんある。
法律や条令は、基本的に社会の変化に対し後追いで定められるものだから、新しいビジネスの足かせになることが多い。宿泊業に関し、当社は時代遅れの不合理な規制に誰よりも悩まされてきた。だが、宿泊者に安全で衛生的な施設を提供するとともに周辺の生活環境との調和を図ることは当然のことで、その基準となる法令の必要性と意義も十分に理解している。
「民泊」の推進に向けて、政治主導の追い風が吹いているように感じられる。しかし、「民泊の合法化」だけに焦点を当てた部分的な規制緩和がなし崩し的に進められるのは厳に慎むべきことだと考える。
旅館業法の目的には「利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進」と記されている。すでに現実の宿泊施設は「民泊」だけでなくさまざまな形があり、改正すべき点が数多く存在する。これを機会に、許認可審査の現場である全国の保健所担当者を含め広く意見を求め、法令の包括的かつ抜本的な見直しを強く望む次第である。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
掲載後、目だった反応はないが、国土交通省の方が来社されヒアリングを受ける機会に恵まれた。20年以上続けてきて初めてのことである、ようやくである。
旅籠屋は、金儲けだけを求めて設立した会社ではない。日本になかったアメリカのMOTELのような経済的な宿泊施設を作って喜ばれたいというだけで始めた事業でもない。多種多様な個人が活用できるインフラを日本全国に誕生させることによって、ひとりひとりが自らの価値観で自主的に旅し、生きていけるような自由な社会が深まっていくことを願って続けていることである。
さらに、その過程で、不合理な規制を改め、偏見や事なかれ主義や先例重視の世の中の雰囲気が変わっていくことを心の底から願っている。
これを機に、ほんの少しでも存在価値が発揮できれば本望である。
- 2015.12.27 ゆく年、来る年
-
日曜日のオフィスで、静かに今年1年を振り返る。
個人的には、去年の春に愛犬マギーを失った痛手が大きく、寂しい正月から1年が始まった。
迷ったあげく、人生最後のパートナードッグを迎え入れることを決め、保護犬の受け入れを検討したが、年齢的に難しく断念。結局4月に子犬2匹が新しい家族に加わった。
2kg足らずだった子犬はすくすくと育ち、もう30kg近くになったが、私が帰れば喜んで飛びついてくるし、いつもじっとこちらを見ている。
寂しがり屋でいつも無言で会話していたマギーとは違い、屈託がなく能天気なふたりだが、命とともに暮らすことが、どれだけ心を暖めてくれることか、どれだけ心を落ち着かせてくれることか。
10年来続けているランニング。未知の世界に分け入っていく好奇心や高揚感は失せてしまったが、負担にならない程度に続けることにしている。
走りたくて走ったことはないが、走り終わって後悔したことは一度もない。私の場合、走る理由は自己肯定感が得られること。
目標だった月間100kmを50kmに下げ、無理してフルマラソンに参加することはもうやめた。年明けには、ハーフマラソンの大会に出てのんびり完走したいと思っている。距離もペースも下がったが、3日空けずに走り続けようと思う。
若い頃から好きなことのひとつ、それはオートバイ。
これは、3年前に自分への還暦祝いとして久しぶりに新車を購入してから熱が復活し、1年ほど前にスポーツライディング用に買ったもう1台のバイクでサーキットランにも参加するようになった。恐怖感もあるけれど、走っていれば少しずつ上達していくのが嬉しい。春になったら、月に1度は革つなぎを着てドキドキしにいこうと思っている。もちろん、無理はしない。背伸びせず、挑戦し続けたいと思う。
若い頃からの変わらぬ趣味と言えばブルースハープ。
いろんなことがあり、練習する心の余裕を失ってしまってしまって、もう数年も前から吹かなくなっている。
でも、教室の手伝いは15年も続けていて、楽しそうな仲間たちとの世界は私にとっての貴重な財産だ。
音楽は、年齢や国籍や言葉と関係なく心を通わせられる。これこそ、足腰が弱っても味わえる最後の趣味になるのかもしれない。
年明けから、再開しようか。
さて、仕事のこと。
今年は1号店オープン、つまり創業から20周年の区切りの年だった。無我夢中の20年、毎日毎日雑用に追われるばかりで、長期的な視点に立ってグランドデザインを描く仕事に十分力を注いでいないという反省がふくらんでいる。
そんな中、周年事業として「オリジナル全国ドライブマップ」を作成したが、それは小さなことにすぎない。来年こそ、中長期的なビジョンやコンセプトを原点に返って深く問い直してみるつもり。そのためには、働く人たちの意欲を保ち高めていくための仕組みづくりや監督官庁への問題提起に正面から取り組まなければならない。
ルーチンワークに埋もれているのはある意味とても楽だが、そこから離れて未知の領域に踏み込むには大きなエネルギーが必要だ。
幸いなことに、私の怒りや願いはこの20数年間の環境の変化にも少しも動じず変わらなかった。ひそかな自負は、創業の思いにそれだけの深さと強さがあったということ。しかし、そこに安住し、過大評価するわけにはいけない。
経営者としての最大の使命は千年事業の基礎を固め、世の中に良い先例を作っていくことにある。
そして、それがおそらく私の人生最後の務めなのだ。
さぁ、犬たちを散歩させ、冬の隅田川沿いを走ってこよう。
- 2015.11.30 テロのニュースで感じたこと
-
先日、パリで悲惨なテロ事件が起きた。一般市民が無差別に標的になった。ひどい話だ。

フランスへの連帯とテロを許さないという意思表示のために、facebookでは三色旗を自分のプロフィール写真に重ねる人も少なくなかったが、私は同調する気持になれなかった。
テロの犠牲者は今回に限ったことではなく、ロシアの航空機でもトルコでもレバノンでもエジプトでも各地で頻繁に起こっており、フランスだけを特別扱いをするのはおかしなことだ。
そしてもうひとつ、あのテロを実行した人たちはいたずら半分の愉快犯ではなく、命を賭した示唆活動を実行したのであって、そこには彼らなりの強い怒りがあったと考えるからだ。
似たようなことは、14年前にも感じたことだ。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件である。
あの時、世界中の人々が驚きアメリカに同情したものだが、私はアメリカがこれほどまでに憎まれ恨みを買っていることが容易に想像できた。
誤解されないように断言しておくが、私はアルカイダやISの肩を持つつもりはないし、テロを肯定するつもりもない。
しかし、19世紀以降、先進国が自国の利益のために「自由」「正義」「博愛」などというもっともらしい美名を掲げながら世界中で繰り返してきた蛮行を知っている。だから、テロの問題は、やくざの出入りのように、お互いが暴力で報復を繰り返したり、神に祈るだけで解決する問題だとは到底思えない。
ところで、数年前から、政財界のトップが「グローバル経済の中で少子高齢化の日本が生き延びていくためには、人間の鎖国を解き、海外からの労働力を広く受け入れるべきだ」発言することが増えている。私はこれに強い違和感を感じる。
海外を旅行していると、3K(きつい、汚い、危険)の仕事に移民らしき人たちが多いのに気づく。ホテルの廊下ですれ違うルームメイクの人たちも同じだ。気持ちがざらつく。申し訳ないような気がしてくる。
安い労働力を得るために、経済的に困窮する人たちを迎え入れる、そんな社会が健全だとは思えない。「平和で民主的な世界にようこそ、努力して同化すれば、すばらしい未来が待っていますよ」と言う人もいるのかもしれないが、私が感じるのは、欺瞞と偽善だ。伏目がちに働く人たちの鬱屈した感情、屈辱感や絶望に気づかないふりをするわけにはいかない。
私は個人の自由を何より大切にしたい。そのために、ひとりひとりの多様性を尊重しなければならないと考えてきた。日本社会は本質的に閉鎖的な村社会なので、「普通」から外れると生きにくい。そうした閉鎖性を緩めて、ひとりひとりが胸を張って自立して生きていけるようにしたい、旅籠屋はそうした願いの中で生まれたのだし、そのこだわりを頑なに守り、反映してきた。
しかし、あらゆる個性や違いがフラットに同居するような社会が望ましいとはけっして思ってはいない。日本人としてのアイデンティティや帰属意識を維持できないような社会に長期間暮らし、その一員になりたいとは思わない。
つまり、風俗・習慣・文化などを共有する人たちがマジョリティとして存在する世の中があり、これに属さない人々は排除されたり不当に差別されることはないけれど、そのマジョリティのルールを尊重する範囲内でマイノリティとして受け入れられている社会、それが私の暮らしたい社会である。だから、私は大量の移民受け入れには賛成できない。
付き合いの長い友人に話すと、そんな保守的な意見は私らしくないと言われる。でも、偽善的な「良識派」になりたいと思ったことはない。
フランスもドイツもイギリスも、自国の利益のために北アフリカや中近東やインドなどからたくさんの移民を受け入れてきた。短期的には経済的なメリットがあり、活力を生んできたかもしれないが、それは格差を固定させ、その割合が一定限度を超えると文化的な摩擦が噴出する。今はそんな段階なのだと思う。
旅籠屋は、予断・偏見・先入観にとらわれずお客様を受け入れることを何よりも大切にしてきた。
社内においても、学歴・職歴・国籍・宗教などにとらわれず社員を雇用してきた。LGBTの人も同様である。
しかし、基本は日本人の、日本人による、日本人のための宿であり、会社であると考えており、それで良いと考えている。海外からの旅行者への集客をしないこと、海外進出を考えていないこと、その理由はここにある。
その意味で、私は、グローバリゼーションには懐疑的だし、TPPの前提にも賛成できない。他の文化に生きる人たちの社会に西欧社会や先進国の正義を振りかざして介入することには反対である。世界はまだら模様でよいではないか。正義はけっしてひとつではない。
- 2015.11.12 東京モーターショー
-
先週末「東京モーターショー」に行ってきた。
数えて44回、会場が東京に戻って3回目。幕張メッセの頃に比べてコンパクトになってしまったような印象を受けた。
ちなみに、第1回は1954年開催だったそうで、私の人生とほぼ重なっている。
そうか、私は日本におけるモータリーゼイションの発展とともに生きてきたことになるわけだ。
「モーターショー」にも10数回は来てるかもしれない。


当然、2輪を中心に見て回ったのだが、展示台数が少なく残念。私には「モーターサイクルショー」の方が楽しい。
ただ「モーターショー」の見所は、時代の空気を感じられる点にある。来場者の年齢層や熱気、人気のコーナー、メーカーの力の入れ所。
今回は、話題の「自動運転」がクローズアップされていた。
数時間かけて展示をひととおり見て回った後、当社もメンバーに加わっている「自動車旅行推進機構」が主催するシンポジウムに参加してきた。
今回のテーマは「カーたびの明日〜未来のクルマは旅をどう変えるか」。
こんなことができるようになる、こんなふうに旅が変わるかもしれない・・・
断片的には面白いアイデアも聞けたが「夢がひろがる」という気分にはまったくなれなかった。
この60年間で、車も家電品も驚くほど便利になり、我々の生活を変化させてきた。みんな新製品に驚き、あこがれを抱いてきた。
でも、最近は、そんなトキメキがめっきり少なくなった。
パソコンやネットや携帯電話の分野では熱が残っているかもしれないが、何かしっくりしないものを感じている人も少なくないように思う。
人間の本能や生理に対して、モノがじゅうぶん高機能になりすぎたのかもしれない。
サービスが押し付けがましくなっているようで、「夢見る」ことを無理強いさせられているようで、頭は面白がるけど、心が躍らない。
逆に、アナログで古臭いものが「懐かしく新鮮で」しっくりきたりする。
仕事がら、高速道路を使って長距離ドライブをする機会が少なくない。退屈である。苦痛である。そんな時、車が「自動運転」してくれればラクだと思う。
でも、そんな未来にワクワクしているわけではない。
総称して「スマート・モビリティ」。ビッグデータの上で管理され、予定調和的な快適さをなぞる。
それは、旅の本質に逆行するものに思えてならない。
年甲斐もなく、最近バイクでサーキットを走り始めている。
革ツナギなどの装備品を含めお金がかかる。休みの日に早起きして疲れてしまう。下手くそで悔しいし、危険じゃないけど少し怖い。でも楽しい。
私の愛車にはABS(アンチロック・ブレーキ・システム)もトラコン(トラクションコントロール)もいらない。
機械任せの安全や便利さを求めるなら、そもそもバイクに乗りたいと思っていないし、旅に行きたいとも思わない。
そんな人生なんてつまんない。
- 2015.11.05 3大うまみ成分
-
先日、バイクツーリングの途中で、キノコ狩りを楽しんできた。ビニールハウスに並べられている木には、すでにたくさんのシイタケが育っており、これを根元からちぎるだけなのだが、傘が開いて胞子を放出する直前のものがグアニル酸が多く美味しいと教えられた。
ちなみに、 昆布のダシから発見されたグルタミン酸、かつお節のダシから発見されたイノシン酸、そして干しシイタケなどの煮出し汁に含まれるグアニル酸を3大うまみ成分と言うのだそうだ。さっそく採りたてのシイタケを炭火であぶって食べたのだが、驚くほど美味しかった。
「子孫を残す前がもっとも美味しい」という説明には説得力があって納得してしまったが、考えたら残酷で申し訳ない話しである。私が見逃せば、無事に胞子をばらまいて思いを遂げていたのかもしれないのだ。
そんなことを考えながらシイタケを見ていたら不思議な気分になった。
「キミは傘を広げ、胞子を放出するために生まれてきたの?」。子孫を残すことが生き物の目的なら、そうなのかもしれない。じめじめした薄暗い森の中で繰り返されるシイタケの世代交代。キミたちの一生って、それだけなの?
生命の本質がそういうことなら、リンゴの木も、犬も猫も、我々人間だって同じはずである。勉強して仕事して、楽しんで悲しんで、それって何なの。
足元には半年前に我が家に迎え入れたワンコがいて、つぶらな瞳でこちらを見ている。
難しい話しは別にして、無条件に可愛くて、一緒にいるだけで幸せ。
生きてるって、不思議だね。

1年ぶりの日記が変な話しになってしまいました。これからは、週記を目指して書き込みます。
- 2014.11.14 地域振興の根源的な意味
-
日記と銘打ちながら、おそらく過去最高、半年以上も間が空いてしまった。
愛犬を失ってから7ヶ月以上が過ぎ、今もマギーのことを話題にしない日はないが、さすがに痛みは少しは和らいできた。
ありがたいことに店舗の業績は順調なのだが、相も変わらず仕事に追われる毎日が続いていて、じっくりと考える余裕がない。
そんな中、今年も「月刊 ホテル旅館」(柴田書店発行)に掲載する原稿の依頼があり、久しぶりに考えをまとめる機会になった。
12月発売の2015年1月号に載る予定なので、フライングにはなるのだが、以下に紹介させていただきたい。
年頭所感 「2015年の展望と課題」
「ファミリーロッジ旅籠屋」1号店をオープンさせたのは1995年夏、夢と不安でいっぱいのスタートでした。
夢とは、海外に無数にあるMOTELのような誰もが気軽に利用できるシンプルで経済的な宿泊施設を日本にも誕生させたい、待ち望んでいる人は少なくないはずだ、全国に展開できれば旅の選択肢が増え、日本人のライフスタイルをもっと自由で豊かなものにできるに違いないという願いです。
不安とは、こんなスタイルの宿が日本で受け入れられるのだろうか、宣伝もできないのにお客様は来ていただけるのだろうか、ビジネスとして続けていけるのだろうかという恐れです。
2015年夏、あれから満20年を迎え、全国50ヶ所でお客様を迎えられる見通しが立ち、わずかな金額ですが安定して黒字経営を維持していける確信も得られるようになりました。もちろん、多くの出会いや幸運に恵まれたおかげなのですが、初心を曲げず、こだわりを守り続けてきた結果であるという自負は小さくありません。
その変わらぬこだわりのひとつ、それが地域への貢献ということです。
最近、少子高齢化や過疎化の進行などを背景に以前にも増して地域振興が叫ばれ、地方創生という言葉も生まれています。メディアは大多数が総論賛成することを前提に報じているようです。しかし私は、このような風潮や論調には違和感を感じます。思考停止が生み出す「正論」に過ぎないからです。
そもそも人口の都市集中は世界的な現象であり、その流れを押し止める必要はほんとうにあるのでしょうか。成り行きに任せるべきだという選択肢はないのでしょうか。経済的な合理性やインフラの投資効率を考えれば、人間の活動地域を集約したほうが良いという考え方は当然あるはずです。情緒的な「正論」では反論になりません。そこに暮らす人々の生活や心情を考えれば「地方を見捨てる」という考え方は暴論として糾弾されるかもしれません。しかし、地域振興の本質的な意義や目的を見定めないと、対応策の立案や評価はできないはずです。
とはいえ、私は20年前から一貫して地域振興は良いことだと考え、収益性の高い大都市近郊よりも地方への出店を優先し、赤字店舗の閉鎖もまったく検討せずにきました。
これは利益や投資効率の最大化とは矛盾することです。なんとなく地方重視というだけでは経営者失格と批判されても仕方ありませんし、苦しくなれば方針を変える場当たり経営に陥る可能性も否定できません。これでは会社のポリシーとは呼べません。地方重視の本質的な意義や目的を明確にしなければならないのです。
ところで話は変わりますが、「yahoo知恵袋」というサイトで、自然界の摂理についての書き込みが注目を集めました。その要旨は以下のとおりです。
・・・自然界における生物の掟は弱肉強食ではなく適者生存である。重要なことは、さまざまな環境変化に対応して種として生き延びていける多様性を用意し(保険をかけて)おくことである。自然環境の変化は無数の可能性の塊であり、形質の良し悪しはあらかじめ判定できない。個体としては弱い人類が結果的に採用した戦略は、集まり協働して文明社会を作ることによって出来るだけ多くの形質を生かし、子孫繁栄の可能性を最大化すること・・・
(全文はこちら)
飛躍と思われるかも知れませんが、無数の地域を大切にするとは地理的な意味での多様性を守ることだと言えないでしょうか。多くの人が地方の衰退を残念に思うのはそのことを無意識のうちに直感しているからではないでしょうか。すなわち、社会全体で多様性を維持することこそ人類の生存戦略に適っている、子孫繁栄のために大切だという本能的な確信です。少なくとも私にとってはそうです。分け隔てなく誰もが泊まれる宿泊施設が必要だという信念も、自由に旅すること自体が人類にとって本質的な営みだと思うのも同じです。
東北では「復旧」なのか「復興」なのかという議論があるようです。震災による荒廃は数十年後の地方の姿を現出させたのだという見方もあります。多様性の維持が人類にとって根源的な命題ならば、一時的で一面的な基準に過ぎない経済的合理性や効率を最優先にするわけにはいきません。辺境を含め地域を守ること、異端や少数派の文化や形質を受け入れることが求められます。いずれも困難で違和感のあることですが、世界中が、先頭を走る日本が示す将来への指針やビジョン、そして哲学に注目しています。
なんとも大げさな話しになりましたが、旅籠屋は継続性のある社会的企業を目指し、こんなことを真面目に考え試行錯誤する会社であり続けたいと思います。
宿泊業は人類の未来を支えていく千年事業だと信じているからです。
- 2014.05.06 「埋められない穴」、ふたたび
-
ゴールデンウィークの連休も、きょうで終わり。 でも、私は日中のほとんどをオフィスで過ごした。
5年以上も続けていたジョギングもやめてしまったし、散歩に出かけることもなくなったし、自宅にいても気持ちが落ち着かない。
というのも、1ヶ月近く前の4月12日、突然愛犬が亡くなってしまったからだ。

左:6歳の頃、右:生後1ヶ月の頃
10年前にも同じ経験をした。その時のことは、前に書いた(2004年8月22日「埋められない穴」)。
その悲しみがあって、1年後に同じ犬種(ゴールデンリトリバー)の子犬を迎え、同じ名前(マギー)を付けたのだった。
あれから8年半あまりが過ぎ、今回もまったく同じことを感じ、ふたたび打ちのめされている。
少し違うとすれば、2代目は両親ではなく私の飼い犬でいつも私にべったりだったこと、3年ほど前に大病したこと(2011年11月19日「我が家の111111」)、
具合が悪くなったその日に突然亡くなってしまったこと、だから喪失感はさらに深く大きいかもしれない。
そして何より、私は10歳、年をとった。
大げさに聞こえると思うが、マギーはペットではなく、家族でもなく、私の一部分だった。
仕事に追われているときは良いが、旅先でも自室でも、体の中心に大きな穴があいたままだ。
とくに、夜なかなか寝付けないのがつらい。
今も、すぐ横で私の様子を見ているマギーの気配がする。
この4日間、静かなオフィスで締め切りのある仕事に追われているのは苦痛ではなく、かえって救いだった。
おかげさまで、「旅籠屋」はおおむね順調だし、スタッフの仕事ぶりも確実に向上している。
私のやるべき仕事は相変わらず多いが、現場の実務は少しずつ減らせるようになっている。
再びあいてしまった穴は、この先生きている限り、もう埋まることはない。
日常と非日常。 安穏と好奇心。 過去と未来。
気がつくと少しずつ潮目が変化している。
ゆっくりと前者に流されている自分がいる。
そろそろ、スローダウンさせていく潮時なのかもしれないと、そんなことを考え始めている。
- 2013.11.20 秘密保護法案
-
今年の4月、本社の主要スタッフであったMくんが会社を離れた。
突然のことであり、引継ぎもままならなかったため、それ以降の半年間はほんとうに大変だった。
ガラス張りの小さな会社とはいえ、当人でないとわからないこともある。
出店やシステムの更新など、対外的な約束事をおろそかにするわけにもいかず、大きなストレスがかかったが、なんとか業務の停滞は避けられた。
特定の個人のスキルや記憶に頼るのではなく、情報を共有し、組織で対応できる仕組みを作らなければと痛感した次第である。
6〜7月は新店オープン準備、8月は決算作業、9月は株主総会、10月はオフィスの改装、そして新しいスタッフも増え、11月に入ってようやくひと段落である。
そんな時、日本政策学校から無料オープン講座の案内メールが届いた。
講義のテーマは、「特定秘密保護法と民主主義について」。講師は元毎日新聞記者・西山 太吉さんである。概要は、こちら。
西山さん個人に関心があったので、土曜日の午後、私としては珍しく人の話しを聴きに出かけてみることにした。
日本政策学校は、 主義主張・政党を超えた自由な議論を通じて多様な民意が反映される「真の民主主義社会」を実現するために推進役となる政治リーダーを育成・輩出することを目的にしているそうで、20代と見える若い人たちも少なくなかった。受講者は100人くらいだったろうか。
還暦を過ぎた私の場合、沖縄返還交渉はリアルタイムの出来事であり、密約は半ば公然の秘密だった。 西山事件のこともよく覚えている。
今の若い人には信じがたいことかもしれないが、当時、激動する政治状況は雨の日に「傘がない」ことよりも身近で切実な関心事だった。
さて、最前列に座る私の目の前に現れた西山さんはすでに80歳を過ぎ、弱々しく小さく見えた。
しかし、生の経験談はさすがに説得力があり、時折力を込める言葉には迫力がある。
1時間の講演が終わり、周囲の人たちと意見交換タイムが始まった。
密約そのものへの驚き、アメリカという国のずるさに対する批判、交渉術の巧拙などについての発言があったが、私の心の中にはもっと別の疑問が浮かんでいた。
一言で言えば、個人と組織の関係について。
どんな組織であれ、組織として機能するためには一定の規律や守るべきルールが生まれ、必然的に個人個人の価値観や思いとは矛盾が生じる。
国家は、特殊性はあるもののひとつの組織には違いなく、秘密保護の問題は両者の本質的な矛盾をどうとらえるかに関わることに違いないと思ったのである。
意見交換の時間が終わり、西山さんへの質問時間が与えられたので、私はこの疑問をそのまま投げかけてみた。
「哲学的なテーマですね」という言葉に続き、誠実に答えてもらったが、短い時間で深められるわけもない。言葉のニュアンスを感じ取り、考えるヒントだけを受け取って講座は終了した。
振り返ると、私はずっと既成の価値観の押し付けや権威に逆らってきたように思う。「個人の自由」を大切にしたいという強い思いがあり、アメリカのMOTELのような宿泊施設を日本にも誕生させたいという願いも、間違いなくその延長線上にある。
しかし、会社を立ち上げ、店舗が増え、人が増えれば、それは間違いなく組織である。気がつけば、標準化の推進とかマニュアルの作成とか、組織を維持強化することが仕事の中心になっている。
人一倍「個人の自由」に執着している人間が、経営者としては社員ひとりひとりをルールに従わせようとしているわけだ。
Mくんは、半年間、ひとりで日本縦断の旅を続けているらしい。幸せな出会いがあり、屈託の無い交歓もあるに違いない。
しかし、その先にどんな世界が生まれるのか、私にはよくわからない。
個人の自由と組織の力、ほんとうに難しい永遠のパラドックスである。
西山さんの言葉から得たヒントをもとに、今も考え続けている。
- 2013.09.02 旅は、自由。
-
旅は、自由。
気兼ねなく、好きな時に、好きな所に行ける。
あたりまえのことのようですが、今世界中で、こんな自由に恵まれた人々がどれだけいるのでしょう。ほんの一部に違いありません。
心と体の健康、ある程度の経済的ゆとり、車社会のインフラ、個人を大切にする平和で安全な社会、これらの条件がそろわないと得られないことだからです。
50年前はどうだったのでしょう。50年後は、どうなるのでしょう。
長い長い歴史の中で、無数の人たちがあこがれ、願い、ようやく手にした夢のような時代と場所に私たちは生きています。
20年前、私たちがアメリカのMOTEL(ラブホテルではありません)を泊まり歩きながら感じたのは、そんな自由のありがたさと厳しさについてでした。
なによりも大切なことは料金を含め多くの人が分け隔てなく気軽に泊まれること、そして、いろいろな個性や違いを受け入れ、少しずつ我慢しあうことが自由を支えているのだということ。
私たちの宿には、温泉やレストランなどの施設も、ことさらのお客さま扱いもありません。使い捨てのアメニティグッズも置いていません。
しかし、1号店からペット同宿を受け入れ(一部客室のみ)、ほとんどの店舗にバリアフリールームを設け、全館禁煙にはせず、2年前からの店舗には非常用の発電機を設置してきました。どれも私たちにとっては当然で大切なこだわりなのです。
マイカー旅行者のための素泊まりのミニホテル「ファミリーロッジ旅籠屋」は、アメリカンスタイルの、シンプルなロードサイドホテルです。
1号店オープンから18年あまり、「こんな宿を待っていた」という声に支えられ、ご利用者は延べ180万人以上、41店舗に増えました。全店直営です。
ご家族4人で1室10,500円から、おふたりなら1室8,400円から。おひとりなら5,250円から。
あれこれのサービスはありませんが、それが自由に旅を楽しんでいただくための特長だと信じています。
ファミリーやご夫婦でのドライブ旅行、ひとり旅、ビジネス出張、ツーリングやサイクリング。
どうぞ、気兼ねなく、好きな時に、好きな所に。
(新聞広告用に、大真面目にコピーを書いてみました。)
- 2013.03.31 求人難
-
おかげさまで少しずつ店舗が増えているので、当社ではほぼ恒常的に「支配人」を募集している。
平均年齢が50歳を超えていることでもわかるとおり、子育てを終えた中高年のご夫婦が多いが、最近は30代も増えている。
ミニホテルというと趣味の延長でできる仕事のように勘違いされる方も稀にいらっしゃるが、応募者の多くは何回かの転職を経験した「苦労人」が多く、二人が力を合わせ胸を張ってできる安定した仕事を渇望していらっしゃるように見える。そうした期待に応えられているかは直接確認いただくこととして、少なくとも「予断・偏見・先入観」にとらわれず、学歴や職歴ではなく人柄重視で門戸を開いているという点は我々の誇りとしているところである。
応募は断続的にあり、年間を通して面接を行い、その後「東京新木場店」での10日間ほどの研修を経て、業務の習熟を兼ねて「代行支配人」として各店舗を回っていただいている。その後、どちらかの店舗の「支配人」に着任いただくことになるのだが、すでに勤務期間が10年を超えるベテラン支配人も何組か誕生し、65歳の退年を過ぎても勤務いただいている方も増えている。興味のある方は、こちらをご覧いただき、ぜひお問い合わせいただきたい。
ところで、求人情報のページにもあるとおり、先月から本社の設計スタッフもあわせて募集している。
これまで、建物の設計については、すべて専属の設計事務所(と言っても、本社内に常駐していただいている個人事務所の所長さんひとり)にお願いしてきたのだが、コンスタントに出店できるようになり、既存店のメンテ業務も増えてきたため、ひとりでは処理しきれなくなってきたのだ。
当面はまず、この所長さんの設計業務を手伝っていただくことが仕事の中心になるが、いずれはハード全般を管理監督する責任者になっていただくことを期待している。
というのも、店舗数が増え当社の社員数は100名近くになっているが、本社スタッフは役員を含め10名足らず、誰もが幹部社員、あるいはその候補になれるような職場なのだ。
建物は、2階建てか平屋の小規模なものであり、建築雑誌に紹介されるような「作品」というわけにはいかないが、年間延べ30万人近くの人々が実際に寝泊りし、「シンプルで自由な旅」を体感いただく施設になっているのだから、その社会的意義はきわめて高い。
要するに、とても意味のある仕事、働き甲斐のある職場だと言いたいのだが、今のところ応募はゼロだ。
マスコミ報道を見ていると、就職難が叫ばれ、やり甲斐を感じられず悩んでいる転職希望者が少なくないということらしいが、当社は検討対象になっていないということなのだろうか。知名度の低い中小企業の宿命なのだろうか。そんな風にひがんでもみたくなる。
我こそは、という自信と意欲のある若い建築家からの問い合わせを待っています。
- 2012.12.25 商売繁盛、とはいかないかもしれませんが
-
アメリカのMOTELのような、誰もが気軽に利用できるシンプルで自由な宿泊施設を日本にも普及させたい。そう思い立って20年が過ぎました。
幸い、たくさんのお客様からの支持をいただき、店舗も本州から四国や九州へ広がってきました。その点だけを見て、商売繁盛ですね、と声を掛けてくださる方もあるのですが、それは違うんですと申し上げたくなります。
というのも、ようやく安定して黒字を出せるようになったといっても、その額は実質で毎年1000万円程度ですし、そもそも売上高や店舗の数などを目標にはしていないからです。
例えば、店舗の数。40近くに増えましたが、それはこうした宿泊施設を全国津々浦々に誕生させて、自由な旅のスタイルを提案し、サポートしていきたいという願いがあってのこと。ですから、赤字の店舗であっても撤退したことはありませんし、今後もそのつもりはありません。また、収益性の高い大都市圏ではなく、あえて地方の空白地帯に優先して出店してきました。
次に、多様性への対応。旅は個人の自由の象徴であり、そのためには可能な限りすべての旅行者を分け隔てなく受け入れ、さまざまな旅の受け皿になろうというポリシーです。そのために、手間や費用が増えるのを承知でバリアフリールームや非常用発電機を設置しペット同宿の受け入れなどを続けてきました。お客様からのお叱りにも関わらず使い捨てのアメニティグッズを置かず、全館禁煙に踏み切らないのも同様の理由です。自由を尊重することはお互いが違いを受け入れ少しずつ我慢しあうことだと考えているからです。
そしてもっとも大きなことは、役所との許認可手続きや、施設所有者の方々との交渉の進め方です。ひとことで言うと、目先の効率や結果を優先させず誠実でまっとうなやり方にこだわってきました。
素泊まりのロードサイドホテルというのは日本では新しい業態の宿泊施設ですから、法令は足かせになり、世間の目は偏見で曇っています。ついつい顔色を伺ってご機嫌をとりたくなるのですが、あえて審査会を重ねたり、審査請求をしたり、何年もかけて説明会を繰り返したりしてきました。
商売繁盛と言われて感じる違和感は、効率や利益にとらわれず努力してきたのに、一部の数字だけしか見られていないという悔しさなのです。
今までなかった商品やサービスを提供するという意味で、「ファミリーロッジ旅籠屋」は、間違いなくベンチャービジネスと呼べるものだと思います。しかし、ベンチャー企業は既存の企業が打ち破れない旧弊や価値観に風穴を開け、問題提起をしていくことにこそ値打ちがあるのだと信じています。事なかれ主義や馴れ合いやごまかしに染まらないことが存在する意味です。
4年前、高速道路のSA・PAに分割民営化後初めての宿泊施設を実現させた時、「政治家とのコネがあったんだね」と言われましたが、そんな方法があることを考えもせずに実現できたことが我々の誇りなのです。
先日、二代目経営者の多い業界の集まりに参加する機会がありました。人並み外れた情熱と実行力で起業した先代に比べ迫力に欠けると嘆く声もありましたが、二代目ならではの難しい立場や悩みもあるようでした。
老舗旅館はもちろん、宿泊業界も同族経営や世襲が少なくないようです。若い世代の方々がしがらみに囚われず進むことが大切だと思います。
リーマンショックや東日本大震災の傷も癒えないなか、2012年は隣国との領土問題や政治の混乱が続き、とても心穏やかに新年を迎えられる状況ではないようです。
海外からの旅行者が減り、国内でも観光旅行の手控えが顕著です。若者の車離れもゆとりや希望を失って消極的になっている結果かもしれません。
でも、旅は人間にとって本質的なもの、宿泊施設は一時の流行を追うべき事業ではありません。
あるお客様から「昔、赤ん坊を連れて泊まりましたが、今はその子が孫と一緒にお世話になっているようです」という便りをいただきました。何のサービスもない宿ですが、ご家族の思い出の舞台になっているわけで、こんな嬉しいことはありません。
また、車椅子での一人旅をされた女性から「気配りが心にしみました。旅に出るのが楽しくなりました。また、がんばれそう・・・」というメールをいただきました。
宿泊業は単調な仕事の繰り返しです。基本は地味な裏方仕事です。でも、人間が人間らしく生きていくために無くてはならない仕事だと信じて疑いません。商売繁盛、とはいかないかもしれませんが、笑顔と優しい気持を忘れず、時を紡いでいきたいと思います。
新しい年が、心のゆとりを失わない1年になりますように。
月刊「ホテル旅館」(柴田書店発行) 2013年1月号「2013年新春展望」より転載
- 2012.09.03 走ること
-
ジョガーになって数年、年間1200kmは3年続いてるけど、月間100kmとなるとなかなか続かない。
たまたま今年は1月から途切れていなかったので、8月も頑張った。
夏は、ランニングには厳しい季節。蒸し暑さで気力もすぐに萎えてしまうので、日を空けずにチョコチョコ走る。
そして、31日の夜、なんとか目標達成。
走ってると言えないほど遅いけれど、日常的に汗を流すのが良いと思っているので、私の場合は、これで満足。
走り終えた後、ひとりじんわり嬉しくて、帰宅後の冷えた麦茶もサイコー。自分に乾杯!
正直に言うと、けっして走りたくてたまらないから走るわけじゃない。
走っている間も、楽しいという感じじゃない。どちらかというと、やっぱり苦痛だ。
健康に良いから、意志強く目的意識を持って続けているというわけでもない。
ただ、一度の例外もなく、走り終えるとかすかな達成感を味わえるので、それを信じて、とにかく走り出す。
この感覚、バイクのロングツーリングによく似ている。
風を切って進む気持ち良さもあって、 ランニングと違い、もちろん、走りたくて走り出すのだが、距離が長くなると途中はつらくなる。
肩は凝ってくるし、お尻も痛くなってくる。そこが高速道路だったりすると単調で飽き飽きしてくる。
ふと、何してるんだろう、と思う。
移動するだけなら、4輪のほうがずっとラクだし、そもそも家でのんびりテレビでも見ている方が良かったかなぁと思ったりもする。
7月、みんなでリレーマラソンに参加するため、秋田まで往復した時は、まさにそういう気分だった(その時のレポートはこちら)。
さらに考えてみると、「ひとり旅」も似たようなものかもしれない。
ワクワク、ドキドキしながら旅立ったものの、あてのない旅は、孤独感や疎外感に襲われて、必ずしも楽しい時間にはならない。
貴重な休みをつぶして、お金も使って、俺は何をしているのだろう、という気持になることもある。
見識を広めることが将来に向けて自分の財産になる、と言い聞かせてみるが、本当にそうなのかと疑う自分もいる。
ホンダのCMじゃないけど、そんなの幻想だ。
自分にとっての財産は、たいていの場合、楽しいことより、嘆息の日常の中にある。
ランニングの最中は、極端に思考能力が低下するから半ばぼんやりしているが、
バイクだとある程度頭も働くので、思考が横滑りしながら、飛躍していく。
そして、とうとう「人生も似たようなものかもしれないな」という考えに達する。
いろいろ勉強させられ、義務やら権利などを教えられ、有為な人生を歩め、と諭されて大人になってきたが、そもそも明確な意志や意欲や夢や目的意識を持って生まれてきたわけじゃない。
いろんな本能的欲求に衝き動かされながら、右往左往してきただけじゃないか。
食べないと生きていけないし、仲間外れにされると生きにくいので、親や教師や友達や同僚や上司や親類や家族や隣人の顔色を見て世渡りしてきただけじゃないか。
そして、心から楽しく喜びを感じる瞬間はほんのわずかで、単調な毎日にため息をつきながら、我慢し続けている時間のほうが圧倒的に長い。
ランニングも、ツーリングも、旅も、人生も、同じ・・・
そんなことを言いながら、またまたホンダのCMのフレーズを借りる。
だからどうした! スタートは、そこからだ!
幸か不幸か、哲学的な悩みで人生を棒に振るほどナイーブじゃない。
先がどうであれ、走り出せばいいんだ。
というわけで、今度の株主総会の日の晩から、5泊のツーリングに出る。
何十年ぶりだろう。
これに備え、バイクもちょっと改造した。
シートをシングルにして、バッグをフレーム直付けに。
ヘルメットにスピーカーを付けて、携帯ナビの音声が聞こえるように。
半分は仕事だけれど、とっても楽しみ。
さて、長い道中、どんな思いが頭の中をよぎるのだろう。
健康に感謝、平和に感謝、自由に感謝。

Before

After
- 2012.05.09 最後の愛車?
-
先日、還暦を迎えた。自分が60歳だなんて、まるで実感がない。
それはともかく、ひとつの区切りだから、自分で自分にプレゼントを贈ることを企てた。
迷わず選んだのはオートバイだ。
もう40年近く切れ目なく乗り継いできたが、最近はホコリをかぶらせてしまうばかりで、たまに乗ろうとするとバッテリー上がりだったり故障していたりで欲求不満がつのっていた。これではイカンと思っていたし、去年あたりから気になって仕方ないバイクも発売されていた。
HONDAのCB1100

と 、KAWASAKIのW800

である。
欲しくなると、60歳どころか10歳の子供のようになってしまう。 カタログを取り寄せ、バイク屋に実物を見に行き、またがったり眺めたりする。
もう止まらない。
決して安い買い物じゃないし、ロクに貯金もないのだから、 衝動買いではないかと60歳の自分が戒める。
しかし、数日経っても思いは冷めない。
東京マラソンも板橋Cityマラソンも、歩かずに5時間切って完走できたことをネタに(もちろん、これらは何の関係もないことなんだけど)自分を説得し、ついに心を決めた。
候補にした2台は、ともにナナハンを超えるビッグバイク。これまで250cc以下のバイクしか所有したことのない私にはドキドキものだ。
だからこそ憧れもある。
いずれも、中年以上のリターンライダーをターゲットにしており、オーソドックスで懐かしい雰囲気。プラスチックを多用した最近のバイクと違い、質感も高い。違いのわかる大人のためのバイク?
迷ったあげく、自分の体格と体力を考え、W800を選ぶ。ちょうど3月1日に新色が発売されたばかり。これはいい。黒に赤。還暦にぴったりじゃないか。
断腸の思いで、2台の愛車を中古バイク屋さんに売り、縁あって紹介された岡山のバイク屋さんに注文する。
そして、約1ヵ月後、なんとか仕事のやりくりをつけて空路岡山へ飛び、津山市のパドックさんに駆けつけ、感動の対面を果たす。
ちなみに、このバイク屋さん、広々とした敷地と店内の雰囲気が素晴らしい。そして何より心のこもったサービスで気持ちの良いお付き合いができるお店だ。「こんなバイク屋さんがあったんだ」と嬉しくなること間違いないので、一押しです。
というわけで、ついに念願の還暦祝いを手に入れ、それも想像したよりずっと乗りやすく楽しいバイクなので大満足。
岡山から店舗に立ち寄りながら東京へ戻った片道ツーリングや、建築中の「富士都留店」や「秩父店」の現場回りや、久しぶりの「軽井沢店」訪問など大活躍。

歳も歳だし、これを終のバイクとして大切に乗り続けるつもり。
いろいろな意味で、ほんとうに、良い買い物をした。
しかし、ロングツーリングをしようと考えると、東京の立地条件の悪さが際立ってくる。
そのあたりの話しは次回に。
- 2012.03.27 非常用発電機を設置
-
(IRリリースレターより転載)
昨年3月の東日本大震災の際には、東北地方を中心に10店舗以上で停電が発生しました。照明や通信設備ははもちろん、冷暖房や給水・給湯も電源を必要としているため、宿泊施設としての機能の多くを失う状況となりました。こうした店舗では、すぐに客室を無料開放したのですが、水もお湯もトイレも使えず、避難されてこられた被災者の方々にご不自由をおかけすることとなりました。ほんとうに悔しく情けないことでした。
当社では、非常時の際、宿泊施設は緊急避難場所=シェルターとしての役割を果たすべきだと考えています。雨風をしのぐスペースと寝具、最低限の食べ物と水があれば、命をつなぐことができます。こうした機能を提供できることが宿泊施設のユニークな特徴であり、社会的使命だと信じているからです。

ついては、具体的には、震災後から必要条件を満たす非常用発電機の調査を行って最適の機器を選定、昨年オープンの「袖ヶ浦店」に続き、「宮島SA店」への設置も完了しました。
なお、この発電機はプロパンガスをエネルギー源とするもので、石油などの備蓄が不要で常設のガスボンベが活用できます。
また、あらかじめ施設全体の配電盤に接続しているため、特別な切り替えなどを行うことなく既設の電気機器に通電されます。
しかも、停電時の起動から、電源回路の切り替え、通電再開時の停止などがすべて自動で行われます。
ただし、発電能力に制限があるため、冷暖房設備などは稼動が困難ですが、照明・通信・テレビ・給水給湯設備は通常通り使用可能となります。
ガスボンベ1本で8時間程度の連続運転が可能なため、数日間は電気を供給し続けることが可能な見通しです。
こうした非常用の設備は平時は不要なものであり、一定の費用負担を生じるため、導入決定には社内でも議論のあったところです。しかし、多様な方々に安心して快適に宿泊いただくことが当社のポリシーであり、バリアフリールームや誰でもトイレと同様、標準化を決断した次第です。
今後、建築中の「富士都留店」「秩父店」を含め、新店舗には同様の設備を常設する予定です。
- 2012.02.23 幻の九州出店
-
「富士都留店」に続き、来週には「秩父店」の工事が始まる。これで、夏休み前には本州で「旅籠屋」のない府県は青森、神奈川、富山、福井、愛知、和歌山、京都、大阪、兵庫、岡山、鳥取、島根のみとなる。店舗数を追い求めているわけではないし、全国制覇などという言葉への憧れもないが、ロードサイドホテルというインフラ施設を津々浦々に普及整備させて、自由な旅の受け皿のひとつにしたいという夢が実現していくのはとても嬉しい。
そんなわけで、以前から早く九州にも店舗を誕生させたいと努めてきた。ところが、これがなかなか実現しない。じつは昨年の秋、ある有名観光地での出店が決まりかけたが、最後になって白紙に戻ってしまった。ほんとうに、ほんとうに残念である。念願の九州1号店が消えただけでなく、実現していれば地域貢献の理想的な姿となる可能性を秘めていたからである。
最近、地方の自治体から出店の打診をいただくことが少なくない。宿泊施設は域外の方が長時間滞在するため確実な経済効果が見込まれる。「旅籠屋」のような宿泊特化の宿であれば、食事も買い物も地元の施設が利用されるわけだから尚更である。そして、宿自身が集客のために地域PRを行う。一過性でない地域振興を長期間にわたって担い続けることになるのだ。
加えて、宿泊施設は遊休地活用という面がある。予約客中心だから、必ずしも幹線道路沿いでない土地でも生かされる。「建て貸し」であれば、地主・家主である地元の企業や個人は家賃という形で長期間にわたる収入を得ることになり、地元の建築会社に仕事が生まれ、資金調達を通してお金が回っていくことになる。
今回の件は、ある町の観光協会からの一通の問い合わせメールから始まった。
全国に知られる観光地でありながら、民宿以外の宿泊施設がない。全国的に名の知られた町でありながら観光シーズンに偏りがあるため大規模な施設は難しく、訪問者は近隣の街に流れて行ってしまう。町有地を借り、観光協会自身が建築資金を負担して、「旅籠屋」がホテルの経営と運営を行う、というスキーム=枠組みである。町役場、町議会、地元の金融機関への提案と説得も進んでいるという。
国の補助金や大手ディベロッパーの投資を待つ他力本願ではなく、町自身が資金を調達しリスクをとって宿泊施設を実現しようというアイデアと熱意に目からウロコが落ちる思いだった。これが実現すれば、全国の自治体が自力で施設誘致を行い、自ら地域振興を具体化する画期的な先例になる。損得計算は二の次で、この計画に参加するのが「旅籠屋」の使命だと即断した。
間を置かずに建物の基本計画や出店条件をまとめ、現地に向かった。町長さんや議会議長さん、担当部署の方々を前にプレゼンを行い、皆さんの熱意と理解を確認することもできた。あとは、議会の承認をいただくだけという段階を迎えた。昨年末の話である。
しかし半月後、冒頭にも書いたとおり、計画は突然すべて白紙に戻ってしまった。たったひとつ、観光協会が行う借入れについて、町が銀行に対する損失補てん契約を行う点についてトップの決断が得られない、そのハードルだけが越えられなかった。
調べてみると、夕張市が破綻した後、総務省から自治体による損失補てんは原則禁止という指導が行われたとのこと。あくまで原則だから、首長判断で踏み切ることは可能なのだが、簡単な決断ではないということらしい。長期間にわたる責任が生じることを考えれば、慎重を期したいという判断も理解できないことではない。
こうして、九州への初出店の話しは幻に終わってしまった。もちろん、同時に通常の出店の話しは進んでいるから、遠からず「旅籠屋」は九州のどこかでオープンするだろう。しかし、そこに住む人たちが皆の知恵と勇気と意志が光り輝やく一灯は掲げられることなく消えてしまった。
残念である。ほんとうに、ほんとうに残念である。しかし、こうしたスキームはどこでも応用できることである。きっと、いつかどこかで・・・。
- 2012.01.20 個人保証なしの融資
-
前回も書いたが、昨年末、念願の代表者個人保証なしの融資が実現した。
ひとつは東京都民銀行(期間1年)、もうひとつは商工中金(期間5年)である。
いずれも、これが初めてのおつきあい。当方から求めたことではあるが、いっさい何の保証もなく融資いただけたことに感激するとともに、正直少し驚いている。当社の事業の将来性や堅実な経営を評価いただいた結果であるとすれば誇らしいことだが、未上場企業において例外的なことであることを考えれば、担当者および支店長の熱意と英断に敬意を表したいと思う。
それにつけても、10年以上も前から取引きいただいてきた金融機関に踏み切っていただけなかったのは残念だった。それぞれの事情はあるのだろうが、金融機関も昔のような横並び体質は変わってきているようで、先例にこだわらない判断を強く求めたいと思う。
そもそも、安定して事業を継続している企業の長期的な発展を考えれば、創業者個人に永続的な関与を求めることは事業の承継を困難にすることを含め健全性を阻害する面があり、今回のケースが中小企業にとっての画期的な先例になればと願っている。
- 2011.12.05 小さな一歩
-
以前にも書いたことだが、1年半ほど前から、取引先金融機関に対し、「今後は借入の際の社長の個人保証条件を外して欲しい」と要請してきた。
十数年前、初めてプロパー融資を行っていただいた信用金庫や、初めて融資いただいたメガバンクには恩義を感じており、真っ先にお願いしてみたのだが、「先例がない」という理由で断られてしまった。取引年数も長く、当社の状況もよくご存知のはずなのに残念なことだった。やはり、金融機関は保守的で、相変わらず横並び体質なのかもしれないと思った。
しかし、諦めるわけにはいかない。設立当初の企業や同族経営の会社ならば一定の合理性があるが、株式会社として社会性と継続性を重視する企業にとって、社長の個人保証は健全な発展の阻害要因となる。不合理な慣習に挑戦するのは当社のDNAであり、存在価値に関わることだからである。「それでは、今後のお付き合いは難しくなります」と意地を張ってきた。幸い、運転資金に困ることはない。
こうして状況が変わらないまま1年が過ぎた。
ところが、今秋「勇気ある経営大賞」の優秀賞受賞のおかげでいくつかの金融機関から「新規の取引を」というお誘いをいただき、同じ条件を提示したところ、ひとつの銀行から「問題ありませんよ」という回答をいただいた。最初は半信半疑だったが、初めての取引にも関わらず、物的人的担保もなく、金利条件も変わらずにすでに融資が実行された。
小さな一歩かもしれないが、ベンチャー企業としての役割を果たせたという意味で、正直嬉しい。
先に書いた三菱東京UFJ銀行の口座もとうに解約した。
これは、何のために企業があり、社会的意義や責任というものをどう考えるかという根本問題なのだ。
- 2011.11.19 我が家の111111
-
2011年11月11日、婚姻届けや記念切符を買い求める人々のニュースが報じられていたが、
我が家では、愛犬が5回目の入院から戻るという、不安と喜びで心落ち着かない日となった。
最初の入院は、9月25日、歯茎にできた腫瘍のための検査入院だった。
病理検査のために軽い全身麻酔で細胞をとるだけのはずが、翌日から体調が激変し、2度目の入院。
さらに腹部からの出血と高熱により、半月に及ぶ3回目の入院。
腫瘍の治療どころか、下腹部、胸、両前足の皮下脂肪が壊死して血と膿が流れ続ける異常事態となり、死を目前に緊急輸血で命をつなぎ、必死の治療が続けられた。
毎朝毎晩、好物の料理を持参してわずかな散歩と食事を与える病院通いの毎日が始まる。
ところが10日後、最悪の状況を脱したかに見えた矢先に、今度は右後ろ脚の股関節脱臼。
これはもう元には戻らないと聞かされ、絶望的な気持ちになった。
この頃が、最悪の時期だったかもしれない。
数日後、病院にいるよりも家で介護する方が良いという判断で、退院。
獣医さんが毎日のように往診してくれ、壊死して開いてしまっている胸や肘の部分を麻酔無しで何回かに分けて縫い合わてくれる。
少しずつではあるが、傷口は狭まり、出血も減って、生気が戻るのがわかる。
しかし、ここまでは当面の危機的症状を抑えるだけで、抜本的な治療は何も始まっていない。
そして2週間、今度は陰部からの出血がひどくなり、各所の炎症は子宮が元凶ではないかとの疑いが濃厚になり、専門施設でCT検査。
予想通り、子宮・卵巣・脾臓の一部に異常が見つかり、急遽、摘出手術を行うことになる。4回目の入院。あわせて、歯茎の腫瘍切除手術も行う。
これで、3つのうち2つの原因にメスを入れたことになる。
幸い術後の経過が良く、翌日には退院。
たしかに、元凶を取り除いたおかげで、下腹部や胸・両肘の傷口も目に見えて治まっていく。
ところが、1週間後、脱臼している後ろ脚の痛みのせいか、歩こうとしなくなる。このままでは、筋肉が萎え、腰にも異常が出てくる危険性があるらしい。もっと先になってからと思っていたが、ここで、とうとう右後ろ脚大腿骨の骨頭切除手術を決断する。
大型犬では賛否両論あるらしいが、「骨同士の接触による痛みがなくなり、筋肉の回復によってかなりの程度自由な歩行が可能になる」という医師の強い勧めに従うことにした。
そして、11月10日、5回目の入院で、骨頭切除手術。
翌日、どんな姿で戻ってくるか不安でならなかったが、ちゃんと右脚を地面について歩いてくる。嬉しそうに尻尾を振りながらすり寄ってくる。
「痛い思いをするのは、これで終わったからね」と言いながら、抱きしめる。
そしてきょうで、丸8日が過ぎた。
食欲旺盛、寝てばかりいたのにすぐに起き上がり散歩に行きたがる。 ソファにも上ろうとする。
明らかに痛みが減っているのだろう。普通の生活に戻ろうとしている。
このまま少しずつ関節周りの筋肉を戻していけば、半年ほどで走れるほどに回復する可能性もあるという。
走れなくてもいいから、ストレスなく自由に歩き回れるようになれば、それが彼女にとって何よりのことに違いない。生活の質が保たれる。
今6歳。大型犬の寿命は短いが、それでもまだ半分。この先、1日でも長く生き生きと暮らしてほしいと祈るばかりだ。
今、ソファの脇で穏やかに眠っている。
それだけで、嬉しくてならない。
この2ヶ月、仕事もほんとうに忙しく、膝の故障もあってランニングも間が空いてしまっている。
吐き出したい思いも溜まっているのだが、心身ともに余裕のない毎日だった。
しかし、ようやく愛犬の病気もようやく快方に向かい、心も少しラクになってきた。
やりたいこと、やるべきことは山のようにあり、際限ないのだが、そろそろ、立ち止まってこの日記に書き付けていこうと思う。
- 2011.09.09 旅籠屋の生命線
-
本日、予定通り定時株主総会を開催し、初めての配当実施の件も承認可決された。
振込先を登録されていない方々には、領収証を郵送し、これを所定の金融機関の窓口に持参いただき、現金を受け取っていただくことになる。所定の金融機関は、三菱UFJ信託銀行、りそな銀行、三井住友銀行の3行である。
これらの銀行には、事前に配当金支払事務委託依頼を行ったわけだが、じつは別の銀行に断られた経緯がある。
三菱東京UFJ銀行である。
グリーンシートに登録して以来、当社の株式事務代行は三菱UFJ信託銀行にお願いしているが、信託銀行は支店の数が限られているため、全国に支店網を持っている都市銀行も加えたほうがよいということで、系列の三菱東京UFJ銀行に問い合わせたわけだ。
当社が口座を持っているのは東京本店営業部なのだが、担当者はいかにも面倒くさそうに「窓口業務を含め、事務受付を行っていないので、受けられません。別の支店に問い合わせてください。その支店が受付を行うかどうかは支店の判断です」と繰り返すばかり。
まさか断られるとは思っていなかったし、納得できる説明ではなかったので、翌日上席の方と電話で話しをした。
頭をよぎったのは、17年前、会社設立の際に、資本金の保管証明書の発行を断られた悔しい記憶である。
(2000年7月20日の日記に「最近、頭にきたこと」と題してその経緯を書いているので、参照ください。こちらです。)
法的に義務付けられたことではないとはいえ、経済活動のインフラを支える企業として、原則無条件に受託する社会的責任があるのではないか、というのが私の言い分で、上席の方も「個人的には理解できますし、申し訳ないと思いますが」と言っていただいたものの、「総合的な判断として、お受けできないのです」ということだった。
17年前、第一勧業銀行に保管証明書の発行を断られたあと、大嫌いなコネを使って三和銀行に引き受けてもらったのだが、考えてみたらそれは現在の三菱東京UFJ銀行ではないか。その事実を申し上げたら、「再度、協議してみます」とのことだった。
しかし、数時間後「昔のことで当時の書類も破棄されており、結論は同じでした」という返答があり、話しはそこで終わってしまった。
一部の大企業に特化するという方針なのだろう。
保管証明書の発行も配当金支払事務の受託も、反社の問題を含めトラブルに巻き込まれるリスクを負いたくないということなのだろう。
そうした理由を正直に明かすこと自体が批判の対象になるということで「総合的判断」としか答えないのだろう。
情けないなぁ。残念だなぁ。日本を代表するリーディングカンパニーなのだから、尚更である。
銀行としての社会的使命感は、どこで置き去りにされてしまったのだろう。
風評やいわれなき批判には胸を張って仕事をする姿勢は、どこで失なわれてしまったのだろう。
17年前の一件以来、当社はみずほ銀行との取引はいっさい行っていない。
今後、三菱東京UFJ銀行との取引もすべて行わないことにした。
自動引き落とし先の変更がすべて終わったら口座も解約する。私個人の口座も閉じることにした。
こんなことをしても、先方には痛くも痒くもないことだろう。
だから、自己満足にすぎないこともわかっている。
腹いせでそうするわけではない。ケンカするつもりも毛頭ない。
ただ、このままにしてしまうと、なにひとつ状況が変わらない。
理由も明らかにせず、取引を拒むということに対して、当社としては預金口座を解約するということでしか異議申し立てをする方法がないというのも情けない限りだが、万に一つの可能性であっても、声なき声が届いて欲しいという願いを込めてのことである。
「仕方ないよ」と諦めず、世の中の大勢や「当たり前」に流されずこだわりを持ち続けることがベンチャー企業の存在意義だというのが当社の信念である。
借入の際の経営者の個人保証の撤廃についても、粘り強く「慣例」の見直しを求め続け、ようやく突破口が空けられそうな状況が見えてきている。
旅籠屋のためだけに言っているのでは断じてない。当社が先例となることによって、後ろに道ができる。思考停止の停滞に風を送り込むことができる。そう期待し、願ってのことである。
先例のない事業を興してきたこと、小企業でありながら信頼を得てきたこと。
この信念と姿勢が旅籠屋の生命線である。
- 2011.08.30 初の配当、初の役員賞与
-
節電に協力しようというわけで、今年、本社はいっせいに夏休みをとった。
店舗がもっとも忙しく大変な時期に、という後ろめたさもなくはなかったが、それぞれ役割が違うのだし、そんな表面的で形式的な気遣いは無責任の裏返しだと割り切った。休み中といえども、問題があれば対応する。本社機能を停止するというわけではない。
6月末が決算日なので、例年7月に入ると会計監査が始まり、複雑な決算手続きに忙殺される。
四半期決算もそうだが、だらだらと長引かせたくはない。遅くとも1ヶ月前後で公表したい。
規定では45日以内にリリースということになっているようだが、見る方だって、2ヶ月近くも前に終わった「過去の状況」では興ざめだろう。
会計監査というのは、一言で言えば「あら捜し」のようなものである。会計基準そのものが朝令暮改だったり、異常に複雑だったり、合理性を欠く部分が多いこともあり、監査の過程で監査法人の公認会計士と議論することも少なくない。
企業の状態を適正に表示するために、誤りや不正がないかをチェックする、この点に異論はないが、以前書いた「ファイナンスリース」の処理など、多くの人がにわかに理解できないような基準を持ち込むのは一部専門家の自己満足ではないかと思ったりもする。
そんなこんなで、ほんとうに面倒くさい1ヶ月が続くのだが、否定的にとらえているわけではない。年に一度の「会社の健康診断」のようなものだ。胃に潰瘍の痕が見つかったり、血圧の高さが指摘されたりするが、その方が良い。自覚症状がないので健康だと思っていたら手遅れの病気だったなんて許されない。会計監査はグリーンシートに登録したことによる「義務」なのだが、ありがたい「権利」とさえ言いたいところだ。
さて、こうして8月5日に「第17期決算速報」をリリースし、その数日後には「株主総会の招集通知」を納品した。
そこには、初めての議案がふたつある。 ひとつは配当金の支払い。もうひとつは役員賞与の支払いだ。
昨年の減資によって累積損失がなくなり、黒字決算が継続できたことで具体化できたことだが、会社設立から17年かかった。
黒字とはいえ、利益は1千万円ほどだから、内部留保すべきだという迷いも意見も当然あったが、慎重に考えていたらキリがない。
配当は1株1,000円で6,245,00円、役員賞与は経常利益の10%で1,800,000円。初めて報われる。感無量である。
黒字を着実に増やして、これをずっと継続したいものだ。
- 2011.04.26 「ファミリーロッジ旅籠屋」の価値
-
震災の発生から、1ヵ月半の時間が過ぎた。
いろいろなことが起こり、いろいろなことを考えた。
以前、株主の方から、「ファミリーロッジ旅籠屋」の価値が見えない、という指摘を受けたことがある。
当時は抽象的な言葉でしか答えらず、あえて返事をしなかったが、今回3つのことをお話したいと思う。
ひとつめの価値、それは空室のある限り、すべての方の宿泊を受け入れたということ。
我々は予断・偏見・先入観にとらわれずにお客様を受け入れることを大切にしている。その姿勢を貫くことが個人の自由や多様性を守ることなのだという信念がある。さらに言えば、日本がこうした個人の自由や多様性に寛容な社会になって欲しいという願いがある。
平時は、こんなことを言ってもなかなか理解してもらえない。あるいは、当たり前のことだと見過ごされてしまうが、ペット同宿を受け入れたり、利用頻度は低くてもバリアフリールームを設けたり、というのは同じ思いからである。
地震直後、30店舗のうち10店舗で、停電や断水が発生した。真っ暗で暖房も給湯も困難、水が出ないのでトイレも流せない。それでも、被災地に近い店舗には家を失った方々が訪ねてこられる。数日遅れて、原発周辺からの方々も増えてくる。宿としての最低限の機能も提供できないので、無償で受け入れるよう指示した。福島ナンバーの車を忌避するなど、考えもしないことだった。
放射能汚染に限らず、新型の伝染病が流行したり、テロや「異常な」犯罪が頻発したりすると、宿泊拒否の話しが聞こえてくる。宿泊施設は、社会の空気にさらされている。風評に惑わされがちな感情と科学的な理性とのせめぎあいの場所にある。
宿泊特化の宿には、ユニークで特別なサービスなどない。だから、否定的な風評にさらされれば、たちまち利用者は引いてしまう。「真偽や是非はともかく、あえて評判の悪い宿に泊まることもないだろう」というのが、大方の本音なのだ。だから、宿の側は空気に逆らわないように保守的になる。
こうした中でスタンスを守るのは、実は想像されるよりはるかに困難なことだ。大きな手間とリスクを引き受ける覚悟を求められているということなのだ。
ふたつめの価値、それはホームページ上で、宿泊者の安否情報を最優先で伝えようとしたということ。
宿泊施設は、ほんの一部とはいえ、利用者にとってのかけがえのない人生の時間や空間を提供している。だから、泊まられる方々の安全やプライバシーを守ることが最大の責務である。そして留守宅には無事の帰りを待つ家族や友人や同僚がいる。
過去と同じく、今回も地震発生直後に行なったのは店舗へ連絡し、けが人の有無を確認し、その情報を真っ先にトップページに掲載することだった。
他の宿泊施設のホームページを見たが、翌朝まで更新されない施設が多かった。そして、予約受付の可否や、通常営業しているかどうかの情報が中心だった。
電話の通じない地域が多かったし、一番大切にすべき気持ちやメッセージが抜けている気がした。
余談だが、「ファミリーロッジ旅籠屋」の建物が地震に強いことをあらためて確認できた。せいぜい一部に細かなクラックが生じた程度である。地面が波打って、駐車場の一部が20cmほども陥没した店舗もあったが、建物はまったく無事である。遮音性能向上の工夫が、結果として堅牢な構造を実現しているようだ。
とにかく、人も建物も無事でほんとうに良かった。
みっつめの価値、それはぎりぎりまで踏みとどまり営業し続けたということ。
残念ながら、「仙台亘理店」(ライフラインがすべて途絶し、来館者もほぼ皆無だった)、「いわき勿来店」「須賀川店」(福島原発が不測の事態を招く危険性が高い時期があった)の3店舗が一時閉鎖を余儀なくさせられたが、いずれも10日ほど後に営業を再開した。
頻繁に起こる余震や、停電や断水が続きガソリンや食料も手に入らない不自由な生活、そして放射能汚染の目に見えない恐怖。支配人の不安や疲労は察して余りある。こうした状況の中であえて支配人に現場復帰を求めたのは損得ではなく使命感だった。
避難であれ、支援であれ、復旧であれ、復興であれ、人が動き活動するためには泊まる場所が必要なのだ。こうした時期に被災地へ赴く人たちには強い意志と責任感がある。こういう時だからこそ店を開けて宿泊施設としての責務を果たしたい。こうした使命感への理解がなければ、支配人達が復帰してくれることはなかったと思う。
以上3つのことは、考えてみたら当たり前のことばかりだ。
照明は必要以上に明るくしない、使い捨てのアメニティグッズは置かない、安心してお泊りいただくこと以上のサービスはしない、不採算店であっても撤退しない。こうした普段からこだわっていることを含め、いずれも地味なことで、普段はセールスポイントになるようなことではない。そのくせ、守ろうとすると事業経営の面ではマイナス面もある。
でも根っこはひとつなのである。
ポイントカードによる顧客の囲い込み、割安感を維持するための料金見直し、ターゲットをしぼった広告戦略、朝軽食メニューの充実、さまざまなご提案をいただく。ありがたいことだし、そういうアイデアを機敏に取り入れることが経営者に求められる才覚のひとつなのだろうとも思う。
しかし、どこか気乗りしない、小手先のテクニックを弄するのはさもしいと感じてしまう。
根っこは同じである。
少なくともロードサイドホテルは旅行者のベースであって、アミューズメント施設ではない。雄弁に語る外向きの演出や集客の策よりも、いつでも安心して宿泊できる宿が存在し続けているという確かさを中心に考えたい。
このようなことが「ファミリーロッジ旅籠屋」の価値であり、「らしさ」なのだということをこの機会に再評価いただければという願いがある。そして、社内ではしっかり共有して欲しいという強い思いがある。
震災の発生から、1ヵ月半の時間が過ぎた。
さまざまの難しい判断があり、さまざまの行動があった。
感情の力があり、意志の力があった。
しかし、根底で支えていたのは誇りだったと思う。
誇りを真摯に守り続ければ、品格につながると思う。
そういう会社を目指したい。
- 2011.03.30 営業再開
-
2日前、約半月ぶりに全店そろっての営業に戻した。
「仙台亘理店」は3/11〜23の13日間、「いわき勿来店」は3/17〜27の11日間、「須賀川店」は3/18〜27の10日間の一時休業。
1995年夏の1号店オープン以来、一日も欠かさずお客様を受け入れてきた時間が、途切れた。
原発事故の収束が見通せない状況だから、これからも何が起こるか楽観できない。
しかし、今は、とりあえず宿泊施設の使命が果たせることに、正直、安堵している。
3/11の地震発生から、20日間近くが過ぎた。
当初のパニック状態が少しずつ収まるにつれ、逆に長期にわたる不安が浮かび上がってくる。
「旅籠屋」にとっても、影響は少なくない。
被災地の近くの店舗だけでなく、広域でキャンセルが相次いでいる。
春休みの旅行を取りやめたご家族が少なくない。
リーマンショック後の不況のように、ビジネス出張も節減の対象になるかもしれない。
意外なところでは、すでに工事を進めている新店の建材資材の一部に納品の遅れが出ている。
夏には、大規模な計画停電も予想されている。
混乱の中でも規律を守る日本人に、世界から驚きと賞賛の声が寄せられているようだが、それは「右へならえ」で動きがちな特性にもつながる。
夏休み、みんながそろって旅行を自粛するムードになるのかもしれない。
オイルショックの時のように、政府やマスコミが「不要不急の時のマイカー旅行は控えましょう」などと言い出しそうな気もする。
語弊を恐れずに言いたい。
右腕が大怪我をしたからといって、寝たきりになって安静にしていることが良いとは思わない。
幸いなことに、無傷の左腕も、両脚もあるじゃないか。
手術の翌日から歩け歩けと言われるように、右腕を守りかばいながらも動きを止めず、血をめぐらせ、体力を維持していく。
痛みに負けず、しっかり食べて、前向きな気持ちを失わない。
そのように元気に毎日の暮らしを続けるからこそ、勤勉で、誠実で、優しく知的な個性をさらに輝かせることができるのだと思う。
そうした意味で、昨夜のサッカーのチャリティーマッチは素晴らしい挑戦だった。
「こんな時に不謹慎じゃないか」という後ろ向きの批判を恐れず、 「目立たないことが無難」という考えに逃げ込まず、
ひとりひとりが自分で考え、それぞれの持ち場で行動していけば良いのだ、という前向きのメッセージを発信してくれたと思う。
再開した店舗では、さっそく復旧関連の方々のご宿泊が増えている。
「佐野SA店」の場合、東北道が緊急車両専用となっていた間、遠くから救援・復興に向かう方々の中継宿泊施設として大いに活用された。高速道路内に宿泊施設があることの意義をあらためて実証できたと思う。
ほんとうに嬉しく、誇らしい。
特別なことは何もしない。
いつもどおり。
一灯照隅。
- 2011.03.24 「須賀川店」、8日間の記録
-
昨日(3/23)、「須賀川店」支配人から、地震直後からの詳細な報告メールが届きましたので、ご紹介します。
-----------------------------------------------------------------------------------------
「須賀川店」を後にする時はとても寂しい思いでしたが、すぐに帰ることができると信じて、「寒河江店」に参りました。
体力の回復と心を鎮め、店舗再開のための準備ということで、ゆっくりさせていただいております。
記憶が新しいうちに震災時の「須賀川店」の様子をまとめてみました。支離滅裂な文章になっていると思いますが、ご了承ください。
●地震発生当日(3月11日)
3月11日午後2時頃、客室清掃も終わり昼食をとっているとテレビで地震警報のアラームが鳴り響きました。急いで外に出ようとしましたが、あっという間に大きな揺れが襲いかかり足を取られながらも駐車場まで避難しました。
とても立っていられない大きな揺れの中、二人で支え合い地面にしゃがみ込んでいました。轟音と共に次第に強くなっていく揺れ、建屋が大きく揺れ、地割れが起こり、車が大きく踊っていました。現実としてありえないようなシーンに恐怖心も隠しきれません。
須賀川市は最大の揺れでしたが、内陸の平野部であったため、津波や崖崩れも無く、市内で亡くなられた方も数名でした。しかし、家屋の全壊・半壊があちこちで起こり救急車がひっきりなしに4号線を行き来していました。
社長の旅籠屋日記でも写真が掲載されております倒壊した林精機は、夕方に火事が発生し、消防車による消化活動がありました。こちらは家が密集していないために周りに火災が広がることはありませんでした。
揺れが収まった時に、建屋が倒れなかったことに安堵感を覚えました。真っ先にガスボンベの栓を閉めに向かうと、地面の陥没と倒れたガスボンベが地震の凄さを物語っていました。ボンベは重く、立て直すことができなかったため、全てのバルブを閉めるにとどまりました。浄化槽のモーターの配管も外れていましたが、すぐに直すことができませんでした。
ラウンジに戻ってみると、無残な光景が飛び込んできました。割れたマグカップが散乱し、観葉植物が倒れ、天窓に置いてあったプランターが倒れたことで土が飛び散っていました。幸いなことに家具類で倒れたのはマグカップが置いてあった棚のみ。コーヒーメーカー、トースター、レンジは無事でした。コーヒーメーカーが設置してある組み立て家具はキャスター付きであったため、地震の揺れをうまく吸収したものと思われます。
現況から本日は通常営業ができる状態ではないので、本日ご予約のお客様に連絡を取り、状況説明と宿泊の確認を行いました。電話が繋がりにくく、21時半頃には1組を除き連絡を取ることができました。最後まで連絡が取れない1組を除き、全てキャンセルとなりました。
連絡を取りながらも、お越しになる場合に備え、ラウンジの片付けや客室の準備も進めていきました。
余震が発生するたびに外に避難していましたが、そのうち余震慣れして片付けに専念するようになりました。
ラウンジとフロント(棚のものは全て落ちましたが、PCが無傷でしたので助かりました)の片付けも終わり、客室点検に入りました。揺れの方向と垂直に置いてあって液晶テレビは全て落下し、2台が液晶部分に損傷を受け、使用不能となりました。
壁に飾ってあった額の落下、トイレの水タンクの蓋もいくつか外れ、床が水浸し、バスタブの蓋の外れ、ドライヤーの落下、カップやシャンプー類の散乱。ベッドやテーブルも大きくずれていました。電球の割れはひとつも無く、窓ガラスは無傷でしたので、ガラス破片が無かったことは幸いでした。どの部屋も多少の亀裂はありましたが、宿泊には支障がないと判断。損傷が一番ひどい15号室も宿泊には支障がないと判断しました。
客室の片付けも終わり、宿泊者を受け入れる態勢を取りました。
一度は本社とも連絡が取れたものの、その後は電話での連絡が困難な状況が続き、インターネットも使用不能となったため、携帯メールでメールを発信しました。そのメールに返信があった時は、すごく嬉しかったです。
その後も携帯メールで本社と連絡を取り合い、初日を無事に乗り切ることができました。
通常営業ができない中、行き場の無い人に宿の提供をとの方針に従い、無償での宿泊提供を開始しました。シングルの方には相部屋をお願いしたり、客室を提供できない方にはラウンジを提供し、ソファーやエキストラベッドで寝ていただきました。
後日、ご出発の際にお心づけを申し出る方もありましたが、丁重にお断りいたしました。
●2日目(3月12日)
翌12日、断水によりトイレに溜まった汚物を流すことが出来ないため、裏の側溝に溜まった水を汲んできてトイレ掃除を行いました。
受水層には1トン弱ほどの水が残っていましたが、断水状態がいつまで続くか不明なため、飲料用としてのみ使用することとしました。
この日は浪江町から家を流されたM様ファミリーが訪れました。人工透析が必要な方をかかえており、須賀川で受け入れてくれる病院を探すことができてよかったです。
全てを無くし今後の不安を抱える中、家族が無事であったことに生きる望みを見出されている様子でした。
郡山市や須賀川市のホテルはほとんど営業しておらず、多くの方が「旅籠屋」を訪れて来られましたが、受け入れには限界があり、全ての人を助けてあげられない自分達の無力さが悲しく、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。
宿泊された方からは「暖かいところで眠れるだけでもありがたです」と言っていただき、私達にとっても大きな励みになりました。
深夜、日も変わった頃、IさんとKさんが13時間かけてポリタンクと水を運んでくれました。これでいざという時にも水の配給にも出かけることができます。本当にありがとうございました。
●3日目(3月13日)
13日、昨日「軽井沢店」の支配人から断水時の対応について連絡いただいた簡易トイレを作成しました。リネン庫にあったに組み立て家具の板を利用し足場としました。ブルーシートを屋根代わりに張り、周りを使用できないシャワーカーテンで覆いましたが、枚数が少なく全体を覆うことができませんでした。しかし、昨日訪れたM様からビニールシートの提供を受け、周囲を囲う作業もしていただき、人目を避けて用を足すことができるようになりました。これでトイレに汚物が溜まることも回避でき、トイレ掃除も楽になりました。
原発の影響でいわき方面から避難した方が多く訪れるようになりました。この日も何人もお断りしなければならず心が痛みました。
宿を求める電話もひっきりなしに鳴り響きますが、状況説明をしてお断りをするしかありませんでした。
宿泊されている方達は、食糧や水を調達してくると私達に提供してくれました。それをラウンジに置き、皆で分けあって食べるようになり、良い協力体制が自然に出来上がってきました。
少し落ち着いてきたので、現況報告を本社宛てにメールを送りました。 (※下の3/13に転載したメールです)
●4日目(3月14日)
14日、宿泊している方が固定化し始め、長期の宿泊になる傾向となってきました。
ガソリンの調達が困難なことも加わり、宿泊者の方達にも疲れが見え始めました。
M様ファミリーには「全て流され、もうこれ以上失うものは無いのだからこれ以上は悪くならない。笑顔でいると幸せが寄ってくるから
笑顔で乗り切りましょう」などと励ましていると、そんなM様一家が他の被災者を励まし始め、困窮の中、「旅籠屋」内に明るく前向きな雰囲気が生まれてきました。
夜、「那須店」の支配人からカップ麺やお菓子、水、子供服、大人用紙おむつなどの支援があり、本当に助かりました。
●5日目(3月15日)
15日、水道工事の業者が入り、水が回復しました。
ライフラインの復旧にともない本日より通常営業を再開することとなりました。
宿泊料金の支払いについては、被災者の方の状況を踏まえ、後払いでもよいとの本社指示に沿って営業しました。
K様はチェックイン時には後日振込みでお話をしましたが、チェックアウト時に現金でのお支払いを受けました。
M様には本日から料金が発生すること、また、今後のことについて後日、相談することにしました。
宿泊者の方達とお話をする時間も多くなり、今後のことについて一緒に考えていこうという雰囲気になってきました。引き受けてくれる親戚をまずあたってもらい、受け入れ先が決まった家族からチェックアウトしていただきました。
しかし、大半の方は「どうしよう、どうしよう」と迷っているばかりです。
本日、水が復旧したことでトイレの水タンク内においてフロートの外れにより水が止まらない客室が2部屋あることがわかりました。
客室チェックの盲点でした。破損ではなく、単に外れただけでしたのですぐに直しました。
●6日目(3月16日)
16日、宿泊者の協力もあり、食糧・水は差し入れでまかなうことができ、宿泊者が飢えに苦しむことはありませんでした。
テレビでは避難所に食糧が届いておらず、わずかな食糧を分かち合って食べる映像などが流れる中、こちらはまだ恵まれた生活をしていることに心が痛みました。
ガソリン不足は相変わらずで、毎日ガソリンスタンドに長蛇の列。販売するかしないかわからないスタンドに早朝から100台、200台と並んだり、5時間並んだすえ、手前で売り切れとなってしまったり、苦労が絶えません。
ガソリンが調達できないがために次の行き先が決まらず、こちらに留まっているという感じです。
●7日目(3月17日)
17日、社長より「支配人と宿泊者の安全を第一に考え、須賀川店の一時休止」の連絡をいただきました。「現在宿泊されている方々に状況を説明し、再び行き場をなくさないように」との指示のもと、宿泊者全員にラウンジに集合してもらい、安全なうちに避難していただくという社長の思いを伝えました。
「本日中に受け入れてもらえる親戚やアパート、避難所を探しましょう」と声をかけたところ、皆さん一斉に動き始めました。私達は不動産屋をピックアップし、必要な方に提供しました。
当時、4組の復旧作業に来ていた方と8組の避難者が宿泊していました。
復旧作業に来ていた方は帰宅、他のホテル、貸しマンションへと移動先が決まり、避難者においても親戚、アパート、警察の官舎、またM様においては埼玉アリーナの避難所へと落ち着く先が決まりました。
だた、いわきから避難中のT様だけは本日出産となりアパートを探す時間がありませんでした。
●8日目(3月18日)
18日、朝、6組の避難者が出発しました。
M様は前夜22時頃出発され、「本当に感謝しています。落ち着いたら須賀川に戻ってきて仕事を探し、必ずお金は払いますから」との言葉を残して行かれました。
他のファミリーとも抱き合い、涙を流すこととなりました。別れ際、「必ずまた遊びに来ますから」と言って手を振り出発されました。
市内で家屋が倒壊したF様からは、「旅籠屋に入ってきた時から運が向いてきた。どこのホテルも受け入れてもらえず、行き惑っている中、受け入れてもらうことができ、どんなに嬉しかったことか。旅籠屋さんの営業休止の話を不動産屋に伝えたら、アパートのリフォームに時間がかかると言っていたものが、一日で入居可能な状態にしてもらえた。助かりました。旅籠屋に縁を持てたことは、僕の一生の宝物です。」とのお言葉をいただきました。
昨日出産されたT様ですが、行き先も探す時間がないことから、いわきの家(20〜30km圏内)に戻ると申し出がありました。他の皆が出発する中、自分達だけが残っていることに引け目を感じたのでしょう。
こちらで行き場が決まるまでいていただいても構いませんと伝えましたが、私達が止めるのも聞かず出発されました。
ところが、出発後間もなくして、「考え直しました、助けてください。こちらでアパートを探します。不動産屋さんを教えてください。」との連絡があり、アパートを一緒に探すから戻って来ていただくよう伝えました。
戻ってきたTさんを車に乗せて、Fさんから教えていただいていた不動産屋に出向き、相談しました。
当初は「1ヶ月という短期での契約はしない」などとしぶっていたが、事情を察してか本日から入居可能な物件を世話してくれました。
Tさんの顔に安堵感が表れました。本当によかった。
目先の利益よりも安全を優先された社長の苦汁の決断により、宿泊者の皆様が早い段階でそれぞれの道を決断することができました。
行き場をなくして訪れた人々が、旅籠屋を閉めたことで再び行き場をなくすことなく送り出すことができました。
これで安心して店舗を閉めることができます。
今月末までの予約確認も済ませ、K部長に連絡しました。
以上が地震発生からの「須賀川店」の様子です。
この8日間、本社の方々や各店支配人、代行の皆様から暖かいお言葉やメールをいただき、何より私達の励みになりました。
本当にありがとうございました。
一日でも早く「須賀川店」に戻れる日を楽しみにしています。
- 2011.03.21 危機管理にあたって、もっとも大切ないくつかのこと
-
地震発生以来、考え、悩み、迷い、決断する中で感じたこと、考え続けていることを、少しずつまとめておこうと思う。
1.会社のポリシーと個人の感覚
原発事故の影響で福島県内から避難してきた人達の宿泊を、何軒かの宿が断ったというニュースを聞いた。
体が震えるほどの怒りがこみあげてきた。同業者として情けなく、やりきれない気持ちになった。
「ファミリーロッジ旅籠屋」でもっとも大切にしていることは、予断・偏見・先入観にとらわれず、あらゆる人を等しく受け入れること、それが本当の意味で、自由で心豊かな暮らしや社会を支えることになる、という信念である。新しい社員が入るたびに社長研修で繰り返し話していることだ。
その裏には私なりの体験や信条があるのだが、そこまでは言わない。だから、何度語ってもピンとこない人も多いだろう。それに、平時はペット連れの宿泊や障がいのある人を積極的に受け入れるという程度の意味にしかならないから、問題になることもない。ほぼみんなの「常識」の範囲内におさまることだから、すんなり受け入れられてしまう。
ところが、今回のような非常時になると、それぞれの「常識」や「感覚」とのズレが表面化してくる。会社のポリシーと個人の気持の差が表に噴き出してくる。
宿泊施設の場合、過去にも、同様の事例があった。いくつかの伝染病患者や街宣車によるいやがらせを受けるおそれのある団体への宿泊拒否。こういう時に、突然のように会社のポリシーが問われることになる。社員は、勤務している会社への忠誠心や理解が問われ、会社は社員に対する姿勢、不安や動揺をどこまで受け入れ、どこまで受け入れないのか、が問われる。
今回、端的に問われたのは、福島第1原発から60km以内にある「いわき勿来店」「須賀川店」を一時閉鎖するかどうかという問題であった。もちろん、迷いに迷った末に最終的に私が決断したことだが、やはり悔しくて、悔しくてならない。
2.本社と現場の関係、トップと社員の関係
今回の大震災への対応について、政府や東京電力などに対する批判がかまびすしい。現時点で評論家のようにアレコレ言うのは何の足しにもならないし、慎むべきだと思うが、情報と判断の一元化が必要という指摘については同感である。
平時は、それぞれの部署で職務分担し、一定の裁量で動けばよい。何もかもトップに情報を集め、判断を仰ぐ必要などない。
しかし、今回のような場合は、事情が全く異なる。
そもそも、非常時において、社会や組織が瓦解し機能しなくなる原因は、外部ではなく、内部にある、というのが私の理解だ。
本社に正確な情報が集まらず、的確で迅速な判断ができず、一方で現場がそれぞれ独自の判断で動き、疑心暗鬼にかられれば、相互不信ばかりが広まり、収拾がつかなくなる。
こういう時こそ、トップは良い意味でワンマンになるべきだと思う。すべての情報を社員に要求し、遅滞なく判断を下し、具体的な指示を出していく。社員は、とりあえずトップを信じ、情報を上げ、指示に従い行動する。批判は後からで良い。
今回、被災地に近い店舗の支配人に対し、他店の支配人から「いつでも逃げておいで」という誘いがあったように聞いた。その暖かい心遣いはありがたいことだし理解できることだが、それは本社に対し申し出るべきことではないかと思う。
3.トップの覚悟
「自分の本音を聞け、本性を見よ」というのが、私の座右の銘である。
この10日間、何回か自分に問うてみた。
トップに確信やある種の覚悟がなければ、的確な判断などおぼつかないからだ。
企業のトップは船の船長のようなものだ。もちろん最後までひとり残るのは私である。何の迷いもない。
中心に立って判断し、全体をコントロールするという最大の責務さえなければ、いつでも危険のある店舗に行き、支配人として店舗を守る。自分の体が複数あれば、今すぐにアチコチに行く。
自問に対する自答は、毎回同じ。なんの揺らぎもない。
先日テレビのバラエティ番組で「偉い人たちは、なんで突然わざとらしく作業服を着ているんだ。なぜ現場に行かないのか。」と批判している人がいた。
こういう一面的で感情的で「一般受けする」発言こそ、無責任で取り返しのつかない内部の瓦解を招く。謹んでもらいたい。
4.鼓舞することと、冷静さを保つこと
非常時は、状況が刻々と変わる。予期せぬことが起きる。
茫然自失の状態になりそうな人間を鼓舞し、時には大きな声を出すことも必要だろう。
しかし、テンションを上げすぎて、周囲を委縮させ、浮足立たせるのは逆効果である。不安は伝播する。
トップはもちろん、本社のスタッフはこういう時こそ冷静でなければならない。
社員の安全や心身の健康を大切に考える姿勢は、もちろん変わらない。しかし、一時の感情に流されるわけにはいかない。会社のポリシーを守ること、長い目で見て社員の暮らしを守ること、必ず一度は踏みとどまって、総合的に判断する冷静さを保ち続けなければならない。
「非常時」と何度も言ってきたが、幸い、人間も店舗も無事であり、直接的な被害はほとんどない。会社の経営状態も安定しており、売上高や利益に一定の減少が予想される程度でのことである。新規店の工事や準備も変更なく進んでいる。
今後、原発事故の復旧状況などを見定めながら、一日も早く3店舗の営業再開を果たし、いつも通りの営業を続けていく。それこそが、最大の社会貢献だと信じている。
幸い、被害を受けなかった西日本の存在は、これからの日本の希望である。
同情や自粛は本当の意味での復興支援にはならない。
- 2011.03.20 東北巡回の記録
-
3月11日の地震発生から6日。
全店、お客様も支配人もすべて無事、建物の被害もほとんどなかったが、避難されてくる方が増えるいっぽう、さまざまな物品の入手が困難になっているとの連絡もあり、「緊急車両」の登録を受けた社有車に物資を満載し、本社スタッフ3名で3月17日の午後、茨城・東北の7店舗の巡回に出た。
まず向かったのは、「水戸大洗店」。途中、ガソリンスタンドには長蛇の列。

「水戸大洗店」(3/17午後)
全館くまなくチェックしたが、建物の被害はない。
しかし、オープンから10年、壁紙や廊下などの汚れが目立つ。
福島方面から避難してこられるお客様も増えているようだが、この状況は申し訳なく、恥ずかしい。
近々、全面的に模様替えをしようと心に決める。

「いわき勿来店」(3/17夕方)
水戸インターから、緊急車両専用となっている常磐道に乗り、「いわき勿来店」へ。
途中の中郷SAでガソリンを満タン補充。
一般道の窮状を見ているだけに、ほんとうにありがたい。
給油ができなければ、そもそも長距離の巡回などまったく不可能なことだ。

「いわき勿来店」(3/17夕方)
この店舗は福島第1原発から約55km、もっとも近くに位置する店舗だ。
地震の被害はまったくないが、支配人の心身の健康を考え、前日深夜、迷いに迷った末に一時休業を決定した。
ここまで、店を守り、通常通りお客様を受け入れてきた支配人の働きに心から感謝するが、
立ち入り禁止の案内を貼り終えると、一気に悔しさがこみあげてくる。
1号店オープン以来16年、初めての決断。
支配人から、「一日も早く、再開したい」との言葉。ほんとうにありがたく頼もしい。

「秋田六郷店」(3/18早朝)
前夜、「いわき勿来店」を出て、東北道・秋田道を走り、深夜0時半に「秋田六郷店」に到着。
東京・神奈川から応援にかけつける警察・消防、そして自衛隊の車両に囲まれながら走る。
途中、宮城県内は雪。
路肩にキャラバンを停め、チェーンを巻く光景が続く。
被災地は真冬並みの寒さなのだ。
「秋田六郷店」も建物の被害はない。
避難してこられる方からの問い合わせが多いが、ガソリンの入手が困難でたどり着けないケースが多いようだ。
周辺のガソリンスタンドには、2kmを超える車の列。異常な光景だ。何とかならないのかといらだつ。

「北上店」(3/18午前)
秋田道を戻り、「北上店」へ。
途中、東へ向かうタンクローリーを見かける。日本海側から運んでいるのだ。
「急げ〜!、頑張れ〜」と心の中で声援を送る。
「北上店」、ここも被害はないが、近くの工場復旧にこられた方を中心に満室。
途中、携行しているガソリン10リットルをお客さまに差し上げる。
びっくりしてしまうほど喜ばれる。嬉しい。

「北上店」(3/18午前)
目の前の大型スーパージャスコにも食料品はないとのこと。
いつもは、あれほど食品があふれているのに信じられない状況だ。
持参したお菓子や食品をここにも置いていくが、通常の朝軽食のサービスがままならないらしい。
団体の方たちは自主的に近くの食堂にケータリングを頼み、支配人が廊下にそのスペースを提供している。
さながら、私設「避難所」の様相。
いつものようにはいかないが、こうして皆さんに宿を提供でき、活用されていることが何より嬉しい。

「寒河江店」(3/18午後)
「北上店」を後にし、東北道を南下、山形道を経由して「寒河江店」に向かう。
応急作業が遅れているためか、山形道は、段差が多い。交通量は少ない。
いつものように「寒河江SA」のスマートインターから出ようとするが、「緊急車両」のため、あえてETCゲートを使っていないため、ゲート
を開けてもらえない。
押し問答するが、手続きに時間を要するので手前の寒河江インターから降りてもらったほうが早い、と言われる。すぐそこに建物が見えているのに数キロ戻る。
こんな時に杓子定規な対応。なんとかならないのか。
「寒河江店」もまったく無事。
ここは避難されてこられた方で満室。未だ唯一ライフラインが復旧せず待機している「仙台亘理店」の支配人とも再会。
先日、安否不明で心配したご夫婦だ。
「ほんとうに良かった、たいへんでしたね」と声を掛ける。
いつもパンフレットを置きに行くお店の人たちが津波で流され・・・と涙ぐまれる。
そうだったのか、みんな心に傷を負っているのだと思い知る。
「寒河江店」の支配人の車に途中で補充した10リットルのガソリンを注ぐ。
「これで買出しに行けます。ガソリンの一滴が血の一滴なんです。何よりありがたい」と言われる。
携行缶を持ってきて良かった!

岩沼市、国道4号沿いの洋菓子店
「寒河江店」を出発し、山形道を東に戻るが、東北道に合流する手前で「この先の橋が通れない」と一般道に下ろされる。
日も暮れ、どこかで夕食を摂らないとならないが、食堂も小売店もすべて閉まっている。
いつもはあれほど賑やかで交通量の多い国道4号線が、薄暗い。
途中、奇跡的に営業中の洋菓子店を発見。
自家製造のケーキ屋さん、手持ちの材料でケーキを作り続けているのだ。
夕食代わりにしようとロールケーキを購入。
これがデザートになるといいね、と言っていたが、結局、他に空いている店はなく、イヤになるくらい腹いっぱいケーキを食べることになった。

「仙台亘理店」(3/19早朝)
未だに断水が続き、唯一ライフラインが復旧していない「仙台亘理店」。
電気もガスも通じており、建物には何の被害もないが、水が使えないとトイレも流せず、宿泊を受け入れることができない。
前夜、なんとか受水槽のポンプを動かそうと試みたがうまく行かない。
建築会社に連絡したが、ガソリンがなく動きがとれないとのこと。
近くの業者さんに来てもらおうとするが、電話がつながらない。携帯も電源が切られている。
被災したのか。
止むを得ず、復旧するまでもう少し待つしかない、との判断を下し、店を後にする。
休業中、2軒目。悔しい。
店を振り返る。
この周辺は津波の被害が報じられたエリアだ。
東の海側へ車を走らせてみる。
仙台東部道路に被害はないようだ。津波がこの土手で遮られたのかと考えていたが、被害はもっと海寄りなのだ。
高架をくぐり、さらに東へ進む。
と突然、風景が一変し、ニュースで見た異様な光景が目の前に広がってくる。
見渡す限りの田んぼの中に、無数の車と瓦礫が散在している。
呆然とたたずむ人たちの姿も見える。
もちろん写真を撮る気にもなれず、長居をしてはいけないと、無言で国道6号に戻る。
わずか数メートルの差で、日常と非日常が連続している。
地獄絵と普段の景色が隣り合わせになっている。言葉がない。

「須賀川店」(3/19午後)
白石インターから東北道に乗り、最後の予定地「須賀川店」に向かう。
ここは、地震直後から、被災者があふれ、一時はラウンジに多くの方が雑魚寝していた店舗だ。
停電や断水が続いており、無償で受け入れていた。
報道ではあまり名前があがらないが、じつはここも福島第1原発から60kmたらずで、「いわき勿来店」と大差ない距離。
「いわき勿来店」とあわせ、ここも一時休業すると2日前に決めていた。
おそらく、地震の揺れはこの店がもっともひどく、支配人から当時の恐怖体験を聞いた。
ものすごい地鳴りが聞こえ、駐車場に亀裂が走り、建物が大きく揺れていたとのこと。

支配人に促され、前面を走る国道4号線の向こう側にある工場を見に行く。
鉄筋コンクリート3階建ての社屋がぺしゃんこにつぶれている。
今回、東北各県を回ってきたが、地震の揺れそのものによる家屋の倒壊を見たのは初めて。
幸い、けが人が1名出ただけだったとのこと。良かった、良かった。
すぐに建物に戻り、全館をチェックしたが、たしかにアスファルトに細かい亀裂があり、裏側の地面が15cmほど陥没している。
1室だけは壁面のボードに割れが見える。
ただ、宿泊に支障があるようなことはない。
たまたまその後宿泊した建築関係の人から「旅籠屋さんの建物は丈夫ですね〜、よく出来てますよ」と褒められたとのこと。
たしかに、遮音や断熱性能を上げるため、壁の合板や柱を基準の倍ほど増やしていることや、鉄筋をとおしたベタ基礎にしていることが強度を上げる結果につながっているのだろう。
正直言って、今回のような大きな地震を想定して設計していたわけではないが、以前の宮城沖地震の時も、中越地震の時も、近くの店の建物はびくともしなかった。今回もそうだ。
しかし、ここだけは、駐車場の補修は必要だと思う。
営業再開後、すぐに対応するつもりだ。

「須賀川店」(3/19午後)
あわただしく閉館準備を済ませ、支配人とともに店を後にする。
「ほんとうにご苦労様でした。」とふたりに頭を下げる。
「すぐにでも戻ってきますよ」と明るい声。
一時休業中の張り紙。
3回目のくやしさを噛みしめる。
こうして、あわただしい巡回が終わり、昨夕、本社に戻ってきた。
普段は休みの土曜日だが、数名が詰めており、今後の対応について全員で話し合う。
地震発生から8日間。
2回の徹夜を含め、平均睡眠時間は3〜4時間で頑張ってきた。みんなそうだ。
しばし、休息をとって、週明けから、全面復旧に向けて、進んでいこうと思う。
- 2011.03.17 再び北へ、現地へ
-
3/11(金)の地震発生から6日。
ラインライン途絶の店舗も、断水が続いている「仙台亘理店」だけとなった。
余震が続いており、周辺の復旧も遅れているが、営業再開の日は遠からず必ず来る。
しかし、福島原発の事故は悩ましい。
解決の見通しが立たず、不安が高まる。
東京電力や政府に対する苛立ちもあるが、現地で危険を冒しながらの懸命の作業が続けられている今、感情的な批判は慎みたい。
とは言うものの、 目に見えない恐怖にさらされている人たちのストレスは限界に近づいている。
東北や関東の店舗に避難してくる方々の数が増えている。
個人的な不安を押し殺しながら、受け入れ続けている支配人たちの気持ちを考えると、居ても立ってもいられない。
こんな時こそ、経営トップがあらゆる情報を把握し、的確な判断と迅速な指示を出すべきだと、本社オフィスを離れずにきた。
冷静に考えれば、今後もそうすべきだと信じているが、私自身が現地に赴き、現場の状況と支配人の心情を受け止めるべきだという気持ちも抑えきれなくなった。
西日本の店舗から届けられた大量の乾電池、緊急調達した各種用品を届ける必要もある。
東北6県については、宅配便の受付が停止されており、自ら車を走らせる以外に方法がないのだ。
というわけで、急遽、東北方面の7〜8店舗を回る。
「緊急車両」の指定を受け、3日間、交替で走り続ける。
- 2011.03.13 地震対応、支配人からの報告メール
-
本日(3/13)夕刻、「須賀川店」支配人から届いたメールです。
-----------------------------------------------------------
現在、南相馬市の津波被害で家を無くしたM様ファミリー15名、
いわき市の会社で自宅が原発付近の方達5名(S様グループ)が宿泊。
S様グループは昨日満室のため、ラウンジにて寝ていただきました。
本日チェックインされる方は復興支援関係の方々です。
M様は着の身着のままで逃げ出したが、あちこちの避難所がいっぱいで
こちらまで来られました(こちらに住んでいる親類を頼って)。
また、透析が必要な方、インスリンの注射が必要な方、高血圧薬治療の方が
お見えになり、市内のクリニックにて治療を受けました。
衣類販売の店が営業してない為、私達の服を着替えにお渡ししましたが、
年配の方や子どもの服が手に入りません。
食料は皆さんの協力で何とか手に入れております。
昨日までお泊りのシャトレーゼのY様から、2度もお菓子や水を
いただきました。S様グループ様からは、カップ麺やジュースを。
また、M様は配給で水を貰ってきてくれました。
須賀川のスーパーはどこも品薄で食料がほとんどありませんが、
郡山まで行けば手に入れることができるようです。
断水のためにトイレの水を流すことができない為、大便対策として
浄化層の一箇所の蓋をはずし、足場用に板を置き、周りをシートで囲み、
簡易トイレを作成いたしました。
近いうちに「停電」となる話や「震度6弱の地震に警戒」といった
ことも流れているようなので、注意して運営いたします。-----------------------------------------------------------
3/11(金) 地震発生直後より、本社全員で手分けし、宿泊中のお客様にケガなどがないか、建物の状況はどうか、直ちに全店に連絡をとり始めた。
すぐにホームページ上に告知欄を設け、お客様や建物の状況報告を開始する。
社内で作成しているので、即刻対応できる。
コップが落ちて割れた、ラウンジの棚が倒れたなどの報告はあったが、幸い、お客様にも建物にも被害はない。
留守宅のご家族に対し、一刻も早くこの情報をお知らせすることが大切だと確認しあう。
西日本を中心に、大半の店舗はじきに確認が取れたが、北関東から東北の店舗とは連絡がつかない。
固定電話はもちろん、支配人用の会社の携帯電話、個人の携帯電話、深夜にいたるまで必死で電話を掛け続ける。
日が暮れても茨城県から福島・宮城・岩手の数店舗の状況がわからない。
ニュースを見聞きしていると不安ばかりが大きくなり、最悪の事態が頭をよぎる。
夜10時頃 ようやく全店と連絡がとれた!
お客様も支配人も全員無事。建物も大きな被害無し。
万歳! 社内に歓声が響く。
オフィスの中心に白板を立て、情報を整理していく。 さながら、「ファミリーロッジ旅籠屋・地震対策本部」。
今夜はもちろん、徹夜態勢。
無事の第一報はそろったが、情報が断片的なため、ライフラインの詳細を整理すべく、順番に再確認していく。
電気・水・ガス・通信のライフラインに不具合の生じている店舗が10近くある。
刻々と通信状況が悪化しているらしく、2〜3店舗とは再度の連絡がとれない。
深刻な津波被害のニュースが流れる。
連絡がとれないのは太平洋に近い店舗ばかり。
何か状況の変化があるのではないかと、社内に緊張感が高まる。
明け方になって、山梨方面に出張していたスタッフがようやく帰社し、今後の対応を相談する。
ひとつふたつと連絡がとれ、「仙台亘理店」が最後に残る。
なんとしても支配人の安否確認をとりたい。
昼近くになり、2名に車で現地まで行ってもらうことを決定。
たどりつけるのかどうかもわからないが、他に方法はないし、事は緊急を要する。
さまざまな物資を積み込み、飲料水を大量に購入し、「徹夜明けの運転、くれぐれも気をつけて」と見送る。
この時点で、ライフラインに不具合はあるが、宿泊可能な店舗に対し、「行き場に困っている被災者を無償で受け入れるよう」指示する。
災害時には、シェルター=一時避難施設として社会貢献しよう、ということは以前から社内で話していたこと。
車で向かったスタッフからは、時々連絡が入る。
渋滞がひどく難渋している。
深夜1時、12時間かけてようやく「須賀川店」到着の連絡。
要請されていた給水用ポリタンクや飲料水を渡したが、館内には被災者があふれているとのこと。
会社の方針とはいえ、断水の中、必死で世話をする支配人の労苦に言葉がでない。
そこからは、比較的道路はすいていたらしい。
明け方近くに「仙台亘理店」近くに迫り、朝、6時過ぎ、「支配人無事! 津波は建物に達していないため、被害無し」との連絡。
良かった! 良かった! と大声で答える。
余震の恐怖の中、駐車場の車の中で2晩過ごし、店を守り続けた支配人に、感謝と敬意。
そして、今夕、「須賀川店」から冒頭のメールを受け取る。
読みながら、涙がにじんだ。
「旅籠屋」がこうした存在でいることを、心から誇りに思う。
さっそく全店に回覧。励ましのメッセージが届き、隣の「那須店」は救援物資を積んで、現地に向かってくれた。
「いわき勿来店」にも、福島原発周辺から避難してきた方々が滞在しているとのこと。
すべては、継続中のこと。
大きな被害がなかったとは言え、売上の減少は避けられず、正直言って、経営者としては頭が痛い。
しかし、多分、大丈夫。
利益を少し減らしても、「旅籠屋」の存在意義をまっとうし、不安なくお泊りいただけるよう最善の策を講じていくことを心に誓う。
3日目の夜。
明朝からの停電対策などに追われるが、今夜も頑張る!
- 2011.01.07 新春互礼会
-
案内状が届いたので、日本生産性本部の「新春互礼会」に行ってきた。
昨年春「ハイ・サービス日本300選」に選ばれ、下部組織であるサービス産業生産性協議会に入会したご縁によるものである。
会場はホテルニューオータニのもっとも広い宴会場「鶴の間」、参会者はおそらく2千人を下らなかったと思う。
国会議員を含め、テレビなどで見かける顔も少なくない。
一般の参会者は名札を付けていないから、旧知の間柄でなければ誰が誰かもわからず、私も誰かと挨拶を交わす機会はなかった。
規模の大小はともかく、たまにこうしたパーティーに参加することがあるが、そこから何かが始まったり生まれたりすることは稀だ。
とすれば、わざわざ出かけて行った価値は、主催者や来賓の発言から何を得るか、ということになる。
牛尾会長に続き、経済同友会の桜井代表、連合の古賀会長、仙石官房長官の挨拶が続いた。
結論から言うと、触発されることは何もなかった。
グローバル経済、地球環境対策、社会保障整備など、耳たこのテーマが総花的に語られるばかりで、心に刻まれるような言葉はない。
つくづくもったいないと思う。
政界、経済界を中心にこれだけの人間が一同に会する機会など、そうそうあるものではない。
新年のご挨拶だから、と言えばそれまでだが、わずかでも魂を揺さぶられる言葉を聞きたかった。
日本人の演説下手、すなわちそれこそリーダーシップの欠如そのものではないか。
時間の無駄、とまでは言わないが、帰路の寒さが身にしみた。
- 2010.12.12 ホノルルマラソン2010 参戦記
-
第39回 ホノルルマラソン2010に参加してきた。
朝3時過ぎに借りてる別荘を車で出発。
出走者は、私、長男、次男、長女の婿さん、次女の婿さんの5人。
交通規制を心配したが、スタート地点のアラモアナ公園の近くまで行けて、3時40分にはスタート地点に到着。
すでに日本人のツアー客がいっぱい。
天気はきのうの昼前から快晴になり、気温はおそらく20度くらいでまったく寒くない。
公園内でゆっくりストレッチしたり、トイレに行ったりして、スタートの30分前、4時半にコースへ。
ゴールタイム5-6時間のエリア。
アナウンスでは、参加者2.3万人のうち、日本人が1.3万人とのことだが、周りは8割がた日本人の感じ。
スタート10分前にアメリカ国歌が流れ、かろうじて海外での大会であることを実感する。
観光収入にはプラスだろうが、逆の立場で考えると、例えば「東京マラソン」の参加者の過半が外国人で、外国語のアナウンスが鳴り響いているというのは、正直なところ地元の感情としてはどんなもんだろう。
そうこうするうちに、前方で花火が上がる。
これがスタートの合図だと思う。
やっぱり花火は気持ちが湧き立つ。
そろりそろりと歩いているうちにスタートラインを通過。
すでに約15分経過。
聞いてはいたが、スタート直後から歩き始める人が少なくないし、グループで並んで走っている人が多いので、とにかく走りにくい。
渋滞をすり抜けながら追い抜いていくのだが、とてもマスペースでは走れない。
それに走り始めると湿度が高いせいか、体が重い。
キロ7分30秒、5kmでやっと7分ペース。
これでは、とてもタイムは狙えないと悟り、一気にモチベーションが下がる。
立ち止まって記念撮影をしている人も多く、ホンルルマラソンの性格がよくわかる。
カラカウワ通りを東に向かう頃から前方の空が白み始め、ダイヤモンドヘッド脇の上り坂の途中で日が昇る。
すごい日差し。
道が狭くなり、渋滞が続く。
心配したほどの勾配ではないが、もう、無理せず時々歩く。
下りに入った頃からはLSDペースでたんたんと走る。
沿道の声援は断続的に続き、高速道路に入る手前の交差点では大声援。
good job! という声が多いが、さすがにアメリカ人は元気が良くて声が大きい。
今日が誕生日と背中に書いて走っている女性を見つけて、まわりのランナーが大きな声でHappy Birthdat To You・・・と歌いだす。
軍服に大きな背嚢を背負って早足で歩く兵隊集団も見かける。
ゼッケンをつけているので、参加者だ。ゴツイ。
見ているだけで重そうで、暑苦しそうで、こりゃ立派な行軍訓練になるに違いない。
高速道路に入ってしばらくすると、折り返して戻ってきた反対側にあの「おにぎりランナー」を発見。
かなり、苦しそう。
新婚旅行を兼ねているのかも。
そんなことを考えていると、見慣れた黄色のTシャツを前方に発見。
長女の婿さん、てっきり後ろにいると思っていたのに、まったくの予想外。
かなりペースが落ちているようで、しばらくすると追いつく。
それから1kmも走らないうちに、借りている別荘の前を通る。
みんなが、イスを出して差し入れを用意して待ってくれている。
隣りの別荘に滞在中の5歳くらいの女の子"ナオミちゃん"もアメリカ人のお父さんと日本人のお母さんと一緒に迎えてくれる。
カルピスを少し飲んで再び走り出す。
間違いなく先頭を走っていると思っていた次男は2kmくらい後ろらしい。
再び2人で走り出すが、長女の婿さんに離され姿が見えなくなる。
無理に追う気力もないのでマイペースで走る。
ここから折り返しのハワイカイまではまだ相当ある。
高速道路なので、単調。
タイム更新の目標を失っているので精神的につらい。
と、突然、前を走っている中年女性が「カメラ、カメラ」と騒いでいるので何かと思ったら、数m横にあの高橋尚子さん、彼女も参加しているのだ。
立ち止まってみんなにハイタッチしている。
駆け寄ろうかと思ったが、タイミングを失ってしまった。
テレビで見るより、小柄でキュートな感じ。
反対側を走る人がどんどん増えてくる
はやく折り返しエリアに入りたいと思うがなかなかたどり着かない。
日差しは強いが、枝の広い街路樹(日立の樹で有名なモンキーポッド)のおかげで、結構日陰がある。
時差ぼけと睡眠不足のせいで、時々眠たくなる。
やっと折り返しエリアのハワイカイ地区へ入ると、素晴らしい高級住宅が並ぶ。水路に面してボートをつないでいる家も多く、アメリカの豊かさを垣間見る。
数キロまわって、ようやくゴール方向へ進み始める。反対側に後続のランナーが延々と続くが、歩いている人が多い。
最後尾を走る長男とすれ違う。
長女の婿さんは5分以上前にすれ違ったらしい。
しばらくして、再び私設応援席の前にたどり着く。
33kmくらい。
はっきり言って、再び走り出すのがかったるい。
「あーめんどくせ〜」と言いながら再スタート
あとは、何とか、6時間切ることと、先行する彼に追いついて1位でゴールすることをかすかなモチベーションにしてなるべく歩く時間を少なくするように努める。
高速道路を下り、カハラモールの横を通って、カハラホテルまでの住宅街を抜けていく。
給水所の間隔が短くなり、高校生くらいのボランティアがコップを差し出してくれる。
氷を入れてあったりしてとても冷たくておいしい。
でも、ガブガブ飲んでいると下痢しそうでこわい。
氷といえば、大きなビニールに詰められ、土嚢のように道端に積み上げてある。
さすがに物量のアメリカという感じ。
その上に座って脚を冷やしているランナーも多い。
住宅街を抜けるといよいよ最後の上り坂。
6時間を切ることだけを気持ちの支えに走っていると、遠くに見慣れたTシャツ。
なんとか、長女の婿さんに追いついた。
「このまま行けば、6時間切れるよ」と声をかけて先に行く。
帰りの上りは往きよりも緩やか。
ピークを越えれば、あとは下り坂、そしてゴールのカピオラニ公園。
最後の直線に入るが、この1kmが長い。
いったん歩こうと思ったが、沿道から「旅籠屋さん、頑張れ!」の声がかかり、走り続ける。
後で聞いたら、スタート地点で並んでいるとき、「旅籠屋、よく泊まるんだ。クロワッサンがおいしいよ」としゃべっている人がいたり、
「お店の支配人がみんな走ってるんですか?」と尋ねられたりした人もいたらしい。
このように声を掛けられことが増えており、嬉しい。
こうして応援に力をもらい、ついにフィニッシュ。
記録は、5時間58分32秒。
フルマラソンは7回目だし、タイムは先月の「つくばマラソン」で出した4時間台の自己ベストより1時間以上遅いし、特別の達成感も感動もなかった。
涙がこみあげてくるなんてないし、もちろん人生観が変わるなんてこともない。
ゴールを抜けてすぐに、貝殻のレイをかけてもらい、道脇に腰掛けて一休み。
しばらくすると、長女の婿さんもゴール。6時間は切れなかったみたい。
疲れきった体をひきずりながら、一緒に完走Tシャツをもらい、水やクッキーやりんごで空腹をみたす。
最後に、預けてあった着替えを受け取って木陰で座り込む。
しばらくして、次男や次女の婿さんもそろい、30分ほど居眠り。
日向は暑いが、木陰は涼しく、寒くて目が覚めた。
長男がなかなかゴールしないので気をもんだが、9時間半頃、フィニッシュ。
5kmからずっと歩いていたようで、意外と元気だった。
今年の正月に私のちょっとした思い付きで始まった今回のマラソンツアー。
家族全員が集っての旅行は、これが最初で最後になると思う。
明日は、次女夫婦の2年遅れの結婚式を海沿いの教会で行う。
それぞれ、忘れられない思い出になってくれればと思う。
ホノルルマラソン、来年も出たいか?
うーん、タイムを狙ってまじめに走るような大会じゃないし、微妙かも。
5〜6歳の子供を連れて走っている親子を何組も見たけれど、完走だけを目的に楽しく走る、というならとても良い大会かもしれない。いずれにせよ、全員が無事に完走。
よかった、よかった。
- 2010.11.09 折れない心
-
政治も経済も、何となく世間は波立っているが、私は相変わらず淡々と走っている。
猛暑の夏が去って、 ランニングシーズン到来。
継続的に続けるようになって3年目、月平均の走行距離は100km以上になり、先月は初めて200kmを超えた。
しかし、走力は一進一退。
10日ほど前にも「第2回 しまだ大井川マラソン」に参加したが、30km過ぎから歩いたり走ったりの状況になってタイムは去年より5分も遅くなってしまった。
70歳過ぎても3時間台で走る人がたくさんいるのに、未だ5時間を切れない低レベル。
人と比較して速い遅いはともかくとして、いつものように自分に負けて歩き出してしまうのが情けない。
2時間を越えてくるとなんとなく脚が重くなり、3時間くらいで心が折れてしまう。
長時間、長期間、何かをやり続けること、負荷に耐え続けることはほんとうに難しい。
旅籠屋も1号店オープンから16年が過ぎた。
社内研修でいつも言うことだが、宿泊施設の運営業務というのは、賽の河原で石を積むのに似ている。
毎日毎日、部屋を掃除して、庭の草取りをして、建物を元の清潔な雰囲気に戻す作業の繰り返し。
良くて当たり前、ほんの小さなことが印象を大きく損ねてしまう。
70点で満足すればラクなのだが、90点を目指さなくなった心の緩みは「匂い」のようなものになって建物に染み付いていく。
歩かないでゴールする人は、私と何が違うのだろう。
とにもかくにも「やり遂げたい」という小さな思いの差なのか。。
当人しか知らない、当人にしかわからないことだけれど、そんな満足の積み重ねが、少しずつ心を磨いていくのだろうか。
ちなみに、ウルトラマラソンのランナーの多くは、さらに何か自分以外へ感謝するような気持ちにならないと走り続けられないと言う。
今月末には「つくばマラソン」がある。
長距離走の面白さは、自分の心や体を感じることができることだ。
いつものように、私の脚は脳を通じて「歩こうよ、歩こうよ」と弱音を吐いてくるだろう。
でも、今回は、心に話しかけてみるつもり。
「ここらで一度、やり遂げてみよう!ゴールした時、少しだけ違う世界が感じられるかもしれない」と。
- 2010.11.02 創業社長の退任
-
最近、お世話になった企業のトップが相次いで退任された。
ひとりは、ディーブレイン証券(現、みどり証券)の出繩社長、もうひとりはリサ・パートナーズの井無田社長である。
ディーブレイン証券は、当社が1999年暮れにグリーンシート市場に登録する際の引き受け証券会社。
当時、営業店舗は「日光鬼怒川店」のみ。「那須店」や「秋田六郷店」の出店準備で苦労していた頃で、出繩社長との出会いがなければ、その後のチェーン展開はきわめて困難なものになっていたに違いない。
リサ・パートナーズの井無田社長との出会いは2004年夏、ある方の紹介でお会いした。初対面ながら当社の事業に強い関心を持たれ、即座に共同出店の意向を示していただいた。その後「東京新木場店」をはじめ14の店舗が具体化したが、それは現30店舗のほぼ半分である。この業務提携がなかったら、現在のチェーン展開はない。
両社とも、設立は当社の3〜4年後。いずれも、従来なかったビジネスモデルを実現したベンチャー企業で、社長の強い思いがあって実現した社会性の高い企業である。
数年前までは順調に業績が拡大していたが、金融情勢の激変が大きな影響を与えたようだ。退任に至った詳しい事情はわからないが、志半ばでの不本意な退場であったことは間違いない。
経営が行き詰ったことについて、トップの責任は重い。批判も当然あるだろう。判断に甘さや誤りがあったのかもしれない。しかし、ベンチャー企業の創業社長のひとりとして、無念の思いは容易に想像できるし、胸が詰まる。
新しいことを興す人と、育てる人と、守り維持する人の適性は違う、というようなことを聞いたことがある。
たしかにそうかもしれない。しかし、リスクを承知で興す人がいなければ、育てることも守ることもできない。
両氏のことだ、新しい挑戦に向けて、捲土重来を期されているに違いないが、少なくとも現時点でこれまでの勇気と情熱と労苦に心からの敬意を表したいと思う。
素晴らしい仕事を残されましたよ。
「ファミリーロッジ旅籠屋」は、 間違いなく、そのひとつです。
- 2010.09.15 2度目の富士登山
-
数年前から企てていた親子での富士登山。
直前に仕事の予定が入ってしまい、3週間遅れの8月下旬、上の息子と2人だけでの登山となった。
昼過ぎに家をでて、夕方に御殿場口の駐車場に到着。
4つあるルートの中でもっとも低い地点(標高1440m)から、もっとも距離の長い御殿場ルート。
かなりハードと聞いていたが、他のルートの混雑は避けたかったし、仮眠する山小屋も満杯だったので、
あえて夜間登って夜明け前に頂上に着いてご来光を拝もうという計画になった。
数年ランニングを続けているので、体力に自信がないわけではないが、高山病がこわい。
強引に無理できる年齢でないことは自覚しているし、変調をきたせば苦しいだけだ。
そんな不安を抱えながら、とにかく、ゆっくりゆっくり登り始める。

人の少ないルートと聞いていたが、8月中旬の土曜。
早々に日が暮れて振り返れば点々と登山者の灯火が線になって連なっている。外国人も多い。
1時間に一度は座り込んで休憩。振り返ると山麓の演習場で夜間の実弾演習の火。遠くに花火大会の火。
20時前に1930mの次郎坊。2時間以上もかかっている。
22時ころに夕食のおにぎりをほおばり、23時過ぎに2590mの新六合目。
延々と足元の安定しない砂礫道で疲れる。
普通なら4〜5時間で到着するはずの7合目に着いたのは、午前2時前。8時間以上も経過。
4時過ぎ、3310mの7号9勺の小屋に着いたころに空が白み始め、1時間ほどとどまってご来光を見ることにする。
さすがに寒いが、素晴らしい日の出を眺める。

5時半前にここを出てすぐに8合目。見上げると頂上の縁が見える。あとわずか、もうひと頑張りと思うが、ここからが長い。
登っても登ってもなかなか頂上が近付いてこない。
3週間前に同じコースを登っている息子も疲れているようで、歩みが遅い。
結局頂上に着いたのは8時ころ。
最初のペースが遅すぎたのか、休みが多すぎて時間をかけすぎたのか。
眠気もあって、精神的にもかなり疲れてしまった。
思えば、40数年ぶり、2度目の富士登山。
前回は、中学生だったか、高校生だったか、昨年亡くなった父との登山だった。
あの時、父は40台半ば、今の私よりずっと若かったことになる。
頂上で力尽きた私を置いて頂上付近を更に歩きまわっていた姿が記憶にある。
剣が峰まで往復してきたのか、お鉢巡りをしていたのか。
「オヤジ、来たぞ!」と小さくつぶやいて、あの時果たせなかったお鉢巡りに挑む。

頂上付近はおそらく数千人はいるだろうという賑わい。
食堂で800円のカップうどんを食べ、最高地点の剣が峰に登り、そのまま右手に恐ろしげな火口を見ながら、その縁を廻っていく。
疲れた体には登りの待つ下り坂さえ恨めしい。ふつう1時間半という行程に、結局3時間以上もかかる。
ここでちょうど正午頃。計画ではすでに登山口まで戻っているはずの時間だ。
一応の目的は果たしたし、ヘリコプターで迎えに来てほしいところだが、自力で下るしかない。
座り込むと眠気に襲われる。心身ともにクタクタ。
足場の悪い砂礫道。一歩一歩に緊張を強いられ、苦行のようだ。
ようやく7合目まで戻り、登りの道から分かれ、待望の大砂走りに向かう。
かつて飛ぶように下った記憶があり、楽しみにしていたが、疲れ切った脚では歩幅が伸びず、逆に筋肉がきしむ。
少しもスピードが出せず、脚が壊れそう。まわりは霧で視界が閉ざされ、人影もない。
無限に続くかと思われるような単調なゆるい斜面が続き、明らかなデジャブーにとらわれ、半ば幻覚状態。
今、自分が何をしているのかがよくわからない。無性に苛立つ。
1時間以上もこんな状況をさまよい、ようやく先行していた息子と出会い、残りの数キロを無言でとぼとぼと歩き続ける。
方向感覚も位置感覚も失いながら、なんとか5時ころに登山口に戻る。考えてみたらほぼ24時間歩きっぱなし。
予定どおり、日帰り温泉に立ち寄って汗を流し、食事をとる。
さっぱりして、ようやく一息つくが、これから東京まで戻らなくてはならない。瞬時に眠りに落ちてしまいそうで、危険極まりない。
年齢制限のある保険の関係で、運転を代わってやるわけにもいかない。ひたすら話しかけながら、渋滞を抜け、0時ころに帰宅。
荷物を置き、ベッドに倒れこみ、3秒で意識を失う。
フルマラソンよりずっとつらかった。
- 2010.08.15 昭和85年8月15日
-
きょうは終戦記念日。昨夜放映されたTVドラマ「歸國(帰国)」の録画を見た。
内容は想定内で、特別の驚きも感動もなかったが、「死」というものを感じさせられ、少々応えた。
というのも、昨日8月14日は昨年9月に他界した父の初盆の法事、そして明日8月16日はその父の誕生日だからだ。
あの世も、お盆も信じてはいないけれど、常に、頭の右後ろあたりに気配を感じているのは不思議なこと。
やはり、ちょっと寂しい。
やはり、ちょっと切ない。
先日、会社の若い連中と雑談していて「戦後」という言葉がほとんど意味を失っているのに、突然気が付いた。
私は戦後の生まれだが、子供の頃はまだ戦争の匂いが色濃く残っていた。
防空壕の跡があちこちに残り、ガード下には白装束の傷痍軍人がたくさんいた。
そして、みんな等しくつつましく、豊かになろうと懸命だった。
ドラマ「帰国」の中で、今の日本人は「豊かさと便利さを勘違いしている」というような科白が出てくる。
「生きることをさぼっている」とも言う。
確かにそうかもしれない。
しかし、人に殺されず、人を殺さずに生きていける「平和」はすべてに勝ることだと思う。
父の死後、級友だった老人に招かれ、昔話を聞きに伺ったことがある。
「戦後何十年も誰にも明かさなかったことだが、じつは特攻隊の生き残りなんです」と、突然告白された。
驚き、そして少し身構えた。
戦争を忘れ、戦死した人々を忘れてしまった現代の世相を嘆き、戦後世代を戒める話しが続くと思われたからだ。
しかし、語られたのは意外な言葉だった。
「将来、日本が攻められ、占領されるようなことがあるかもしれない。
しかし、占領されればいいんです。
・・・死んじゃいけない。敵であっても人を殺しちゃいけない。彼らにも人生がある、家族がある。
私は日本人を信じている。占領されたって、いつか日本人は立ち直る。
死んだ人間はけっして生き返らないんだから・・・」
人間は、とくに男は強がりたい生き物だ。
卑怯者よばわりされるくらいなら勇ましく死にたいと叫んでみたくなる生き物だ。
政治家を含め、「偉い」人達にそういう人が多いかもしれない。
飛行機の故障や天候など、偶然が生死を分かった。
死んでいった仲間への思い、事実の重さが、50年以上の沈黙を強いた。
誰よりも「勇ましく」生きたように思えるその老人の言葉に、私は深く心を打たれ、言葉を失ってしまった。
来月17日の父の命日は、会社の株主総会の日でもある。
この不況下で黒字に戻せたこと、そして・・・
報告を笑顔で聞いて欲しかったが、それはかなわない。
昭和85年8月15日、深夜。
- 2010.06.25 会社借金への個人保証
-
睡眠不足と戦いながらのサッカー観戦が続いている。
オランダ戦はパブリックビューイングに行ってきたが、叫ぶ機会もなく敗戦。今朝のデンマーク戦は、自宅で何度も絶叫。
個人的にはカズを帯同させて欲しかったし、俊輔に活躍の場を与えて欲しいが、予想を覆してのグループリーグ突破はもちろん嬉しい。政治や経済の面では、日本の存在感が軽くなるばかりだが、サッカーの影響力は絶大だし、ここはひとつ世界中に「日本」をアピールして欲しい。
さて、仕事の話し。
あと数日で決算日を迎える。
前期は5期ぶりの赤字となり、今期は黒字に戻すことを目標としてきたが、これは間違いなく達成できそうだ。よかった。みんなの地道な努力のおかげだ。
損益の数字以上に喜ばしいのが、営業キャッシュフローが安定してプラスで着実に増えていること。
例年、夏休み前の賞与支給後がもっとも資金が枯渇する時期だが、今年はキャッシュが潤沢で、運転資金を借り入れる必要がない。数年前まで、資金繰りの不安に苛まされる日があったことを考えると、夢のようだ。
こんな時に限って、取引先の金融機関から新規融資の打診を受ける。
「運転資金の心配はないのですが、自社で出店するとなれば設備資金としての借入は必要となります」と答える。というのも、最近、なかなか出店の話しが決まらないので、久しぶりに土地建物を自社で所有することも考えているのだ。「ついては、経営者の個人保証という条件を見直してもらえませんか」と尋ねてみる。
現在の借入残高は2億円以上あるが、すべて私が連帯保証人になっている。中小企業が借入れする場合、当然のように経営者の連帯保証が求められている。
創業当初の会社、実質的に経営者の個人企業のような会社の場合、経営者個人が責任をもって会社の経営にあたることを促すために連帯責任を課すことの合理性を否定しないが、一律にこれを求めることは納得できない。
私は、親族に経営を引き継がせることはまったく考えていない。家業として特定の個人や家族に依存するのではなく、文字通りの法人として自立した社会的存在になることを志向している。これは会社の私物化や公私混同を防いで企業の透明性を高め、最適な人物に経営を引き継いでいくことにつながると信じている。
連帯保証の条件を外してもらうには、通常、ふたつの方法しかないらしい。
ひとつは株式公開すること、もうひとつは上場企業の傘下に入ること。
事業の発展を考えるとき、株式公開することには一長一短がある。経営者の個人保証を外すために株式公開するのは本末転倒である。同様に、ベンチャー企業がそのために既存の企業に飲み込まれなければならないのは馬鹿げたことだ。
長年の慣例ですから、と金融機関の担当者は否定的である。
事業規模が拡大すれば、借入額の単位もかわってくる。億単位の保証を個人に求めることに実質的な意味はなく、ある種の脅迫である。これでは後継者探しは至難のこととなる。
金融機関は中小企業がいつまでも個人企業であり続けることを求めているのか。
株式公開しか進むべき道がないと考えているのか。
企業の健全な発展を金融機関自身が阻害しているように見える。
創業者である私は、もちろん「旅籠屋」の発展を望んでいる。
しかし、終生保証人でいることを受け入れるつもりなどまったくない。
- 2010.04.30 新聞を読もう!
-
昨秋スタートした「店舗利益向上プロジェクト」の影響で広報宣伝担当としての作業も増え、なにかと目先の仕事に追われて忙しい。
おかげで、日記で愚痴る余裕がなくなって久しい。
第3四半期報告書のリリースも終え一息ついたので、以前から考えていたことをひとつ書いておこうと思う。
待望のゴールデンウィーク、年末年始以来のまとまった自由時間。
貴重な休日を漫然と過ごしてはもったいないので、今回も「やるべきこと」のリストを作る。きちんと実行できた例がないのだが、多少は役に立つ。その中で毎回掲げることのひとつが「たまった新聞を読み終えること」だ。
ときどき苦笑してしまうのだが、私は、新聞にひととおり目を通さないと気持ちが落ち着かない性質だ。出張や旅行から戻ると、律儀に古いほうから見始めて数日後にようやく「今日」になる。
一日の朝夕刊を読むのに30分前後はかかるから、費やしている時間は馬鹿にならない。
時間だけでなく気力も消費しているので、結局他の事を何もできずに寝てしまうことも珍しくない。これでは、本末転倒のような気もするが、やめる気はない。
最近、新聞を読まない人が多いと聞く。若い人はとくにそうらしい。理由を尋ねるとニュースはテレビでもやってるし、知りたいことはネットで調べられるから、ということだ。
声を大にして言いたいのだが、新聞は読んだほうがいい。それも、スポーツ紙や経済紙ではなく、総合紙を。
理由はふたつ。
ひとつ、新聞は「知りたいことを知る」のではなく、「知らないことに気づき、知りたいことを見つけられる」ものだ。知らず知らずのうちに見出しが目に入ってしまう、そこが素晴らしい点だと思う。総合紙であれば、ひととおりの分野が概観できる。
ふたつ、新聞という座標を手がかりに自分の立ち位置が自覚しやすいということ。問題意識や意見なんて突然湧いてくるものだとは思わない。新聞を読んでいると、世間一般の関心事や問題がなんとなく伝わってきて、断片的かつ情緒的な反発や共感が、新聞紙面での論調や論点とぶつかりながらまとまっていく。
新聞に書かれていることは世の中のごく一部にすぎないし、大なり小なり歪んだ「正論」でしかない。
そのことを忘れると、思考停止の「常識人」になってしまう。
しかし、だからと言って、新聞の助けを借りずに、広い視野と見識と判断力が自分の中にあるなどというのは過信であり傲慢である。
新聞ときちんと付き合わない人は支離滅裂で自己チューのモンスターになりやすい、そんな気もするがどうだろう。
大げさに言うと、私は新聞のおかげで自分のアイデンティティをつくり、なんとか保てている気がする。
青少年諸君、新聞を読もう!
- 2009.12.30 節目の年
-
あと1日で今年も終わる。来年は2010年、平成22年。
そうか、あの9.11から10年近くが過ぎたのか。元号が変わって20年以上も過ぎたのか。
なんとなく無我夢中で生きているから時の経つのを忘れてしまっている。
それにしても、今年は、変化の大きい1年だった。
新年早々、下の義娘が所帯を持ったのをきっかけに我が家を改築、20年以上の変則的な生活に終止符を打って夫婦と愛犬1匹での生活がスタートした。
春には上の義娘が出産して初孫が誕生、ジージになった。
いっぽうで、1月早々から父が病床に伏せって、長い自宅介護を経て9月に他界した。
残された母に立ち直ってもらおうと半ば強引に部屋を改築、遺品の整理をしながらようやく片づけも終わりつつあるところだ。
2月には「偲ぶ会」を催し、3月には故人の遺志にしたがい故郷の川に散骨に行く。
そんな中でも、ランニングは続けている。
今年の走行距離はあと3kmで年間1200kmになる。月平均100kmだ。
毎月のように大会に参加し、フルマラソンにも3回出た。
記録は少しずつしか伸びないが、体重も体脂肪率も下がり、体力は確実に向上した。
それになにより、走ることが習慣になり、精神的にどれほど救われたか知れない。
流れる汗は憂さを忘れさせ、息苦しさや筋肉痛は無条件に自分が生きていることを実感させてくれる。
無為に時間を過ごしていないと思えることが、心を軽くしてくれる。
仕事のほうは、不景気の影響などによる5年ぶりの赤字決算と稼働率の伸び悩み、そして新規出店の難航と表面的には停滞の年になった。
しかし、多くの支配人と対話し、業務の見直しや改善に力を尽くす、充実した1年でもあった。
テレビでも紹介され、少しは知られる存在になってきたようだ。
上げ潮に乗ってはやされるのも悪くない。
知名度やステータスが上がるというのも悪くない。
しかし、そんな上っ面の見栄えで自分たちを見失うなんてばかげている。
きっと来年も、そろりそろりと前進する年になるだろう。
周囲から見れば、焦れったい歩みかもしれないが、毎日すべきことをする、それで良い。
シンプルで自由な、旅と暮らしをサポートする。それで良い。
それだけ、根本的に価値のある仕事をしていると変わらずに信じていられるからだ。
今年は、変化の大きい1年だった。
後に振り返れば節目の年だった、ということになるのかもしれない。
でも、一喜一憂せず倦まず弛まず進む。
その結果、来年、どんな景色が見えてくるのか、とても楽しみなのだ。
- 2009.09.18 幹さんと株主総会
-
本日開催の第15期定時株主総会、10名ほどの株主の出席をいただき、先刻、滞りなく終了した。
5年ぶりに赤字決算になり、厳しい叱責も覚悟していたが、暖かい励ましの言葉もいただいた。
任期満了にともない、甲斐 幹が退任し、店舗開発部長である森 弘と、店舗管理部長である小島 裕生が新任の取締役に選任された。
甲斐 幹は、私の父である。
15年前、旅籠屋の会社設立資金を出資してもらい、その後も金融機関から相手にされない時代、何度かつなぎの運転資金を融通してもらった。取締役として15年余り、いっさい無給でありながら、陰ながら会社を支えてくれた。
年初より、病床に臥せっており、はやくから退任を決めていたが、最後の総会は欠席となった。
というのも、任期満了前日の昨夕、残念ながら遠くへ旅立ってしまったからである。
寝たきりとなって8ヶ月、本人の希望もあり、自宅での介護を続け、幸い痛みや苦しみも少なく、眠るように息を引き取った。
数日前まで、いつものように私が口元に運ぶスプーンから夕食の粥を食べてくれた。
数時間前までは、呼べば目を開いてくれた。
ろうそくの炎のように消えそうになる命の火を揺らせながら病いと闘っていた。
母は両手でその炎を包み、消えないように必死に守り続けていた。
しかし、とうとう、最期の1時間、握り続けた手が反応を返してくれることはなかった。
最後まで「寒河江店」に行きたいと望んでいたが、叶わない願いとなった。
株主総会の会場は、本社近くのいつもの貸しスペース。
部屋に入った途端、昨年まで隣りに座っていた姿が思い出され、一瞬胸が詰まった。
朝、妻から父愛用のネクタイとベルトを渡された。
これを身につけ、いつものように「参加」してもらった。
ここ数年はすっかり安心し、滅多に仕事の話をする機会もなかったが、「旅籠屋」の発展を心から願い、店が増えていくことを喜んでくれていた。
ただ1人の子供として、個人的な思いは尽きないが、旅籠屋にとって、ひとつの時代が終わり、新しい時代を迎えている気がする。
遺志を裏切ることなく、努めて行きたいと思う。
きょうの株主総会が、その第一歩になるのかもしれない。
幹さん・・・
私は、幹さんが激しく我が身を燃え立たせて生きてきたことを知っています。
時にはその熱に焼かれ、時には暖められてきましたが、確かにその炎は周囲を照らしていました。
いつも一生懸命の後姿を見ていましたよ。
男として、人間として、立派な人生でした。
社会的地位とは関係なく、誇れる父親でした。
「ごまかすな」
幹さんが私の心に焼きつけた血の刻印です。
ありがとう。
- 2009.08.24 1年ぶりのナイトマラソン
-
先週の金曜日、去年に引き続き、8名で今年も「葛西臨海公園ナイトマラソン」に参加した。

コースは去年と同じだが、なぜか逆周り。
ランニング大会に出るようになって丸3年。最初は断続的だったが、最近は毎月のようにどこかしらの大会に参加するようになり、ジム通いなどの練習も年間を通じて続けるようになっている。
私個人の10kmベストタイムも、初回の79分47秒(2006年7月)から56分21秒(2009年4月)へと、着実に縮まっている。
そこで今回もベスト更新を目指したいところだが、なにせ気温も湿度も高く、秋からのシーズン到来前の足慣らしと割り切る。
案の定、走り始めたとたん汗が噴出し、精神的にとても苦しいレースになった。
それでも、ちょうど走力が拮抗しているTさんと抜きつ抜かれつの競走になったことが励みになり、去年の記録を約1分半縮めて57分34秒でゴールすることができた。
それにしてもこの大会、途中の距離表示もほとんどないし、ゴール付近の時計もない。電気計測しているにも関わらず、速報も一部しか掲示されない。このタイムも計時を担当した会社を調べて電話し、無理に教えてもらったものだ。
最近のランニングブームを反映して、間違いなく大会が増えているが、どうもランナーの思いを理解していない大会が少なくない。圧倒的大多数の参加者はトップ3の表彰などではなく自分のペースやタイム更新を目指して走っている。だから距離表示や時計の設置は必須なのだ。
主催者の裏方の苦労はもちろんたいへんなものだと思うが、ランナーの望みに応えることを基本にして欲しい。逆に参加賞のTシャツやタオルなんてなくていいのだ。
公私ともにストレスの多い毎日だが、走ることで気分転換ができる。努力して良いことをしている、という気持ちが心を健康にしてくれている。50歳代も半ばになって始めたことだから、上達する余地は大きくない。率直に言ってタイムも市民ランナーの初心者レベルだ。でも「今日の自分が、人生で一番若い」という言葉を頼りに向上心を持ち続けていたいと思う。
10月には5kmと10kmの大会に出場する。11月には2度目のフルマラソンだ。
いずれもベストを更新する。
近々、ホームページの片隅にランニングサークル「チーム旅籠屋」のコーナーを設けて参加予定の大会やタイムを載せようかと考えている。
皆さんもご一緒にいかがですか。
- 2009.08.03 3年ぶりの8耐観戦
-
1987年以来、毎年のように観戦に行っている「鈴鹿8時間耐久ロードレース」。
公私ともに忙しく、ギリギリまで迷っていたが、3年ぶりに現地で観戦することにした。しかも、今年は久しぶりに友人とふたり、バイクでのロングツーリング。高速道路の休日特別割引を活用しようと2ヶ月前にETC取り付けを申し込んで、それもなんとか間に合った。
思い返せば20歳の頃、近所の自転車屋さんで3千円の中古カブを買って以来、初めはゲタ代わりのつもりだったのにすぐにバイクの虜になった。その魅力を語る言葉は世の中にたくさんあるが、要は性にあっていたということだろう。
寝袋やテントを積んで野宿ツーリングに行ったり、あちこち分解したりちょっとした改造をしてみたり、ミニバイクレースに出ようと練習してみたり、トライアルバイクを買って毎週のように山へ出かけたり、いろんな思い出がある。
そんな中、30代も半ばになって初めてレース観戦にいく機会があり、言葉で表せないような衝撃を受けてしまった。
そのあたりの経緯は12年前に書いたこちらの旅行記で。
その後、縁あって、8耐に挑戦し続けるプライベーターをサポートし「チーム旅籠屋」として参戦(2000年、2001年)したりもした。
バイクとの出会いがどれほど私の人生を豊かにしてくれていることか。
さて、今回の観戦旅行。
8耐といえば基本は7月末の開催、真夏のイベントの代名詞になっている。少しでも炎天下の走行を減らそうと、初日金曜日は仕事を終えたあと、夜のうちに走って途中の「ファミリーロッジ旅籠屋・牧之原店」へ宿泊することにする。
ところが、 いきなりの雨で時間がかかり、吉田ICを下りた時点で土曜日(23時に間に合わないことは途中から支配人に連絡済み)。幸か不幸か、初日から休日特別割引の適用を受けることになった。
深夜0時半、 宿に到着。すでに明かりが消え、静まりかえっているため、すぐにエンジンを切って車寄せの端にバイクを駐める。びしょぬれになった服を脱いで暖かいシャワーを浴び、持参のモバイルPCでメールチェックして、広いベッドでくつろぐ。手前味噌ながら「ファミリーロッジ旅籠屋」は、シンプルだけど、とても心地よい。2輪のツーリングにももっと使って欲しい、と思う。
2日目、外は今にも雨が降り出しそうな鉛色の空。今回はプライベートでの利用なので宿泊料金を支払い、遠慮なく朝食のパンやコーヒーをいただいてカッパを着て出発。
伊勢湾岸道が開通し、鈴鹿周辺道路が整備されたおかげで、サーキットへのドライブは格段に楽になった。途中、前半は雲が切れて夏の日差しにさらされたものの、後半はまた土砂降りの雨に見舞われて靴は再びグショグショ。2時半頃には到着したが、予選は裸足で観戦。
サーキットは大幅な改築直後で、園内もスタンドも大幅に雰囲気が変わっている。来場者も少ないので、屋根のかかっているV2スタンドはとても快適。
以前サポートしていたライダー達はその後も参戦し続けており、予選落ちを繰り返していたが、今年はギリギリのタイムであすの決勝に出られることになった。素晴らしい。知人が走っているとなれば、観戦の楽しみも比較にならないほど大きくなる。
夕食を済ませ、定宿に着いて、友人とバイク談義をしながら眠りにつく。
いよいよ決勝当日。天気予報は曇り時々雨だが、空は明るい。 10時半過ぎに席につく。 まわりは空席が目立ち、ゆっくり観戦できそう。
11時過ぎからはチームとライダーの紹介。聞こえないとは知りつつも、予選突破した知人ライダーに大声で声援を送る。 40過ぎても挑戦し続けている一途な思いに拍手。
11時半、予定通りスタート。
50台以上のマシンがいっせいに始動して1コーナーへ飛び込んで行き、2分ちょっとの静寂のあと、一群の流れとなってホームストレートに戻ってくるときの音と光景は何度経験しても感動的だ。
生身のライダーが時速250kmを超えるスピードで加速しながら次々に駆け抜けていく。真っ赤になった純粋な人間の意志そのものが迫ってくる感じで、心が震えてしまう。血が騒ぐ。
その後のレース経過は省略。
途中、3回ほど土砂降りの雨になり、4回もセーフティカーが入る大荒れのレースになったが、結果、応援していたヨシムラのチームが優勝。
知人ライダーのチームも、なんと35位で無事完走。きっとピットで喜びを爆発させているに違いない。良かった、ほんとうに良かった。おめでとう。
過酷なレースだったせいで、ゴールの時の感動も大きく、パレードラップで全車が戻ってきた時は泣きそうになった。
庇の深い席にいたため、雨にも降られず、直射日光にも当たらず、今年は快適な8時間。無理して来てよかったな、と思う。
いつもなら、宿に戻ってのんびりと余韻を楽しむところだが、今回は帰りのロングツーリングが待ってるので、すぐに気持ちを切り替えなきゃならない。サーキットホテルのレストランでいつものように夕食を済ませ、小雨模様の中、亀山から新名神を抜けて今夜の宿である「レストイン多賀」へ。これも高速道路料金節約のためだ。
もっとも通行量の多い名神・東名・中央高速のSAにこそ、「ファミリーロッジ旅籠屋」があればこんな遠回りなどしなくて済むのに。
というか、民主党の公約が実現して、高速料金がタダになってしまえば、この辺の事情も一変してしまうかも。今回ならインターの出口脇にある「土岐店」などが最適だ。
いずれにしても沿道にあると言う意味でSA・PA内の宿泊施設の利便性は変わらないのだから、中日本高速道路の英断を望みたい。
そんなことを考えながら夜の新名神に入った後は夜空の雲も消え、快調に走り、11時半には多賀SA内にある「レストイン多賀」にチェックイン。すぐに大きな風呂に入って、リフレッシュ。なんとか、無事ここまで来たぞ。
一夜明けて、いよいよ、東京に戻る月曜日。
当たり前のことだが、肝に銘じているのは、とにかく無事に旅を終えること。気を引き締めて、走り始める。
今回乗ってきたのは、所有している2台の250ccバイクのうち、ロングツーリング向きのKAWASAKIのエリミネーター。
もう1台のYAMAHA R1-Zは高速道路の長距離走行には向いていない。以前、仙台から走ってきたときの旅行記はこちら。
調べてみたら、エリミネーターを買ったのは15年前、1994年の9月。旅籠屋を設立した直後、まだ1号店の構想を立てている頃だ。
最近は、めっきり乗る機会も減っていて、高速を走るのも久しぶりだったが、エンジンは快調。なにひとつ不具合は感じなかった。
しかし、けっして無理はせず、時速100km以下でたんたんと走る。行きと同じ道を通るのも能がないし、交通量も少ないだろうと、帰りは中央高速に走ることにしする。
ずっと、小雨模様の天気の中、夕方7時前、明るいうちに無事帰着。
450kmは長かったけれど、 真夏の太陽にも焼かれず、土砂降りにもあわず、かえってラッキーだったかもしれない。
ETCは、ほんとうに便利だった。安かったし、2輪で高速使うなら必須。
8耐、思い切ってバイクで行ってよかった。ウルウルした。
しかし、時間に追われて走るロングツーリングはつらい。
宿泊した「牧之原店」をはじめ、「浜名湖店」「桑名長島店」「伊賀店」「彦根店」「土岐店」「小淵沢店」「韮崎店」などが沿線にあり、近くを通るたびに「支配人」の顔や店の様子を思い浮かべたりした。
機会を見つけて、これらの店に泊まりながらゆっくり旅したいと、 何度も何度も考えた。
- 2009.07.15 なにわ節
-
きのうは、久しぶりにひどく落ち込んだ。
仕事を終えた後、あえて自分を鼓舞しようといつものようにジムに行き、5km走って、その間は忘れられたが、夜中になると目が覚めて眠れなくなった。
というのも、楽しみにしていた新しい出店の話しが、最終段階になって暗礁に乗り上げてしまったからだ。
そもそもは先方から持ち込まれた「建て貸し」の話しで、現地を訪ね、条件面で譲歩し、質問にも誠実に答えたつもりなのだが、上層部からのゴーサインが出なかったらしい。考えてみたら、ちょっと失礼な話しではないか、とも思うのだが、景気低迷の中、経営者の判断も慎重にならざるを得ないのだろう。
思い返せば、業務提携先であるリサ・パートナーズさんの協力を得て比較的容易に出店数を増やせるようになったのはここ2、3年のこと。それ以前は、ひとつひとつの建て貸し案件を具体化するために、何度もオーナーへの説明を繰り返し、結局実を結ばないケースも少なくなかった。
くやしい、情けない、今回、そんな苦い思いを久しぶりに味わった。
1号店オープンから15年が過ぎた。店舗も30に増えた。高速道路内の宿泊施設という画期的な出店も実現した。
相変わらず、儲かるビジネスにはなっていないが、それは創業の理念を重視し続けていることの結果でもあり、社会的使命を実直に果たそうとしている証しであるとの自負もある。
つまり、数年前より、ずっと実績も積み、信用力も上がっているはずなのだが、それでも相変わらず「信頼してもらえない」とすれば、なんとなく虚しくなる。悲しくなって思わずため息が出る。
新規出店に関して、当社は一時的なキャピタルゲインを得ているわけではない。オープン後、長期間にわたってコツコツと宿泊営業を続けていく積み重ねがすべての利益の源泉である。だから、新規出店を続けなければ、経営が成り立たないというような自転車操業とはまったく無縁である。というより、出店ペースの上昇は当面の赤字店舗を増やす面があるから、損益上は出店を抑制するほうがプラスだったりする。
だから、今回のことも損得の面で嘆いているのではない。
しかし、旅籠屋のオープンを支え、それを生業の柱にしている実直な取引先がいくつもある。そして、支配人になる日を待ちながら全国を飛び回っている「代行支配人」の夫婦が何組もいる。こうした人たちにとって、コンスタントな新規出店の継続は死活問題である。
彼らの期待と望みに応えたい。それが、私の一番の願いであり、ため息の理由でもある。
それを「なにわ節」と批判するなら甘んじて受けよう。アマチュア経営と揶揄するなら、そのとおりと答えよう。
「経営者は心の中に鬼を一匹飼っておけ」という言葉があるが、情に流されない厳しさを持つという意味では納得するが、会社の利益のためなら周囲の犠牲を省みないということなら断じてそれは私の流儀ではない。
旅籠屋に関わる人間がハッピーになれないなら、いったい何のためのビジネスか。
暗礁に乗り上げてしまった今回の出店用地。 おそらく、他には有効活用が難しい土地だと思う。 しかし、旅籠屋にとってはとても面白い立地だと感じている。
海水浴を楽しむ子供たちの笑い声、近くの事業所を訪れる馴染みのビジネスマン、のんびりと周辺を散策する年配のご夫婦。
地域を照らす小さな灯火となる宿。社内のみんながそんな光景を思い描き楽しみにしていた旅籠屋。ちょっとした波の一押しで船が暗礁を越え、再び進み始めることを願って止みません。
- 2009.07.13 ファイナンス・リース
-
「桑名長島店」「寒河江店」と2週連続のオープン準備が無事終了し、きょうから決算監査が始まった。
第3四半期報告書で公表したとおり、
・出店スピードのアップによる新規店舗(軌道に乗るまでは赤字になるケースが多い)の増加、
・店舗増に対応するためのスタッフ増員による本社経費の増加、
・昨年来の不況によるビジネス客を中心とする稼働率の低下、
などの要因により、今回の決算は残念ながら赤字を免れないのだが、悩ましいのは「ファイナンス・リース」の適用によって、会計上1千万円近くの費用が増えてしまうことだ。それも、単年度だけでなく、今後の新規店舗を含め毎年積みあがっていくのだから、経営上の影響はきわめて大きい。
当社の場合、初期の3店舗を除き、店舗の不動産は所有せず、借り上げて家賃を払いホテルの経営と運営を行っているわけだが、先例のない業態であることや会社の知名度を含め信用力が十分でないこともあって、賃貸借期間20年間を通じて家賃保証することで土地建物のオーナーのリスクを減らし、出店契約をまとめてきた。
こうしたことから、従来の「オペレーティング・リース取引」ではなく「所有権移転外ファイナンス・リース取引」に区分されることになり、今回の決算から「リース取引に関する会計基準の運用方針」に従った会計処理を課せられることになったわけだ。
契約内容も毎月の家賃支払額も変わらないのに、会計処理の方法だけが変わることになる。
具体的に言うと、不動産を購入・取得していないにも関わらず、同等の金額をリース資産・リース債務に計上するため、貸借対照表の金額が一気に増えることになる。
また、リース債務は現在価値で割り引くため、実際の家賃支払額より小さくなるため、差額は支払利息として計上されることになる。
そして、この利息額の算定に利息法が適用されるため、少なくとも契約期間の半ば過ぎまでは定額法による場合よりも割高になる。
つまり、定額法で良ければ、従来の支払家賃≒(リース資産の)減価償却費+支払利息となり、損益上の差はほとんどないのだが、利息法適用となると、従来の支払家賃<(リース資産の)減価償却費+支払利息となり、損失が増大することが利益額に大きな影響を与えることになるのだ。
1店舗あたり、毎年100〜200万円も費用が増加すれば、出店すればするほど赤字が大きくなり、向こう10年くらいはどんなに頑張っても黒字復帰が難しくなる。とすれば、これは当社のようなビジネスモデルを会計制度が結果的に否定していることを意味する。
「ファイナンス・リース」に該当するかどうか。利息法の適用が必須かどうか。
専門書を精読し、監査法人と研究を重ね、公認会計士協会に何度も判断を仰いだが、結論が変わることはなかった。
たしかに、全額家賃保証の賃貸借契約は、ある種の「隠れ債務」を抱えていることであり、会社に万一のことがあった場合の解散価値が貸借対照表から読み取れないことになり、会計の透明性から言えば好ましいことではない。
また、リース債務が減っていくに従って利息の額が減っていくという考え方も至極当然のことと言える。
だが、そもそも会計基準とは一般的な合理性だけで、定めてよいものなのだろうか。
例えば営々として事業を営んでいるメーカー企業が時価会計の適用だけで、突然大きな損失計上が課せられ、経営破たんの危機にさらされる例が少なくないらしい。時価会計がほんとうに企業価値を正当に表すのかという疑問は、本家本元であるアメリカからも発せられ、運用基準が揺れているようだ。加えて、企業会計の継続性・連続性という観点から、運用基準の大きな変更は決して望ましいことではないはずだ。
「隠れ債務」というリスクを負っているというが、そもそもベンチャービジネスというのはそれなりの経営リスクを背負ってスタートするのであり、そのリスクを厳密に費用化すれば、いつまでたっても黒字化できない事業となる。投資家保護は大切だし、経営の透明性も重要だが、今までだって、リース取引の詳細は注記で示していたのだし、すべてをB/S、P/Lに反映しなければならないというのはいかがなものか。
だって、多くの人は赤字は赤字としか見ないし、金融機関の融資条件も株式市場の上場条件も会計基準の変更に配慮するとは期待できないからだ。
今回のことを契機に、今後の出店については家賃の保証期間を20年から15年に短縮させることにした( 詳しくはこちら)。
監査法人との検討を経て、公認会計士協会にも確認したが、これだと「所有権移転外ファイナンス・リース取引」に当たらないからだ。
たしかにオーナーのリスクは多少高くなり、出店交渉に影響が出るおそれもあるが、旅籠屋の実績や信用力も10年前とは違うだろう。誠実に説明して、理解していただくつもりだ。
それにしても、都市計画法といい、旅館業法といい、労働基準法といい、会計基準といい、どこへ行っても、旅籠屋のビジネスは「想定外」で苦労が絶えない。
やれやれ。
- 2009.04.06 高速道路料金の値下げ
-
3月28日から、大都市圏を除き、ETC車両の土日祭日料金が1,000円に値下げされた。
「壇之浦PA店」「佐野SA店」に出店しているため、メディアから「値下げの影響は?」という問い合わせや現地取材が相次いでいる。
短時間ながら、テレビでも各局のニュースで放送されたようだ。
SAやPA内に宿泊施設があり、高速道路から下りずに泊まりながら長距離ドライブができることは、まだまだ知られていない。だから、こうした報道で知名度が上がることは歓迎すべきことだ。
また、今回の値下げ措置によってドライブ旅行の機会が増えれば、すべての店舗において利用者増につながることだからありがたいことではある。
しかし、なにか釈然としない。
それは、ふたつの点においてである。
ひとつめは昨年の「深夜割引率拡大」から相次ぐ料金改定そのもに対する疑問。
すなわち、高速料金が政治家や国土交通省によって「おもちゃ」にされていないかということ。
道路公団が分割民営化された目的のひとつは、各高速道路会社が創意工夫を行い、コスト意識を高めながら、自主的に事業の改善と発展を推進していくことにあったはず。国が株式のすべてを所有しているとはいえ、高速道路会社は民間企業だ。そのサービス価格がこのように外部の都合で大幅に変えられ、その差額が自動的に補填されるのであれば、社員のコスト意識など育ちようがない。私がその立場なら「あほらしくて、やってられない」と思うだろう。
大型車が対象に含まれないのは?だが、まぁ緊急の景気対策という狙いはわからないでもない。しかし、数年前あれだけ大騒ぎした民営化の理念はいったいどこへ行ってしまったのか。無定見なご都合主義とはこのことではないのか。
ふたつめはメディアの報道姿勢。取材の主旨はどれもこれも値下げによって、通行車両が増えたとか、SAPAの売上が増えたとか、表面的な現象の確認ばかり。せいぜい、「実施時期のズレ」や「二重支払い」などの揚げ足取りを付け加えるくらいで、前述したような基本的な問題意識は素通りのまま。あの「正義感」はどこへいってしまったのか。政治部と社会部は違う、アレとコレとは別の話しとでもいうのか。
「予約は増えてますか?」「事業には追い風でしょうね」なんていう、無邪気な電話取材に対して、いちいち上のようなことをぶつける気にもならないが、「そうですね、ありがたいことです」なんて答えるのも面白くないので、次のように話すようにしている。
両店ともオープン1年未満なので、明確な比較はできませんが、問い合わせは増えているようですし、利用者が増える要因にはなると思いますよ。
ただ、レストランやトイレと同様の基本的な利便施設として何年も提案し続け、ようやく出店を実現したわけですから、今回のような目先のことで一喜一憂するようなことはありませんよ。
- 2009.03.25 スポーツ、スポーツ
-
WBC、日本優勝!
いつもはサッカー中心で、野球観戦の機会は少ないのだが、WBCの日本戦は別。ほぼ全試合、TV中継を見ながら声援を送った。
きのうは、その決勝戦。一時デスクワークを中断して皆で思い切り応援したいところだったが、残念ながら催事に呼ばれて出先で仕事。
電車の中でワンセグ放送を見続けるが、 ヒットは出るのに、あと一本が出ずに残塁の山。点差は僅少。なんとも落ち着かない。
こんなにドキドキするのは久しぶり。
催事場に着いてからも携帯ニュースから目が離せず、試合終了でようやく緊張から解放された。
一気に霧が晴れたような爽快な気分。
優勝おめでとう。そして、最高の感動に感謝。
とはいえ 、以前、エリートスポーツの舞台裏を知る機会もあり、背後には醜悪な争いが渦巻いているのは想像に難くない。
国別対抗となれば、ヒステリックなナショナリズムも水をさす。
しかし、わざわざそんな負の面ばかり見つめてもつまらない。
日本も韓国も、チーム一丸となって全力を尽くして戦い通した。
心折れることなく鍛錬を続けた長く単調な時間、圧力に屈しない集中力と覚悟、チームプレイに奉仕する精神。
そういう「純粋な」闘争心に素直に心動かされたいと思う。
いきなりレベルの違う話になるが、10日前、初めてフルマラソンに挑戦し、無事完走した。
5時間半近くもかかるようなスローペースだが、それでも2年半皆で断続的に続けてきたジム通いがあったからこそのこと。
ゴールした後、期待したほどの感動はなかったけれど、走ることを楽しめるようになったり、早起きしてジョギングしたりするほど、心が軽くなっていることに嬉しい驚きを感じている。
健全な肉体があっても健全な精神が宿るとは限らないが、バランスを崩した肉体を背負いながら健全な精神を維持することは至難のことだと思う。
その点、スポーツはいい。体を動かすことはいい。
何も足さない、何も引かない、自分の身体だけのことだから余計なものがない。汗が出始めると雑念が消える。
肉体だけでなく、精神もシンプルにしていければ良い。ほんとうにそう思う。
- 2009.02.16 市民ランナー
-
4年前から匿名でSNSに書き込むことが多く、こちらではすっかり筆不精。
タイトルだけ書きかけのままアップしてしまったり、情けない有様だが、心配無用。いたって元気だ。
その証拠に、最近は、早起きして毎日のように走ってる。
昨年末に左足中足骨を疲労骨折してしまい、今も全力は出せないが、逆にマイペースで走るようになり、なんとなく楽しさを感じるようになってきた。走るのが楽しいなんて、信じられない。
今週末は、本社全員参加で「日産スタジアム駅伝大会」に3チームで参加。
来月は、「荒川市民マラソン」でフルマラソンに初挑戦する。
話題のランニングシューズ、newtonやTAIKANもさっそくゲットして試走した。
(以下、半分こじつけだが・・・)
企業経営は、長距離走。一時的なスピードや、オーバーペースは禁物。
ジョギングペースで良いから、安定して着実に走り続けること。
間違いなく、沿道の景色は変わってくる。
- 2008.10.14 アメリカ視察旅行
-
9月末から10月初めにかけて、6泊8日のアメリカ西海岸旅行に行ってきた。
実際に アメリカのMOTELに泊まり、「ファミリーロッジ旅籠屋」の原点を体感するため4年前に始めた視察旅行。
本社スタッフに続き、各店舗の支配人を順番に派遣し、今回は7組目、8組目の4人に私と店舗管理部長が同行し、総勢6人で出かけた。

およそのスケジュールは・・・
1日目
朝ロスに着いてレンタカーに乗り込み、ハリウッド散策、ビバリーヒルズを抜けてサンタモニカの海岸で昼食。
そのまま海沿いを北上してOxnardという所のMotel泊。
strong>2日目
寒気のせいか霧のかかっている海岸沿いを北上。途中有名なリゾート地Carmelを散策して、Seasideという町のMotelに宿泊。
3日目
昼過ぎにサンフランシスコに到着、北の金門橋を往復して街に戻りMotelを見つけて車を停め、夜まで市内散策。有名なフィッシャーマンズワーフでイタメシをとり、坂を上りながら市の中心部へ行きケーブルカーでまた港へ戻ってお約束のカニやエビを食べて夜にはMotelへ。
4日目
東へ進み、ヨセミテ国立公園を横断して砂漠地帯へ。ゴーストタウンになった廃墟を抜けて、Tonopahという田舎町のMotelに宿泊。
5日目
やっぱりリクエストの多いラスベガスに行くことにし、デスバレー横の砂漠地帯を延々と走り昼頃到着。早々にMotelを見つけてチェックインし、あとは中心部のストリップサウスを深夜まで3万歩も歩いて端から端まで散策。途中カジノに2箇所入ってスロットマシンで散財。
6日目
朝ゆっくりして、10時に出発。夕方早くロス空港のレンタカー営業所隣りにMotelを見つけて宿泊。夜に中華の店を見つけて最後の夕食。
7日目
レンタカーを返して空港で搭乗手続き。何時間も時間をつぶして夕方に離陸。満席の機内で12時間の辛抱。
8日目
無事成田着。預けていた車に乗り込み、左右を間違えないように注意しながら東京へ帰還。
私にとって、ロスは約15年ぶり。思い返してみれば、あの旅を機に事業を構想し、会社設立を考え始めたのだった。
サンランシスコは約13年ぶり。ひとつめの店舗「日光鬼怒川店」建築中の時だった。
感慨深いものがある。
今回、私以外は全員アメリカ本土は初めてなので、事故やトラブル無くみんなに旅を楽しんでもらえることばかり考えていたので自分の楽しみは二の次。
でも、その目的は果たせたので良かった。
以前と違うのはレンタカーに日本語のナビが付いていたので凄くラクだったこと。
かなり治安が良くなっているようで、危険な匂いをほとんど感じなかったこと。
MOTELの料金を含め、物価が高くなっているように感じたこと。
などが、全般的な印象である。
詳しくは、後日、ファミドラの「旅レポ」番外編にでも投稿する予定。
- 2008.09.04 ハイウェイホテルの存在意義とSAPAの役割
-
(社)日本道路協会の機関誌「道路」2008年8月号に掲載された拙文を以下に転載する。
---------------------------------------------------------------------------------
ハイウェイホテルの存在意義とSAPAの役割 株式会社 旅籠屋 代表取締役 甲斐 真
「壇之浦PA」と「佐野SA」に、相次いでハイウェイホテルが誕生した。
当社は、欧米に無数に存在するMOTELのような、マイカー旅行者が誰でも気軽に利用できるロードサイドホテルを我が国にも誕生させるため、「ファミリーロッジ旅籠屋」をチェーン展開してきたが、「壇之浦PA店」と「佐野SA店」についても、提案段階からプロジェクトに参加し、両ホテルの経営と運営を担っている。
SAPAに宿泊施設を設ける意味や条件、現状と課題、そして今後のSAPAのあり方について、率直な意見を申し上げたいと思う。

「壇之浦PA店」(右奥)
●はじめに
関門自動車道「壇之浦PA」(4月下旬)と東北自動車道「佐野SA」(7月下旬)に、西日本高速道路・東日本高速道路にとってそれぞれ初となる宿泊施設がオープンした。これらのプロジェクトに参加し、両ホテルの経営と運営を担うことになったことは、当社にとって限りない喜びである。企業としての損得で申し上げているのではない。7年前、道路公団の時代からSAPA内への宿泊施設の設置の必要性を強く訴えてきたが、その第一歩が踏み出されたこと、そのことが何よりも嬉しい。
率直に申し上げて、現時点で当社にとって利益が見込める確信などまったくない。20年という契約期間を通してずっと赤字を背負う事業になるかもしれない。しかし、我が国に欠落していた基盤施設が誕生することによってマイカー本来の利便性が発揮され、合理的な旅行スタイルが可能になり、モータリーゼイションの発展と成熟に近づくことができる。日本人のレジャースタイルや生活スタイルに新しい選択肢と自由を提供することができる。そのことに価値がある。これこそ、当社の創業目的であり、変わらぬ理念であり、存在意義だからだ。
●MOTELをお手本に生まれた「ファミリーロッジ旅籠屋」
アメリカを車で旅すると、行く先々の街や村で、MOTELという看板を掲げたミニホテルを数多く目にする。モーテルというと、日本ではカップル専用のラブホテルを連想する向きが多いが、本来は、車で旅する人が誰でも気楽に利用できる、素泊まりのロードサイドホテルのこと。ほとんど何のサービスもないかわりに、とても自由で、驚くほど安く泊まれる。高級ホテルと異なり、ゴージャスでリッチな気分を満喫するというわけにはいかないが、子供連れの家族旅行や友人とのドライブ、そしてビジネスでの宿泊には必要十分な施設であり、実際、アメリカでは、店舗数が1000を超えるチェーンがいくつもあるなど、その数はガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどより多く、車社会になくてはならないインフラ施設として人々の生活を支えている。この事実を知っている人は意外に少ないようだ。
当社の「ファミリーロッジ旅籠屋」の構想は、こうした自由で経済的な宿泊施設を日本にも実現させることを目的にスタートした。2度のアメリカ視察を経て、1995年8月、待望の1号店が誕生。以来13年、日本では先例のない業態であり、さまざまな困難にも直面したが、予想を越える多くのご利用と「こんな宿泊施設を待ち望んでいた」との声を励みに、北は秋田・岩手から、西は山口まで26の直営店舗を展開するに至っている。
●SAPAに宿泊施設を設置することの意味と条件
すでに7000kmを超える高速道路が整備され、広域のネットワークとして機能している。必然的に長距離のドライブが増えており、運転者が安全かつ快適に長時間の運転を行うためには、物販・飲食に加え、十分な休憩をとれる施設が必要不可欠である。これがSAPAに宿泊施設が存在すべき基本的な理由である。楽しさ、新しさ、といった言葉が冠せられ、SAPAを活用する収益事業という表現も見受けられるが、それは本質的なことではない。宿泊施設はトイレやガソリンスタンドと同じように、本来「なくてはならない」施設なのであり、すべてのSAに存在して不思議ではない施設なのである。
さて、こうした宿泊施設に求められる条件とは何か。基本は3つあると考える。
第1は、誰もが泊まれるという汎用性。家族や友人グループなど数人での宿泊にも、ひとりでの宿泊にも対応できる施設であることが求められる。ビジネスマン向けのシングルルーム中心のホテルでは利用者の多様性に応えられない。「ファミリーロッジ旅籠屋」の場合、客室はバストイレを含め約25㎡の広さがあり、幅1.5mを超えるクイーンサイズのベッドを2台設置しているため、季節や曜日によって利用者の構成が変化してもすべての客室を利用いただくことができる。もちろん、将来、客室構成の異なる複数の宿泊施設が並存することになり、全体として対応可能であれば条件を満たすことになる。
第2は、宿泊特化。SAの多くに24時間営業の飲食・物販施設がある。宿泊施設自体がこうしたサービスや機能を持つ必要はどこにもない。限られたスペースを浪費する無駄な設備投資は行うべきではない。ただし、24時間営業の施設を持たないSAPAの場合この限りではない。
第3は、安価な料金設定。誰もが気軽に利用できるためには宿泊料は低廉でなければならない。「壇之浦PA店」「佐野SA店」の場合、他の「ファミリーロッジ旅籠屋」と同様、レギュラーシーズンなら家族4人で1室10,500円、2人なら1室8,400円、ひとりなら5,250円としている。十分にリーズナブルな料金と考えるが、いかがだろうか。SAPA内に広大なスペースがあって多様な宿泊施設が立ち並ぶような場合も、少なくともひとつはこうした料金の施設が必要だと考える。
●「壇之浦PA店」「佐野SA店」の現状
4月23日にオープンした「壇之浦PA店」(14室)の6月末までの客室稼働率はちょうど55%である。まずまずの滑り出しというところだが、これから夏休みに入り、初年度60%という当初目標をクリアーできればと期待している。ちなみに、利用者の構成は1/3が子供連れのご家族、ビジネス利用も少しずつ増えて2割近くになっている。ここは、PA側だけでなく、一般道路側からもアクセスできるが、ほぼ半数ずつという状況である。
「佐野SA店」(14室)は7月24日オープンのため、現時点ではまだ実績値が存在しないが、予約開始が遅れたこともあって夏休みの予約が低調である。ここは一般道路側からのアクセスができないが、どのように利用されるのか、どのような旅行目的の方が宿泊されるのか、ひじょうに興味深い。
今まで、多くのドライバーにとって高速道路は一刻もはやく目的地に到着するために通過する線であり、滞在する対象ではなかった。現時点で両ホテルの認知度はまだまだ低いが、たとえ知られてもどのように活用してよいのかイメージが湧かないという状況ではないだろうか。他の「ファミリーロッジ旅籠屋」と同様、口コミで少しずつ利用者が増え、SAPA内のホテルならではの利用がなされ、存分に活用されることを願っている。
●SAPAにおける宿泊施設具体化の課題
ご承知のとおり、アメリカの場合、高速道路の大部分はフリーウェイ、つまり無料である。本線脇のレストエリアにはトイレしかない場合が多い。出入り口が頻繁にあり、そのつど周辺の飲食施設や宿泊施設の案内看板があってドライバーを誘導してくれる。出入り自由だから、高速道路自体がこうした利便施設を設ける必要性がないのだ。しかし、日本の高速道路は基本的に閉じた空間であり、寄り道をすると通行料が割高になることもあって、SAPAに多くの機能が求められることになる。
ここで重要なことは、日本の高速道路の在り様はこうした与条件のもので整備されたに過ぎず、何もかも「公的機関」が計画的にすべてを用意する必要はないということである。既存の状況を唯一の当たり前のものと考えるべきではない。既成概念や先例主義にとらわれず、本質的かつ長期的な視点で大胆に発想し議論する必要がある。
「壇之浦PA店」「佐野SA店」の具体化には、他の「ファミリーロッジ旅籠屋」の場合と異なるさまざまな手続きが求められ、当初の計画をはるかに越える長い月日を要した。初めての試みであるため、止むを得ない面もあるが、これらの経験に学び手続きの簡素化や基本的な取り組み姿勢を変えていかなければ、高速道路全体の利便性を飛躍的に高め、車社会を発展成熟させる芽を摘んでしまうことになる。
語弊を怖れず、解決すべき課題を3点挙げたいと思う。
第1は、SAPA内に施設を設ける際に求められる連結許可手続きの問題である。まず、審査会が半年に1度しか開催されず、プロジェクトの進行が滞ることがあった。今後は、持ち回りで随時審査されるようになると聞いているが、これは大きな改善だと思う。ちなみに、道路公団が分割民営化された目的のひとつは、各高速道路会社が創意工夫を行い、コスト意識を高めながら、自主的に事業の改善と発展を推進していくことにあったと理解している。とすれば、年度ごとの予算主義や随意契約への規制は、ダイナミックな事業運営の足かせとなる。もし、そういう発想や規制が残っているとすれば、厳しいけれど自由な「民間企業」に脱皮されることを願ってやまない。さまざまな事情や深慮遠謀があるにせよ、お役所的な「先回りした指導やルール」は過保護や過剰規制となって企業の健全な発展を阻害する虞がある。保有機構や国土交通省の後ろからのサポートに期待する次第である。
第2は、高速道路会社自体に残るお役所的な雰囲気である。あくまで印象に過ぎないが、本社から現場への指示命令系統がスムースでなく、あわせて監督官庁や自治体などお役所の顔色をうかがう臆病な体質が感じられる。目先の決済や許認可を通すことが目的になり、本質的な議論や検討を避けて波風を立てないことに腐心しているように見える。これは大企業全般に共通する体質だが、もっと誇りと自信を持ってチャレンジしていただきたい。とかくマスコミは問題点ばかりを批判するが、アメリカに比べ日本の高速道路がいかに快適に整備されているかを主張してよいと思う。かつてのオイルショックの時と同様、地球温暖化防止が叫ばれる中で再びマイカー使用が批判される風潮が出始めているが、誰もが、いつでも広範囲に移動できるという「自由」の価値は限りなく尊く重い。モータリーゼイションという概念の基本的価値の根本には経済的合理性よりも前にこうした価値があるのであり、高速道路の運営者は普遍的な「文明」や「文化」を支え守っているという自負と責任を持っていただきたいと思う。
また、「佐野SA店」においては具体化に数年以上の年月を要したことから新規のプロジェクトでありながら、途中で担当者の異動が何度もあったことは残念なことだった。機械的な定期人事によるものであったとするなら、立ち入った意見ではあるが一定の配慮があって然るべきではなかったかと思う。
第3は、高速道路に限った問題ではないが、市街化調整区域における宿泊施設の建築制限の問題である。都市計画法によれば、無秩序な開発を防ぎ、生活インフラの整備を総体的に保証していくため、あえて市街化を抑制する地域を定め、原則として建物などの建築を厳しく制限している。ただし、車で通過する人たちに最低限の利便性を提供する「沿道サービス施設」を例外と定め、ガソリンスタンド・小規模な飲食・物販施設の建築を認めている。問題は、その中に宿泊施設が含まれていないことである。「佐野SA」は、従来道路関連施設として都市計画の対象外であったが、民有地になったことによって地域地区の指定を受けることになり、周辺にならい市街化調整区域と指定されてしまった。閉じたエリアであるSAを周辺の指定に合わせるという判断も理解しにくいことだが、そもそも車社会のインフラ施設であるべきロードサイドホテルが「沿道サービス施設」に含めれないことが不合理である。そのため、14室のミニホテルを建築するにあたって、SA全体の開発行為申請を行い、多くの手間と時間を要することになった。
これまで日本において欧米のようなMOTELが普及しなかった原因のひとつにはこうした法的規制がある。法律は現状の後追いになるのは止むを得ないことだが、今後、ロードサイドホテルの普及にともない適切な改正がなされるよう働きかけを行っていかなければならないと考えている。一企業の利益誘導になる、というような批判を受けることが容易に想像できるが、求めているのはそのような矮小な次元のことではない。

「佐野SA店」
●SAPAの将来について
ここ数年、スマートインターやウェルカムゲートなど、外部に開かれたSAPAを推進する動きが具体化している。前者については、インターの距離が離れているために、道路周辺の人々に十分活用されていない現状を比較的低コストで解決する妙案として歓迎されている。後者については、SAPA内の商業施設が周辺住民に利用可能になることによる利便性と収益性の両面の貢献が評価されている。
もちろん、こうしたメリットはその通りなのだが、本質的な議論が深められていない気がする。例えば、大都市圏内のSAに大型のショッピングモールを建設して周辺からの買い物客を集めたり、自動車のショールームを設けるなどのアイデアには疑問を感じる。高速道路外で足りているサービス施設をわざわざ限られたSA内のスペースに設置して利用者を呼び込む社会的必要性がどこにあるのだろうか。オープン化の目的のひとつがSAPAへの集客のためにあるとすれば、高速道路の存在意義を逸脱しているように感じる。
私見だが、SAPAのオープン化は、内から外に対しては地域のハブとして機能することによって地域の活性化に寄与すること、外から内に対してはSAPAを利便施設として周辺に開放して地域に貢献することが基本的な目的になるべきではないかと考える。
前者については、周辺の自治体や観光協会の案内窓口を設けて地域のPRや情報提供を行い、高速道路を下りて周辺の観光・飲食・物販施設へ誘導するような機能を強化すること。
後者については、公共性のある施設の少ない地方の郊外で有効だと思うが、商業施設だけでなく、高速道路の広域性を生かして病院や診療所を設けるのも意義のあることだと思う。ガソリンスタンドの再編が進んで数が減少する中、SA内のスタンドを外部から使えるようにするのも一案である。
こうした観点に立てば、SAPAに入って高速道路を走行せず再び出て行くという利用は例外ではなく積極的に認め促進していくべきである。現在、こうした利用についての可否や料金についての方針が明確に定められていないようだが、利用料金は無料もしくは最低限の金額としていただきたい。
●おわりに
当社は、創業から十数年のベンチャー企業である。いろいろと批判的なことも申し上げたが、当社をビジネスパートナーに選び、先例のないプロジェクトを推進された西日本高速道路・東日本高速道路の決断には心より敬意を表したい。
ようやくふたつのホテルがオープンしたが、利用する人々に喜ばれ、地域に貢献する施設としていけるかどうか。良き先例となって全国に広まっていくかどうか。それは、間違いなく、ホテルの経営と運営を担う当社の責任である。新しい旅のニーズに応え、高速道路の新しい活用に道を開く施設として、全力を尽くす所存である。末永いご愛顧ならびにご指導・ご鞭撻を賜りたい。
- 2008.08.23 ナイトマラソン
-
以前にも書いたけれど、3年前から本社内で始めた体重・体脂肪測定とジム通い、そしてランニング大会への参加、なんと今も続いている。
ただ、さすがに今年は忙しく、3月の荒川市民マラソンから時間が空いてしまったが、昨夜、久しぶりにみんなで参加した。
第2回 葛西臨海公園ナイトマラソン、10kmのランニング大会だ。
こうした大会にエントリーすると、それが目標になって、継続的に走るようになる。
今回も、忙しさに追われてしばらく途絶えていたジム通いを5月から再開していた。
本社の新スタッフも半ば無理やり誘って、合計6名。
この日のために作った「TEAM旅籠屋」のオリジナルTシャツを着て夕暮れの葛西臨海公園へ。

葛西臨海公園は、東京ディズニーリゾートの近く、東京湾に面した広い公園で、今回はその中の5kmコースを2周する。

午後7時半スタートの夜間マラソンとはいえ、まだ8月。最大の問題は気温の高さ。去年は熱中症で救急車で運ばれた人が2人いたらしい。
ところが、当日を迎えたら、先週までとは一転して、突然秋になったような涼しさ。日が暮れる頃には気温は20度ちょっとくらい。
海沿いだから気持ちの良い風も吹いて願ってもないコンディション。
私個人は、先週の土曜日に10数年ぶりにギックリ腰になり、ギリギリまで参加断念止むなしという状況だったが、前日くらいからなんとかまっすぐ腰を伸ばして歩けるようになり、とりあえずスタートラインにつくことに。
初めてのランニング大会となる新メンバーもしきりと不安を口にしていたが、とうとう定刻になりヨーイドン。
・・・タッタッタッ、ドタドタドタ、ゼーゼーゼー・・・
人によってペースも表情も違うけれど、結果全員無事完走(完歩)!
私も、走っている分には腰の痛みも気にならず、5月からの努力が実って、自己ベストを更新。
長い間の目標であった1時間をギリギリ切って59分55秒でゴール。
やったー!
オリンピック選手の半分にも届かないスローペースだけれど、タイムなんて問題じゃない。
自分の脚だけで、頑張って走りきれた満足感が、最高の金メダル。
旅籠屋の場合、私が下戸ということもあって、飲みニケーションの機会はほとんどない。
取引先との接待付き合いもまずないし、ゴルフやマージャンもゼロ。 要するに、仕事ばっかり。
だから、ジム通いやこうしたランニング大会参加がオフィスを離れた唯一の集まりということになる。
といっても、別に「親睦を深める」という意識はない。体に良いことをして自主的に楽しもう、ただそれだけのこと。
でも、私が「行こう、行こう」というから、気の進まない人にはちょっと苦痛なことかもしれない。
もちろん、強制なんかしないし、しちゃいけないことだけど、できたら、全員がマイペースでずっと続けていければ良いな、と思っている。
「ファミリーロッジ旅籠屋」は、マイペースで自分なりの旅や時間を楽しむ宿。
忙しく観光施設を回り、お金で楽しさを買うような旅は推奨していない。
決してこじつけるわけじゃないけれど、 だから、それぞれの店舗の周辺を歩いたりジョギングして楽しめる「散策マップ」を作りたいと昔から考えている。
何ヶ月か時間がもらえたら、私が全店をまわってそれぞれの支配人と手作りしたいのだけれど、いつになったら実現するのやら。
目の前を見ると、「株主総会の召集通知」の作成締め切りが数日以内に迫っている。やれやれ。
- 2008.08.08 眠れないときもある
-
北京オリンピックが始まった。
楽しみにしていたサッカー、男女とも初戦でつまずき、気分が悪い。
気力を吸い取られてしまったようで、11時には床についた。
ところが、3時過ぎに目が覚めてしまい、そうなるとアレコレのことが頭に浮かんできて眠れなくなる。
しばらく、ネットをうろついているうちに外は明るくなり、思い切って起き出すことにした。
最近、こういう日が増えている。
気分を軽くしようと朝風呂に入り、食器を洗い、汚れが気になっていた便器やテーブルを拭き、朝刊を読み、6時にはオフィスに出てきた。
3月から7月にかけてオープンが7つも続き、何ヶ月も文字通り目の回るような忙しさだった。
それが終わるとひと段落、と思っていたが、決算に向けた監査や年度替りに伴う書類更新に追われている。
きのうも、毎月の稼働率のグラフを作成してサイトにアップしたが、単純作業を26回繰り返すことになる。
店舗が増えることはもちろん本望なのだが、単純にその数だけ心配事も増える。
停電した、パソコンが動かない、予約でお客様と行き違いが生じた・・・まわりの席からそんな電話のやりとりが毎日のように聞こえてくる。
本社はほんとうに忙しい。
人数のやりくりがつかないと専務をはじめ店舗管理スタッフが店舗の代行勤務に出かけるし、忙しい店には掃除のヘルプにも出向く。
店舗開発のスタッフは、出店候補地を探したり、役所への事前相談や周辺説明に遠方を強行軍で走り回る。
全員がそろう日はほとんどない。
店舗からは毎週、毎月報告書が送られてくる。電話はひっきりなし。
建物の不具合や、用品備品の補充依頼。運営上の質問や相談。
支配人のストレス軽減を最優先に取り組もうと、少しでもはやく対応することにしているが、どれも簡単なことではない。
毎日数十通も届くアンケートハガキの処理や問い合わせへの対応、これも待ったなしだ。
仕事を追いかけるようにしよう、と言ってはみるものの、日々の雑務は増えるいっぽうで、日常業務を追い越すのは容易なことではない。
毎晩、終電間際まで残っているスタッフに「無理するなよ、つぶれないようにね」と声をかけた事も一度や二度ではない。
今年に入って、本社も派遣を含めて3名のスタッフが増えたが、それでもゆとりが生まれたという実感はない。
みんな一生懸命だ。
みんな誠実に仕事に取り組んでいる。
そうしたスタッフに恵まれていることを、つくづく幸運だと思う。ありがたいことだと思う。
猛暑が続いている。
毎日のように、どこかで突然の雷や豪雨が発生している。
地震もある。
昼食もそこそこに汗まみれになって走り回っている支配人たちの姿が思い浮かぶ。
こうした社員たちに報いたい、気持ちの張りを持ち続けてもらえるようにしたい・・・。
そのことが頭から離れない。
きれい事を言っていると思われるかもしれないが、旅籠屋に関わった人が、みんなそれなりにハッピーになれること、
そうでなくては、会社が存在する意味がない、と心底思っている。
十年ほど前、あるホテルコンサルタントを訪ねた時に言われた言葉が頭をよぎる。
「そんな薄利のホテルを直営でやるなんてばかげている。ややこしいことが増えるばっかりで3店舗が限界だよ。俺なんか、土地活用のアイデアを提案するだけだ。リスクはないし、儲かるだけだ」
数年後、彼は耐震偽装事件の関係者としてマスコミに登場していたが、結局、そこでも責任は問われなかった。
根本的な考え方が違う、冗談じゃないと腹を立てた十年前の怒りを反芻する。
しかし、あまりに忙しいとイライラする。
ついつい言葉がきつくなる。
取引先にも失礼な態度をとることがある。
生来のわがままがコントロールできなくなる。
申し訳ないことをしてしまったなぁ。
これじゃイカンなぁ。
どこかで不信感を持たれているかなぁ。
大きなトラブルになる兆候を見落としてないかなぁ。
アレコレのことが頭に浮かんできて眠れなくなる。
- 2008.05.07 禁煙室について考えていること
-
厚生労働省の調査によると、習慣的な喫煙者は20歳以上の男性で40%を切り、20歳以上の男女全体で25%を下回ったそうだ。ちなみに、外国と比較するとヨーロッパやアメリカは男女の差が比較的小さいが、15歳以上の男性の喫煙率は15〜30%以下のようだ。アメリカが男女とも20%以下というのは、想像していたよりずっと低い。室内禁煙の所が多いせいか、建物の出入り口にたむろして吸っている人を頻繁に見かけるので、どうもリッチな白人とそれ以外では様子が大きく異なるような印象を持っている。日本よりずっとポイ捨てする喫煙者が多いし、喫煙者=レベルの低い人間、というイメージがあったりするのかもしれない。
ところで、私は、40年来の喫煙者。数年前から、本社オフィスの机では吸わないルールにしたので本数は半減したけど、1日20本くらい。
それにしても、昨今、愛煙家はますます肩身が狭い。
全席禁煙のレストランにはまず行けない。だからスターバックスも敬遠している。あそこではくつろげない。
何より、海外に行くときの長時間の飛行機は苦痛で、カナダで泊まった全室禁煙のホテルでは氷点下のベランダで震えながら吸ったものだ。シンガポールでは、喫煙者もそこそこ見かけたが、屋外でも吸えるところは限られているので、気ままな散歩の途中「ちょっと一服」という楽しみが味わいにくい。
加えて最近困るのは、社外での打ち合わせや会議。
少し早めに着くようにして、外で一服してから訪ねるのだが、1時間を超えるとつらくなってくる。長くなる時は「喫煙室はありませんか」と聞いて、「ちょっと小休止しましょう」と言うこともある。
どれも20年くらい前には考えられなかったことだ。机にも会議室のテーブルにも灰皿があって、吸い放題だった。映画館で「煙が邪魔でスクリーン見えにくいよ」と腹を立てたことさえあった。
ちなみに、ずっと以前に禁煙した父は「人にとやかく言うことじゃない」と何も言わないけれど、息子たちは、一緒にいて吸うと煙たがるし、訪ねていくと換気扇の下やベランダに行かされる。
もちろん、タバコは肺がんになる危険性を高めるし、体によいことは何もない。それに、まわりの人たちにも受動喫煙によって悪い影響を与えるから、自分勝手な振る舞い、ということになる。
喫煙を自己弁護できる理屈はどこにもないし、吸わない人に「体に良くないよ、迷惑だよ」と言われると返す言葉がない。そこが、つらさを倍増させる。
と、ここまで来れば、 もう禁煙しないのが不思議なくらいだが、今のところ、私にその気はまったくない。
中毒なのだから、吸わないことで大きくなるストレスを引き受けるのがイヤだからだ。
「人間、不健康になる自由もあるでしょ」とうそぶいている。
いえ、これは冗談ではなく、信念みたいなものでもある。ここが、重要。
前置きはこれくらいにして、ここからが本題。「旅籠屋」におけるタバコの話し。
最近、「禁煙室希望」「禁煙室をもっと増やして」と言われることが少なくない。「健康増進法を遵守しているのか?」というメールをいただいたこともある。
その時に返した回答は以下の通り。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
・・・「●●店」では、2室およびラウンジを禁煙室とする予定でございます。自販機コーナーやコインランドリーは外廊下に面した半屋外のため、とくに制限を設けませんが、外部に数箇所灰皿を設け、喫煙をこれらの場所に誘導する予定にしております。
ラウンジの禁煙措置や喫煙場所への誘導などはすべての店舗で数年前より実施しており、禁煙室につきましてもすでに数店舗で試験的に行っておりますが、近々、全店に禁煙室を設定する予定にしております。
弊社では、「シンプルで自由な旅をサポートする」ことを設立以来のポリシーとしており、出来る限り制約を設けず、多様な方々に自由にご利用いただくことを目指してまいりました。「受動喫煙」による健康への悪影響はまた別の次元の問題だというご意見があることも承知しておりますが、結果として、喫煙者に「不自由を強いる」面があることも否定できず、禁煙室の設定ではなく換気の徹底などで対応する方針を採ってまいりました。また、こうしたことは「努力事項」とはいえ、本来法律で縛るべきことではないという考えもございます。しかしながら、どうしても、室内に匂いの残る場合があり、非喫煙者の割合も過半を超えてお客様から要望の多いこともあり、「健康増進法」や「世論」や「他の宿泊施設の状況」とは関係なく導入に踏み切った次第でございます。
以上、不十分な対応とのご批判を甘受しつつ、禁煙室の増室につきましては状況を見ながら進めていく所存でございます・・・・
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
宿泊施設の場合、音や匂いは「泊まり心地」に大きな影響を与える。
以前、アメリカのMOTELを泊まり歩いたとき、葉巻や香水や汗臭い匂いが気になったことが何回もあるが、たしかに気分は良くない。だから、タバコを吸わない人が、その残り香に神経質になるのも、よくわかる。
「旅籠屋」の場合、「沼田店」を除いて、ほぼ全室2方向に窓があるから、換気には都合が良い。朝、お客様がチェックアウトしたら先ず行うのは、窓を開けて外気を通すこと。
それでも、匂いが残ることもある。
タバコばかりが問題視されるけれど、じつはキムチの匂いはもっと深刻。強い香水の匂いが充満して困ることもある。
支配人はけっして、こうしたことに無頓着でも放置しているのでもない。換気はもちろん、ベッドカバーを天日干ししたり、使っていないシーツを含め、すべてのリネンを洗濯に出したり、消臭剤や脱臭機を使って手間をかけて努めていることも理解して欲しい。もちろん、満室にならない限り、こうした部屋を使うことはない。
しかし、しかしである。
語弊を恐れず言わせていただくが、一部の人たちからの「ヒステリックな非難」には、寛容さを求めたい。
不特定多数の人が宿泊するのだから、「前の晩、どんな人が、どのように泊まったかわからない」 のが当然なのだ。
あまり神経質になられても、自分の都合ばかりを言われても、対応には限界があることを理解して欲しいのだ。
子供や幼児は、騒いだり夜鳴きしたりする可能性があるけれど、制約なくお泊りいただいている。
いつも家族同様に暮らしているペットも、一定のルールやマナーという条件をつけて、自然に受け入れてきた。
車椅子の方、養護施設の子供たち、基本的にどんな人でも受け入れる。
社内のマニュアルにはこう書いている。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
・・・さまざまなお客様がいらっしゃいます。外見などの印象が悪くても、汚さず、騒がず、気持ちよくお泊りいただける方もあれば、その逆の場合もあります。同じ方でも、ご家族での利用の時は問題なかったのに、会社の同僚との宿泊の時は傍若無人だったということもあります。予断・偏見・先入観でお客様を「判定」し、失礼な対応をとらないようにしてください。
年齢の離れたカップル、不自然な家族、滞在目的の不明なひとり客、どうみても高校生以下にしか見えないカップルなど、不可解に思えるお客様もいらっしゃいますが、それはこちらの予断であり、プライバシーに属することですから、我々が関知すべきことではありません。実際に周囲に迷惑をかける可能性を確信できない限り、等しく通常のお客様です。
お役所的な発想では「疑わしきは事前に排除する」となりますが、それはトラブル発生の予防や対応の責任を放棄していることで、その結果、利用者の多様性や自由を損ねてしまうことになります。「旅籠屋」は「自由な旅をサポートする」宿です。そうした「自由」を守るために、お客様が引き起こすかもしれないトラブルを予防したり解決したりすることに要する手間とリスクを引き受けているのだという意識を持っていてください。おおげさに聞こえるかもしれませんが、私がアメリカのモーテルで感じた「日本に欠けているもの」のひとつはそうした「自由と責任」の意識です。我々も組織や肩書きを離れた時、軽んじられたり、詮索されたりして不愉快で情けない思いをさせられることがあります。社会的にマイノリティの立場にある人を、いわれなく差別したり区別したりすべきではありません。逆の立場になって、失礼な態度をとってしまうことのないよう気をつけてください。「旅籠屋」が大切にすべき精神は、こうした点にあります。
なお、泥酔状態などで正気を失っている方、著しく不潔で異臭を放っているような方など、明らかに施設を汚損したり、他のお客様に迷惑をかけることが確実である場合は、断固として宿泊を拒否することができますが、これは例外中の例外と考えてください・・・
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ペットも泊まれるなんて、非常識。ペットアレルギーの人もいるかもしれないのに。
なんで多数の非喫煙者がそんなに追いやられなければならないのか理解できない。
私がアメリカを泊まり歩いた時、部屋の匂いが気になったり、店の人の態度に腹が立ったりした時に思ったのは、良くも悪くもこれがMOTELだということ。外国だし、自分の都合を言っても始まらない。いやなら高いHOTELに泊まれば良いのであり(とはいえ、高いからサービスや気配りが行き届いているなんて保証はどこにもないのが普通)、自分自身で総合的に判断して選択していけばよいのだ、ということだった。そして、私には、それでも気楽なMOTELが性に合った。自己責任による判断、それは日本国内でもある程度は言えることではないかと思う。
自己弁護のために言っているのではない。「旅籠屋」がアメリカの安MOTELのようで良いとは思わない。
ただ、「旅籠屋」は万人のためのものだが、万人受けするつもりは初めから無い。
「自由であり、多様性を受け入れる」ということは、そういうことだと思っている。
・・・とはいえ、「禁煙室」は、遠からず全店に設置し、少しずつ部屋数を増やしていくことになると思います。
- 2008.05.06 (前日の)蛇足
-
それにしても、なぜスーバーアグリのチームをサポートする日本企業は現れないのだろう。
ようやく部品メーカーによるサポートが決まり、その経営者は実際の計算はともかく、「個人オーナーのチームが存続すべきだ」とコメントしたそうだ。
これがドイツの企業であることが情けないくて悔しい。
私に経済的余裕があったら、100万円でも寄付するし、「旅籠屋」に余裕資金があったら、株主や社員に批判されてもスポンサーになるのに。
最近、若者の「車離れ」の傾向が顕著らしい。
携帯電話代の負担増。楽しいことの多様化。バーチャル体験による満足。
原因はいろいろ言われているけど、いずれにしても、マイカーやマイバイクが「個人の自由」としての実質的、あるいは象徴的な意味を失いつつあるのかもしれない。
だとすると、マイカー旅行も無条件に価値あるもの、みんなが求めているもの、と言えなくなりつつあるのか。
そうだとすると、思い浮かんでくるのは、「マトリックス」などの映画に登場する、リアルとバーチャルが渾然とした「めまい」がするような気味の悪い感覚、そしてバーチャルな世界を現実と思わせてマインドコントロールするような、あのそら恐ろしい世界だ。
- 2008.05.05 ガソリン税問題と車文化
-
ガソリンの値段がまた上がった。
そもそも30年以上も続いている「暫定」税率の現時点での必要性、無駄な道路づくりにつながらないための一般財源化の是非、などいろいろな主張があるようだ。とりあえず、何がベターなのか、よくわからない。
しかし、議論の中で聞こえてくる「地球温暖化防止のために、課税は継続強化すべきだ」という主張に、強い違和感を覚える。
「ガソリンなどの化石燃料を使うと、二酸化炭素の排出量が増える」
↓
「二酸化炭素の排出量が増えると、地球温暖化が進む」
↓
「だから、ガソリン税の維持強化による消費抑制には、合理性と正当性がある」という三段論法である。
こんな主張に、抵抗なくうなずいてしまう人が少なくないことにあきれてしまう。
こんな「もっともらしい正論」に飛びつくコメンテーターの幼稚さと思考停止に、「またか」と思う。
1970年代のオイルショックの頃にも、似たような議論があった。
当時は、狂乱物価と深刻な構造不況による高度成長の終焉という劇的な変化があり、経済的な面での緊急性があったが、
同時に、「省エネ」と「大気汚染防止」というスローガンが声高に叫ばれ、マイカーが「悪者扱い」にされた。
テレビの深夜放送中止、ネオンサインの消灯、そして自動車レースの自粛である。
大気汚染や無秩序な開発による環境破壊を正当化するつもりなど、もちろんない。
日本を含む先進国に住む我々の「快適な生活」が、有限な化石燃料や天然資源に支えられ、これが「公平かつ適正に」使われていないことへの問題意識も、当然ある。
人為的な要因によって、「急激に」地球温暖化が進行していることへの危機感も共有している。
かつて私は、「循環型社会」を日本で初めて提唱したコンサル会社に勤め、有害廃棄物の適正処理や、可燃ゴミ廃棄物の資源化プロジェクトに取り組んでいたのだから、無関心であるわけがない。
そもそも、一面的な「正論」の尻馬に乗り、勧善懲悪というか、誰かを悪者にして済む問題ではない。
だが、ここで論じたいのはそんなことではない。 感じている違和感は、少し次元の異なることだ。
先日、メディアの人に、こんな質問をされた。
「石油価格が高騰しています。地球温暖化防止の問題もあります。長い目で見て、マイカー使用を前提としたロードサイドビジネスの将来性や社会性について、どう思いますか?」
事業の収益性とか、店舗の拡大計画とか、株式公開の見通しとか、そんな取材が多いなかで、これは良い質問である。
当然なされるべき質問である。
その時、私が感じ、考え、答えたのは以下のようなことである。
一般の個人がマイカーを持ち、利用できるようになったのは、ここ2〜30年のことです。
その最大の意味は、誰もがいつでも行きたいところに行ける「個人の自由」を獲得したということです。
これは、有史以来数千年をかけてようやく人類が手にした「自由」です。
おそらくは、車の絶大な利便性や経済的な波及効果が、やむなく、図らずも為政者に認めさせた「個人の自由」です。
その価値は、環境問題や目先の経済的合理性を相手に秤にかけられ、二者択一を迫られるようなことではありません。
次元の異なることであり、手放してはならない貴重なことであり、はるかに本質的で重たいことです。
オイルショックの時、いくつかのルール変更や配慮はあったものの、ヨーロッパではF1レースは当然のように続けられました。
ライトアップが全面的に消されたという話しも聞きませんでした。
かつて、第二次大戦の中でも続けれらたクラシックコンサートを尊ぶ映画が作られ、共感を得ています。
そこには、人間の尊厳や人類の文化というものに対する長い歴史に培われた揺るぎない価値観というものがあります。
これから先、車に限っても、代替燃料の開発、電気自動車や燃料電池自動車の開発など、資源の節約、省エネルギーなど環境負荷を低くする動きは当然進められるでしょうし、進められなければなりません。
しかし、かつての日本のように、「車の使用は、軍用や商用を優先とし、レジャーのためのマイカー利用は自粛すべし」などという、「正論」や「世論」や「指導」に安易に乗っかるべきではありません。
短絡的な「二者択一」の罠にはまる必要はありません。
車社会、モータリーゼイションという言葉が語られるとき、日本では産業の発展とか、利便性とか、そういう面ばかりが語られる。
もっと本質的なことに気づくべきじゃないか、ヒステリックな目先の批判に動じることなく、本質的な価値を掲げるべきではないか。
「シンプルで自由な、旅と暮らしをサポートする」というのは、そういうことなのだと、私は言いたいわけなのです。
- 2008.04.27 オープンセレモニー
-
意外に思われるかもしれないが、新店舗のオープン日には、誰も行かないし、何もしない。
本社スタッフ総出のてんやわんやのオープン準備は半月ほど前に終わっている。
13年前、1号店開業の時は、なんとなく「常識」にとらわれて現地で簡単なパーティを催したが、その後は支配人だけが、静かに普段どおりお客様をお迎えする、それだけだ。
宿泊業は、息の長い、地道なビジネスである。一過性のお祭り騒ぎは必要ないし、そもそも旅籠屋には似つかわしくない。
しかし、例外もある。2年前にオープンした「東京新木場店」、そして今回オープンした「壇之浦PA店」である。
「東京新木場店」は、念願の東京湾岸エリアへの出店だったし、リサ・パートナーズとの業務提携による1号店。
少しでも知名度を上げたかったし、 広くメディアの方を招待して記者発表を行った。
そして、「壇之浦PA店」。
これは、西日本高速道路初の宿泊施設であり、テープカット、記念植樹を含め、驚くほど盛大なセレモニーが開かれ、会長自ら参加された。下関市長をはじめ、警察・消防・商工会議所の皆さんも参列された。



正直言って、こうした「形」に違和感を感じないわけでもなかったが、これは大きな期待をこめて先例のない決断に踏み切った勇気と熱意の証であり、誠にありがたいことであり、主催者の一員として挨拶することが少し誇らしかった。
実際、テレビ・新聞・ラジオと多くのメディアの方々が集まり、ニュースとしてたくさん取り上げていただいた。
当社だけでは、とてもできることではないし、一日もはやく、多くの人たちに存在が知られ、旅行者に活用されるようになることを心底願っている。
あとは、期待以上の満足を提供し、高速道路を利用するドライブ旅行に新しい可能性を切り開いていく、それが我々の責任であり、夢である。
セレモニーの有無を問わず、建物が完成して、オープンを迎える時にいつも思うことがある。
それは、必ずしもスポットライトを浴びない人たちのことである。
組織の中で、物事をスムースに実現していくためにある種のリスクをとりながら準備を進めた担当者。
限られた予算と工期の中で、大きなストレスを感じながら多くの業者をコントロールした現場監督。
雪の日の寒さの中で、真夏の暑さの中で、ほこりまみれになって自らの手で建物を作りあげていった職人の人たち。
そして、もちろん、慣れない地に赴任して、すべての責任を負いながらお客様を迎える支配人夫婦。
どんな仕事も同じかもしれないが、すべての基本は現場にある。
当たり前のことを当たり前のようにやる、それはなんとなくできることでは決してない。
「ここは、手を抜かずにきちんとやっとこう。もう少し、頑張ろう」。こういうひとりひとりの思いの積み重ねがある。
すべてはこれからですが、とりあえず、すべてのみなさんへ、感謝!
ほんとうに、ありがとうございました。
- 2008.03.22 出店ラッシュ?
-
この1ヶ月で出店決定のリリースを3回も行った。4ヶ月なら6回だ。
去年の初め12店舗だったのが、今年の夏前には倍以上の26店舗になる。
数年前、毎年1店舗しか増えていなかったのがウソのようだ。
もちろん店舗が増えるのは嬉しいことだが、 もともと、売上や店舗数の急増を最優先で追い求めてきたわけではない。
高速道路SAPAへの出店など、戦略的に重要な案件が重なった。
オープン時期が夏休み前と後では、売上やその後の稼働率に大きな影響を与えるため、この半年間かなり無理して追い込んだ結果である。
これ以上ペースを上げるつもりはない。逆に抑えている。
さっそく、「内部体制大丈夫?」という突っ込みも入った。予想通りである。当然である。
「旅籠屋」には親会社という後ろ盾があるわけじゃない。無理して転んだりつまずいたりするわけにはいかない。
すでに年間延べ15万人を越える利用者、古くからの取引先や株主、そして(正直に言って私がもっとも大切に思い責任を感じている)平均年齢が50歳をこえる数十人の社員にとって、安心して付き合っていける会社であり続けることがすべての基本である。そうでなければ、創業の志を実現することもできない。
プロアマ問わず、社外のアナリスト諸氏には、会社の表面しか見えないだろう。
もしかしたら、社内でも本社の人間以外には見えにくいかもしれない。
じつは、この1年、新規出店の何倍もの労力と費用を、リスク対策や管理体制の見直しや効率化につぎ込んできた。
日常の雑務に追われて後回しなっていく流れに必死に抗いながら、なんとか船を上流へ進めようともがいてきた。
データベースサーバはデータセンターに預けた。
個人情報保護と顧客対応の一元化を図るため、メールシステムも近々一新する。
HMS(フロントと会計を統合したオリジナルの基幹システム)の改良も毎年のように続けている。
セコムと契約して全店セキュリティシステムを導入した。
支配人の負担軽減のため、夜間電話の対応策も実施寸前だ。
総務労務の管理も専門のコンサルと協議を進めており、システム構築に着手した。
昨年末、1ヶ月かけて実施した全店チェックをもとに、改良工事も始まった。
あわせて、バリアフリー化の工事にも着手した。
実質的な設計スタッフも4人に増えた。
数年来の宿題だった社内ネットのリニューアルもついに始まる。
そして、こんな中でも、役所とは妥協せず面倒くさい問題提起をし続けている。
審査請求が2件、近々、ついに中央官庁のヒアリングも受けることになった。
年初から開始した本社スタッフの募集。
全員が揃うスケジュールを見つけながら、すでに8人面接した。来週は7人に会う予定。
4月に入ると「伊賀店」「壇之浦PA店」のオープン準備で身動きがとれなくなる。
なんとか、今月中には、頼りになる新しい仲間と出会いたい。
体力、気力を振り絞って、会社をワンランクアップさせようと、みんな、ほんとうに力を尽くしている。
「出店ラッシュ」なんて、ほんの一面のことだ。
- 2008.02.28 東西の高速道路に「ファミリーロッジ旅籠屋」
-
4月23日オープン予定で建築工事が進んでいる「壇之浦PA店」に加え、東北自動車道・佐野SAへの出店も今夏オープンを目指して動き出すことになった。
思い返せば、7年前の2001年夏、当時の日本道路公団 新事業開発室の方に「高速道路のSAPAにこそ、誰もが利用できる宿泊施設が必要ではないか」と進言して以来、「車社会に必須のインフラ施設としてのロードサイドホテルの必要性」を、繰り返し提案してきた。
これは、当社の創業目的そのものを実現することであり、自らの利益拡大とは次元を異にする動機によるものだった。
実際、 当時は店舗数もわずかで会社は大赤字。「できれば、日本で唯一の汎用ロードサイドホテルを実現している旅籠屋こそが具体化には適任だし、そうなれば嬉しいけど、難しいだろうなぁ」という気持ちだった。
その願いが、ついに実現することになった。
これが我々にとって、どれほど嬉しく誇らしいことか、理解してもらえるだろうか。
なぜ、SAPAの限られたスペースに宿泊施設?
・・・本来、必須のインフラ施設なのであり、今までほとんどなかったことの方が不合理。
なぜ、旅籠屋?
・・・けっして知名度は高くないが、日本において汎用のロードサイドホテルを展開する唯一無二の会社であり、10年以上にわたって実績と信用を積み重ねている。
今後、メディアを含め、いろいろな問い合わせが増えるだろう。
高速道路はとかく批判的にとり上げられることが多いから、ある種の先入観や偏見を持って取材される可能性もあるだろう。
「高速道路利用者の利便性向上や地域貢献」に直接つながる事業を実現するんだ!
他のことは知らないが、今回の計画が西日本高速道路(株)や東日本高速道路(株)の関係者のそうした強い思いと必死の努力の結果であることは疑いない。当事者として、そのことは断言できる。
民営化して間もない大組織が、前例のない事業に取り組む、旅籠屋のような「無名」の企業にホテルの経営や運営を託す。
きっと、さまざまな抵抗や批判や注文がついたに違いない。
その決断が容易なことでなかったことは想像に難くない。
私が子供の頃、郵便局に小包を持っていくと、紐のかけ方が悪いなどと叱られた。「送ってやってやる」という姿勢だった。
今の宅配便に慣れた人には、これがどれほど画期的な新事業で、我々の生活を便利にしたかが理解しにくいかもしれない。
コンビニも、ファミリーレストランも、携帯電話も、すべてそうだ。
そして、そこには、無理解や減点主義と戦った人たちがいる。目先の利益を度外視して道を拓いた人たちがいる。
両高速道路会社の人たちとは随分議論した。今後のSAPAのあり方や可能性についても意見交換した。
ここからは、当社が全力を出す番だ。皆さんの思いを裏切ることなく、利用者に喜ばれるホテルを責任を持って経営・運営していかなければならない。
5年10年後、「えー昔は泊まるところがなかったの? それで長距離ドライブ旅行してたの?」と言われる時代が来て欲しい。
ご安心ください。10年以上、コツコツやり続けてきたことです。
- 2008.02.23 ハーフマラソン、ビリで完走
-
好天に恵まれ、初のハーフマラソン、無事完走。
5km、10kmもあったけれど、ハーフの参加者は150人くらい。
とにかく無理せず走って完走、が目的だったので、
スタート直後に全員に抜かれていきなり最後尾の一人旅。
前の人との差も大きかったので、途中、折り返し地点の案内看板を持った人が引き上げてくる途中、などという屈辱も味わったけれど、とにかく1回も歩かずに、走りぬいたぞ。
1km8分、時速7.5kmペース、という歩いているみたいな速度。
何回も走った10kmに比べると息はまったく苦しくないし、のんびり多摩川の河原の景色を見る余裕もあり。
ジムでマシンの上を走っているより、ずっと気持ちいい。
途中、もう少しペース上げようかな、とも考えたけど、余力は最後にとっておこうと自重。
しかし、やっぱり15km位から脚が重くなり、結局イーブンペースのまま、盛大な拍手に迎えられゴールイン。
これはトップとビリだけに与えられる栄誉。
3時間以内で完走が目標だったけれど、タイムは2時間42分57秒。
ちなみに、一緒に参加した会社の2人は、それぞれ1時間59分45秒と2時間25分59秒。
本日の教訓、現状ではフルへの出場はやっぱり無謀。
何回か、ハーフを走って、脚を丈夫にしないと無理、というのが実感。
ただ、ハーフを走っておくと、精神的には10kmが短く感じられてラクに思えるかも知れない。
次は、3/16の荒川市民マラソンの5km。
脚はラクだけど、心肺機能にはハード。
去年は30分2秒だったけれど、更新できるかなぁ。
走り終えて、すでに6時間以上経つけれど、今も脚がジンジンする。
今夜は、ゆっくりTVでサッカー観戦しよう。
- 2008.02.20 求む、本社スタッフ
-
何年もなかったことだが、この4日間で2度も徹夜してしまった。
出店契約の内容について、ある大会社との最終調整が難航しており、どうしても眠れないのだ。
昨夏、オフィスが3階から1階に移ったが、それでも職住近接には違いないので、寝付けないとゴソゴソ起き出して、ひとり「出勤」することになる。
会社同士の交渉事だし、別に後ろ向きのトラブルでもないから、死活問題などではまったくないのだが、長期間にわたって誠実かつ責任を持って「旅籠屋」の店舗を経営・運営していく基本に関わることだから、表面的な議論や形式的な合意で済ますわけにも行かない。
繰り返し、繰り返し、必死にこちらの真意と考え方を訴えるのだが、通じない。 大会社だから、あら捜しをする人やトップと直接話ができないのがもどかしい。今更ながら、企業文化や体質のあまりの違いに暗然とする。
まぁ、そんな話しは置いておくとして(これ以上は書けないのだ)、先日から本社スタッフ募集の活動を行っている。
出店ペースが上がり、もうじき20店を越えるが、本社のスタッフは私や専務を含めわずか5人。
仕事の「量」もさることながら、職務分掌を明確にして組織的に仕事をこなしていく体制を作って「質」を向上させていくにはどうしても人間が足りないのだ。
それに、「旅籠屋」の今後を考えれば、次代を担う人材を確保し育てていかなければならない。
出店経費が増え、損益的には少しの余裕もないのだが、これ以上決断を先送りにするわけにはいかない。
紹介予定派遣や人材紹介の会社に、初めて声をかけ、10近い先に求人を依頼している。もちろん、このホームページのトップでも募集している。こちら。
ようやく、応募者が集まり始め、あすから面接が始まる。
募集要項にも書いていることだが、当社に入れば文字通り「幹部候補社員」になる。大会社のように歯車の一部になるようなことはあり得ない。すぐに経営者と同じ目線で、感じ、考え、腕を振るうことができる。
それに何より、日本に先例のない事業、それもすべての人の暮らしを「豊か」にできる仕事にまっすぐに取り組むことができる。
社長が徹夜で仕事をしている、なんて書くと「ドン引き」されそうだが、朝礼で大声を上げ、鉢巻して残業まみれになるような「体育会系」の会社などではまったくない。
私が言うのもなんだけれど、仕事で自己実現を図りたい人には、これほど働き甲斐のある会社はないと思うのだが、ここ1年、「旅籠屋で働きたい」という直接の応募はほとんどない。
新聞のインタビュー記事を読んでいきなり手紙を書いて社長を訪ね、その場で転職を決めた経験のある私の感覚からすると、人材紹介会社経由でしか応募がないのはさびしい限りだ。
できるだけたくさんの人に会い、なんとか3月中には新しいメンバーに加わって欲しいと考えている。
まずは「旅籠屋 孤軍奮闘中!」を読んでいただき、どこかの「ファミリーロッジ旅籠屋」を訪ね、強く心が共鳴した人がいたら、ぜひ売り込んできて欲しいものだ。
ほんと、待ってますよ。
・・・始業時間が近づいてきた頃になって、少しずつ、眠くなってきた。
今週末は、初めてのハーフマラソンだし、今夜からはぐっすり眠れますように。
- 2007.09.24 発売から、2週間
-
きのうは、ひさしぶりの完全オフにして、浅草から有楽町まで散策。曇天だったが、ようやく暑さも和らいで散歩日和。
目的は、書店めぐり。そう、今月10日に発売された拙著「旅籠屋 孤軍奮闘中!」が、ほんとうに本屋さんに並んでいるのか、自分の目で確かめようというわけだ。
まずは、浅草橋駅近くの本屋さん、大型書店じゃないし、やっぱり置いてない。
次は、秋葉原の書泉。ここならあるだろうと期待していたが、尋ねたら「お取り寄せになります」とのこと、うーん。
なんとなく弱気になって神田のブックファースト。あったあった!書棚に3冊並んでる。嬉しくて携帯で写真撮影。
続いて日本橋の丸善、ここで購入したという話しを聞いていたから、きっとあると思っていたけど、目立たない場所にひっそりと1冊。
もしかしたら、売り切れ寸前ということか?!
そんな妄想にひたりながら、本日の最終目的地、三省堂書店・有楽町店へ。
自社の出版物だし、ここなら目立つ場所にあるに違いない。足早に入り口脇の「話題の新刊書コーナー」へ。
・・・ない。
せめて、ここでは「話題にはなってることにしてよ」とブツブツ言いながら2階のビジネス書の書棚へ。
ありました、ありました、20冊くらいが平積みになってる。こうでなくちゃ。
これなら売り切れの心配ないし、少し迷ったけれど、証拠写真を撮ったあと、1冊持ってレジへ。
調子に乗って、「この本、売れてますか?」 「当店だけなら、すぐにお調べできますよ」 「えっ! お、お願いします」
待つこと数分、ドキドキ・・・。
「あのー」 「ハイッ」 「昨日までのデータですが」 「ハイッ!」
「・・・ちょっと、売れてないみたいで」 「・・・ゼロ・・・?」
「はい、お客様が最初のお買い上げ、のようで・・・」
・・・ 聞かなきゃよかった。
- 2007.09.22 高速道路への出店
-
きのうは株主総会と恒例の「事業報告会」。
例年以上に多忙な中、資料作成をとおして前期を振り返り、今後の計画を練るのは「しんどい」作業だったが、立ち止まって考えるのはとても大切なこと。
そして、今年も株主の方々から、的確かつ率直な提案や質問をいただき、とても参考になった。ありがたいことだ。
・店舗増にともない、ホームページのリニューアルの計画はないか?
・沖縄へは出店しないのか?
・利益率を上げるため、「東京新木場店」に続く大都市への出店は計画していないのか?
・取締役の定員は? 監査役報酬枠を決めない理由は?
・リサ・パートナーズや高速道路に依存しすぎる出店に問題はないか?
・無料のニュースリリースサイトの活用を検討してみてはどうか。
やはり、今年のエポックは、高速道路への出店であり、皆さんの関心も高かったようだ。
ちょっと記憶があいまいなのだが、初めて日本道路公団に宿泊施設の提案をさせていただいたのは、2000年か2001年、少なくとも6年以上も前のことだ。
「マイカー旅行者の誰もが気軽に利用できる宿泊施設は高速道路に必須のインフラであり、運営会社の義務です。旅籠屋が事業機会を得られるかどうかは別として、実現に向けての協力は惜しみません」と何度も申し上げたものだ。
それが、2年前の分割民営化を経て、当社も参加する形で具体化しつつあるというのは、本当に本当に嬉しいことだ。
先例のないことであり、採算に乗るのか、やってみなければわからない。もしかしたら当社にとって長期間にわたって赤字の店舗を引き受けることになるかもしれないが、それは大きな問題ではない。
「旅行者が、気軽に安心して泊まれる 自由で経済的な宿泊施設の提供し、 シンプルで自由な旅と暮らしをサポートする」という創業の目的を考えれば、その実現は当社の存在意義そのものなのだ。必ずや良き先例になりたいと考えている。
ところが、最近意見交換したコンサル会社の方の話しでは、SAやPAでのテナント募集はなかなか難しいのだそうだ。
いわく、商圏が見えない、利益が見込めない。運営側も高速道路の将来像が描けていないようなのだ。
しかし、どうして、現状だけで判断するのだろう。もっと、コンセプチュアルに発想しないのだろう。
そもそも、一般道路と同じ物差しでSA・PAの立地をとらえるのはおかしいし、現在の延長で見るのも能がない。 違った視点で考えてみるべきではないか。
一般道路と同じようなショッピングセンターを作ってみても仕方ない。造成のためのコストが割高になるし、高速料金を払ってまで買い物や食事に行く人は少ないのだから、同じ土俵で規模やイメージを競うのは本筋ではないと思う。
一部で、車のショールームを作るという計画を耳にしたことがあるが、私はそんなものを高速道路上に設ける必然性を感じない。貴重なスペースの無駄遣いではないかと思ったりもする。
いっぽうで、ETC利用車が外部と出入りできるSA・PA(スマートインター)も増えつつあるし、宿泊施設の設置も具体化しつつあるのだから、高速道路はたんに通過する閉じた線ではなく、SA・PAも孤立した点ではなくなりつつある。
SA・PAに必須の機能は、通行者に対し、従来どおりの中継地点として、さらに周辺地域という面の核として必要最小限の物と情報を提供することに特化すればよいと思う。
たとえば、簡単な診療所、自治体などの広報センター、周辺施設や観光などの案内所(いずれもパンフレットを並べているだけの場所ではなく、ヨーロッパの都市などにある親切なガイドが常駐する旅行者センターのような機能を持つところ)、さまざまな店舗のショップ(そこで何を売るかではなく、地元の名産品や名店を紹介して、誘導するようなショーケースで十分)など、ハブ的な機能を集めてみてはどうだろう。
アウトレットモールとか、温浴施設とか、洒落たショッピングセンターなんて、スムースに誘導できれば、外部にあるほうがずっと利用者に喜ばれると思うがどうだろう。
話しが宿泊施設と離れてしまったが、少し考えてみるだけで、高速道路の可能性は大きく広がっているように感じられる。
高速道路会社や国交省の人と、もっとこういう話しをしてみたいなぁ。
- 2007.09.16 無自覚、無責任
-
「金沢内灘店」でのオープン準備の真っ最中に、安倍退陣のニュースを知った。
「ありえねー」と驚くと同時に、かなり腹が立った。
一般のサラリーマンだったら、どうだろう。
中小企業の経営者だったら、どうだろう。
みんな、心身のストレスを抱えている。
自殺を考えるほど追い詰められている人も少なくない。
辞めたら、家族や社員が路頭に迷う。
取引先や株主に迷惑をかける。
みんな、そういう責任感にぎりぎりの所で引き止められて、耐え難きを耐えている。
前から何度も書いているとおり、私はお役人が大嫌いだ。
なぜ嫌いなのか。
最大の理由は、許認可権限など「人の自由を制限する力」を持っているからだ。
「人に命令できる権利」というものは、本来きわめて特殊かつ異常なものであって、それを持つ者は重大な責任とさまざまな義務を負っていることを自覚しなければならない。
そのことに無自覚で、当たり前のように上からものを言う連中が少なくないのだ。
一国の宰相の抱えるストレスは並大抵のものではないだろう。
過酷な権力争いの醜悪は、地獄の業火に焼かれ続けているようなものかもしれない。
しかし、首相は最大の権力者であって、もっとも大きな責任を負っている人間だ。
ルーキーでもあるまいし、職責の重さと困難について、ある程度の予想と覚悟はあっただろう。
それを今になって匙を投げるというなら、それは、自分の体力や精神力の程度を見極めていなかったということだ。
食べきれないなら、最初から箸をつけてはいけない、ということだ。
こんな人間に、ある種の覚悟を匂わせながら「美しい国」などという資格はない。
「再チャレンジ」などを語る資格もない。
退陣と同時に、代議士も辞めて政界から退くのが、最低限の常識でしょうに。
- 2007.09.15 本が出た
-
トップページで紹介しているとおり、数日前に「旅籠屋 孤軍奮闘中!」という本が出版された。
以前、住宅メーカーに勤めていたころ、何冊かの本を企画したことがあるが、自分が著者という本の出版は、生まれて初めての経験。部数が少ないので案じていたが、東京・横浜・大阪など、大きな書店には並んでいるようだ。なんだか面映い。
内容の多くは、この「旅籠屋日記」に書いてきたことなのだが、少しでも考えてきたこと、感じていることが伝わって欲しいと心から願っている。
残念ながら、まだ反響はほとんどないけれど、読者の中から、「旅籠屋で一緒に働いてみたい。」という人が現れないかと密かに期待している。
それにしても、この数ヶ月は忙しかった。出店が増え、毎月のようにオープン準備の作業に出かけるようになったし、店舗が増えれば、何かとトラブルも発生する。加えて、8月の酷暑の中で行った本社オフィスの改築・一部移転はたいへんだった。物理的な荷物の移動だけでなく、今は通信環境のややこしい整備もあるし、書類や資料の整理にはたいへんな手間暇がかかる。
今週は「金沢内灘店」のオープン準備に出かけ、昨夜戻ってきた。来週は「土岐店」着工会議などに出かけ、金曜日に株主総会。それが終わると、とりあえず一段落する予定。少しは余裕ができるかもしれない。
ただ、この機会に、去年からの宿題、内部統制をからめた業務の整理やマニュアルの整備など、本社や店舗の仕事をシステマチックに、効率的に進めていけるような大作業に力を集中させなければならない。今、このタイミングでレベルアップしておかないと、ますます余裕がなくなって難しくなるのは目に見えている。ある意味、日々の仕事から離れての作業だから、自分たちで馬力を出さないといけないし、力技の仕事になるが、ここは余力を振り絞ろう。
ありがたいことに、あさっては祭日。あした、株主総会用の資料を作ることにして、数ヶ月ぶりに休みをとろう。成り行きで衝動買いした電子ドラムも叩きたいし、年末の発表会に向けたハモニカの練習も始めなくちゃいけない。
さて、きょうはもう試合終了にして、散歩がてら浅草ROXの本屋に行こう。売ってるかな? 買っちゃうかも!
- 2007.05.02 三菱UFJ信託銀行
-
新店のオープン準備や、パンフレットの地図作成(あれは、すべて私が描いているのだ。情報の取捨選択やエリア区分がややこしくて、社外に頼むのは時間とコストがかかりすぎる)に時間をとられ、四半期報告書の作成が進んでいない。規定は45日以内らしいが、できるだけ早く、遅くとも30日以内のリリースを心がけてきたが、今回はぎりぎりになってしまいそうだ。あすからの4連休中に仕上げよう。
それでも一日パソコンの前に座っているのは気が滅入る。
そこで、気分転換を兼ね、バイクを飛ばして三菱UFJ信託銀行に通帳の記帳に行ってきた。最寄りの店舗というと大手町の本店しかないので、経理担当もなかなかそのためだけに出かける機会がないからだ。天気も良く爽快。たまには走らせないとエンジンのかかりが悪くなるし、一石二鳥。
幸い、日本橋にも支店を見つけたので、立ち寄ってATMへ。
ところが、 持参した通帳が受け付けられない。ここは旧「三菱信託」系の店舗なので旧「UFJ信託」系の通帳記入は窓口でしか出来ないとのこと。
合併して1年半以上経つのにシステム統合が進んでいないというのはどういうこと?
もともと店舗数が少なく不便を強いられていたので、同じ三菱UFJフィナンシャルグループの傘下に入った時点で、三菱東京UFJ銀行のATMでも記帳できるように、と再三要望していたが、それどころの話ではない。
合併には、大手金融機関としての事情があるのだろうが、一般預金者の利便性を考えてのことでないことはこれで明白。そもそも、どっちを向いて仕事してるの?
そのくせ、毎月毎月、1枚ぺらの「証券代行ニュース」を定形外郵便で送ってくる。借入返済の通知も事前事後と2度ずつ送ってくる。送料が無駄だから改善した方がいいと何回も提案したけれど、相変わらず。
コスト意識はないの? そういう問題意識を持つ行員はいないの?
こういう会社が融資先には顧客第一主義とか経営の合理化なんて偉そうに言うのだろうか。
もしそうだったら、冗談じゃない。お笑いだ。
- 2007.03.06 マイペース
-
以前にも書いたが、一昨年の春から、みんなで、毎週、体重や体脂肪率を計り、ジムに通ったりしている。メタボリック・シンドロームに危機感を感じ始めていたからだ。おかげで、30%に向けて増え続けていた体脂肪率ももう少しで20%を切れるところまで落ちている。
去年の7月からほぼ月1回のペースで続けているミニマラソン大会への参加も、シェイプアップに大きく貢献している。
それにしても、自分たちが「走る」なんて、1年前には想像もしていなかったことだが、一度参加してみると走り終わった後の達成感は格別で、すっかり「病みつき」になってしまっている。
本社スタッフといっても4〜5名、年齢も幅があるし、走力も違う。速い者は10km45分前後だが、最年長の私は「1時間以内が目標」という低レベル。
10km走ると言うと、知らない人は驚いて感心されたりもするが、70歳過ぎで35分、という人もいるくらいだから、私などほんのジョギングペースで、いつも最後尾に近い。
ひとつ弁解させていただくと、じつは初回の練習の時に膝を痛めてしまい、毎回、痛みが出ないよう膝をかばいながらの走りなのだ。
それでも、昨年7月の初挑戦の時の79分からは少しずつタイムが縮まり、最近は65分は切れるようになった。
話題の「東京マラソン」も10kmコースに参加、2週間後にも別の大会に出て、自己ベスト更新を狙ったが、残念ながら果たせなかった。64分が壁?なんてお粗末。
前者は、氷雨の中、人込みをかき分けながらだったので止むを得なかったが、後者は天気もよく、膝も痛くならなかったので納得がいかない。
原因は、前半あまりにもスローペースだったからだ。後半のペースで最初から走っていたら、60分そこそこで走れていたかもしれない。くやしい。
ところで、最近、ますます仕事が忙しい。
3〜4月に3つ店舗がオープンするし、その後の出店計画も目白押しだ。
例えて言えば、おいしそうな料理が次から次へと目の前に並ぶような状態なのだが、もちろん、これが血肉になるには、迅速に消化できる丈夫な胃腸と、成長していく身体を支える骨格や器官の発達がともなわなければならない。食べ過ぎが原因で病気になり、倒れてしまっては意味がない。
人間の体の場合、元来「食料不足」に耐えるようにシステムが作られているから、「飢餓状態」でない限り「飽食」や「過食」の方が病気の原因になりやすい。
旅籠屋の場合も、 ひもじい思いをしながら何年もやってきたから、たくさんの「ご馳走」には体が慣れていない。
「貧乏人根性」丸出しで、出されたものに端から喰らいつきたい衝動にかられるが、まぁ、ここは慎重にいこう。私の走りとは逆に、まわりにつられてオーバーペースになると、途中で腹痛リタイアなんてことになりかねない。ちゃんとトレーニングして、毎回完走していれば、目に見えて体力は向上していく。必ず、余力は増えていく。
膝の痛みは、ランナーに多い「腸脛靭帯炎」らしい。膝のまわりの筋肉を鍛えたり、ストレッチを充分に行えば改善するらしく、そう心がけている最近は確かに痛みが出にくくなっている。
心肺機能も確実に向上しているから、 弱点をカバーできれば、60分切りも遠くないだろう。
- 2006.12.26 ネットマナーの低下
-
今に始まったことではないけれど、ネット上でのマナーをわきまえない書き込みや振る舞いに苛立つことが多い。
ホームページを開設して、来年の2月で10年になるが、一貫して誰もが自由に書き込んで閲覧出来る「ゲストブック」を開いたままにしている。
不特定多数の一般ユーザーを対象にしている企業で、こうした場を持っているのは、ごく少数ではないか。背景や経緯を省いて一方的に批判的な書き込みをされると、それが悪意によるものでなくても、読む人に影響を与え、場合によっては大きな誤解やダメージを受けることになるからだ。
だから、一部には「ゲストブックは閉じたほうがいい」という意見がある。賢明かつ妥当な判断だと思う。
批判される側は衆人環視の中で「さらし者」にされるけれど、書き込むほうは、匿名だし、そんなことに気づいている人は少ないだろうからだ。
リアルな世界では、誰かを批判しようとすれば、それなりの根拠が求められ、発言への責任と逆批判のリスクを負うことになる。例えば、どこかのレストランの前で「ここの料理はおいしくないぞ」と道行く人に訴えるには、それ相応の覚悟が求められる。
普通なら、まずそのレストランの人に直接苦情を言うべきなのだ。いきなり、店の前で「営業妨害」をすることなどありえないし、許されない。
ネットでは、こうした世の中の手順や常識が「お手軽に」無視できてしまうし、実際無視される。
「旅籠屋」にご宿泊いただいて何か不愉快に感じられる点があれば、まず直接その店にご意見をいただきたいと思う。
「ゲストブック」に批判的な書き込みがあれば、すぐに状況を調べ、速やかに「お詫び」や「弁解」や、ちょっとした「こだわり」を書く。ただ、これに対して、再度の書き込みがなされることはほとんどない。「言いっぱなし」「文句の付けっぱなし」なのである。
ネットというのは、自由であることが命だと考えている。検閲された情報掲示板なんて、意味がない。
だから、意地を張って、完全にオープンな「ゲストブック」を維持してきたが、残念ながらネットマナーが向上する気配は見られない。情報の発信者であることについての自覚が育っていない。そろそろ潮時かもしれない。
「ゲストブック」以外にも、「旅籠屋」のことが話題にされるサイトがいくつかある。
残念ながら、書き込みの多くは、「知ったかぶりの中学生」程度のもので、話にならない。そもそも発言は浅薄な思いつきを「一家言」のごとく偉そうに語っているに過ぎず、発言に責任をとるつもりも、とれるとも思っていない。人間として最低だと、私は断じてはばからない。
- 2006.11.15 会社解散
-
ショッキングなタイトルだが、もちろん「旅籠屋」のことではない。
私が、昔、勤めていた会社の話。
いろいろあって、大学を卒業したのが26歳。
「サラリーマンには絶対向かない」という周囲の声と「サラリーマンにだけはなりたくない」という自らの願いを裏切って、就職した会社。
2〜3年続くかな、という予想だったが、結局12年半在籍した。
その会社が解散してしまうらしい。
驚くと同時に、複雑な心境。
退職したわけだから、批判的に見ている部分はもちろん多い。
でも、良くも悪くも、社会人、ビジネスマンとしてのイロハを教えていただいたわけで、あの頃の経験の上にしか今の自分はない。
日本にも合理的で質の高い住宅を作ろう、という目的意識のもとで、竹中工務店や新日鐵の共同出資で設立された、ユニークな会社。
そういうコンセプト重視の企業のDNAは、間違いなく私の心の中に受け継がれている。
親会社から役員が天下ってくる会社の「経営者不在」の問題点や、プロパー社員の情けない状況も苦い体験として刻まれている。
もともと、起業なんて夢見ていなかったし、状況がほんの少しでも違っていたら、転職なんてしなかったかもしれない。
当時の同僚は、きっと会社の幹部だろう。
会社が解散したら、この先どうするのだろう。
きっとたいへんだろうな、と思う。
会社の利害関係者(ステークホルダー)という言葉があるが、社員だけでなく、その家族、顧客、たくさんの取引先、そしてもちろん株主。
経営者としての社会的責任と義務、そのために必須な資質や能力のことをあらためて考える。
- 2006.10.21 非常識
-
おとといは、「軽井沢店」の敷地で着工前打ち合わせ。数日後には着工だ。
きのうは、「千葉勝浦店」の敷地に地縄を張って着工会議。
そして、週明けの月曜日には「須賀川店」の確認申請書提出。
12月から来春にかけては、3箇所で並行して工事が進むことになる。 こんなこと、初めて。
かなり忙しいけれど、前向きな作業はあまり苦にならない。
この段階に来るまでの心労が大きかっただけに、かえって嬉しい。
というわけで、やれやれ、という気分の週末の土曜日だが、朝8時半に電話で起こされた。
「オタクの株を買おうか考えてるけど・・・」と来た。
「はい」
「3店オープンするらしいけど、資金はどうしたの?」
「土地や建物を当社で取得するわけではありませんので、とくに資金調達の必要はありませんが」
「あっそう。ところで、株式の分割とか増資とかないんだろうね? 薄まると困るからね」
「いえ、それは、あるともないとも、この場で一部の方だけにお答えすることはできません」
と、まぁ、(文章にすると伝わらないけれど)こんな小ばかにしたような調子でのやりとりが続いたのだけれど、だんだん我慢できなくなって
「あの、初対面の方にタメ口聞かれる筋合いはありませんよ。失礼じゃないですか」と言ってやった。
「親しみを感じてたもので」などと弁解していたが、冗談じゃない。いい加減なウソをつくんじゃない。
自分の利殖の手段として旅籠屋の株を利用することが目的で、旅籠屋自体には興味ないんでしょう。
中小企業なんて万事レベルが低くて、その経営者なんて信用できないと思ってるんでしょう。
こっちは「株を買ってやる立場なんだから、ありがたく思え」と腹の底で考えてるんでしょう。
違うというなら、投資先の社長にいきなり電話してアレコレ質問するとき、オタクなんて、言うかね。
人間としての常識の問題でしょう。
敬語を使え、なんて、言わないけれど、友達じゃないんだから、普通の言葉を使いなさいよ。
旅籠屋の場合、公募増資の時から出資いただいている株主の方がたくさんいらっしゃる。
そして、株主総会の場に限らず、貴重な提案や情報提供をしていただくことが多い。
それは、もしかしたら、とても珍しいことで、経営者としては得がたい幸運なのかもしれない。
だから、こういう「株主」に慣れていないのかもしれない。
でも、慣れるつもりもない。
と、ここまで書いて、先日、別の日記に「田舎モン」と題して書いた文を思い出した。
言いたいことは同じなので、転記する。
---------------------------------------------------------------
「田舎モン」
電車を乗り継いで、有楽町まで買い物に行ってきた。
むかついたので、珍しく昼間から、書く。
混んでもいないのに、電車の出入り口に立っている兄ちゃん。
二人分の席を占領して平然としているオヤジ。
後ろから続く人などお構いなしに扉を締める女。
そういうのを「田舎モン」と言うんだ。
回りのことなど気にする必要がないという傲慢さ。
回りの空気をさっぱり読めない鈍感さ。
こういう無神経な人は、人影もまばらな田舎に行っちゃってください。
都会暮らしには向きませんから。
多様性には馴染めませんから。
思考停止の無表情。
生きる値打ちも資格もない、と言いたいくらい。
絶対に友達にはしたくないタイプ。
間違っても子供など再生産せずにひっそり暮らしてくれ。
---------------------------------------------------------------
要は、社会生活を営む人間としての常識をわきまえろ、ということだ。
あー、こっちは、土日も忙しいのだ。
午前中には老母を病院に連れて行き、午後は犬の予防接種。
今夜はバンドの練習で、あしたは10kmマラソンだ。
- 2006.09.22 株主総会
-
きょう、第12期定時株主総会だった。
とくに大きな動きもないので、今回は少ないかなと思っていたが、社員・役員株主を除いて10名以上の方々が参加された。
グリーンシートに登録して、一般の株主の方々を前に事業の報告と見通しを語る公式の集まり。 数えてみたら、これで8回目。
初めての時は、カチカチに緊張して、リハーサルを行ったりしたが、最近はすっかり平常心。
慣れもあるけれど、「軽井沢店」の件で「つるし上げのような反対運動」にさらされた経験が生きている。
多勢に無勢、罵詈雑言を浴びせられてもひるまず対応してきたことで、精神的に少し強くなったかもしれない。
もともと、隠し事のない会社だし、やましいことは何もない。問題点があれば率直に詫びればいいし、主張すべきことは主張すればいい。実態以上に、大きく虚勢を張る必要もないし、小さく卑屈になることもない。
そんなわけで、自然体で臨んだわけだが、総会後の「事業説明会」では6人の方からいくつかの質問をいただいた。
今後とも、赤字店をクローズする考えはあるか?
店舗拡大の手法として、フランチャイ ズ方式をとる考えはないか。
予約サイトの活用をもっと拡大してはどうか。
ホームページ(「旅籠屋日記」を含む!)の更新が滞っているようだが。
中高年旅行者の増加に対応した広告戦略は?
利用者として、支配人の第一印象に良し悪しがあるが、どう考えているか?
どの質問も、期待していただいている気持ちが伝わってきて、ほんとうにありがたい。
なんとなく、このページの更新もしないままでいたけれど、これではイカンと反省した次第。
必ずしも、業務に直接関係ない話しもあるかもしれませんが、どうか気楽に読み流してください。
- 2006.06.09 シェイプアップ
-
去年の5月から、毎週、本社の男性スタッフ全員(と言っても、設計事務所の人を含めてわずか4人)で体重や体脂肪率を測ってグラフを掲示している。
デスクワーク中心で、目に見えて肥満が進んできたからだ。
私も「鬼怒川店」にいた頃から比べると、10kg以上も太った。
時々、区のスポーツセンターのジムに行ったりするくらいで、みんなで何か特別のことをしているというわけではないが、中には体重が15kg、体脂肪率が10ポイントも減少して別人のようにスリムになった社員もいる(彼の場合は、個人でトレーニングしたり食生活改善に努めている)。
さて私だが、体重が−3kg、体脂肪率が−4ポイント。
効果はわずかだが、無自覚のまま過ぎていたら、逆の結果になっていたかも。
食生活管理や筋トレもいいが、やっぱり有酸素運動で体の中から鍛えないとね、というわけで、7月にみんなで10kmマラソンに参加することにしている。
ちなみに、全員愛煙家なのだが、これも、2年ほど前から自分のデスクで仕事しながら吸うのは止めようということにしているから、かなりの節煙になっている。
いずれも、みんなで無理せず続けていることだから、決して苦痛ではない。
毎週月曜日の体重測定は健康談義に花が咲き、楽しく一週間がスタートする。
オフィスも、秋から1名スタッフが増えることになり、これに備えて書類や資料の整理を始めた。
本社の業務をすべて洗いなおし、職務分掌を明確にし、ファイルサーバの中も整理整頓する。
体も仕事も、まずは成り行き任せになっている日常の無駄をそぎ落とし、シェイプ・アップすることが肝要。
どちらも、生活習慣病=成人病にならないうちに、血をさらさらにするのだ。
しかし、問題は今夜開幕のサッカーW杯大会。
夜更かしと睡眠不足と間食と運動不足の予感・・・
- 2006.03.20 証券会社とグリーンシート
-
今回、「東京新木場店」オープンに先立って、初めてプレス向けの内覧会を開催した。
東京に店舗が誕生するという機会を活かして、できる限り知名度を上げたいと考えたわけだが、PR会社の尽力もあって、いくつかのマスメディアで旅籠屋を取り上げていただいた。
同時にリリースしたリサ・パートナーズとの業務提携のニュースも注目されたようだ。
いつものことだが、少しニュースになると、いろいろな会社から引き合いや問い合わせの電話が入る。
もちろん、嬉しいことなのだが、かつて冷たくされた会社からだと「今頃になって・・・」と恨み言を言いたくなる思いもある。リスクをとらず目先の打算でしか動かない企業とはつきあいたくない。ベンチャー企業は、ビジネスの方法論にもこだわるべきなのだ。
これはもう1年ほど前からのことだが、銀行や証券会社からのコンタクトが増えている。証券会社の場合、IPOに向けてのアプローチということになるのだが、私は、必ず「貴社は、なぜ、グリーンシート市場の株を取り扱わないのですか?」と尋ねることにしている。
先日も、業界のリーディングカンパニーであるN証券の方に「取引が少なく利益にはつながらないでしょうし、現在のシステムにもいろいろな問題はあるでしょうが、本来の意味での株式市場を育て、日本経済全体の発展を考えれば、貴社こそが積極的に関わっていくべきではないですか?」と申し上げたが、具体的な反応はなかった。
数日前もC証券からIPOに向けた主幹事証券がらみで会いたいという電話があったので「まず、グリーンシート株の取扱いをされることが本筋ではないですか?」と申し上げたら「ウチはそれはできないので、結構です」と電話を切られてしまった。
グリーンシートに登録して6年半、すっかり古株になっている。
だから、ずっとグリーンシートの流れを見ているわけだが、率直に言って疑問に思う点も多いし、本来の目的に沿って成長しているようにも見えない。とくに「拡大縁故増資」については、数年前、ディーブレイン証券の出縄社長と長時間議論したが、残念ながら方針は変わっていない。
しかし、アーリーステージにあるベンチャー企業にリスクマネーを提供する場という意味で、グリーンシートはかけがえのない市場であり、その社会的意義はますます高まっていると思う。
当初、求めに応じてあえて設けていた株式の譲渡制限を、数百万円の費用をかけて撤廃したのも、グリーンシート市場の拡大と普及という目的を理解したからだ。
それなのに、取扱証券会社の数は少しも増えず、取引数が少ないから株価による企業評価という市場としての機能も果たしていない。残念なことだ。
いろいろな事情はあるだろうが、存在意義や社会的使命という観点に立って、証券会社各社の参加を強く望みたいと思う。
余談だが、せっかく譲渡制限を外したのに、どうして松井証券は旅籠屋の取扱を始めないのだろう。
以前は、もちろん、取り扱いますよ、と言っていたのに。
IPOを考えると、株主数の増加は一長一短があるし、別にあらためて申し入れるつもりはまったくないのだが、取り扱わない理由を聞いてみたい気はする。
- 2006.02.25 アナログ
-
昨秋、株主の方から、新聞の書評欄のコピーをいただいたことがある。
旅籠屋と重なるところがあるのではないか、とのコメントが書き添えられていた。
アメリカのスモールタウンばかりを結ぶ車での一人旅紀行。
ビビッとくるものがあり、早速書店を回って手に入れ、一晩で読み終えた。
「語るに足る、ささやかな人生・・・アメリカの小さな町で」 駒沢 敏器 著、NHK出版 2005.7/25発行
文字通り、ロードムービーを見ているような、少し切ない旅気分があふれている素晴らしい本だった。
都会や観光地だけを駆け足でつまみ食いする旅では決して気づかないアメリカ人の暮らしが、行間から伝わってくる。
十数年前、初めてMOTELを泊まり歩きながら感じた世界の背景が、じっくりと表現されている。
お奨めの一冊である。
別のところで、これもある株主の方が「旅籠屋はアナログなビジネスだと思う」と評されているのを目にしたことがある。
思わず、そのとおりかもしれない、と膝をたたいた。
サービス業だから、機械的な数値で測りにくい、マニュアル化しにくいビジネス、という意味もある。
しかし、ご指摘の主旨は、「あえて素っ気無い雰囲気にしようとする二重のこだわりを感じる」ということなのだと解釈した。
ひとつは、「雰囲気」という抽象的なものにこだわるアナログ志向、もうひとつは数字を至上としないこだわり重視の経営姿勢。
個人的には、こうした理解者に恵まれていることを、ほんとうにありがたいことだと思う。
最近、耐震偽装問題や、東横インの違法改造問題や、ライブドアのニュースが騒がしい。
私は、バブルの頃の「一億総不動産屋、一億総株屋」と言われた時代のムードを思い出した。
当時、この流れに乗らなかった経営者は「時代遅れの頑固者、保守的で無能な経営者」と批判されていた。
それが、バブル崩壊後は「さすが、先見の明のある堅実な経営者」と再評価される。
まったく世間の無定見にはあきれてしまう。
ただ、当時批判された経営者たちの多くは「なんとなく、どこか違うと感じて、その気にならなかっただけだよ」というのが正直な気持ちであったように思う。
根拠としての理路整然とした経営判断基準を問われても答えにくかったに違いない。
これは、アナログな感性の問題だ。
世の中の動きが速い。断片的な情報が飛び交い、「世論」の風向きもコロコロ変わる。
頑迷だったり、保守的であることが良いとはまったく思わないが、今の時代、ある種のバランス感覚や常識やこだわりを失わないことがとても大切なのではないかと思う。
音楽だって、私もカラオケはMIDIで作るけれど、それはハモニカで「歌う」ための練習用ツールに過ぎない。ブルースハープは肉声にもっとも近いアナログ楽器、サンプリングでの再現は、まぁ無理でしょう。
「楽天トラベル」で宿を検索して事足りるような旅のスタイルも、やっぱり好きになれないな。
- 2006.02.03 痛み
-
業績の下方修正、などという、情けない四半期報告書をリリースした日にこんな日記を書くと、「弱気な発言は経営者失格!」とお叱りを受けるかもしれないが、およその事情は開示したのだから、もう心境を吐露してもいいだろう。
歯が1本痛いだけで、靴づれを1箇所作っただけで、何もかも台無しの気分になる。
心の痛みも同じ・・・
たったひとつでも悩ましいことがあると、生きていること全体がつらくなる。
ところが、考えてみたら、小さな雲が浮かんでいるだけかもしれない。
他は青空の広がるすばらしい天気かもしれない。
そうやって、少し離れて状況を見てみると、「なーんだ、降水確率10%」と知って気持ちがラクになる。
健康に慣れていると、痛みに弱くなる。 ほんの一部分の痛みで重病人の気分になる。
快晴じゃなくても、元気に暮らせる心を持ちたい!
・・・この半年間、こんなことを自分に言い聞かせ鼓舞し続ける毎日だった。
個人の金儲けなどという私欲にとらわれず会社を興し、この10余年、社会に貢献する事業であるという誇りを支えに、誠実に仕事をしてきたつもりだが、考えもしなかったような露骨なエゴに直面し、重度の人間不信に陥りそうだった。
これまでも、先例主義に凝り固まった役所や金融機関の無理解や事なかれ主義に抗って道を切り拓いてきたが、人間としての最低限の礼儀もわきまえないこれほどの侮蔑と敵意を浴びるなど、想像したこともなかった。
正直言って、逃げ出したいという誘惑にかられる瞬間もあったが、踏みとどまって、真正面を向き続けてきた。創業の志を裏切ることはなかった。
ベンチャー企業というものは、周囲との摩擦がある所に存在意義がある。
問題は解決したわけではないし、これからも、予期せぬ壁にぶつかるに違いない。
しかし、この半年間の経験は、間違いなく会社を強くした。
絶対に逃げない、絶対にあきらめない。腹をくくれば怖いものはない。それが教訓である。
営々と努力を続けても、実業の世界はそう一本調子にいかないものだ。
・・・それにしても、結局はひとり背水の陣に立つ社長というものはしんどいもんです。
- 2005.11.28 経営者の仕事
-
10月後半、3回に分けて本社全員で全10店舗をまわった。
新規の出店候補地の視察も兼ねていたので、あわただしい出張だったが、得るものは多かった。
じかに建物の雰囲気を感じ、支配人の表情を見て気がつくことがたくさんある。
せめて半年に1度は足を運ばなければと痛感した次第。
今月に入り、先週は泊りがけで「九十九里店」のオープン準備に出かけた。
ガランとした建物に家具が入り、絵がかかり、草花が植えられて表情が生まれてくる。
なにか部活の合宿みたいな楽しさがある。
作業を終え、役所の検査も済ませて、ひとつのホテルをみんなで作り出したような喜びがある。
少しずつ店舗が増え、店舗管理担当者の仕事は増えるばかり。
新規出店の話しも順調に増え、開発担当者や設計士さんは図面や書類作りに忙殺されている。
電話も郵便もメールも来客も増えるいっぽうで、「雑用」に追いかけまわされている感じがする。
やりたいこと、やらなきゃならないことに手が回らない苛立ちがある。
そろそろスタッフを増やさないといけない。オフィスも手狭になってきた。
でも、広い所にたくさんの人間がいれば良いというわけでもない。
お役所みたいになったら死にきれない。
業務の洗い出し、合理的な分類と再構成、職務分掌の明確化と権限の委譲、そして情報の一元化。
まずは、そういうグランドデザインを描いてみなければいけない。
・・・これこそ経営者の仕事。
- 2005.08.22 腹立たしくて、悲しい
-
社会的地位や経済的余裕は、人間を寛容にすると思っていた。
高い教養や文化的な素養は、人間を予断や偏見から自由にし、周囲に流されない勇気を与えると期待していた。
しかし、それはどうも逆らしい。
自分たちの価値観ばかりを語り、排他的に「自分たち」を守ろうとする。
多様性を受け入れる心のゆとりを失ってますます狭量になり、ヒステリックに選民意識にしがみつく。
こんなことが世界中で起きている。身の回りにもある。
腹立たしくて、悲しい・・・
- 2005.08.12 役員賞与
-
1号店がオープンしてから丸10年、ようやく念願の黒字転換を果たした。
1000万円は超えるだろうと予測していたが、ややこしい決算処理を終えてみたら、700万円どまりだった。
新設された外形標準課税による法人事業税や法人住民税だけで約400万円は痛い。事業規模の割りに資本金が大きく、店舗が各地に点在しているので負担が大きくなるのだ。
赤字の繰越があるから所得割の法人税はかからないけれど、固定資産税が140万円。締めて税負担は550万円。なんだかなぁ。納税以外の面で随分と世の中に貢献していると思うんだけどなぁ。
まぁ税制の不合理については、別の機会に吼えよう。
ところで、少ないとはいえ一応黒字になったのだからと、密かに楽しみにしていたのが役員賞与。
しかし、昨日の取締役会で会計士に確認したところ、なんと、累積損失がある間はダメなのだそうだ。
えーっ ?! 知らなかった・・・
ようやく減少に転じたとはいえ、累損は1億5千万円近くあるから、これでは少なくとも数年はもらえそうにない。
がっかり、ほんとうにがっかり・・・
当社の役員報酬は、取締役3人と監査役1人の合計4人で1425万円。
取締役のひとりは私の父で、退職金をはたいて出資と貸付を行ってくれたのだが、これまで1円も払っていない。申し訳ない。
昨年就任していただいた監査役にも交通費プラスくらいしかお支払いしていない。申し訳ない。
役員だから、もちろん、従業員と違ってボーナスなどない。
世間と比べて月々の役員報酬が少ないことなど、大きな声で言うようなことじゃない。
元々金儲けが事業を始めた動機じゃなかったし、お金に換えられない喜びも得てきた。
しかし、子供の学費やらなんやら、私個人の家計はずっと赤字続き。
今回楽しみにしていた初めての役員賞与だって、右から左に消えていく運命ではあったのだが。
仕方ないから、役員報酬を増額してもらおうか、と考えているのだが、そうなると会社の営業費用が増えて利益を減らすことになる。
うーん、悩ましい。
責任の重さやストレスの大きさ、なんてことを持ち出す前に、
社長だって、専務だって、もう少しゆとりのある生活をしたいぞ。
- 2005.07.16 楽天トラベル
-
「ファミリーロッジ旅籠屋」1号店が誕生して、ちょうど10年になる。店舗もようやく10に増えた。
社内コミュニケーションの密度を保つためにも、初めて「全社会議」なる集まりを持った。
過去10年の概括、現状、そして今後の10年のビジョンについて語ったが、具体的な課題のひとつとして、「楽天トラベル」(旧 旅の窓口)などの宿泊予約サイトへの対応を取り上げ、方針を示した。
きっかけは株主総会での株主からの提案。
「旅行代理店などに依存しない」というポリシーを曲げ、例外的に登録に踏み切った。3年前のことである。
集客そのものよりも、存在を知ってもらうための広告宣伝の一環と割り切っての決断だったが、幸か不幸か年々集客の実績が上がってきている。
9月からは、販売手数料が大幅に上がり、実質10%になる。このままで良いのか、原点に立ち返って考え直すべき時ではないかという問題意識があった。
新聞報道によれば、すでに「楽天トラベル」経由の宿泊予約はJTBの半分程度になっているらしい。ビジネスホテルの中には依存率が20%を超えている所もあり、手数料の値上げは業界で大きな問題になっている。先日はテレビでも取り上げられていた。
宿泊施設の側からは、「寡占企業の横暴だ」「もっと手数料の低いサイトへ乗り換えよう」というような声が聞こえてくる。切実な問題であり、そうした感情は痛いほどわかるが、その次元で不満を言っても解決策は見えない気がする。
片方に多数のユーザーがあり、他方に多数の宿が散在する。それが、現場ではなく、予約という契約行為で売買されるのだから、ネットによるマッチングサービスに向いている面がある。好むと好まざるとに関わらず宿泊予約サイトの存在感はますます大きくなっていくに違いない。
加えて、大幅な値上げといっても、既存の旅行代理店の手数料よりは安い。
そして、何より、空室にするよりもマシなのだし、だからこそ登録し、実際、売上の増加を喜んできたのだから、感情的に異議を唱えてみても、根拠が弱い。楽天の強気も、ビジネスとして考えれば当然なことであり、そんな次元で議論していても勝負は見えている自業自得、他力本願のツケを払うしかないというわけだ。
物であれ、サービスであれ、直販に特化しない限り、サプライヤーと中間業者と最終販売業者は本来熾烈な主導権争いの関係にある。家電メーカーと量販店、メーカーと卸業者と巨大小売業者の血みどろの戦争は、過去何十年も繰り返されてきたことだ。
宿泊業界は、サイトビジネスであり、画一的でないことに安住し、自らを甘やかしてきたのではないか。
残念ながらというか、当然というべきか、新聞の記事もテレビの報道も、それぞれのすれ違いの主張を紹介するばかりで、こうした点に踏み込む問題意識さえ提示しない。
おそらく、宿の経営者の多くも、業界団体でさえも、どっちが得か、どう交渉しようかという戦術論に終始しているように見える。
理屈ではわかっていても、なんとなく面白くない。そういう感情の源に何があるのか。問題の本質はきっとそこにある。
集客を外部に依存すること、それは価格決定権を含めた自らの経営権を低下させることを意味する。手数料の支払いによるコスト増を認め、値引きを受け入れ、場合によってはサービスの内容さえ決められてしまう。宣伝を代行され、宿のセールスポイントも自らの言葉で語れなくなる。無意識に感じている不満の原因はそこにある。
自主独立の権利、それは企業の生命線である。その権利は命がけで守らなくてはならない。そのためには、自らの商品の差別化をはかり、自力で広くアピールしなければならない。
かつて、困難だったこうしたことが、ネット社会の出現によって、小規模な企業にも可能になってきた。端的にはホームページの開設や電子メールの活用である。
ネットは分散処理の世界。人類が、歴史上初めて手にした、中央集権的でない個別分散型の双方向の情報伝達環境だ。無数の個人やグループや組織が、特異性を維持したまま存在しうる、本質的に多様性を内包した世界だったはずだ。
工場生産品でない宿泊施設が個性を売り物にするなら、こうしたネット世界に活路を見出し、ネットの特性を守るよう働きかけていかなければならない。
楽天は、IT業界の寵児ともてはやされているが、一度、彼らのネット観を尋ねてみたい気がする。
「旅の窓口」時代は許容していた個々の宿自身へのリンクボタン、それをすべて消し去ったのはなぜか。
千差万別の施設の紹介を画一的なフォーマットに押し込め、価格帯で検索させるのはなぜか。
ポイント制をスタートさせ、リピーターさえも直接予約から遠ざけようとするのはなぜか。
答えは簡単。マッチングサービスを成立させやすくするために、利用者と宿の多様性を単純化したいからだ。それが、手数料ビジネス発展の最短距離だからだ。
しかし、それでいいのか。ネット社会の未来はそれでいいのか。情報が単純化され、記号化され、多様性を失っていくことでよいのか。情報を一部の企業が寡占する世界に戻すことでよいのか。
いつものように「あるべき論」にたどり着いてしまった。「ビジネスの本質は、効率である」という主張に徹する人たちとはここでお別れである。
私、そして「旅籠屋」のモチベーションと存在意義は、別の道の上にある。
前者会議で示した方針? 結論だけ言えば、当面登録継続である。
そう、中小企業はじっくり、しつこく、したたかに行く。
- 2005.06.28 バカ正直
-
ここ数ヶ月、頭から離れなかった心配事・・・
仕事での大きな課題が、ようやく解決に向けて動き出した。
役所の帰り、車の中で、「良かった、良かった」と何度も声を上げた。
新しいことを起こそうとする時、許認可権限を持つ役所との交渉は、ほんとうに骨の折れることなんです。
法律は、事実の後追いだから、結果的に守旧的な存在で、世の中の新陳代謝を妨げようとする。
行政官は法を執行する立場だから、法律の時代錯誤を訴えても運用の幅には限界がある。その立場は理解しているつもりだ。
それでも、「決まりは決まりだから」と聞く耳を持たない役人も少なくない。そういう場合、裏に責任逃れの事なかれ主義が露骨に透けて見えて腹立ちを抑え切れなくなることがある。
先日も、枝葉末節にこだわる労働基準監督官に、思わず「あなたは、どういう志を持って労働基準監督官になったんですか。労働者の待遇や職場環境を向上させたいという気持ちがあったからじゃないんですか。それなら、実態無視の法律の条文にこだわる職務に矛盾を感じませんか。法の不条理をもっとも肌身で感じている現場の行政官として、自分が何をすべきか考えるべきではないですか」などと詰め寄ってしまった。
今回も、もしどうしてもラチがあかなかったら、都道府県はもちろん、中央官庁まで行く覚悟を決めていた。さらに、場合によっては行政訴訟を起こして法の不合理を正すことも視野に入れ、友人の弁護士に相談したりもしていた。
最近、ベンチャー企業経営者の能力や経営姿勢について、厳しく問いただす投資家の意見を頻繁に眼にする。その苛立ちや怒りはかなりの部分理解できるし、共感することも少なくないが、所詮株価の上昇だけを期待する意識は共有できるものではない。
経営者にとって、初期の事業資金を提供してくれた出資者は文字どおりエンジェルである。その恩を忘れることはないし、決して忘れてはいけないと思っている。しかし、経営者は株価を上げるためだけに事業を行っているわけではない。
めいっぱい陳腐な言い方になるが、少しでも世の中の役に立ち喜ばれるために新しいビジネスを興し育てているのだ。少なくとも私は、株式公開による株価の高騰が天使に報いる唯一の方法であるとは考えていない。もっともっと大切なものを含めて恩返しすべきだと信じている。ベンチャー企業が創業の志を失ってしまったとしたら、それこそ恩人に対する裏切りじゃないか。
役所との交渉に臨むとき、その場逃れのごまかしや、政治家を使っての圧力など、結果重視の方法はいくつもあるだろう。それを知らないほど世間知らずではないし、その選択肢を潔癖に否定するほど青くもない。
しかし、可能な限りそんなことはしたくない。
とにかく、誠心誠意、趣旨を説明して、法の目的に適っていることを訴えて理解してもらう。
そして、きょうの担当者からは、こちらの熱意への理解と、それに応えようという誠意を感じることができた。私には、それ自体が、嬉しく幸せなことだ。
愚直でバカ正直なやり方だと、自分でも思う。でも、それでいいのだとも思う。心の底で公共工事の入札制度の不合理を痛感しながら談合を繰り返し、バレると心にもなくお詫びする大企業のコピーなんてヤナコッタ。
- 2005.05.10 もうすぐ10年
-
今年のGWはカレンダーにも恵まれ、売上は10日間で1千万円を超えた。かつて「鬼怒川店」初年度の年間売上が2千万円強であったことを考えると感慨無量だ。
別に、過去を懐かしんで自己満足にひたるつもりもないのだが、この1週間の間にも、TDnetに天下の大企業と肩を並べて開示情報が掲載されたり、週刊ダイヤモンドに間接的ながら紹介記事が載ったりと、これまでの歩みを実感できる事象が続き、隔世の感を禁じえない。
四半期報告書でも発表したことだが、いよいよ店舗展開のペースが上げられそうな状況になってきたし、今期は悲願の黒字転換も実現できそうだ。資金繰りの不安から解放されつつあるのも嬉しい。
7月下旬には、1号「鬼怒川店」オープンから丸10年になる。何か記念イベントでも、という案もあったのだが、旅籠屋らしく実質本位に徹し、支配人のアメリカMOTEL視察旅行をスタートさせ、その後、初めての全社会議を開くことにした。会社の原点とこれまでの歩みを確認し、次の10年に踏み出そうということだ。
朝日新聞の記事(小林慶一郎のディベート経済)で説かれていたとおり、「会社は外との関係では市場論理で利益を追求していても、内部は共同体的な倫理規範で運営されるべきものだ」と、私も感じている。
「社員が共同幻想を持てない会社は結局、よい仕事はできないし、利益も上げられない」そのとおりだと思う。矛盾するふたつの倫理規範をいかに調整し、止揚させていくか、それが経営者の描くべきビジョンであり、理念だと思う。
- 2005.03.23 質的変化
-
時の過ぎるのがはやい。歳のせいばかりではない。片付けるべき仕事が多くて心身両面で走り回っているせいだ。
嬉しいことに新規出店の話が次々に持ちかけられる。おかげで最近は出張の連続。車中の時間が退屈でもったいないから、ネット接続でき、仕事や打ち合わせのできる大きな車でも買おうかと話しているくらい。
事業のこうした拡大は、当然、質的な変化を会社に求めてくる。
社内マニュアルの充実、個人情報保護法対策を含めたリスク管理や管理体制の整備、前に進む以上の労力と時間を足元固めに費やしている感じ。
こういう作業は、ある意味後ろ向きの仕事だし、外からはうかがい知ることのできないことだから、会社が停滞しているように見えるかもしれないのがちょっと悔しい。
でも、功を焦って気を緩めたら取り返しのつかないことになる。とりあえず走って行ける所まで進んだ後で振り返ればよい、という考え方もあるだろうが、つまずいてころぶことは絶対にできない。
ニッポン放送の件で「会社は株主のものだ」という意見を「わけ知り顔」で語る人を見かけるが、株価を唯一の物差しにして企業価値を計る、なんていう考え方は私にはまったくない。
単なる言葉ではなく、心から顧客の満足、社員の生活、そして取引先との共存共栄を大切に考えたいというのは私の譲れない信条だ。
とくに、毎日現場で働いている社員の立場を他の誰が責任を持って考えられるというのか。人の尻馬に乗る無責任な「世論」や「進歩的な」知識人なんかに影響されて借り物の「正論」になびく経営者がいるとしたら、そんな人間、私は嫌いだ。
おっと、話が脱線した。
私はニッポン放送の新株予約権発行差し止めの決定を当然だと思うし、株主を軽視しているわけでもないので誤解されては困る。本題は質的変化が求められてアレコレやるべきことが多くて忙しい、という話だった。
質的変化というと、「ファミリーロッジ旅籠屋」という宿泊施設の将来像についても社内で議論する機会が増えている。
都市型の店舗は郊外型と形態を変えるべきなのか、3階建て4階建てはどうか、客室数を増やすのはどうか、部屋の広さは、料金設定は・・・などなど。こうした戦略的なテーマを議論できるようになったこと自体、感慨無量なのだが、すぐに延々と議論が続いてしまうのは悩ましい。
奥が深くて、普遍性のあるテーマなので、その内容は、日をあらためてじっくり吟味することにしよう。
- 2005.02.04 歯がゆい
-
第2四半期報告書をリリースした。売上げは堅調に伸びているのだが、通期の利益予想は下方修正。毎回1日でも早くリリースすることを心がけているのだが、期待を裏切るような内容になる時はさすがに筆が重い。経過勘定の処理が年々厳密になって単純な前年比較が難しくなったとか、店舗が増えたからとか、まったく言い訳にもなんにもならない。固定経費の見積もりが甘かったなんて、恥ずかしい限り。我ながら情けない。歯がゆい。
きのう、野村證券主催の「株式公開セミナー」を聞きに行った。時々、こうした無料セミナーの案内をもらうことがあり、これまではひとりで参加していたのだが、「そろそろ共通認識に」と考え、3人で出かけた。取引所の人の話は型どおりだったが、上場コンサルや監査法人の実務担当者の話は結構生々しくて面白かった。「形式基準を満たして公開にこぎつけても、その意味を理解していない経営者が多く、そういう企業はつまずく」という指摘には説得力があった。具体的なチェックポイントの指摘もあったが、グリーンシートが実践的な上場準備の場になっていることを再認識。しかし、もう5年だぞ。歯がゆい。
>
トップページで告知しているから周知のことだが、昨年秋、ある不動産投資会社から「湾岸店」具体化のための高額の資金提供の申し出を受けた。湾岸への出店は何年も前から夢であり、ほんとうに願ってもないチャンス。目の色を変え、汗をかき、知恵を絞って東奔西走しているのだが、3ヶ月間が過ぎても用地決定に至らない。「建て貸し」とは異なり、「売り地」を探すのは容易だと考えていたが、さまざまな理由があって東京湾岸は例外なのだ。これとは別に、SPCや証券化による出店スキーム構築の提案も受けている。これも願ってもない話し。間違いなく、湾岸店はその具体化の突破口となる。株式公開のためには将来性を約束する事業計画が欠かせない。責任ある事業計画には計画的出店を可能にする「手法」が必要。扉の前に立っているのに右往左往している。歯がゆい。
まぁ、しかし、これまでも開くはずのない扉をいくつも通ってきた。だから、きっといつかは開く。しかし、いつかではなく、今すぐ開けたい。扉の向こうの世界を見たい。あ〜歯がゆい。
- 2004.12.03 アメリカMOTEL視察
-
11月23日の勤労感謝の日が終わると、年末年始を除き、春まではもっともお客さんの少ない季節だ。そのタイミングを狙って、本社スタッフにアメリカMOTEL視察に行ってもらっている。こんな商売をやっていながら、じつは大部分の社員はアメリカのMOTELの実体験がないのだ。もう何年も前からこういう機会を作りたいと考えていたのだが、経済的にまったく不可能だった。今も余裕があるとは言えないのだが、資金繰りを左右したり、黒字計上に支障をきたす状況ではなくなった。留守を守りながら、ようやく念願がかなった幸せをしみじみと感じている。
12年前、初めてMOTELを泊まり歩いた時に受けたカルチャーショックを今でも覚えている。サービス業というイメージからかけ離れた、素っ気無い宿。1室20ドルというクラスになると建物も部屋も、そして人間もけっして上等とは言えず、なんとなくわびしい印象を受けたものだ。ところが、慣れてくると、あえて飾ろうとしない、こちらのご機嫌をとろうとしない開き直りが快く感じられるようになった。より高級に、よりゴージャスに見せようという「みせかけ」を追わないだけ、ウソがない。設備が劣り、建物が古びていれば、それなりに料金を安く設定する。かといって、卑屈になっている風でもない。「俺のところは、こんなだけど、まぁ見かけほど悪かないよ。ちゃんと快適に眠れるし、シャワーだって部屋についてるぜ。何より安いのがサービスだろ」って胸を張ってる。なんだか正直で潔い。こっちも割り切って泊まるから余計な期待をしない。高級志向のホテルと違って、「どうだ、凄いだろう」という押し付けがましい威圧感が微塵もないから、やけに気楽な気分になってくる。
今頃は、2軒目のMOTELでの朝。時差ぼけも治まり、右側運転にも慣れて、そろそろ旅気分にひたれるようになった頃だろうか。同じ宿に泊まり、同じ旅をしても、感じることは人それぞれだ。だから、彼らが私と同じような感想を持つことはないかもしれない。それはそれで良い。ただ、今後の「旅籠屋」の事業展開にあたって、リアルな体験を共有しながら話しが出来ることは大きなプラスになるに違いない。そう、旅ばかりは実際に行かなきゃ味わえないものなのだ。
来年からは、各店舗の支配人にも、順次出かけてもらう予定だ。なんだか、私も、やっぱりまた行きたくなってきたぞ。
- 2004.08.22 埋められない穴
-
きのうの昼過ぎ、愛犬マギーが遠いところに行ってしまいました。無念です。悲しいです。
11年あまりの一生は「旅籠屋」の歴史と重なります。次から次にたくさんの思い出が浮かんできます。 両親の飼い犬ですが、半分近くは私と一緒に暮らしていました。会社設立の前後、狭いマンションの一室に預かった頃はまだトイレが覚えられず、汚物まみれになって毎日お風呂場で洗ってやりました。「鬼怒川店」がオープンして私がひとりで住み込んでいた頃はお客さんが来るたびにフロントに走っていって愛嬌を振りまいていました。東京に戻って今のビルに皆が集まって住むようになってからは各フロアーを行ったりきたりして心を癒してくれました。
いろいろと苦しかった毎日、邪気のない表情と仕草にどれほど救われたか知れません。それに比べ私はどれだけの愛情を与えてあげたのだろうか。やはり悔いが残ります。振り向けばいつもマギーがいた、そんな感じです。
8月に入ってから突然様子がおかしくなり、24時間交替でつきっきりの看病をしました。私も深夜から明け方近くまでオリンピックを見ながらそばに居ました。進行が速く、20日足らずであっという間に遠くへ行ってしまいました。
きょう、マギーはダンボールの棺に入れられ、荼毘にふされました。息をしなくなった時、冷たい骸になっていく時、焼却炉の中に消えていく時、驚くほどわずかの骨になってしまった時、何度も何度も声を上げて泣きました。どんなに愛しく思っても、もうなにひとつしてあげられません。空いてしまった穴を埋めることができません。
ペットロス、珍しいことではありません。 たかが犬のことでと笑う人もいるでしょう。でも、いつもそばにいた愛する者を失った悲しみは同じです。これからは、何を見ても何をしていても「彼女がそこにいたこと」を思い出し、胸が締め付けられるような思いに苦しめられます。時間だけが薬だと知っています。少しずつ、ほんの少しずつ、つらい思いが軽くなっていくのでしょう。
こういう時、つくづく歳をとるのはいやだなぁと思います。忘れられない悲しみが心の底にたまっていきます。そういう思い出が増え、だんだんと生きていくのがつらくなっていきます。人生とは大切な人を失っていくことだと聞いたことがあります。どうせそんな悲しみに囚われてしまうのなら、あくせく努力したり、前向きに頑張ってきたことに一体何の意味があったのだろうと空しくなります。
今、お別れを言う気には到底なれませんが、とりあえず「ありがとう」と心の底から言います。とてもとても心の優しい犬でした。 ほんとうに、ほんとうにありがとう。
- 2004.07.31 感動した
-
サッカー日本代表の国際試合は可能な限り全試合見ているが、今夜のアジアカップ準々決勝、日本対ヨルダン戦は忘れられない試合になった。
感動した。
テニスで言えば、3回のマッチポイントをリターエースではね返したようなものだ。サッカーの世界においてアジアの地位は低い。だから、世界的に見ると、あまり注目されていないのかもしれないが、間違いなく「奇跡的な勝利」として歴史に残るべき試合だったと思う。しかし、記憶されるべきは「大逆転勝利」という結果よりも、日本代表選手たちの戦いぶりだったと思う。
ホスト国にあるまじき地元観客の愚劣な態度には毎回頭に来ていたが、そういう環境の中でも感情を抑えながら最後の最後までひたむきに全力を出し続けた選手たち。陳腐な言い方だが、サムライという言葉が頭をよぎった。今日の試合を見た人の多くが、代表選手たちの「感情をコントロールする意志の力」に心動かされたと思う。相手を茶化したり投げやりな態度をとらないフェアな態度、四面楚歌の状況でも自分を見失わない冷静さ。仮に敗戦に終わっていたとしても彼らはツバを吐きかけたり、レフェリーに暴言を投げつけたりせず静かにピッチを後にしただろう。以前は、そういう物言わぬ「おとなしさ」が日本人の「ひ弱さ」に感じられることも多かったが、海外で「冷や飯」を食わされながら自暴自棄に陥らず精進を続けてきた選手たちの活躍は次元の違う「たくましさ」として伝わってきた。
日本という国や、日本人に失望することの多い昨今、久しぶりに日本人であることに誇りを持てた。 愛国心とか誇りというものは、学校で君が代を歌うことを強制したり、教育基本法にことさら言葉を足すようなことじゃないと思う。政治家も、企業人も、目先の保身や利益だけに振り回されず、周囲に迎合せず信じる道を進むべきなのだと、私はあらためて思ったしだいである。 敬意と共感こそが、誇りと愛情の強固な基盤になる。
日本人も捨てたモンじゃない。日本人の持っている国民性の良質な部分を確認できたようで、私はとても嬉しかったし、背筋が伸びた。
スポーツバラエティやワイドショーの次元で矮小化しないでほしいな。
- 2004.05.12 「旅籠屋日記」に関する考え方と今後の方針
-
過去1週間の書き込みにあるとおり、この「旅籠屋日記」の性格付けと書き込み内容について、株主の方から重要な問題提起をいただいた。直接いただいたメールおよび社内での意見交換を踏まえ、私の見解と今後の方針を説明させていただきたい。
■提起された問題の主旨と、これに対する基本的見解
提起された問題の主旨 これに対する基本的見解 個人と法人を明確に区別すべきである 経営者の個性や信条が企業活動を牽引し方向付けしていくことは否定されるべきことではなく、逆に他社との差別化や社会的な存在価値を高めていくために必須の要素であると考える。ただし、公私混同による私物化や利益相反行為を排除するため、自主的に一定のルールを設け、今後はこれに従う。 会社の業務に直接関連のない話題には触れるべきではない 企業の理念や事業のコンセプトは、業務の遂行をとおして具現化されるべきである。ただし、それらは本来抽象的な目的意識や価値観を含むものであり、その醸成のためにも経営者個人が具体的な業務との関連の中でしか語ってはいけないとは考えない。 社会的、政治的、宗教的なメッセージは掲載すべきでない 企業が事業活動を離れた政治的、宗教的目的を追求することは適当でない。しかし、企業が社会的存在である以上、その活動は一定の社会性、政治性を持つのであり、それを自己目的化せず、企業の理念や事業のコンセプト実現のために行うのであれば制約を設ける必要はないと考える。 事業の拡大や株式公開などにともない、経営者個人の発言は慎むべきである 不特定多数の株主を含めた利害関係者の増大と多様化に対する配慮、マスメディア報道などによる予期せぬ反応に対する慎重さが求められるが、部分的な反発や誤解のみを恐れた自主規制は本末転倒である。したがって、現時点では本質的な方針変更は必要ないと考える。ただし、批判や誤解に対しては速やかに対応し、理念やコンセプトを理解いただくよう最大限努める。
■経営者個人が、経営者であることを明示した上で行う個人的発言について守るべきルール
・ 会社の公式見解ではなく、個人的な意見であることを明示する。
・ 個人サイトに関する費用は個人が負担する。
・ 結果的にであっても、短期的にも長期的にも明らかに会社の利益を損ねる言動は慎む。
・ 発言の責任は、会社ではなく個人に帰することを認めたうえで行う。
■具体的対応
1.個人的な性格の強いコンテンツは、個人契約の別ドメインのサイトに移動する。
2.ただし、「旅籠屋日記」は「旅籠屋」の事業紹介やコンセプトを訴求する性格を持ち会社にとっての有用性が高いと考えるため、従来どおり「旅籠屋」サイト内に置き、会社の公式見解ではなく、個人的な意見であることを明示したうえでサイト来訪者が容易に閲覧できる状況を維持する。
3.「旅籠屋日記」は「旅籠屋」のコンセプトを生み出し実現しようとする創業社長のメッセージであり、名称の変更は行わない。
4.「旅籠屋日記」の書き込みについては、上記のルールに従い、個人的な利益につながる発言を行わず、たとえ結果的にであっても、短期的にも長期的にも明らかに会社の利益を損ねる言動は慎む。ただし、社会的、政治的な内容であることのみをもって利益を損ねるとは断定しない。
5.5月6日の書き込みについては、それ以降の書き込みによってその主旨を詳細に語っており、そのこと自体が「旅籠屋」の企業姿勢を表す面もあり、また利益を損ねていると断定できないため削除しない。
6.「旅籠屋の主人」というネット上の呼称は、前後関係なく発信され誤解と悪印象を生じる可能性を否定できないため、今後は用いない。
7.1は別ドメインの取得などに時間を要するため5月末までに、その他については即刻実施する。
以上が、数日間考えに考えた結果の結論です。結果的に、大きな変更はないように思われるかもしれませんが、問題提起の主旨と心情は理解したつもりで、おかげで曖昧だったスタンスは、より自覚的で明確なものになりました。話題の選び方や表現のトーンなどにも多少の変化が生じるかもしれません。私としても、結果として多くの誤解を招く「独りよがり」は本意ではないからです。たしかに今までのように気楽に無邪気に書くことは難しくなりました、かと言って当たり障りのないことばかりを書くつもりはありません。
もちろん、 今後、更なる問題提起によって、「旅籠屋日記」に関するスタンスをさらに見直すことも当然ありうることです。引き続き、率直なご批判やご意見をいただければ幸いです。
- 2004.05.10 思案中
-
前回の書き込みのあと、十数通のメールをいただいた。批判、助言、内容はさまざまだが、率直な気持ちのこもったものばかりで、ほんとうにありがたい。他の掲示板に寄せられている意見も「旅籠屋」を気にかけていただいてるからこそのものである。心から感謝している。ネットを使ったコミュニケーションの世界に出会ってもう10年を越えたが、必ずしも愉快なことばかりではなかった。しかし、このように多くの方と気持ちよく意見交換できるのは幸せなことだ。この場を借りて深くお礼を申し上げます。
さて今回提起された問題について、あまり時間をかけずに判断し、改めるべき点は改めていかなければならない。具体的には、
●5/6の書き込みを削除するかどうか。
●この「旅籠屋日記」そのものを削除する、あるいは私個人のサイトを作ってそちらに移動させるかどうか。
●「旅籠屋日記」というタイトルを変更するかどうか。
●「旅籠屋の主人」というパソコン通信の頃からのハンドルネームをやめるかどうか。
などの点について、結論を出さなければならない。しかし、その判断を下すためには、先例や通例にこだわらず以下のような問題について考えなければならない。
●会社と経営者個人の関係
●狭い意味での経済活動を超えて会社のカラーや意思表示をすることの是非
●立場や目的を異にする利害関係者(お客様、株主、経営者、社員、取引先など)の関係
●会社の発展(グリーンシートへの登録、公開市場への上場など)によって、おのずと考え方を変えていくべきなのかどうか
寄せられた貴重な意見を参考にしながら、以上のような問題を思案している最中だが、連日の睡眠不足もあり、いま少しの時間をかけて結論を出したいと考えている。
ところで、さまざまな意見に触れながら、感じたのは、やはり私の言わんとしたことがそのとおり伝わっていないこと、ポイントのずれた指摘が少なくないことだ。
例えば、私はイラク問題を取り上げてはいるが、言いたかったことは政治的なことではなかったし、いわんやイデオロギーなどとは無縁のことだった。語弊を恐れずに言うが、多くの人の感受性の中に一種の「アレルギー」のようなものがあるのかもしれないということを強く感じた。
「国は等しく国民の生命と財産を守る義務を果たすとから国であり得るのではないか。とすれば自己責任論は大きな勘違いではないか・・・そのことの是非はともかく、感情的な好き嫌いではないそういうレベルでの本質的な議論が必要ではないか。」というのが、私の主旨だったのだが、これに正面から応えていただいたメールは1通だけだった。
高校生だった頃、世の中に対して批判的なことを言うと、父から「子供のくせに生意気言うな。国があるおかげで、生きていられるんだ。オマエはアカか!」などといきなり怒鳴りつけられて、それ以上は、何も言えなくなるような経験をよくした。その時に感じたある種の情けない気持ちを今回もかすかに感じてしまった。
多くの人の中には、社会問題について真剣な議論をすることに対する警戒心というか、嫌悪感というか、ある種の「生理的なアレルギー」というようなものがあるのかもしれない。異常に身構えて、感情を高ぶらせてしまうような感じ。天下国家を論じることは、本来、恐ろしいことでも、畏れ多いことでも、常軌を逸したことでも、やばいことでもないはずなのに、みんな何かタブーだと感じているみたい。だから、日本人は口論はできても創造的な議論ができず、論理的な思考が苦手なままで、新しい異質なものを理解して受け入れるのに消極的。私はそういうことにいらだっているわけだが、アレルギーはおそらく無意識の感覚なので、「思考停止、偽善、事なかれ主義、自己保身」などと叫んでも反発を買う結果にしかならないのかもしれないという気がしてきた。
私は、タブーなしに議論することが当然のことだった時代の洗礼を受けたが、そういう感性を持つ人間はとても少数派なのかもしれない。「国家とは何か」なんて話しは、教師はもちろん、友人ともしたことのない人が圧倒的に多いのかもしれない。そういえば、許認可をもらう役所で、「法律の目的に立ち返って話しをしましょう」なんて噛み付くと、役所中の人が驚いた顔をして静まり返る。残念ながら、そういうことなのかもしれない。
もしそうだとしたら、それはとても由々しきことだが、私の書き込みが独りよがりだという批判も理解できないではない。逆効果を招く無理押しをしていたのも言えるからだ。
こんな書き方をすると「尊大な言い方をするな!」と叱られてしまいそうだが、これはアレコレ考える中での私なりの反省のひとつ。自分の言いたいことを正直に言ったつもりでも、多くの人に誤解されてしまうのであれば、言い方を変える必要があるのかも。そういう点を含め思案中である。
- 2004.05.07 「旅籠屋日記」の削除について
-
昨日の書き込みに関して、株主の方々からのいくつかの厳しい批判を目にした。
感情的な反論はともかくとして、「会社のホームページなのだから、業務に関係のない個人的な思想信条や社会的、宗教的、政治的な話題を載せるべきではない。公私混同ではないか」という指摘については、私自身がかねてより気にしていたことでもあり、真摯に受け止め、自分の考えをまとめてみるべきだと思った。
本来言う必要のないことであることを承知で初めにことわっておくが、私は政治党派や宗教に属したことはなく、特定の政治イデオロギーを信奉しているわけでもない。あくまで、個人として日々感じ考えたことを書き連ねているだけである。昨日の書き込みも、政治的な主張をするつもりはなく、「常識」にもたれかかって「正論」を振りかざすような思考のあり方や感性に反発を感じ、この気持ちを表明したいというのが主旨だった。この日記の以前からの「読者」なら感じてもらえると思うが、私は結果としての主義主張の違いではなく、その過程で「偏見や先入観や表面的な規則や多数派の常識」にこだわって新しいもの、変わったものを排撃しようとする人たちの思考停止に逃げ込む体質に異議をとなえてきた。それは、「ロードサイドホテル」という先例のないビジネスを産み育てる中で味わってきた情けない思い、やり場のない怒りをぶつけたかったからだし、書くことで挑戦し続ける自分の思いを再確認する原動力にもしてきた。
結論が違うのはよい。ただ、感覚や感情ではなく本質的なレベルに踏み込んで議論する姿勢を共有したい、そういう思いを繰り返し言ってきたつもりだ。何か政治的な目的や魂胆があったわけではまったくない。単に私がそういうことに無性に腹の立つ人間で、黙っていられなくなる性格だった、それだけのことだ。実際、拘束された人たち自体を直接非難も擁護もしていないし、自衛隊派遣の賛否にも触れていない。とりあえず私の言いたいことはその点にはないからだ。
「旅籠屋日記」は7年前、このホームページ開設と同時にスタートさせた。当時は、たった1軒だけの小さな宿(「鬼怒川店」)のオヤジで、住み込んでいるのは私一人。「こういう事業を始めた自分という人間の心情を吐露したい。どこかの誰かと微かにでも接点を持っていたい。聞いて欲しい。」という「公開日記」というような感じだった。ところが、グリーンシートに登録して株主が増え、事業も少しずつ拡大した頃から、「個人的な思い」をこの場に載せることに、私自身迷いや懸念が生じてきた。実際、外部から批判を受けたこともある。
だが、「日記と書き、独り言としている以上、これを会社の公式見解と受け取る無粋な人はいないだろう」と深刻には考えなかったし、「自己規制せず本音を書いて欲しい」という声もあって、なんとなくこの状況を変更しないできた。
しかし、今回指摘されて考えたことだが、仮にどこかの企業の社長個人の「日記」が公開されていて、その中で「勧告を無視してイラクに行くような人間は非国民だ」というような断定的な書き込みを見たら、少なくとも私はその企業の商品を買いたくなくなるかもしれないと思った。その企業が大規模な会社で社長がたんなるサラリーマン社長と思える存在だったら、会社と所長個人は別と納得しやすいが、彼が創業社長で彼の個性がその企業のカラーを体現しているような場合、間接的にでもその社長個人を利するようなことはしたくないと感じるだろうと思った。これは、その「日記」が会社のサイトとは別の個人サイトにあったとしても、おそらく大差ない。
ひるがえって、旅籠屋の場合どうだろう。後者であることは自他ともに認めるところだ。とすれば、私の言動は会社の印象に大きな影響を与えるに違いない。理屈はともかく感情的にはそうだ。重ねて言うが、私は既成の価値観に盲従しない姿勢というものを訴えたかったのだが、具体的な社会現象や事例をあげて語らざるを得ない限り、社会性や政治性から完全に逃れることはできないし、冷静に主旨を読み取ってくれる人たちばかりとは限らない。
とすれば、「旅籠屋日記」は閉鎖してしまうしかないように思う。会社のサイトはもちろん、私が「旅籠屋」という会社と関連して見られる限り、個人サイトにおいても「個人的意見」を述べることはやめたほうが良いように思う。
思い返してみれば、私がこの事業を構想し具体化しようとした動機は、「お仕着せを受け入れるのではなく、自分なりの価値観で旅や人生を選んでいくような世の中になって欲しい。そうすれば、日本はもっと自由で生きやすい国になるに違いない」という思いだった。「シンプルで自由な、旅と暮らしをサポートする」という創業理念にこめた願いはそういうものだったし、「旅籠屋」が増えることはその物理的な基盤と感受性を醸成することになると信じてきた。それは、今でも変わらない。既存の価値観への反発は、「旅籠屋」の事業を推進するエネルギーであった。私にとって「旅籠屋日記」への書き込みは「旅籠屋」の事業そのものの理念に通じていることをあらためて自覚した。
当たり障りのないことを書けばよい、という意見もある。少し考えてみたが、きっと当たり障りのないことなど、あえて書く気は起きないと思う。個人サイトに書けばよい、という意見もある。しかし、それは上に書いたとおり、形式的には良くても、実質的には私がリタイヤしない限り、似たりよったりのことだと思う。
「とても代表取締役として信任できない」と言われ、「会社のホームページの乗っ取り」「私物化」と決め付けられる。情けない。こうして、創業者は会社の成長にあわせて口を封じられ、邪魔者扱いされていくのか。「業績に悪影響を与える」という「正論」の前で、企業は利益以外の存在価値や社会的存在を積極的に語れなくなっていくのか。こうしていつのまにか会社は無色透明になり、人畜無害になっていくのか。コンセプトを語らない「旅籠屋」って何なのか。・・・正直言って、そういう感情もある。
しかし、今や旅籠屋という会社の利害関係者は数多い。5年前、公募増資に応じた株主の人たちに報いたいとずっと考えてきた。苦々しい思いで「旅籠屋日記」を読んでいる従業員もいるはずだ。両極端を選ぶことが解決策ではないのだろう。バランスの取れる場所があるかもしれない、しばらく多くの人の意見を聞き、自分自身の心の中をのぞいて考えてみようと思う。
正直言って、迷い悩んでいます。どうぞ、率直なご意見をお聞かせください。直接、私宛のメールでお願いします。
それまでの期間、経緯を理解してもらうためにも「旅籠屋日記」はこのまま公開しておきます。
- 2004.05.06 「正論」には同調しない
-
イラクで拘束されていた日本人が解放されて半月が過ぎた。ワイドショー番組が嫌いなので、家族たちの当初の言動を見聞きしていないが、その後にわき起こった異様な「世論」の盛り上がりや政府高官の発言には強い違和感を感じた。前もって言っておこう。私はこういう「世論」に組しないし、「自己責任論」にも賛成しかねる。
国の方針に反した行動をとるなんて自由の履き違えで、自分勝手だ。再三の退避勧告を無視して入国したのだから自業自得だ。自衛隊撤退の交渉の材料にされ、結果として国全体を難しい立場に追い込んだくせに、「残りたい」とか「また行きたい」なんて非常識だ。「戦争中」の国に行ってボランティアなんて、そもそも考えが甘いのではないか。世間知らずの未成年のくせにこんな行動をとるなんて親のしつけがなってないのではないか。助けて欲しいという気持ちはわかるが、声高に政府の方針を批判する家族の発言は自分勝手だ。自由には責任がともなう、救出にかかった費用は、当然負担すべきだ。・・・「自己責任」を強調する「世論」の大筋はこんなところか。
こうした発言の多くは、ちょっと聞くと道理にかなったことのように聞こえるし、当人は常識をわきまえた良識人としての心地よさを感じているだろう。しかし、「常識」にもたれかかったような「正論」は、疑ってみる必要がある。自分が彼らの立場だったら、自分の家族だったら、彼らが政府の職員だったら、有名企業の社員だったら、医療援助のスタッフだったら、・・・など、要素をいろいろと置き換えてみると感じることが違ってくる。もしかしたら、多数派に同化しようとする事なかれ主義、自分を棚に上げて人を批判する偽善、多数派に迎合しない頑固者を「村八分」にする卑劣な自己保身、そういう無意識が隠れているかもしれない。感覚的に「心地よい」結論に逃げ込む前に、根拠のない先入観や偏見にとらわれて自分の感覚が汚染されていないか、まず自覚的に心の中をチェックしてみる必要があると思う。それは例えば、以下のようなことだ。
●独自に活動しているNGOメンバーやフリージャーナリストを不可解な人種と考え、公職にある人よりも信用できないと思い込んでいないか。
●大きな組織の判断や行動は誤りが少なく、その命令に従って行動している人間は正しい。組織に頼らず個人の自由意志で行動している人は思慮が足りず身勝手だと決め付けていないか。女性や未成年者を自立した人間ではないと蔑視していないか。
●外国とのつきあいは政府や企業など、広く認知された組織の人間が「責任」を持って行うべきことで、個人や任意の民間団体がしゃしゃり出るべきことではない、と断じていないか。
●政府や企業が行えないこと、行おうとしないことを行い、隠していることを正せるのは一体誰なのか。利害に影響されない純粋な人道的な支援や、人間同士の交流や情報交換を行うことは非難されるべきことなのか。
●国を「家庭」の延長のようにみなしていないか。国家と国民の関係を、任意の契約によって成立している組織と個人の関係に置き換えて混同していないか。。
●国家の最大の義務は国民の生命と財産を守ることだが、国策に沿わない人間はその対象から除外してよいと解釈していないか。為政者に都合のよい選択権を与えてよいのか。
●少数意見の尊重という理念が、なぜ民主主義の本質のひとつであるとされるのか、その経緯や歴史の教訓を忘れていないか。
私も、知らず知らずのうちに偏見と先入観に染まっている人間である。だから、上に挙げたことの多くは、私自身の心の中にある意識でもある。周囲の多くの人が似たような意識を持っているなら、それに同調して「みんなが言ってること、無理ないよねぇ」と認めて「常識」や「良識」に埋もれてしまいたい誘惑も感じる。
私はNGOで活動している人たちと直接の面識がない。だから、中には信用の置けない「にわか人道主義者」や、自分勝手な「偽善者」や、思慮の浅い「世間知らず」がいる可能性を否定しない。同時に、周囲の反対に負けず、安穏な生活を犠牲にして信念を貫こうとする志や勇気を持つ人達がいることも否定できない。今回の事件に巻き込まれた人達がそのどちらかはわからない。しかし、それはどちらでも良いことだ。
私が考えたのは次のようなことだ。
●自分と異なる言動を実行する人の存在は愉快ではない。まして、その結果が少しでも自分に影響を与えるとしたら、その言動を封殺したくなる。しかし、自分が逆の立場に立つことだってある。正しいと思って行動しているのに多くの人から理解されないこともある。偏見や誤解を受け、数を頼んだ脅迫的な批判にさらされることもあるかもしれない。自分だけならともかく、関係のない家族や友人知人までが偏見を持って白眼視されるかもしれない。プライバシーが暴かれ、さらし者にされるかもしれない。だから、他人を批判するには、正確な情報にもとづく理解や冷静な議論が必要である。その機会を確保するために、たとえ非常識に思える意見であっても、その表現と行動の自由は最大限保障されるべきだ。圧倒的多数が少数を押さえつける状況は、取り返しのつかない先例を認めることになる。
●儒教の影響かもしれないが、日本人には独特の集団帰属意識があり、個人を犠牲にして集団の利益に従うことを美化する傾向がある。しかし、組織というものは矛盾を孕んだ存在であり、権威や権力は一人歩きして必ず誤りを犯す。組織の規律や意思決定システムは尊重すべきだが、個人の異議申し立てや逸脱した言動の余地を残すことは絶対に必要である。組織や集団に従う犠牲的精神は密かに抱くべきものであって、強要すべきものではない。
●我々は自由意志によって国と任意の契約を結んで国民でいるわけではないし、町や村の住民であるわけでもない。国家や共同体についての素養がないので、論理的で説得力のある見解を表明できないが、自由意志で選択できる企業や集団と混同できないものだと感じている。気に入らないなら国籍を捨てろ、他へ引っ越せというのは暴論である。国家や自治体は同じ目的を共有する者たちの共同体ではないし、為政者は慈愛あふれる保護者でもない。国は「国民の生命と財産を守る」義務を負っているからこそ、絶対的な権力で国民に法律の遵守や納税の義務を課すことを認められているのだと私は信じている。だから救出活動に人と金を使ったのは当然のことであって、費用を求めるなどということは論外のことだ。加えて、「生命と財産を守る」相手は、国民等しくであって、その思想信条や属性はもちろん国の政策に反対か賛成かによって異なるべきものではないと思う。助けを求められるから助ける、という性格のものでもないし、助けてあげるという擬人的な行為でもない。重ねて言うが、国は「国民の生命と財産を守る」義務を果たすと信じられているから国であり得るのではないのか。人質のために救出するのでなく、国が国であり続けるために救出活動を行う、そういう性格のものだと理解しているが違うだろうか。だとすれば「自己責任論」を語る政治家や政府高官は、何か大きな勘違いをしていないか。
●以上のことを前提に考えれば、国民全体に不利益をもたらすことが明確であるような特殊な場合を除き、個人が国の政策に沿わない行動をとることを非難したり禁止すべきではないと思う。今回のイラク問題のように国論を二分するような問題の場合はなおさらである。したがって、たとえ戦時下や紛争中の国や地域であっても、退避勧告が出ている場合であっても、個人がその判断で赴く自由を禁止すべきではないし、それが、人道的支援や報道目的によるものであれば、その勇気と決断には最低限の敬意を払うべきだと思う。
ここまで書きながら、問題は「国家とはなにか」という点に集約されることに気付いた。戦前の日本は「家」を拡大した集団として語られていたようだが、それは明らかに欧米の近代国家とは異質の性格を持っていたようだ。今回、国内で沸き起こった「自己責任論」に対し、欧米諸国から驚きと違和感が表明されたのも国というものに対する意識の違いがあるからかもしれない。欧米型の国家が唯一の国家形態だという前提を設けるつもりは毛頭ないが、政治家にはこうした次元の議論をして欲しいと思う。国家とはどのような存在なのか、何のために存在するのか、国民との関係はどうあるべきなのか、我々日本人が曖昧ななままにしてきた問題をわかりやすく説明して欲しい。その点を抜きにして憲法改正論議を進めるわけにも行かないのではないか。
余談だが、今回、空港にまで出かけていって「自業自得」などという個人批判のプラカードを掲げた人がいたのには驚いた。意図的な示唆行動なら別だが、そうでないならあまりにも幼稚で短絡的じゃないか。彼らは、いつも世の中が自分の味方だと思っているのだろうか。自分が少数派の立場に追い込まれた時「自業自得」の看板が自らに向けられる前例を今作っていることを自覚しているのだろうか。あと、政府高官が個人を批判し「責任」を求める発言にも驚いた。それはとてもアンフェアで非常識なことだという自覚はないのか。信じられない。
長くなってしまった。「正論」に同調しない書き込みは気を遣う。言葉尻をとらえて、感情的な批判が帰ってくるプレッシャーがある。「正論」の持つそういう圧迫感が息苦しい。しかし、黙っているのは自分らしくない。「長いものや声の大きさに負けるくらいならベンチャー経営者失格だぞ」と大げさに突っつく従順でない自分に負けた。
- 2004.05.04 ゴールデンウィーク
-
随分と間が空いてしまった。去年の暮れから「戦略経営者」という雑誌に駄文を連載しており、表現エネルギーを消費してしまっている影響もあるが、私生活の面でも「アレもコレも、やらなくちゃ」という気持ちが大きくなって、ゆっくりと文章を書く気持ちのゆとりがない。日記を書くよりも、読みたい本を読んだり、買ったままになっているパソコンソフトを使えるようにしたり、ハモニカの練習をしたり、そういうプレッシャーが強い。でもやっぱり、仕事のことが頭から離れないのが最大の理由だ。
10日ほど前に1年半ぶりの新店がオープンした。7月オープン予定の店も順調に建築が進んでいる。その後の出店計画も具体化しつつある。10店舗になるのも遠くないだろう。
しかし、店舗が増えれば心配の種も増えるわけで、このゴールデンウィーク期間中も、各店の状況が気になって落ち着かない。さきほど、ようやくGW最後のチェックインが確認できて、ようやく心に平穏が訪れた。久しぶりに「日記」を書く気分になったというわけだ。
5月1日から4日間、ありがたいことに全店満室になった。早くから予約で満室になっていた店も多いが、実際はキャンセルによる入れ替わりが多く、中には予約しながら現れない「No Show」もあって、当日チェックインを終えてしまわないと安心できない。最後のお客様を迎えて、ようやくホッとしている支配人の気持ちが伝わってくる。満室が続くと客室の掃除も肉体的にたいへんだが、それ以上に頻繁に起こる予約変更への対応やNo Showやオーバーブッキング発生の不安に対する精神的プレッシャーは経験したものでないとわからない。その意味で、各支配人には「ほんとうにお疲れ様でした」と心から言いたくなる。「任されている」というのは良い面もあるが、他に頼れないという重圧もある。何と言っても旅籠屋を支えているのは支配人の責任感と忍耐力。とにかく、素直に感謝。あした掃除が終わったら、ゆっくり一服してください。
この2月、延ばし延ばしにしていた健康診断をついに受けた。10数年ぶりのこと。一部再検査を受けたりもしたが、深刻な異常はないようでほんとうにホッとした。ストレスや運動不足による生活習慣病の兆候はあるらしいので、GWは意を決して毎日プールに通って泳いでいる。あしたはいよいよ最終日。心身ともに健康でいることが私の最大の務めなのだ。
ほんとうは、前から書きたいことがあったが、重たいテーマなのでそれは今度。今夜は、束の間の「充足感」にひたっていよう。
- 2004.01.27 「常識人」の偽善
-
前回、「異常」を「正常」にできると書いたが、それは出来る限り予断や偏見にとらわれないで物事や人物を見るぞ、世の中の色メガネを少しでも透明にするぞというような意思を表明したつもりだった。
店舗数が増え、延べ利用人数も20万人近くになって、最近でこそ「旅籠屋」の説明に苦労しなくなったが、10年前、「鬼怒川店」を準備している頃は随分と情けない思いをした。日本ではモーテルというとラブホテルの代名詞になっているので「アメリカに無数にあるロードサイドの素泊まりのミニホテルです」と説明するのだが、彼の地のモーテルを利用したことのある人は稀で、言葉の端々に「そんなこと言っても、結局ラブホテルじゃないの。よしんば違うスタイルを目指しても結果的にラブホテルになってしまうんじゃないの」という疑念や警戒心が透けて見えた。出店用地を探そうにも不動産屋には相手にされず、旅館業法にもとずく営業許可申請を出した保健所では喧々諤々の論争になったりした。「『施行細則』や『通達』の枝葉末節を機械的に押し付けるのではなく、法律の趣旨にもとづいた判断をすべきじゃないですか」。信じられないかもしれないが、そこにはフロントカウンターの大きさまで書かれてあったりするのだ。冗談じゃない、そんなことは役所が決めることじゃない。「そもそも法律が想定していないスタイルの宿泊施設なので判断できないというのなら、県の保健衛生課であれ、中央の厚生省であれ、行くとこまで行って話しをしようじゃないですか」と声を荒げたりしたものだ。
しかし、そんな話しをしながら、私の中ではもうひとつ大声で叫びたくなることがあった。「しかしですねぇ。『旅籠屋』は該当しないにしても、そもそもラブホテルのどこがいけないんですか。防火や防犯について問題があるとすればその点を規制すればよいことで、SEXを目的に利用すること自体は何ら不自然なことではないし、それはプライベートなことじゃないですか」。公序良俗とか風紀とか、そういう「常識」に寄りかかり、当然のように押し付けようとする法律や役人の態度が我慢ならない。
世の中の「常識」というものは、長い間に醸成された文化の一部だし、集団のアイデンティティを保つ合言葉のようなものだと思う。だから、単なる合理性だけで判断してはいけないし、一定の敬意を払う必要があるとも思う。だがそれは、時代の変化の中で必ず形骸化し、偽善という形で個人の行動や思考を束縛する。可能性を開く自由の頭を押さえつけ、リスクを承知で新しい価値を生み出そうとする勇気の足を引っ張って踏み絵を踏ませる。
人間、年を重ねて経験を積めば、必ず「常識」で重くなる。年長者の「常識」は、必ず若い世代の「非常識」を排撃しようとする。世の中、心地よい結論を先に決めておいて、「常識」を総動員してくどくどと説教するオトナが多い。間違いなく、私もそのうちのひとりだ。だからこそ、出来る限り、思考停止に陥らず、自覚的でいたい。そう自分に言い聞かせているというわけなのです。
- 2004.01.21 人間は、みんな「異常」
-
私は、テレビのワイドショーのレポーターが嫌いだ。何か事件があると、近所の人から「おとなしい、いい人だったんですけどねぇ」などというコメントをとって、「何が、彼を異常な犯罪者に変えたのでしょう」なんて、自分たちとは異質の人間のように言う。冗談じゃない。そもそも「正常な人」なんていない、つーの 。ワイドショー正義感が多くの人を思考停止にし、世の中を悪くしていると、本気で信じているくらいだ。
私は、これまで、多少の逸脱はあったにせよ、基本的に普通の場所で、平凡に生きてきたと思っている。周囲の目を気にする、臆病な小市民のひとりだ。少しだけ平均値と違うとすれば、わがままで、自分勝手で、こらえ性がないから、「俺はこうしたいんだ。なぜ思い通りにならないんだ。世の中の方がおかしいんじゃないか」といつまでも駄々をこねるというところぐらいか。そんな、「平凡な私」でも、出会ってきた人間たちは、自分自身を含めて、それはそれはいろんな人がいたし、いろんな面を見せられてきた。
前にも書いたが、スポーツ選手であれ、ミュージシャンであれ、政治家であれ、個人の人間力をベースに大衆を相手に事をなす人というのは、「異常な」負けず嫌いであり、「異常な」自信家である、私はそう思っている。「平凡な」サラリーマンや主婦であっても、ねたみや嫉妬の炎を燃やしたり、退屈な日常や未来から逃げ出そうと「自分でも驚くような妄想」にふけることは珍しくないと思う。陳腐な言い方になるが、「正常」と「異常」は連続しており、誰の心の世界も、驚くほど広く、深く、、そして暗い。平凡に生きてきた私が、なぜこういうことを断定的に言えるのか、と自分でも不思議なのだが、それは子供の頃、今でも信じられないような激しい姑を見ながら育ったせいかもしれない。
サラリーマンの時はラクだった。イヤイヤでも、毎朝目覚ましがなって規則正しく一日が始まり、会社には自分の席と仕事が用意され、とりあえず利害を共有する見知った顔が並んでいた。良くも悪くも結果が出て、ボーナスや昇進で評価が確認できる。屋内競技場のようなもので、叫んだ声は必ず誰かの耳に届き、こだまして返ってくる。あらかじめ線の引かれた走路があり、それは閉じている。もちろん、家に帰っても同じこと。夫やお父さんという立場と義務があり、不自由だがやるべきことは「常識」が教えてくれた。
屋外は違う。一人暮らしの学生時代はそうだったかもしれない。もっと自由だったが、孤独で、どうしてよいかわからなかった。ノイローゼになりかけた。会社勤めを辞めてからも、少し似たような状況があった。
自殺する人が多いらしい。精神を病む人も多い。「異常な」犯罪も増えているという。でも、本来、人間は何でもできる。どんな「異常」な人間にもなれる。「正常」に生きているのは、たまたまそういう環境に身を置いている、置かされているからに過ぎない。そのことに気づいていないらしい人が多いのは、考えたらそれこそ何より「異常な」ことだ。養老さんの言う「死」と似た面があるかもしれない。だから、私は用心深いし、臆病だからこそほんの少しは「異常」を「正常」にできる人間だと思っている。新年早々、へんな日記になったな。
- 2003.10.28 ダイエー優勝、おめでとう
-
西鉄ライオンズが消滅してから、巨人嫌いは続いているけれど、とくに贔屓の野球チームというものは無くなってしまった。しかし、今回の日本シリーズ、一応福岡県出身の私としては自然にダイエーを応援する気持ちが湧き上がってきて一生懸命声援を送った。やったね、日本一おめでとう!
東京育ちの人と話していると、九州を全部一緒くたに見ているのを感じるけれど、とんでもないことだ。私は北九州の出身だから、「博多とだって文化圏が違うんだよ」と言っても理解してもらえない。東京だって、浅草と中野じゃ違うだろうに困ったものだ。
12歳の終わりに東京に引っ越してきた私には、地方出身者と東京育ちの人の気分の両方が理解できる部分がある。方言を笑われたくなくて神経質になっていた気持ちも覚えているし、中心地にいる心のゆとりみたいなものもわかる。劣等感と優越感。しかし、それも遠い昔の話し。もはや東京と地方の違いなんて、ほとんど無くなってしまっているのかもしれない。
- 2003.10.13 読書の秋
-
待望の3連休だったが、どうも風邪を引いたらしく、テレビを観る(F1、ラグビー、サッカー、MotoGP)以外はほとんど寝ていた。いくら眠ってもすっきりしないのだ、きょうは、かなりよくなったけれど、生憎の雨なので、珍しく本を読んでいる。雑誌を除くと、滅多に本を読まないのだが、先日買った「会社はこれからどうなるのか」は、なかなか面白い。東大の経済学部の教授が執筆した本だが、インタビューを元にしているせいか、とてもわかりやすい。経営者の端くれとして、自分の経験や立場に引き付けて読めるので、どんどん興味が湧いてくる。
10代の頃は、難解な哲学書などをむさぼるように読んでいた。残念ながら集中力や理解力の低下は否定できないが、当時の読書姿勢は生きている。「単なる知識にせず、自分の問題として、考え抜く」ということだ。言い換えれば、「自分をいじめる」ということ。
最近、直接間接に「旅籠屋」について、批判や疑問をぶつけられることがある。総じて日本人はディベートの訓練が出来ていないから、すぐに感情的になってしまう。ネット上の匿名の意見交換の難しさもある。個人的には、弁解したいこと、反論したいことはあるが、経営者としては「沈黙」するしかない。こうして会社のホームページに個人的な「日記」を掲載していることがギリギリの線だ。
真摯に受け止め、言葉ではなく、実際の会社の活動で応えていく、そう自分に言い聞かせてます。所詮、切実さが違うもの。
(誤解のないよう、最後の言葉について主旨を補足しておきます・・・公開の場で批判される側の我々にとっては、ひとつひとつの指摘が深刻かつ重たい意味を持ちます。加えて、すでに取り返しのつかない汚点になっていたり、一朝一夕に解決できない問題であったりすると、その批判が正しいものであればあるほど、もどかしく感じます。この二つの意味で、彼我の立場の相違を理解いただきたいと思います。無視したり、軽んじたり、できないから切実なのです)。
- 2003.10.07 感傷の秋
-
とうとう梅雨の明けなかった8月、残暑の9月が去り、10月になった。気温が下がり、さわやかな風が吹き、空気が澄んできて、夜が早くなった。
秋だ。
草木が芽吹く春が一番好きな季節だが、秋も悪くない。しかし、気をつけていないと、メランコリックな気分に悩まされる。思春期の少年たちの父親よりも年くってるくせに、何が「感傷の秋」だと笑われそうだが、たぶん、生理的にそういう体質なのだろう。日照時間のせいか、気候のせいか、毎年この季節になると妙に物憂い気分にとりつかれる。こんな夜は、徒然に日記でも書いてみる。
9月19日・・・株主総会の日だった。例年10名前後の参加があるのだが、今年は6名と少なかった。6月末の決算日からの2ヵ月半、年々複雑になる一方の決算処理に随分と時間をとられた。税別会計や経過勘定など、会計処理を厳密にしようとすると手間がかかる。ようやく数字がまとまったら、決算速報・決算短信・会社内容説明書の作成、並行して総会招集通知などの作成もある。社内の作業スタッフは私一人だから負担が大きいが、業績は着実に進展しているし、何一つ隠し事のない会社だから、まっすぐな気持ちで取り組める。来年は設立10周年、初の黒字達成で、ささやかに祝いたい。
9月21日・・・はるばる浜名湖畔までB'zの屋外ライブを見に行った。折からの台風で道中は暴風雨だったが、コンサート途中から雨も上がった。5万人の聴衆、大規模なステージ、巨大なPAシステム、屋外ならではの花火の演出。それなりに楽しくはあったが、ひりひりするように緊張感や興奮は味わえなかった。みんな良い子だ。ロックもバイクも、今やエンターテイメントであり、レジャーのひとつ。
9月27日・・・久しぶりに整形外科に行った。6月末の交通事故から3ヶ月。指の怪我の最終チェック。もちろん、骨は固まっているが、レントゲン写真を見ると、関節が少しつぶれて、ギザギザになっている。しばらく力を入れていると曲がるのだが、油の切れた蝶番のようで元通りの動きからはほど遠い。医者は「ギターは無理かもしれませんね」と言う。憧れのストラトキャスターを買って「そのうち練習しよう」と思っているうちに、こんなことになってしまった。いっそ、弦を張り替えてサウスポーに転向しようかとも思ったが、それはやめて、どこまで回復するか見届けてやるつもり。
10月3日・・・パシフィコ横浜に「旅行博」を見に行った。アメリカのモーテルチェーンのブースにも寄ったが、「旅籠屋」のことはまったく知られていなかった。少し、悔しい、さびしい。この展示会は初めての見学だったが、メインは世界各地の観光スポットのPR。「ロシアの釣りツアー」など、旅行会社のパンフ棚では見かけない情報がいっぱいだった。世界中に行ってみたい、ほんとうにそんな気になった。いつか、戻りの予定を立てずに、何年もの旅に出たい。
10月5日・・・息子のバンドのライブを見に行った。みんな、思ったより、ずっと上手だった。あまり自己主張しない彼が「プロのミュージシャンになりたい」と言う。自分も、若い頃、一時期そう夢見たことがある。才能と運に恵まれるのなら、背中を押してやりたい。表現者として生きていく人生は悪くない。でも、何より得難いのは「持続するパッション」。人生の多くはドラマと無縁の平板な日常のダラダラ坂。実感から言えば、退路を断つような人生は勧められない。ピュアな気持ちを買ってやりたい、という気持ちとの板ばさみ。
10月7日・・・新店舗の話し。建物建築費の見積りがなかなか想定額に収まらない。住宅メーカーにいた経験から推察するに、積算部の担当者が過去の常識から抜け出せないのではないか。材工一式、現場経費、出精値引なんていうやりかたを続けていては、いつまで経っても建設業界は生まれ変われない。みんなわかっているのに体質を変えられない。そろそろ腕力と決断力のある工務店経営者とめぐり合えないものか。
更け行く〜秋の夜〜。珍しく、日記らしい日記が書けた。なぜか、今夜は心穏やか。
- 2003.07.16 つまらん
-
新規出店を促進させるため、先日、あるリース会社を訪問した。会計士や証券会社から「不動産リースも可能らしいよ」と紹介されたので勇んで出かけたのだが、結果は「決算報告書や事業計画書の内容を見て与信枠を検討します」という返事だった。
「つまらん、お前の話はつまらん」という金鳥のテレビCFのセリフが頭に浮かんだ。そんな型どおりのことなら、プレゼンするんじゃなかった。
自分でも申し訳ないと思うくらい、私はお役所に行くとすぐに頭に血が上る。話しをする前からケンカ腰になっているみたいだ。前世で役人にいじめられたのかもしれない。
役所に限らず「そういう決まりになっていますから」とか「そんな前例はありませんから」などと言われると瞬間的にアドレナリンが体中に分泌される。担当者が悪いんじゃない、ないものねだりなんだよ。短気は損気、もっとねばり強く・・・と頭ではわかっているのだが、黙っていられなくなる。
こういう自己中心的な性格もアントレプレナーの必須要件、確かにそんな気もするが、最近ますますこらえ性がなくなっているようで気になる。会社設立から9年が過ぎ、多少知名度も上がってきたせいで知らず知らずのうちにプライドだけが高くなり、ひたむきさを失いつつあるのかもしれない。
- 2003.07.15 大当たり
-
えーい、書いちまえ。
20日ほど前、待望の8号「浦佐店」の契約調印の帰り、関越自動車道で派手な交通事故を起こしてしまった。
土砂降りの雨、水しぶきをまきあげるタンクローリーを追い越した直後、突然タイヤのグリップがなくなり、中央分離帯や路側帯のガードロープにぶつかりながら高速道路上でアイスダンスを踊った。典型的なハイドロプレーニング現象というやつだ。スリップしている間にタンクローリーと衝突したためか車は修理不可能の全損状態になってしまったが、同乗のTさんも、ローリーの運転手にもケガはなく、私がちょっとした切り傷と左手人差し指の骨折を負っただけで済んだ。このように人的被害は最小限だったが、路上で止まってしまった私の車を避けようとしたトラックがこれまた派手にスリップして路側帯につっこんだこともあって路上には車のパーツが散乱。翌日の新聞によると、関越の上りはその後1時間半も全面通行止めになったらしい(皆さん、ほんとうにごめんなさい・・・)。
事故を起こしといて言うのも説得力がないが、バイクで何回も痛い思いをしたから、私は普段からとても安全運転。車間はたっぷりとるし、急発信・急ブレーキなんて無縁だ。今回もスピードはもちろん100km以下。では、なぜ?
冷静に考えて思い当たるのは、タイヤの摩耗が進んでいたことだ。昨秋の車検の時にも交換を勧められていたのに替えなかった。走行距離7万kmで無交換は、やっぱり無茶でした。
教訓1・・・赤字でも、タイヤをケチルな、金使え。
教訓2・・・雨の日の、「スリップ注意」は、うそじゃない。
会社に戻ってきてから「社長に万一のことがあったら、どうするんです」とボコボコに叱られたけれど、おっしゃるとおり。反省しています・・・
以前、1年以上にわたって悩まされた「五十肩」の時も困ったが、今回も人差し指が使えないのはまったく不自由。パソコンは右手の一本指打法なので問題ないが、洗面所でも、風呂でも片手ではなんともならない。あさってで3週間になるので、ぐるぐる巻きの包帯と副木が外れ、着脱可能なキャップになるらしい。そろそろ動かし始めないと指全体が固くなってしまうそうだ。第2関節の骨が少しつぶれて割れたような状態なので完全に元に戻ることは難しいらしいが、日常生活に不自由がなければ良い。しかし、なんとかギターが弾けるくらいには治って欲しいぞ。
なお、車はほぼ減価償却が終わっており、任意保険やJAFのおかげもあって会社への実害はごく少額で済んだ。良かった。
- 2003.06.12 勇気ある経営大賞
-
東京商工会議所で、今年から「勇気ある経営大賞」という顕彰制度がスタートした。「独自の技術・技能や経営手法によって、新たな製品・サービスを生み出した革新的、創造的な中小企業を顕彰し、その活動を支援。後に続く企業に目標と希望を与え、中小企業に内在する無限の可能性を引き出し、産業の再生に貢献。」というのが制度の主旨。
「これなら、旅籠屋も該当するぞ」と意気込んで数日かけて資料をまとめ、今年の初めに勇んで応募した。10社ほどの入賞企業に与えられる賞金も魅力だったが、何より「ファミリーロッジ旅籠屋」という事業のPRや「旅籠屋」という会社の社会的信用力の増大につながればというのが目的だった。
応募から数ヶ月、ようやく5月になって第1次、第2次審査の結果についての連絡があり「応募187社の中で、25社に残っているので、第3次の実地審査に伺いたい」との要請を受けた。この実地審査で10社程度に絞り込まれ、それがほぼ入賞企業となるらしい。密かに期待していたので、本社スタッフ一同大喜び。5月下旬の実地審査も終え、ここ数日はその結果を待ちながら、何度も郵便受けをのぞきに行くという毎日が続いていた。
そして、きょう・・・待ちきれずに電話で問い合せたところ、残念ながら選外との返事。あ〜がっかり。ほんとにがっかり。具体的な事業は東京都以外で展開しているのがいけなかったのかなぁ、やっぱり赤字企業だからかなぁ、宿泊業と言うことで先入観を持たれたのかなぁ・・・。もちろん、選考の過程はわからないことだ。
旅籠屋は、多くの旅行者に従来なかった利便性を提供し、車社会に必須のインフラを整備していく先導役になる企業なので、制度の主旨にはぴったりの会社だと思ったんだけど・・・。
窓の外と同じく、きょうは本社の雰囲気もすっかり暗く沈んでしまっている。しかし、別にこれで会社の値打ちが下がるわけじゃないし、気を取り直して頑張ろう(と、自分に言い聞かせよう)。
あ〜、しかし、どんな企業が選ばれたんだろうなぁ。「強く推す選考委員も居たので、ぜひ次回も応募してください」と言われたけど、気分的にそれはないよね。それにしても、あ〜残念。
- 2003.04.21 残念
-
4/7に書いた加藤大治郎、昏睡状態が2週間続いていましたが、20日未明、とうとう逝ってしまいました。
鍛え抜かれた鋼のような体だったのに、とうとう力尽きて灯が消えたという印象です。
わかりやすく言えば首の骨が折れているような状態だったらしく、意識が戻ったとしても最悪の後遺症が残るという見方もありましたから、これで良かったのかもしれないという思いもあります。
しかし、輝きの頂点を迎えようとした時期に、むごいことです。残念です。冥福を祈ります。合掌・・・
- 2003.04.11 農協に失望
-
ありがたいことに、「早く旅籠屋をアチコチに増やしてください」というメールをいただくことが多い。もちろん、誰よりそうしたいし、手元に100億円というお金があれば、今すぐにでも日本全国に100軒の「旅籠屋」を誕生させる(需要は十二分にある)のだが、お金に余裕がないというのはほんとうに悔しい。機会損失もいいところだ。儲けるチャンスを失っているという意味だけでなく、多くの旅行者が不合理な費用と時間を負担せざるを得ない状況が続いているのが情けない。
5・6・7号店がそうであるように、現在「旅籠屋」は遊休地のオーナーに建物を建てていただき、これを当社が長期間借り受けてホテルの経営・運営を行うという形で出店している。「旅籠屋」は基本的に郊外立地なので、出店可能な遊休地は全国にあり、土地だけ貸したいという地主の方はそれこそ無数にいらっしゃるのだが、あらたに建築費を負担して活用をしようという方は限られてしまう。20年間の家賃保証で、追加の費用負担も実務負担もまったくないのだから、たいへん堅実で安定した活用法だと自負しているのだが、世の中の雰囲気が臆病になっているせいか決断を先送りするケースが少なくない。
というわけで、「北上店」のオーナーのような方は貴重な存在なのだが、その方に「私と同様、市街化区域内に非営農地を持っていて、税負担が重い遊休地を活用したいと考えている人は全国にたくさんいるはずだから、農協にこうした活用法をひろくPRしてもらってはどう?」という提案をいただいた。1年近く前のことだ。さっそく、昨年5月、全国農業協同組合中央会(JA全中)の地域振興部に連絡をとって、事業説明に伺った。幸いとても興味を示していただいたが、「こうしたことは全農の方が適当なのです」というわけで、翌月、同じ建物の中にある全国農業組合連合会(JA全農)生産資材部を訪ね、再度プレゼンをさせていただいた。こちらでも同様にとても興味を示していただいたのだが、「具体的なことは東京支所が担当していますので」というわけで、半月後、またまた同じ建物の中にあるJA全農東京支所の担当部署を訪ね3回目の説明を行った。「面白いですね。具体的な案件があったら連絡します」というところまでようやくたどり着いたというわけだ。
しかし、この話しは残念ながらそれっきり何の反応もない。せめて、アパートやマンション以外にもこういう活用法がある情報だけでも伝えてほしい、と思ったのだが、大きな役所みたいな組織だし、これ以上催促するわけにも行かない。
そんなことを前述の「北上店」のオーナーに愚痴ったところ、「それなら、農家の多くが購読している新聞に取り上げてもらってはどう?」という助言をいただいた。気を取り直して日本農業新聞のデスクを訪ね、4回目の説明。すでに、10月。
ここまで来れば、賢明な皆さんにはその後の状況は書かなくても察していただけると思う。残念ながら、改めての取材はなく、1行の記事にもなっていない。
どんなビジネスであれ、売り込みはたいへんだ。結果がすべてなのだから、一方的にこうした相手の「無理解」を嘆くのは経営者としてはほめられたことではない。よく分かってます。だから、今まで書かなかったんです。
しかし、最近、現在最終段階に入りつつある出店交渉の中である地主さんから言われたことで、とうとう私も書かずにいられない心境になった。その地主さんは「旅籠屋」を建てて土地活用する決断をされたのだが建築費の融資相談に行った農協で「どうせラブホテルじゃないですか」と言われて断られたそうなのだ。
地元の町役場は「町の活性化になることですからぜひ出店してくださいよ」と大歓迎なのに、あー農協って何なの?。
もちろん地主さんは、他の金融機関に相談されているので、きっと計画は実現すると信じているが、
私はもう農協には心底失望している。
- 2003.04.07 目を覚ませ
-
いっこうに金欠病の症状が改善しないこともあって、今年も日本GPはテレビ観戦となった。ますます観客が少なくなったようで、それはもちろん私が責任を感じる話しじゃないけれど、ちょっと申し訳ない気がした。レースはいずれも白熱していて面白かったし、とくにMotoGPクラスには、久しぶりにKAWASAKIやDUCATIが戻ってきたので今シーズンは興味しんしんだ。
しかし、加藤大治郎選手の大クラッシュには衝撃を受けた。コース上でまったく動かないので、尋常なケガではないと思ったが、ヘリコプターで搬送されたあとの情報がない。ネット上を探し回ってようやくたどり着いた掲示板での書き込みによると24時間経過した現在も重体とのこと。事故直後は心臓が停止していたが、その後蘇生に成功し、体温や血圧は戻りつつあるが意識が戻っていないらしい。
まだ26歳で、10日ほど前に長女が生まれたばかりだというのに、なんということだ。
レース、とくに2輪のロードレースには転倒事故がつきものだが、ライダーの命にかかわる事故だけは絶対に起こって欲しくない。「チーム旅籠屋」をサポートし始めて、必ずしもマスコミで報道されない重大事故が少なくないことを知り、また、生身のライダーたちを知り、この思いはますます強くなった。
大治郎、目を覚ませ!
一昨日、久しぶりに時間がとれたので、「東京モーターサイクルショー」を見に行ってきた。冬のような天候だったが、場内は大にぎわい、バイク好きがたくさんいることは嬉しかったが、メーカーのパンフレットを見て商品ラインナップが極端に少なくなっていることに驚いた。50ccのスクーター、アメリカン、大型スクーター、ほとんどそれだけだ。無骨なロードスポーツがすっかり姿を消しているのが寂しい。バイクに乗ることだけで白い目で見られた時代、だからこそ「肩で風を切って」走っている自分の姿に酔えた時代はすっかり遠くなってしまったようだ。それはそれで仕方のないことなのだが、こんな時代に「我が身一つ」で命がけでサーキットを駆け抜けている魂が消えてしまうのは絶対にイヤだ。
大治郎、目を覚ませ!
- 2003.03.28 春なんだ
-
正月以来、なんだかんだと気ぜわしい。
子供の受験・アパート探し、引っ越し2件、そして、ハモニカの演奏会出演・・・などなど。
プライベートだけじゃない。
設計スタッフを迎え入れるための本社オフィスの模様替えや倉庫の整理。ようやく、新規出店が相次ぎそうな気配もあり、社外の設計スタッフに半ば常駐してもらうことになったのだ。
店舗の稼働は、ばらつきはあるが、総じて好調。代行要員のやりくりなどで本社の管理責任者は東奔西走している。
世の中に目を転じれば、もちろんアメリカのイラク侵略で大騒ぎ。北朝鮮情勢も不穏だ。
言いたいことはたくさんあるけれど、そんなこんなで、なんだか落ち着かない。そう、啓蟄、春なんだ。忙しくなりそうだぜ。
- 2003.01.22 金持ちになりたい
-
「忘年会」「新年会」とは縁のない私だが、正月に高校時代の友人たちと会うのは恒例。昨夜は仕事で知り合った知人とほぼ1年ぶりに3人で集まったが、もしかするとこれも恒例になるかもしれない。気の置けない人たちなので楽しい。5年10年後には、どんな話しをしているのだろう。「最近、旅籠屋日記が月記にもなっていない」とお叱り(?)をいただいたので、何か書いてみようか。
「最近アタマにきたこと」が話題になったが、そうそうひとつ言い忘れていた。毎日のようにかかってくる投資勧誘の電話。主として商品先物取引の誘いなのだが、これは不愉快だ。「運用する資産なんてありませんから」と断るのに「いぇいぇそんな謙遜を」と返してくるからアタマに血が上る。「小なりと言えども社長だから多少の金はあるのだろう」という「オヤジくさい常識」もイヤだが、ホント金のない現実に思いが行って情けなさで腹が立ってくる。人が忘れようとしていることに触れるなよ。
大企業で働いている高校のクラスメートと比べたら年収は半分以下かもしれないが、そんなことはどうでも良い。自分で会社を興し、やりたい仕事をしているのだから、銭金に換えられない満足感や充実感を得ているし、将来の楽しみもある。でも問題は今現在の絶対的な不足、どうしても毎月の家計が赤字になって、まったくゆとりがないことなのだ。
私は酒を飲まないし、打たないし(たまの宝くじとtotoくらい)、もちろん買わないからホント品行方正のつつましい暮らしぶりなのだが、故あって扶養控除がないせいか天引きされる税金や保険料が高くて手取り収入が低い。そこから生命保険料を払い、かつて会社の株を買ったときの借金を返し、加えて子供たちの学費がある。この春からは下の息子も大学進学なので、また国金の学資ローンの返済が増えることになる。何だか貧乏を自慢するみたいで品が悪いのだが、やっぱりたまにはバーンと無駄遣いできるゆとりは精神を健康に保つのに必要なゆとりじゃないだろうかと心底思う。あー長年の欲求不満でどんどん下品になっていく。
とは言え、私の部屋には通販で衝動買いした腹筋トレーナー(3種類もある)やスチームクリーナーやほとんど使っていないDTMソフトや飾り物のギターがあったりするから無駄遣いがないとは言えないのだけれど、それくらいは許してよ。これでも、年老いた両親と食事に行った時は私がご馳走すべきじゃないか、誕生日プレゼントくらいはずみたい、たまには海外旅行に繰り出したい、と心の底では思っていて、肩身の狭い思いをしているんですよ。少しは見栄を張りたい。
まぁしかし、金がないと言っても、幸い両親が健在で多少の蓄えもあるようだから、気持ちのどこかで甘えている部分がある。相撲の土俵の「徳俵」という感じ。昔々フリーターやって一人暮らししてた時の「切羽詰った貧乏」とは違う。しかし、この歳なら親の生活費を負担するのが筋じゃないの・・・って考えていたら気持ちが暗くなってきたので、この話しはもうおしまい。
まぁいいさ、そのうち、有り余るお金の使い道に悩む話でも書くさ。しかし、もしかするとそんな話しの方がずっとずっと暗い?
- 2003.01.16 もうひとつの喜び
-
年が改まってもう半月が過ぎた。去年は、ほぼ決まりかけていた新規出店の話しが最後の最後で白紙になってしまい、盛り下がって暮れたが、今年こそは飛躍の年にしたいと思う。
各店舗は、「鬼怒川店」「那須店」「秋田六郷店」が伸び悩むいっぽうで、2年目を迎えた「山中湖店」「沼田店」「水戸大洗店」が大躍進、昨夏オープンの「北上店」が大苦戦・・・空模様に例えれば「晴れ、所により薄曇り」という感じなのだが、数年前のように「明日の天気は明日になってみないとわからない」という状況ではないから、もう雨具の心配はいらない。というのも、利用いただければきっと気に入っていただけるという確信があるからだ。「旅行者が、気軽に安心して泊まれる、自由で経済的な宿泊施設の提供」という事業目的のひとつは着実に実現されつつある。
事業目的のひとつ? そう、じつは、「旅籠屋」には二つの目的があるのだ。創業以来のキャッチフレーズ「シンプルで自由な、旅と暮らしをサポートする」の「暮らし」という言葉に込めたこと、それは「地域に調和する資産活用事業の創出と、堅実で自立した生活基盤の確保」ということだ。利用者ではなく、「旅籠屋」という施設を提供する(「旅籠屋」を誘致することによって遊休地を活用する)オーナーや、住み込んで運営業務一切を行う支配人夫婦の存在が、もうひとつの大切な目的なのだ。
10年前、友人に案内されてアメリカのMOTELを数多く見て回ったときに感銘を受けたのは、シンプルで合理的な宿泊施設のスタイルだけではない。じつはそのこと以上に、そこで働く人たちの有り様にに強い印象を受けたのだ。田舎町の郊外にポツンと建っているMOTELを訪ねると、その支配人の多くは移民の家族だったり、中高年の夫婦だったりする。おそらく彼らはニューヨークやシカゴに行ったこともなく、最先端のビジネスともアメリカンドリームとも無縁であるに違いない。しかし、彼らは、夫婦で、家族で一軒の宿を切り盛りしながら、誰に媚びることも、臆することもなく、マイペースで自分たちの人生を営んでいる。
日本は狭い。物理的に狭いというより、価値観の一元化が進んでしまって息苦しい。人間が過去から現在までの学校・勤め先・居住地などの表面的な属性で測られてしまう。例えば、サラリーマンに向かない人、都会に向かなかった人にとって日本は生き易い国ではない。脱サラとか脱都会といった言葉には、どこかしらに暗いイメージとそのイメージを払拭しようとする「から元気」の気負いがある。本来、どこで、どう生きようとそれは個人が自然体で選び取り受け入れていけば良いことなのに、目に見えない物差しが当てられてしまう。
最近知ったデータによると、アメリカには20室以下の小規模なMOTELが4万軒ほどあるらしい。その規模なら、多くは都会から離れた場所にあるだろう。アメリカの田舎を車で旅したことのある人なら思い出してもらえると思うが、人里離れた道路沿いに看板の灯を掲げて「自分サイズ」の暮らしを営んでいる家族がアメリカじゅうにいるのだ。「旅籠屋」の一軒一軒がそんなかけがえのない生活の場になれたら・・・私が夢見たのはそういう日本だ。
「旅籠屋」は現在7店舗。代行支配人を含め、8組のご夫婦に店舗の運営ををお願いしている。人選にあたって、基本的に学歴や職歴は関係ない。ご夫婦の仲がよく、誠実で実直な方、人柄第一である。だからというわけでもないが、さまざまな経歴を持った方々がいらっしゃる。「履歴書」上ではマイナスのこともあったりするが、人柄とは関係のないことだし、逆に豊かな人生経験のせいか、人間として素晴らしい方々ばかりだ。
「旅籠屋」の二つ目の目的。これは事業の成果として表に出ることではない。利用者にも関係ない。傲慢な言い方だと斜めに受け取られたりもする。肩書きで人間を見ない、当たり前のことをしているだけなのだが、曲解されるのも癪にさわるので、あまり言わないできた。しかし、これは間違いなく「旅籠屋」の存在意義そのものなのだ。
それにしても、「地域に調和する資産活用事業の創出」という部分も、そろそろたくさんの人に理解して欲しいぞ。死んでいる土地が生まれ変わりますよ。
- 2002.11.05 同情できないよ
-
竹中問題とか言われて、銀行がたいへんらしい。金融危機とか、私にはよくわからないけど、でも、どうも銀行には同情できない。だって、大手金融機関の場合、20歳代で年収800万円以上ってほんと?私なんか、今もってそんな給料もらったことないよ。そんなに人件費を使ってる企業に同情なんてできないよ。冗談じゃないよ。おかしいよ。
- 2002.10.26 無神経
-
北朝鮮拉致問題で大騒ぎだ。数十年前、北朝鮮を理想郷のように持ち上げて、在日朝鮮人の「帰国」や日本人妻の「北行き」をあおったマスコミが、今度は被害者可哀想の大合唱だ。いつも正義の味方、インテリ面して世論を引っ張っているつもりの風見鶏。あー嘘ばっかり。無責任。不和雷同。
新聞によると、5人の一時帰国者を「北朝鮮に戻さずに、このまま日本に永住させる」方向で国が検討しているらしい。なんだか、みんな「そうだ、それがいい」と拍手を送っているみたいだが、私はとんでもないことだと思う。大いに違和感を感じる。
だって、彼らは、20年以上も北朝鮮で生活し、子供を育て、社会の一員として何かしらの立場を築いてきているわけだし、その生活を周りの人間が壊す権利はないんじゃないの。「20年も待ったんだ。2度と会えなくなるかもしれない」という年老いたご両親の心情はもちろん理解できる。しかし、子供たちには子供たちの生活が、孫たちにも孫たちの人生がある。今、日本に戻ってきてゼロから新しい人生を始めることがほんとうに幸せにつながることなのだろうか。孫たちにとっては言葉も文化も価値観も違う国であり、なおさらのことだ。帰るか残るか、それを決めるのは当人たちの判断、当たり前のことじゃないか。
日本に帰国した中国残留孤児の方々のその後をテレビで見たことがある。祖国に戻ったから幸せになるなんて幻想だ。どこかに日本人の傲慢があり、ベタベタの距離感の欠如があり、無神経な押し付けがある。5人が家族とともに日本で暮らし始めたとして、果たしてどういう人生が待っているのだろう。当人たちの立場になって想像してみたらどんなシーンが浮かんでくるだろう。ワイドショーレポーターが追い掛け回し、何かトラブルがあれば手のひらを返したように「国のおかげで戻ってこれたのに、国が生活費の面倒までみているのに・・・」なんて言い出しかねない。
自分の頭で考えず、いつも人の噂話にばかりに耳をそばだてている日本人。薄っぺらな道徳観、無責任な同情、ワイドショー世論に迎合する愚民政治。相変わらずご都合主義のマスコミ報道なんかに惑わされず、わがままに自分たちの個人的な意思を表明して欲しい。「今度は、皆さんが私たちを日本に拉致するのですか!」って叫んだら、鈍感な偽善者たちはなんと反応するだろうか。
- 2002.09.15 人間不信
-
昨日、当社の第8期定時株主総会が開かれた。赤字拡大の理由や出店スピードの遅さなどについて厳しい指摘もあり、続いて開いた事業報告会とあわせ、3時間以上の会議になった。もともとシャンシャン総会にするつもりなどないし、会社経営についての率直な意見交換をすることはとても意義のあることだから時間がかかるのは悪いことではない。日々最善を尽くしているつもりでも、社内ではどうしても「慣れ」や「常識」に流されている面があるから、利害関係者からの刺激は貴重である。そっさく、週明けに今後の事業の進め方についての検討会を開き、指摘された点をじっくり受け止めて改善策を実行していくことになった。多数の一般個人投資家の存在は、IRなどの面で負担になることもあるが、一定のチェックがかかるという点では経営の健全化にプラスになると思う。
それはそれとして、一部に心外な発言があったのは残念なことだった。「(細かい数字の解釈に関して)そんなこともわからないのか」あるいは「本社の人間は、店舗に食わせてもらっているのだから」・・・。初対面の人間にそんなことを言われる筋合いはまったくないのだが、そんな発言が出てくる背景には経営者一般に対する不信感があるのだろう。どうせ、ロクな経営をしていないに違いない。能力のない人間が偉そうに経営者ヅラをしているんだろう・・・そんな先入観があるのだろう。
50年も生きていると癒えることのない傷がいくつかはある。会社も設立から8年が過ぎて、思い出したくない出来事も少しは経験してきた。あえて振り返ってみれば、そのほとんどは人間関係の問題、もっと具体的に言えば人間不信を突きつけられたことによって受けた心の傷である。人間関係なのだから相対的な問題であり、誰が良くて誰が悪いと一方的に結論付けられないことで、だからこそ迷宮に入り込んだまま心の底にトゲをもったまま沈殿してしまうのである。
自分の思いがまっすぐに伝わらない。誤解されて反感を買う。予断や先入観で判断され、軽視され、侮蔑され、拒絶される。こちらが懸命であればあるほど、受ける傷は深い。悲しく、情けなく、腹立たしい。
残念ながら、これは一定の知能と引き換えに人間に課せられた負の宿命なのだろう。逆の立場に立てば、私も多くの人に対し、無神経で無遠慮な言動を繰り返してきたのかもしれない。予断や偏見にとらわれず、常に相手に対する敬意を失わずに接すること、自らに対する戒めとすることにしよう。
何だか、オヤジくさいエッセイみたいになってしまった。オマエらしくないと叱られそうだ。
それにしても、いつも不信感を突きつけられる政治家ってたいへんだなぁ。どういう精神構造の人たちなんだろう。
吉田茂じゃないけれど、私ならすぐに「ばかやろう」だ。
- 2002.08.15 8耐、曲がり角
-
先日、鈴鹿サーキットに8耐観戦に行ってきた。今年は25回目の記念大会ということだったが、私が初めて見に行ったのは10回大会、1987年のことだ。以来15年間、ほぼ欠かさず通っているが、はっきり言って年々つまらなくなってきているように感じる。往復の交通費や宿代やチケット代を合計して5万円前後の出費に見合うだけの満足感が得られなくなっている。ここ3年間は微力ながらサポートしている「チーム旅籠屋」が参戦しているので、まったく違う感動や落胆があったりするが、それは別の話し。あくまでレース観戦者としての感想である。
8耐は世界のトップライダーが参戦する唯一の耐久レースということで、世界的にも特別なレースである。日本は世界の2輪産業の中心を占める4大メーカーの地元、しかも市販者に近いマシンが走るレースということもあって、メーカーもライダーも真剣勝負の争いを繰り広げる。加えて特筆すべきことは、このレースがプライベーターにも門戸が開かれている点だ。そもそも耐久レースというのは予期せぬトラブルやアクシデントが起きる可能性が高いから強い者が必ず勝つとは限らない。事実、かつては世界のHONDAがヨシムラやモリワキに敗れるという番狂わせも珍しいことではなかった。1987年も、残り5分にヨシムラのマシンが転倒して優勝を逃すという最高にドラマチックなレースだった。これ以降の大会でも、残り1時間を切ってトップのマシンがリタイアしたり、夜間走行になって接近戦になるなど、劇的なシーンがいくつも演じられてきた。
ところが、ここ数年は、トップチームであるHONDAの独走優勝が続いている。プライベートチームはもちろん、他のメーカーワークスチームもかなわない。そんなこともあってか、とうとう今年はカワサキのワークスが参加を取りやめてしまった。
最高レベルの真剣勝負でなければレースとしての値打ちは低くなってしまう。だからHONDAが手を抜かず全力でマシンを開発し、トップライダーを集めてくるのは素晴らしいことだ。しかし、事前あるいは途中の段階でほとんど結果の見えてしまうレースほどつまらないものはない。
1周コンマ数秒のタイムを縮める、何時間走ってもトラブルを起こさないマシンの開発には、たいへんな資金と技術力がかかるに違いない。それはもう以前のような卓越した個人の能力や情熱では届かないレベルに達してしまっているのだろう。最近のレース結果は、偶然ではなく、必然の結果のように思える。そこが、レースとしては、大問題なのだ。
たしかに、レース観戦の環境という面では、周辺道路の整備、スタンドやトイレの増設、順位ボードの改善など、主催者サイドの努力は明らかだ。それなのに肝心のレースがつまらない。
レースには、参加する者の真剣勝負の競い合いという面と観戦する者を魅了する興行というふたつの面がある。8耐に関しては、これらの食い違いが徐々に大きくなってきているといえるのではないだろうか。ひじょうに乱暴に言えば、アメリカは後者に重点を置き、ヨーロッパや日本は前者を重視しているように感じられる。4輪のカートとF1を比較するとわかりやすい。これはモータースポーツに限ったことではなく、スポーツイベントすべてに言える。そうした中で、サッカーのWカップのように世紀を越えて続いている大会の運営者の知恵には敬服せざるを得ない。守るべき伝統と時代に合わせた手直し、貫くべき原則と臨機応変の妥協。矛盾するものを容認し、清濁を併せ呑んでまとめ上げていく手練手管には畏敬の念を抱かざるを得ない。これは、日本人には苦手なことだ。
メーカーワークスの参加台数を2台以下に制限してはどうか、改造範囲を極端に制限してはどうかなど、レースを面白くするためのアイデアはいくつか思い浮かぶけれど、結局はモグラたたきに終わるに違いない。さて、どうしたものか。
- 2002.06.17 サッカー文化
-
Wカップも残りわずかとなった。なんと、日本が決勝トーナメントに進んでいる。おかげさまでベルギー戦は実際にスタンドで応援できたし(観戦記をまとめました)、時差に悩まされずテレビ観戦できるし、存分にサッカーを堪能している。
Wカップはスポーツにとどまらず国と国との戦いだという人がいる。少々大げさではないかと思っていたが、確かに、サポーターの応援ぶりを含め、それぞれの国民性が強烈に伝わってくる。生活の中でのサッカーの占める濃淡、代表チームへの思い入れの強弱に、さまざまな背景や事情が見え隠れしている。サッカー文化と言われることの意味を少し理解できたような気がする。
残念ながらベスト16で敗退してしまったアイルランド。最初から最後まで全力で戦う選手たちの気迫に魅せられたが、それ以上にサポーターの気持ちの強さに感銘を受けた。解説によれば、緑の装いのサポーターの半分はアイルランド本国からではなく、世界中から母国の応援のために集まってきた人たちなのだそうだ。民族のアイデンティティの強さに驚かされる。これは、アイリッシュたちの悲惨な過去や差別の歴史と無縁ではないだろう。
現在ほとんどがフランスで生活していながら、かつての宗主国にだけは負けたくないというセネガル選手の思いにも心打たれた。民族や国家への帰属意識は、長い間他国の支配を受けていた国ほど強いのかもしれない。アフリカ諸国・東欧・南アメリカ、そして韓国。熱狂的な応援であっても西欧諸国の場合とは質的に違うような印象を受ける。
さて、いっぽう、日本の場合はどうか。イケメン軍団に浮かれるミーハーはご愛嬌として、国家や民族の尊厳を賭けた戦いという意識は希薄なのではないか。国内の日本人だけではない。ブラジルの日系人社会では、1世は日本、2世以降はブラジルを応援する傾向があるのだそうで、血の薄さを感じてしまう。よく言われるように、島国という地理的な条件、自然に恵まれた温暖な気候、他国の侵略によって存亡の危機をさまようことのなかった歴史が、世界でも稀な「こだわりのない国民性」を育み、許してきたのかもしれない。
加えて、私のように戦後教育を受けた世代には、日の丸を掲げ、君が代を歌うことに躊躇する習性がある。日本チームを応援しても、他国への敵愾心をあらわにする所までは行けない。事実の解明や責任の所在を曖昧にすることで居場所を探してきた戦後は、我々に妙な後ろめたさとフラストレーションを与えてきた。その典型が韓国に対する遠慮がちな気分だ。
ところが、どうも味わったことのない胎動が生まれ始めている。日韓共催という現実と、参加各国のむき出しの国家意識・民族意識を目の当たりにして、思いを屈折させ沈めていたぶ厚いベールが少しずつ剥ぎ取られていくのを感じる。学校でも国技館でも一度も君が代斉唱に加わったことのなかった私が、さいたまスタジアムでは大声で歌った。サポーターの掲げる無数の日の丸に泣きそうになるほど感動した。これは悪くない気分だ。長い間のコンプレックスから少しずつ解放され、くびきが解けはじめ、薄暗い霧が晴れていく感じ、体中が軽くなっていくような気がする。
チュニジア戦をテレビで見ていたら、スタンドの若いサポーターたちが「日本、大好き」というパネルを掲げていた。若者の多くが生まれ育った国に愛想をつかし、自己実現の場を外国に求める幻想を追っている日本、その気持ちが痛いほどわかるだけに、この光景は鮮烈な印象を私に与えてくれた。たかがサッカー、されどサッカーである。政治家たちが国旗・国歌法を強行採決したのとはまったく別の次元で、日本人であることに自然に誇りをもてる状況が、そしてその気持ちを素直に表現する気分がWカップの舞台で現実のものになりつつある。
争ってはいけないというトラウマに捕われ、平和的解決という結果だけを追って妥協することに慣れ過ぎた日本人。争わないために本音を隠し続けているうちに自分を見つめ語ることを忘れてしまった日本人。我々にとって、サッカーというスポーツは、勝つために自らを見つめ、徹底的に競争し争うことのすがすがしさをほんとうに久しぶりに見せ付けてくれている。選手たちの闘争心や喜怒哀楽の表現が、眠っていたものを呼び覚ましてくれているように感じる。
私は、ずっと日本人であることに誇りを持ちたいと願い続けてきた。日本人も捨てたもんじゃないぞ、日本は素晴らしい国だと思わせてほしいと願い続けてきた。それなのに、政治の世界もビジネスの世界もロクにニュースがない。うんざりするような事が、もう何十年も続いている。トラウマを克服できず、出る杭を打ち無菌化することを良識のように吹聴してきたマスコミ、逆に形式的な組織論や威圧的なナショナリズムに頼るしか能のないエスタブリッシュメント。そんな中で無我夢中にピッチを走り回り真摯に戦い続ける選手たちは、確かに一陣の風を送ってくれている。
もちろん、こんなことは当の選手たちの意識とは無縁のことだ。しかし、微かに吹き始めた風によって晴れてきた霧の方向に求めていた何かがあるという予感がする。Wカップが終わり、皆が再び視線を落としてしまう前に、再びベールで心を覆ってしまう前に、この風が止むことなく吹いてくれないものか。
肝心のマスコミのお粗末な感性はどうだ。「次の試合、日本は勝てますかねぇ」という分析と、人気選手の追っかけと、サポーターの熱狂ぶり、伝えるのはそればかりだ。たとえばストイコビッチを招いたなら一言でも旧ユーゴが分裂し、かつての仲間がスロベニアやクロアチアとして参加していることについてのコメントを求めみたいとは思わないのか。アイルランドのサポーターの心情に迫るインタビューはできないのか。残念ながら、風はまた止んでしまうのだろう。
- 2002.06.03 毅然としろ
-
いよいよ、明日だ。日本・ベルギー戦。ゼッケン85番、HATAGOYA(そんな選手いない?サポーターの私ですよ!)という名前入りのレプリカユニフォームを着て、応援に行くのだ!
かなり心配したけれど、先週チケットも手元に届いたし、準備万端。今からドキドキしている。
しかし、今回のチケット問題はいったいどうなっているのだ。テレビを見ていても明らかに空席が目立つ。マスコミ報道の断片でしか情報が入らないが、FIFAの利権がらみのお手盛り業者選定。お人好しのJAWOC。後手後手の対応。あー情けない。4年前の教訓はどう生かされたのか。結局、世界を牛耳るFIFAにコケにされっぱなしじゃないの。韓国では訴訟を検討中、日本側は白紙だそうだ。どうして怒らない、どこまでお人好しなんだ、この国の偉い人たちは。
だいたい、世界を相手にするのだから、約束は破られる、正直者はだまされると思って準備すべきじゃないの。肝心のチケットもお金も相手の手の内にある、なんて、交渉も駆け引きもできゃしない。あー情けない。今となっては、とにかく世界のマスコミの報道を圧力に利用して、最大限声高に脅しをかけるしか残された手はないのだ。その点、韓国サイドの対応は、完全に正しい。争わないことが美徳なんて、日本人同士でしか通用しないことだ。ブラフでもよいから、世界中に見える形で、とにかくケツまくって相手を追い詰めろ。
日本サッカーの実力を世界に示すこと以上に、これは重要な勝負じゃないのか。
イギリスの印刷会社になめられるような日本ってなんなのよ。
追い詰められるチャンスは今しかないぞ。責めるなら今しかない。パス回ししてないで、ゴールへ迫れ。
- 2002.05.27 Wカップ再び
-
なんと、今週末にはWカップが開幕する。今から、ドキドキしている。しかし、先日の日本代表のメンバー選考の結果には納得できなかった。4年前のカズ落選の驚きと失望を思い出した。少し長くなるが、その時に書いた日記の一部を再録する。
・・・中田を選ぶことと、カズを外すということには、共通の思考基準があるように思う。すなわち、勝負にこだわるための合理性に従おうするか、儒教的なメンタリティとの調和を重んじるか、ということである。多分、前者はグローバルスタンダードの厳しさであり、後者は「日本的な甘さ」なのだろう。今回の決定の当事者である大仁強化委員長もこの点をわきまえており、「弱肉強食は世界の常識でも、日本では違う状況もある」という発言に迷いの深さが表れている。
スポーツの世界に限らず、日本人が世界の舞台で生きていかざるを得ない現在、その特殊性や未熟さを指摘されることが多い。私も日本や日本人の曖昧さや理念の欠落に苛立つことが多いのは、この日記に繰り返し書いているとおりである。しかし、ここで忘れてならないのは、グローバルスタンダードに同化すること自体を目的とするのなら、いつまで経っても亀を追うアキレスに過ぎないということである。アメリカ的な合理性が唯一の基準ではないし、ヨーロッパ的なマキャベリズムが成熟の証しでもない。我々は日本の伝統と体験をもとに独自のモデルを提示していくことが大切なのだと思う。それはもちろん、かつての矮小化された民族思想に回帰しようなどというものではない。
話しが大袈裟になったが、私個人はW杯において、勝利という結果よりも、記憶に残るパフォーマンスを日本代表に期待している。それは外国に対してだけでなく国内に対してもそうだ。カズの言葉にあった「誇りや魂」を重んじる「美学」を体言してみせて欲しいと願っている。その意味で、カズを外すなら、あえて中田を外して欲しかった。このままミニ・ブラジルやミニ・ドイツを目指してどうなるというのだ・・・
読み返してみて、私の感性が4年前と変わっていないことに気がついた。今回も、俊輔や名波を、そしてカズを選んで欲しかった。「日本代表」とは、日本最強のチームである以前に、我々の多くが納得し、気持ちをひとつにして応援できるという意味で「代表」であって欲しいと思う。とはいえ、私を含め大部分の人間は、結局はマスコミの論調に引っ張られて物事を見ている。だから、トルシエは俊輔や名波やカズを選ばないことが失望を招かないように、注意深く世論誘導をしておくべきだったのだ。気持ちよく、だまして欲しかった。
私個人の毎日は、悲喜こもごもである。運命を呪いたくなることもあったりする(仕事のことじゃないですよ。為念)。しかし、それはそれとしてWカップを楽しもうと思う。幸運と善意によって、日本・ベルギー戦のチケットをゲットできたのだ。ありがとう。燃え尽きてくるぜ。
- 2002.03.12 信用調査
-
新店舗の建築コストを合理的に節減するため、今年に入って工場製作部材について多くのメーカーと直接交渉を行った。結果として、旅籠屋用のオリジナル製品を組み立ててもらったり、調達ルートを一本化して安価な価格で供給してもらうことで話がまとまった。これも、「旅籠屋」の実績が認められ、コンスタントに店舗が増えていく見通しを信頼してもらえるようになったからこそである。
しかし、当然のことかもしれないが、その過程で、当社に対する信用調査の依頼があったようで、先月、東京商工リサーチや帝国データバンクの調査員が続けて訪ねてきた。「沼田店」以降、土地所有者に建物を建てていただき家賃を支払う方式での出店が続いているから、数年前から何度もこうした調査を受けており、調査員とも顔なじみになっていたりする。当社はIR情報をすっかりオープンにしているし、まったく何の隠し事もない、おそらくとても珍しい会社なので、調査自体にはもちろんなんの問題もない。逆に取引先の信用調査の売込みを受けたりして、無料で調査レポートが送られてきたりする。
というわけで、なにげなくそのレポートを眺めていたら、「***店」の建築をお願いした建設会社が昨年末に倒産していた事実を知った。工事自体は数年前のことだから当社が実害を被ることはないのだが、工事中に何度も顔をあわせて打ち合わせをしたその会社の専務さんの顔が思い出された。日本の金融機関のおかしな習慣で、中小企業の借金にはすべて役員個人の連帯保証が義務付けられたりするから、おそらく彼個人の生活も滅茶苦茶になっているに違いない。気の毒でならない。
先日も、出店候補地を探してくれていたある中堅ゼネコンの経営破たんがあり、担当者から律儀に電話をもらって、思わず励ましの言葉を送ってしまった。
幸い、当社は売上も支払いもすべて現金だから、他社の影響を受けることも、その逆もないから安心なのだが、もし手形商売だったらと思うとぞっとする。この不況の中、赤字会社でありながら、毎晩枕を高くして寝ていられる私は幸せ者かもしれない。
この周辺、浅草蔵前界隈は古くからの問屋や小さな工場が数多く集まっている場所である。ここ1年くらいの間、散歩の途中で、閉店の挨拶や差し押さえの文書を見かけることが珍しくなくなった。あの店員さんは給料をもらえたのだろうか、上に住んでいたに違いない社長さんの一家は夜逃げでもしたのだろうか、ついつい、そんなことを想像してしまう。気の毒でならない。
企業の経営破綻には、連鎖倒産のような不運な要因もあるだろうが、経営者にはやはり見通しの甘さやリスクヘッジを怠った責任がある。しかし、中小企業の場合、経営者自身が個人の財産や生活の場を失うということで、結果的にその責めを負わされているように見える。それにくらべ、相変わらず「減点されない」ことだけを行動の規範として逃げ回っている「大企業的な」サラリーマンたちの見苦しさが腹立たしくてならない。そんな余剰人員を飼っている会社こそ、はやくガラガラポンとなったほうが良いのだ。
利益の額だけで企業の価値が語られて良いとは思わない。なんでも競わせる社会が人間を幸せにするとは思わない。しかし、リスクを負って決断し行動している人たちの勇気が正当に報われる社会であってほしい。そして、つまづいても軽蔑されず再起できる世の中であってほしい。がんばってください、S専務!
- 2002.02.20 悲しいこと、嬉しいこと
-
冬季オリンピックももう終盤だ。あちこちで審判の公平性が問題になっている。明らかに政治的な力学が働いてしまっている決着のつけ方を含め、やりきれない気持ちになる。競技者でなくて良かった。
昔勤めていた会社の同僚が亡くなったとの知らせ。とても誠実でまっすぐな男だったのに。なぜ、どうして。10年以上も会っていないし、詳しいことはわからないが、彼らしく生きられた47年間だったのか。多分、会社を辞めてよかった。
通夜には行かなかった。許せ。
鈴木宗男と田中真紀子が参考人として登場した予算委員会。たたきあげの「濁」と、評論家的な「清」。泥試合。水掛け論。政治家でなくてよかった。
NHKで田中正造の一生を紹介していた。生涯を賭けて足尾鉱毒事件を闘った人だ。彼の言葉をふたつ。
いにしえの治水は地勢による。
あたかも山水の画を見るごとし。
しかるに今の治水はこれに反し、定規をもって経(たて)の筋を引くごとし。
山にも岡にもとんちゃくなく、真直に直角につくる。
治水は造るものにあらず。
我々はただ山を愛し、川を愛するのみ。
いわんや人類をや。
これ治水の大要なり。
真の文明は山を荒さず、川を荒さず、村を破らず、人を殺さざるべし。
前回の日記の前段について、意見をいただいた。誤解を招かないために補足する。
私は、酒を飲んだり食事をしたりして交友を深めることを否定するつもりはない。むしろ、こうした時間を共有できることこそが友人であり、知人であることの本質であるとも思っている。ただ、酒を酌み交わすことが「つきあい」の前提であるとか、心を通わすことに必須のことであるといった「酒飲みの押し付けがましい作法」に納得しない。そういうことです。
- 2002.02.10 そもそも何のために
-
私はアルコールが苦手だ。社交的な性格でもない。だから、ノミニケーションから逃げ回ってきた。サラリーマン時代、「そんなことでは勤まらないぞ」と上司に言われたことがあるし、事業を立ち上げた後も「夜のつきあいは情報収集に必須ですよ」とアドバイスされたこともある。たしかに付き合いが悪いことで世界を狭くしている面もあるだろうが、今更このスタイルを変えるつもりはない。ストレスに強い人間じゃないし、イヤなことはイヤ、それでいいと割り切っている。だいたい酒を飲んで深まる相互理解や親睦ってなんなのよ。
というわけで、酒を飲みながら語り合う機会というのは年に数回もないのだけれど、気心の知れた人と、ベタに仕事がらみでなければ、気軽に出かけていくこともある。
つい数日前、そういう珍しい夜があった。メンバーは私を含めて4人。2人はここ1〜2年の間に会社を興した20代の社長さんたちである。事業を始める際に多少のアドバイスをしたこともあって、その後の状況と今後が気になる。
いろいろと話しを聞いてみると、やはりなかなかたいへんらしい。一部は私が通ってきた道であり、悩みやつらさがよくわかる。そうした逆境にあっても情熱と自信を失わないのはすばらしい。刺激を受けることもあった。最後には「旅籠屋さん、最近円くなったというか、余裕が出来てハングリーさが薄れてきたんじゃないですか。もっとガンガン行ってくださいよ」なんて言われてしまった。そんことないのにねぇ。
言いたい放題の5時間だったが、私はその夜、ひとつの重要なことを考えさせらた。そもそも何のために事業を始めたのか、何のために会社があるのか。自分に問うてみる。重くて、深い。
情熱は往々にして個人的な情熱である。しかし、事業を始めると、なかなか思うように行かない。いきなり黒字ということは稀だ。利益が上げられなければ会社を続けられないから軌道修正をしなければならなくなる。そして、ようやく軌道に乗り始め、事業を拡大しようとすると自分ひとりでは出来ない。社員が増え、組織が生まれる。株主が増えることもある。こうして会社の利害関係者は多様になり、複雑になっていく。それぞれの段階で、会社を生み出し育ててきた経営者の「情熱」が「企業の目的や存在意義」になり得ているのかが問われることになる。立場の違う利害関係者にも受け入れられる一定の普遍性と合理性を持っているか。逆に、経営者個人の意欲を失わせる方向に向かってはいないか。
これは、どの企業にとっても重要な問題である。とりわけベンチャー企業にとっては、死活的な問題である。あまり語られることのないテーマのようだが、日を変えて少しずつ考えてみようと思う。
- 2001.12.23 気持ち
-
気が付いたら年の瀬、もうすぐ今年も終わる。歳をとるにつれ、時の経つのがはやくなる。しかし、今年はいろいろなことがあって例年になく長かったような気がする。1年前を思い出してみる。まだ、山中湖店も沼田店も水戸大洗店もなく、工事も始まっていなかった。オープンして最初の冬を迎えた那須店や秋田六郷店は利用者が急減し、気をもむ毎日だった。寒さが厳しく、水道管が凍ったという悲鳴だけが届いていた。
あれから1年、店舗数は倍になり、那須店や秋田六郷店の稼動率も大幅に増え、黒字化の見通しも開けてきた。他の類似施設が苦戦を強いられている中、「旅籠屋」が踏ん張りつづけている理由は何か。ひとことで言えば、それはひとつひとつの店舗の灯を守りつづける支配人ひとりひとりの気持ちが生きているからだ。
何回か書いてきたことだが、今年も頭に来ることがあった。いくら正直に熱意を込めて語っても乗ってこないベンチャーキャピタル。1円たりとも与信枠を拡大してくれないリース会社。機械的な対応を崩さない大手銀行や信用保証協会。たらいまわしの役場。ピントはずれのマスコミ。
ないものねだりであることはわかっている。機械的な対応しか出来ないシステムになっていることもわかる。しかし、私が悔しいのは、そこで働く人たちから本物の気持ちが伝わってこないことだ。
先例がどうであれ、示されている基準が何であれ、その背後にある理念を自分の心とし、どうして信じる所に立って進もうとしないのか、どうして形式的な壁に抗おうとしないのか。君たちはそうして一生をむなしく送ればよい。弁解と愚痴だけをまとってうつむいて歩くがいい。
語弊を恐れず言おう。金や名声なんてどうでも良いことだ。気持ちを入れて仕事をしていただける人たちと出会い、悩みや喜びを共有できるのなら、それで私は充分に幸せだ。
社内の態勢も少しずつ整い、もちろん来年も「旅籠屋」は大きくなっていく。誰もがシンプルで自由な旅を楽しめる日を目指して、たゆまず進んでいく。しかし、少なくとも私が経営者である限り、気持ちの入らない仕事はしない。ナイーブな言い方だが、そのかすかな熱が利用者に受け入れられている本質なのだと信じている。一灯の光明、一隅を照らす。感謝!
Tenderlyを聴きながら書いているので、ついつい情緒過剰になってしまう。年末年始の休みの間にハモニカでコピーしてみようか。
- 2001.12.22 マイブーム
-
夜、ひとりでパソコンに向かっている時、よく音楽を聴いている。やっぱりBluesが多いのだけれど、気に入れば何でも聴く。最近のマイブームは、氷室京介の「Tenderly」。先日発売になったバラードコレクションCDの中の1曲。リピートに設定して、今夜はもう延べ1時間以上、同じ曲を流しつづけている。私には、かつて、ほとんど非音楽的生活を続けていた空白の10年間があって、Boowyと出会ったのは残念ながら彼らが解散した後だったが、偶然見かけたライブ映像に捕らわれた。好みの分かれるところかもしれないが、氷室の周囲には強烈なオーラが漂っていて、強い引力で彼の世界に引き込まれてしまう。「Tenderly」・・・マイナーの単純な甘いラブソングなのだが、不覚にも涙ぐんでしまったりする。
ここ数日に限って言えば、ルルティアの「ロストバタフライ」や「愛し子よ」、ピンクの「Get the party started」がお気に入り。いずれも、ラジオやテレビでちょっと聞いて気になった曲。ネットで検索したら、ビデオクリップがストリーミングで見られるからラッキー。お試しあれ。
- 2001.12.09 「旅籠屋」の値打ち
-
10月の「水戸大洗店」で年内の新規出店は終わり。おかげさまで、各店ともまずまず順調で、念願の黒字転換も見えてきた。キュッシュフローもほぼ均衡しつつあるし、必要な場合には、近くの信用金庫から随時運転資金を借り入れることもできるようになった。半年前と比べても劇的な変化である。中小企業の経営者としては、「資金繰り」が何よりも大切なことだから、その悩みや不安から解放されつつあるのは一番の幸せである。
というわけで、少しは暇になってもよさそうなものだが、なんだかんだと忙しい。各店舗を回ったり、いろいろな基本文書を整備したり、システムの見直しを始めたり、出店予定地を見てまわったり。要は、次の飛躍に向けて足元を固めているという感じなのだが、それはそれで、やるべきことは山のようにある。そのほとんどは地味な仕事だが、これはとても大切なことだと思っている。
やってきたこと、やろうとしていることを客観的に考えれば、もっと派手に注目を集めても良いような気がしないでもないが、大風呂敷を広げて「受けを狙おう」という気はまったくない。堅実にやっていれば、それだけで無視できない存在になる。そういう広がりとインパクトを持った事業だと確信しているからである。
「旅籠屋」を支えているのは利用者の評価、そして各店舗の支配人たちの毎日の仕事の積み重ねである。利用者の笑顔が支配人のモチベーションを高め、社員のちょっとした気配りが利用者の満足につながる。そんな良い循環をしっかりと維持できるような形にしていきたい。
なんだか、きれいごとを言っているようだが、そういうことではない。周囲の人に、がっかりしたと失望されたり、不誠実だと非難されたくない、それだけのことだ。結果としてみんなが少しずつハッピーになれる事業であることが、「旅籠屋」の目的であり、値打ちなのだ。
- 2001.10.14 マスコミのセンス
-
先日、あるテレビ局から取材の打診を受けた。ごく限られた広告宣伝しかできないから、こうした取材は大歓迎である。
ぜひに、と答えたが数日して再度電話があり、「最近注目されている新しい宿泊施設はユニークな工法や設備を採用して建コストを大幅に下げているようですが、旅籠屋さんの場合、何か目新しい工夫はありますか?」という質問を受けた。宿泊施設の場合、イニシャルコストを下げることが事業の成否に決定的な影響を与えるから、当社でもさまざまな工夫を行ってきたが、ハード面で特別目新しい大規模な変革というものはない。そのとおり答えたらなんとなくがっかりしている様子だ。先方の取材ポイントが見えてきた。
「車社会のインフラとして欠落していた宿泊施設が誕生し、旅行スタイルに変化をもたらすことが重要です。そういう観点で取材していただけませんか?」
例えばウォークマンや携帯電話は、装置の小型化ではなく、その普及によって多くの人の生活スタイルが劇的にかわったことに画期的な意味があったのではないか、私はそういうことを訴えたかったのだが、話はかみ合わなかった。だって、利用者にとって工法や設備のコストなんてどうでも良いことではないか。
結局、取材の話はそれっきりとなってしまった。
マスメディアの力は大きい。だから、メディアの人たちを無条件にかいかぶる傾向がある。しかし、私に言わせればろくでもない人間も少なくない。ジャーナリストとしてのセンスのない連中が、勘違いして偉そうにしている。アホくさ。
- 2001.09.19 私は、「報復戦争」に反対です
-
いつものように、夜遅くまでパソコンの前でダラダラ仕事をしていたら、交替勤務で「山中湖店」に滞在中だったK取締役から電話が入った。「テレビ見てます?えーっ見てない?大変、大変、ニューヨークの貿易センタービルに飛行機が突っ込んで、ペンタゴンも燃えてますよ!」こんな夜遅くに何を冗談言ってるんだろう、と一瞬ムッとしたが、すぐにTVをつけたら冗談じゃなかった。
それからというもの、すっかり睡眠不足である。おとといからはニューヨーク証券取引所の株価も気になって熟睡できない。
正直に言ってしまおう。他所のケンカは面白い。犠牲者のことを考えたら不謹慎だが、こんなにドキドキする出来事なんて滅多にない。そういう感情を持つことを否定する人がいるとしたら、そういう不正直な正義感の方が危ないことだと言いたい。当事者でないのだから思考は共有できても感情が違うのは仕方がない。その上で考えるしかない。私は自分の心をごまかさないし、自分の脳味噌で考える。
パレスチナ人のようにお祭り騒ぎをする気分にはなれないが、私の中に最初に湧き上がってきたのは「アメリカ人の思い上がりが招いたことだ。1人勝ちは出来ないということだ」という感情だった。そして1週間、私はいろいろと自問自答してみた。
この事件がニューヨークではなく、東京で起こっていたら、どう感じただろう。どうすべきだと考えただろう。
ブッシュ大統領や小泉首相が言うとおり、アメリカ一国ではなく、自由とか民主主義という人類全体の価値観に対する敵対行為なのだろうか。そもそもその価値観とは疑いもなく人類全体が共有しているものなのか。
犯人を捕まえ法で裁く、ということと、「戦争」による報復とはどう違うのか。
盗人にも一分の理、という見方は、エセ知識人的なナイーブすぎる偽善か。
日本は世界にどう見られているのか、どう見られたいのか。気にしている世界とはどの世界なのか。
本格的な戦争になって日本も当事者になったら、私も徴兵に応じて戦場に行くだろうか。
マスコミ報道を見る限り、アメリカは「戦争」に向けてまっしぐらだし、日本は湾岸戦争の時の「汚名」を晴らすべく日の丸を立てて出来るだけ格好良く振舞いたいらしい。一見もっともらしい正義が声高に叫ばれ、威勢の良い勧善懲悪の主戦論が勢いづいている。
私は本来直情的で、駆け引きの嫌いな単純な性格だから、はっきり言って、多くのアメリカ人のように「やられたらやり返す」という気持ちに乗りたいし、1兆円も金を出してバカにされるより自衛隊にもガンガンやってもらって「男気のある日本」として一目置かれたいという気持ちもある。それを「男らしい」と呼ぶのはわかりやすいし、じつは「男らしくない」と呼ばれるのを何より恐れる政治家たちの心情も痛いほどわかる。あー早くガンガンやっちゃってください、と心のどこかですっきりしたがっている自分がいる。
しかし、しかし、しかし。いろいろ考えた末の私の今現在の気持ちはそうした単純な感情を厳重に否定している。報復「戦争」には反対だし、アメリカの尻馬に乗るのもやめて欲しい。理由は、かいつまんで言うと以下のとおりである。
1●今回の事件は、一個人の狂気によるものではなく、長期間かつ広範囲の現実の中で生み出されたことであり、勧善懲悪的な報復で根本的に解決出来る問題ではないこと。
・・・必ず、後継者が登場し、中東で何十年も続いている状況が世界的に繰り返されるだけではないか。
2●我々は知らず知らずのうちにアメリカを中心とする情報や価値観に足場を置いて物事を見ており、西側世界が他の世界に対して「合法的、国家的」テロを行ってきたかもしれないことを公平に理解しているとは言い切れないこと。
・・・パレスチナ問題ひとつをとってみても、アメリカが一方的に「報復」と言える立場ではないのではないか。
3●同様に、無意識のうちに肯定してしまっているグローバリズムというものが、アメリカ中心の経済的効率性や価値観の一方的な押し付けになっており、けっして人類全体の普遍的な「正義」や「幸福の拡大」になっていないのではないかという疑念を捨てきれないこと。
・・・法治主義、民主主義、経済的合理性による多様性の保証などは、長い間に人類が積み重ねてきた英知の成果であると思うが、現時点では富の偏在を生み、逆の結果を招いている現実があるのではないか。
4●「戦争」とは、法治主義の放棄であり、かろうじて積み上げてきた「人類全体の正義」の共通認識を裏切る行為であること。
数日前、「マーシャル・ロー」という映画を見た。設定があまりに今回の事件に酷似しているため、テレビ各局が放映を中止しているようなので、レンタルビデオで見たのだが、じつに示唆に富んでいた。こういう時こそどんどん放映すれば良いのに、困ったものだ。
それにしても、どうして、あっちでもこっちでも争い事が起きると「神様」が大声で呼ばれるのだろう。よっぽど神は戦争が好きなのだろう。だから神なんて信じないほうが良いのだ。それと、報復「戦争」反対なんて言うと、日本ならすぐに非国民扱いに違いない。先日、アメリカの議会で「報復戦争についての臨時支出」にたったひとり反対票を投じた議員がいたそうだが、そういう人がいるところがアメリカの良いところだと思う。田中知事も見直したぞ。
- 2001.08.17 夏、休む
-
忙しいのは、ある意味で幸せなことだ。一応健康ならではのことで、周囲と関わりをもっている証しでもある。思いっきり自由気ままな時間を渇望しているが、何もすることがなく、誰からも頼られない相手にされない毎日を想像すると、そんな自由は私には耐えられそうにない。だから、間違いなく今の私は幸せなのだ。そう自覚しなければいけない。
わかっているが、やりたいこと、やらなければと思うことが次々と積もって山がどんどん高くなる。周囲の目も気になって心穏やかでない。しかし、割り切るしかないと自分に言い聞かせる。旅籠屋の主人、はもらんの裏方、そして年老いた両親の息子、滅多に会えない子供たちの父親。八方いい人になりたいが、中途半端になるのがわかっている。
そう、今週は、お父さんする!と決めたのだ。勇気を持って、休む。いろんなことを引き受けて、旅籠屋の主人を抑えこむ。御免。
- 2001.06.15 深夜の楽しみ
-
おかげさまで、3店舗のオープンが決まり、工事も順調に進んでいる。既存店も冬期の不調から一転して好調だ。正直言って、「那須店」「秋田六郷店」の1年目は期待値を下回ったが、2年目に入って稼動率・売上とも前年を大きく上回っており、ひと安心である。今後は、前年同月比という数字が出るから励みになる。それにしても、去年から今年にかけては毎日が試行錯誤の繰り返し、予期せぬトラブルや人に言えない苦労もあったが、チェーンオペレーションの貴重なノウハウを蓄積してきたことは間違いない。
というわけで、相変わらずメチャクチャに忙しい。延々と忙しい。ホントいつまでたっても貧乏暇無しなのである。
ところで、思わせぶりなタイトル。なにも怪しい告白を始めようというのではない。夜更かしは楽しい、という健全な話しだ。
突然だが、ここで私の毎日の生活パターンを紹介しよう。
起床はなんと朝8時半過ぎ。通勤時間が数秒だから(自室の隣がオフィス)、新聞を見ながらコーヒーを飲んで、それでも10時前にはちゃんと仕事モードに入れる。そのあとはその日のスケジュール次第だが、午後2時頃の昼食をはさんで9時頃の夕食までは電話や来客や雑用に追われながら「あーゆっくり仕事をさしてくれい」とわめきちらしながらドタバタしている。
そのあと夜も10時頃になり、あとはのんびり読書したり、ギターやハモニカの練習でもすれば、私の人生もずっと豊かになるに違いないのだが、知らず知らずのうちに扉を開けてオフィスのパソコンの前に座ってしまう。そうこうしているうちに11時を過ぎ、各店のフロントが閉まる時間になって「ガラガラじゃーん」とか「スッゲー、ほぼ満室!」などと一喜一憂し、日付が変わる頃扉を閉めて退社するわけだ。疲れ果ててしまわないと仕事から上がる気になれない、そんな感じだ。
さぁここでおとなしくベッドにもぐりこめば肉体的には健康的なのだが、なぜか私にはどうしてもそれができない。毎朝のように「もっと早く寝れば良かった」と自分を責めているのに、誘惑に抗しきれず無意識のうちにテレビのスイッチを入れ(通常はヒストリーチャンネルかスターチャンネル)、また昨晩と同じようにダラダラと夜更かしをしてしまうのである。そのうち、2時頃になっていよいよ睡魔に襲われ起きていられなくなると一大決心をして床につくのである。
そもそもである。意欲を持って仕事に取り組んでいる人なら誰だって時間に追われているのが普通であって、ゆとりある暮らしなんて縁がないに違いない。しかし、大部分の人の場合、24時間365日、プレッシャーに神経をさらし続けることは不可能で、その人なりの方法で息抜きをして精神的なバランスをとっていると思う。寝る前の推理小説、通勤電車でのコミックス、パチンコ・マージャン、競馬にアルコール、ワイドショーにネットサーフィン・・・その共通点は一瞬でも「我を忘れられる」ことか。私の場合、それが深夜なんとなくぼんやりダラダラとテレビをながめることなのである。
あしたは土曜日、夜には東京に戻って(今「秋田六郷店」に滞在中)心置きなく夜更かしするぞ。
・・・ここまで書いて、やっぱりこういう習慣は本気で改めなければならないという気がしてきた。
- 2001.04.20 偽ネットワーク技術者
-
天邪鬼の私は、ときどき「旅籠屋は、どうせローテクビジネスですから」などと、すねてみたりする。だが、ツールとして使っているという意味で言えば、この規模でこれほどネット技術を活用している企業は少ないのではないかと思う。
本社内のLAN、本社と各店舗を専用線で結ぶWAN、オリジナルのフロントシステム。もちろん、すべての情報は一元的にデータベースに集約されいる。加えて、ウェブサイトを開設して予約受付を始めたのは、もう4年以上も前のことだ。そのあたりの苦労話しはこの「旅籠屋日記」に詳しい。
しかし、残念なことに、当社にはPCの専門家もネットワーク技術者も存在しない。そんな人材を抱える余裕がない。その結果、しわ寄せは他でもない私に来る。昨年「那須店」近くに落雷があって、PCやルーターなどが即死した時の救急隊員は私である。つい数日前、「鬼怒川店」のネットワーク変更にともななうOSの入れ替えやルーターの設定に夜なべ仕事をしていたのも、この私である。
誤解のないようにくれぐれも言っておくが、「社長自らが出かけていってするような仕事じゃない」などという発想は私にはない。まわりに不平不満を言っているのでも、もちろんない。きちんとわかってもいないくせに、仕方なくこうした作業を行って、何が間違っているかもわからず失敗を繰り返してしまうことがじつに情けないのである。
自慢ではないが、ITなるものが、仕事にどれだけの恩恵をもたらすか、そのために仕事の進め方自体をどのように整理統合すべきか、という点について、私はその本質をかなり的確に理解し、当を得たシステムを作り上げてきたつもりである。しかし、システム構築の個々の具体的な作業は、本来職人の領分である。そして、私には、聞きかじりの知識や我流の断片的な経験があるばかりで、しょせん偽ネットワーク技術者に過ぎないのである。
それなら、潔く専門家に任せれば良いものだが、その費用は「旅籠屋的には」とんでもない金額だったりする。そして、パソコン周辺には「もしかしたら、俺にも何とかできるかもしれない」という幻想を抱かせる雰囲気が漂っていて、背伸びしながらも試行錯誤を繰り返してきたという次第である。そして、結果的になんとかなっているから、始末が悪い。
ところで、この7月には「山中湖店」「沼田店」がオープンし、「旅籠屋」もいよいよチェーンらしくなっていく。人・物・金・・・あらゆる資源が不足しているという意味で、当社もベンチャー企業の典型なのだが、そろそろあらゆる面で態勢を整えていかなければならない段階に差し掛かっている。本社と各店舗を結ぶネットワークやその上で動いているソフトも、6月には抜本的なシステム変更を行う予定である。セキュリティの問題もあり、詳しくは書かないが、この変更によって、急速な店舗増加にも対応できるシステムとなる。ハードやシステムの設定・メンテも格段にシンプルになる。通信費もかなり割安になる。
というわけで、またまた偽ネットワーク技術者の出動となるわけだが、あー、もうルーターの設定だけはイヤだ。ほんとうに何がなんだかわからずに仕事するのはイヤだ。今から気が重い。ほんとうは、人の整備が何より必要なんだよね。
- 2001.04.09 文章って怖い
-
最近の日記を読んだ知人から「なんとなく心配」ということで連絡があり、久しぶりに食事をした。
「こんな文章を読んだら、投資家の人たちに否定的に受け止められるんじゃないの!」と言われて、「うーん、そういうものかなー」と驚いてしまった。「事業の方は着実にステップを登って、ようやく多店舗展開できる段階まで来たし、発言の裏にそういう自信があることをわかって欲しいなぁ」と答えたが、読み返してみたら、確かに弱気にとられそうな雰囲気が漂っていたかもしれない。
困った、困った。そうじゃないよ。逆なんだよ。ここまで来ても「旅籠屋」の値打ちを理解できない連中はホント大馬鹿だって言いたいだけなんだよ。
でも、仕事とは直接関係ないところで何かとストレスが多く、気持ちが滅入っていることのは確かだ。文章って怖い。そういう気分が知らず知らずのうちにしみ出していたのかもしれない。しかし、問題の多くは一応の解決に向かって動き出した。あー、明日からは、仕事だけに全力投球するぞー。
時代が、社会が、「旅籠屋」のメジャーデビューを首を長くして待っている!なーんちて。
- 2001.04.05 未だ出会えぬ人
-
きょうは、半年前から準備していた「第三者割当増資」の払込期日だった。まだ、公式なIRを行っていないので、具体的な内容には触れられないが、残念ながらベンチャーキャピタルからの出資は一部にとどまってしまった。この点については、3/16付けの日記でも触れたが、20社を超える企業との協議をとおして、日本のベンチャーキャピタリストの実像の一部を垣間見ることができた。
いっぽうで、一昨年の公募増資の時に株主になっていただいた個人投資家の方などからは、予想をこえる支援をいただいた。目先の数字ではなく、間違いなく「旅籠屋」という企業とその事業をご理解いただいたうえでの追加出資であり、経営者としてこれほどありがたいお金はない。
株式市場のシステムは、純粋に損得の世界であることが存在の基本であることは間違いないことなのだが、人間の意思や意志が働くことを排除するものではないし、それこそが現在と未来をつなぐ市場メカニズムの妙味だと思う。
難解な指標や解析手法を用いて、企業の将来価値を算出する数式もあるのだろう。その点で評価すれば、リアルビジネスである「旅籠屋」は地味な存在なのかもしれない。しかし、多くの人が信頼し、期待し、共感すれば、それは間違いなく目に見える数字となって実現するはずだ。事業家の立場から見れば、それこそが事業の目的とか理念とか社会的意義と言えるものであり、もっとも大切にしなければならないものだと私は考える。
残念ながら、こうした点について理解いただけるベンチャーキャピタリストに、私は出会えなかったように思う。
そもそも、投資対象をベンチャー企業に特化するプロの投資家に必要なこと、それはいったい何なのだろう。
公開が見えてきた企業の匂いをかぎつける嗅覚?それも必要だろう。しかし、そんな程度でなら、おこぼれにあずかるハゲタカやハイエナに過ぎない。冷徹な計算と読みの向こうに、目に見えない新しい価値創造を仕掛けていく、それこそベンチャー企業への投資の醍醐味ではないのか。
プロの投資家に、事業家のロマンを共有して欲しいとは思わない。しかし、立場は異なっても、より高い次元で、共鳴できる世界があると、私は信じたい。骨のあるプロの投資家はどこに隠れているのか。
- 2001.03.16 あるベンチャーキャピタリストへ
-
先刻は、お時間を割いていただき、ありがとうございました。
じつに残念ですが、致し方ありません。
結果は同じでも、率直な意見交換をさせていただいたことに、感謝しています。
当面、間違いなく無駄な時間と労力を強いられることは気の重いことですが、
「旅籠屋」の普及が、これからの日本と日本人に大きな可能性を与えることを信じ相変わらず努めていく所存です。
おそらく、こうしたナイーブな物言いが、違和感を感じられた点だったかもしれません。
事業は、こうした思い入れとは関係なく、自律的に利益を生み出す構造であるべきことは無論のことなのですが、しかし
そのモデルを生み出し導いていく事業家には、密かに守るべき矜持というものがあり、
それこそがベンチャービジネスを起こす人間の存在意義なのだと、私は考えたいのです。
立場は異なりますが、時代に新しい可能性を提供していくという意味では
ベンチャーキャピタリストも同様であるとは言えないでしょうか。
群盲の投資家の資金に意味を与えることが使命、と言えば非合理的と笑われるでしょうか。
ならば、そもそも投資の合理性とは何なのでしょう?
ともあれ、「旅籠屋」が他の十の企業よりも投資価値のないという結果は無念でした。
未練がましい怨み言を申し上げるつもりはありません。
けっして皮肉ではなく、今後のご活躍を期待しております。素晴らしい仕事です。
頑張ってください。
- 2001.02.04 ストラトキャスター
-
昨夏、下の息子にねだられてギターとアンプをプレゼントした。ギターはフェンダーのストラトキャスター、アンプはマーシャルである。知らない人にはまったく伝わらないことだけれど、かつてロック少年であった私(今もそうだな)にとっては、いずれも夢のような憧れのブランドだ。御茶ノ水の楽器屋街で買い求めたのだが、驚いたことにそういうブランドの品々が信じられないような値段で売られている。日本製だから多少値打ちは下がるといえ、あの「ストラト」が2万円くらいから買えるのだ。マーシャルのアンプだって個人練習用のような低出力のものだから同じような値段。あわせて5〜6万円なのだから、私はすっかり浦島太郎になっていたわけだ。さっそく家に持ち帰って音を出してみたのだが、これまたびっくり仰天。下手くそな私が弾いても、あのシャリシャリ・パキパキあるいはメロウなあのストラトの音がするのだ。アンプも抜けのいい、あるいは適度に歪んだパワフルな音がするのだ。まるで、自分がクラプトンかベックになったような幻想にとらわれる瞬間がたしかに味わえる。
30年前、フェンダーとかギブソンとかのロゴの入ったギターはガラスケースに入っていたのではなかったか。マーシャルなんてプロのステージ写真の中だけの存在ではなかったか。それが今自分の腕の中に抱かれて、それらしい音を出している。あーなんという幸せ、なんという悦び。あの頃、ありったけの金をはたいて買ったレスポールもどきのアリアのギターはこんな音で私に幻は見せてくれなかったぞ。
冷静に考えれば、あの後も円の価値は上がりつづけていたのだ。
というわけで、私のギターへの興味は30年ぶりに呼び覚まされた。そして、辛抱たまらず、この正月明けに私も自分のストラトキャスターとフェンダーのアンプを衝動買いしてしまった。あわせて7万円くらい。自由になる金がほとんどない(これは本当のことです)私には無謀な出費なのだが、人生は老後のための貯金をするためにあるのではないという主義の私には充分に賢明な決断であったと、あえて言う。
今年に入って、出張などで家を空けることが多く、居ても仕事に追われてゆっくりギターにさわれる日も少ない。それでも部屋の片隅に置かれている「ブラッキーもどき」の姿を見るだけで私はドキドキするほど幸せである。
- 2001.02.01 それぞれの人生
-
正月に、昔いっしょに映画をつくっていた仲間たち5人で集まった。25年ぶりの再会もあった。頭が薄くなって帽子をかぶっている奴、すっかり白髪の増えた奴、でも、それらを除けば外見はそう変わりはない。
商社マン、弁護士、映画監督、ハウスハズバンド、ベンチャー会社社長。
こう表現すれば日経新聞の交遊録のネタになりそうな華々しさだが、別の表現をすれば・・・やめておこう。
みんな、それぞれに「肩書き」や「職業」などでは計り知れない25年間の時間があり、今の生活がある。会話の端々に重たい現実が見え隠れするが、あえて深入りはしない。それで良いのだ。
「また会おう!」そう言いあって別れたが、その時の笑顔がなぜか嬉しかった。
新しくオープン予定の店舗の支配人募集などで、昨年暮から10組以上のご夫婦に面接させていただいた。年齢は40代から60代。ふたりそろっての面接であり、それぞれのご夫婦の人生が垣間見えてくる。年上の方に立ち入った質問をしなければならない場面では、心苦しい。思わず向こう側に座っている自分を想像してしまう。
それぞれの人生。要するにそういうことだ。それにしても、波長のあっている夫婦っていいね。
- 2000.12.03 ストリート・ミュージシャン
-
先日、もし宝くじがあたったらどうしようという話しで盛り上がった。マンションを買うという人、海外旅行に行くという人、私もすっかりその気になって考えたけれど、真っ先に浮かんだのは旅籠屋の株を買って、その資金で新しい店舗をオープンさせたいっていうこと。どうしてもすべての思考が「旅籠屋」中心になってしまう。というわけで、さっそくお金を出し合って年末ジャンボを買ったんだけど、ほんと、当たってくれないかなぁ。
いつも現実に追いかけられているから、夢を思い描くのは楽しい。もう一度生まれ変われたら、サッカー選手兼ミュージシャンになりたいって言ったら「女の子に騒がれたいという下心が丸見えだ」とバカにされたが、それは誤解だ。サッカー選手といっても別に一流選手でなくても良いから、自由自在にボールを扱えてドリブルやパスができたらどんなに楽しいだろうって思うのだ。しかし、これは年齢的にもう叶わぬ夢だ。しかし、もうひとつのミュージシャンならまだ可能性がゼロというわけでもない。これも、プロになるという必要はなくて、要は何か楽器をマスターして、自在に演奏できることにあこがれているのだから練習すればできるかもしれない。
例えば、大好きなブルースハープ。これなら、少しは吹けるし、その気になって練習すれば、ストリートミュージシャンとしてデビューできるかもしれない。きょうも、歩行者天国の路上で、若いハーピストがひとりで吹いてた。とても、輝いて見えた。
誰か、ブルース大好きなギター弾きで、休みの日にストリートでやってみようか、なんて夢見ている人、いませんか。半分マジです。
- 2000.11.21 失望
-
今回の政局ドラマ、なにか大きなことが起きるのではないか、とワクワクしながらテレビを見ていたが、私的には最悪の結果に終わってしまった。なんだかんだと言いながら、結局永田町の人たちって、浪花節と権謀術策のグチャグチャの世界で行動を決めることがよくわかりました。古い体質に決別!なんて言ってた加藤さんには、その政策はともかく、合理的な思考方法にもとずいて行動しようとする姿勢に期待していたのに、まったく失望してしまった。欠席を決めた後の派内の集まりで「山崎さんと私のふたりだけは賛成する。皆さんは残ってください」なんて言ってる姿は滑稽そのものだった。「大将ひとりでは行かせない」という型どおりの引止めとウソ涙。20年前のスポコンドラマ・・・正視に耐えなかった。
権謀術策なら、とことん鉄面皮の策士の方がわかりやすくていい。政治信条に殉じるという潔さを演じとおして欲しかった。だいたいアメリカの大統領候補だったら、人前で涙を流しただけで失格の烙印を押されてしまうというのに、あー甘い、甘い、情けない。
これで、ますます日本が嫌いになる若い連中が増えるのだろう。旧来の浪花節的な日本人思考とは一線を画し、しかも幼児性の抜けた「おとな」の政治家は居ないのかね。
マッカーサーが言ってから50年以上も経ったのに、日本人の精神年齢は未だ小学生並なんだろうか。
- 2000.11.19 IRセミナー
-
先日、「IR実践セミナー」なるものに参加した。株式公開を計画している企業を対象に、IRの意味や具体的な方法について、多彩な分野の専門家がレクチャーしてくれるセミナーだ。昼食をはさんで1日8時間、3日間の講習は、かなりきついものだったが、当社の場合、すでにVIMEX市場に登録し、一定のIR活動をおこなっているため、理解しやすく参考になることが少なくなかった。
そこで、あらためて再認識させられたことがある。それは、いったん株式を公開してしまうと企業の経営者はもはや自由に発言をすることが許されない、ということだ。
「旅籠屋」という新しいスタイルの宿を1人でも多くの人に知ってほしい、そういう願いからこのホームページを開設し、同時に「旅籠屋日記」というコーナーもスタートさせた。もう4年近く前のことである。そして、1年前までは難しいことは何も考えず、気分次第で考えていること、感じていることを書いてきたのだが、今はそうもいかない。例えば、こんな人に会ったとか、こんな場所に行ったとか、こんな企業の人と話をしたなどということは、それがどんなに面白い話でもそのまま表に出すことができない。投資家の方々にとって、それが事業の動向を占う重要な情報になってしまうからだ。
ならば、仕事に関係のないことを書けばよいようなものだが、私の日常生活のほとんどが仕事を中心に回っていて、どこへ行っても、誰と話をしていても仕事と結び付けて考えてしまうから、仕事からまったく離れた日記なんて、逆に書く意欲が湧きにくいのだ。
IRの基本は、「隠さないこと」「うそをつかないこと」「タイムリーに語ること」なのだそうだ。自慢ではないが、「旅籠屋」について、私は何一つ隠し立てするようなことはないし、時に無邪気すぎるほど会社の状況をオープンにしてきた。ところが、ホームページでの情報発信は必ずしも全員の目に触れるわけではないから、ここだけで情報発信するというのはフェアでないということになるらしい。
私にとって「旅籠屋」は単にお金儲けの手段としてのビジネスではない。自分自身がこれまでの人生で感じてきたこと、好ましく思うこと、嫌いなこと、すなわち夢や理想を実現したいという気持ちがモチベーションの基本にある。とりわけ、ベンチャー企業にとって、経営者のこうした想いこそが企業の活力やビジョンの源泉のひとつになっているのは自然なことであり、その志が企業の存在価値を決める重要な鍵になるのだと思う。だからこそ、株主や投資家の方は経営者がどういう性格で、どういう感受性の持ち主かということに大きな関心を持つのだろう。
あー困った。感じたことをもっと自由に書きたいのに、それができない。つまらない。ほんとうは、公式発表される「結果」よりも、その「過程」こそワクワクするようなドラマがあるのに・・・って、こういう発言も控えたほうがよさそうだ。
鮮度は多少落ちるかもしれないが、「アンフェア」にならないように注意しながら、血の通った話しをしていこう。
- 2000.10.11 ラジオ出演
-
ひょんなことから、「FMさがみ」(83.9MHz)という神奈川県のローカルラジオ局の取材を受けた。
社会を支える重圧で疲れている40代以上が夢を取り戻し、楽しんで、みんなで元気になろう、という主旨の「中年ネットワーク」というプログラム。毎週日曜日24時から30分放送されている中高年の応援番組だ。
ユニークなのは、この番組を提供しているオーテックという会社。不登校、引きこもり、高校中退者等の社会復帰を支援するフリースクールを主宰し、あわせてその親たちを対象にさまざまの活動を続けている。「見ないふり、知らないふりをして、思考停止で逃げ回る」人の多いご時世に逆らって地道な活動を続けていることに、素直に敬意を表したいと思う。この会社のサイトをぜひご覧いただきたい。
さて、インタビューの方だが、問われるままに、ぺらぺらとしゃべった。聴き直してみると、はからずも「旅籠屋の主人、半生を語る」みたいな内容になっていた。録音データをいただいたので、どうぞ聴いてみてください。
前編(10月1日放送分)と後編(10月8日放送分)のふたつ、いずれもリアル・オーディオのファイルでそれぞれ4.4MBあります。
自分の持っている自己顕示欲や幼児性を、私は、否定しない。だって、大なり小なり、みんなそういう気持ちを持ってるんじゃないの。
というわけで、照れくさいけれど、聴いて欲しい。正直言って、そんな気持ちであります。
- 2000.09.04 トラブルこそノウハウだが
-
「旅籠屋」が3軒になって初めての夏休み。おかげさまで、8月の客室稼働率は「鬼怒川店」が95%、「那須店」が94%と、月末の2日間を除いてほぼ満室。「秋田六郷店」も43%と健闘した。1ケ月の売上も1,500万円を超え、前年度の売上高の1/3以上を稼ぎ出した。しかし、こう忙しいと各店の支配人は心身ともにクタクタである。私も「鬼怒川店」「那須店」に3日間ずつ手伝いに行ったのだが、久しぶりに汗だくになって走り回った。
それにしても、こんな忙しい時なのに、というか、こんな時に限って予期せぬトラブルが発生する。
ひとつめのトラブルは、8月5日。「那須店」の脇に立つ電柱に落雷があって、WANのシステムが機能しなくなった。電話線を経由して異常な電気が流れ込んだらしく、本社のサーバーとの間でデータをやりとりするルーター、電話やドアホンをコントロールするターミナルボックス、そしてさらにパソコンやモニターの電源ユニットまでも破壊し、フロントシステムはもちろん電話もつながらなくなってしまった。電話については翌朝にNTTが臨時のTAを設置してくれて通じるようになったのだが、フロントシステムが使えないので、空室状況もわからずチェックイン・アウトの作業もままならない。慌ててルーターとターミナルボックスの新品を購入し、翌々日に「那須店」に駆けつけ復旧作業を始めたのだが、とりあえず支配人所有のノートパソコンを代用できるようにするのにの2日を要してしまった。私のような素人にとって、データ送信のためのルーターの設定は難解にすぎる。ちなみに、完全復旧は、パソコンの修理とモニターの交換を待つことになったため、さらに半月の時間を要することになった。
ふたつめのトラブルは、8月16日。当社のホームページの中身が収めてあるレンタルサーバーの交換にともない、「ゲストブック」への書き込みなどサーバー側にしか保存していないデータの一部分が消えてしまったこと。これは前からバックアップを取っておくようにとのアナウンスがあったのに私が作業を怠っていたために起こったことで人為的なミスである。
みっつめのトラブルは、8月26日。私が常用しているノートパソコンのハードディスクが突然クラッシュしてしまい、そこにしか保存していなかった過去7年間のすべてのメールや最近作成した文書のデータなどがすべて失われてしまったことだ。ハード自体は即日交換してもらったが、データの読み込みは不可能とのことで、取り返しのつかない事態になってしまった。この1週間、OSを含めすべてのソフトをインストールし直し、さまざまな周辺機器が使えるよう設定をし直したが、これだけでもたいへんな作業になってしまった。
「旅籠屋」の経営や運営は、パソコンやネットの活用なくして成り立たない。一連のトラブルは、そのことをあらためて思い知らせてくれた。それは、システムにトラブルがあると業務に重大な支障が生じるということであり、またその危険性は常に存在するということなのである。
後ろ向きに嘆いても仕方ない。トラブルこそ未来への教訓。こういう経験こそがノウハウなのだ・・・とため息まじりに言ってみる。
- 2000.07.20 最近、頭にきたこと
-
「那須店」と「秋田六郷店」のオープンから一息つく間もなく、急遽決まった「鬼怒川店」の改修工事と決算の処理に忙殺されている。前者は昨日予定どおり工事が完了したが、後者はまだ作業半ばというところだ。
昨秋の公募増資をきっかけに精度の高い会計処理を行う義務と責任が生じて事務が煩雑になっているということに加え、これをベースに今後の事業計画を策定するための戦略的な分析と判断に時間を要するということなのだ。
というわけで、相変わらずゆっくり日記を書く余裕もないが、最近ちょっと頭にきたことがあるので、書き留めておきたい。
先日、私個人として学資ローンの申込みに銀行に行ったときのことだ。当面必要な額だけを臨機応変に自由に利用したいのなら「カードローン」の方が適しているとのことで、200万円の枠で申し込み手続きを行ったのだが、数日後、見事に断られてしまった。
毎月の役員報酬の振り込みと公共料金の支払いなど、すべてこの銀行の口座を利用しているし、もちろん過去にブラックリストに乗るようなことは何もしていない。たしかに経営者とは言っても会社未だに赤字だし、私個人の年収は同年代の大企業サラリーマンよりはかなり少ないと思うが、それにしても、たかだか200万円の信用も与えられないのかと愕然とした。
後日、別の都市銀行の担当者にこの話しをしたところ、「審査は別のセクションで機械的に行うので、個別に要素を加味して判断するのは難しいのですよ。勤続10年以上のサラリーマンなら通る可能性が高かったのでしょうが・・・」ということだった。
審査基準の判定を単純化して、手間暇のコストを節約しなければならない事情はわかる。しかし、それは、リスクをとるかどうかの判断を省略していることでもある。リテールバンクを標榜する銀行の実態を垣間見た気がした。ないものねだりをするつもりはない。しかし、正直なところ、ひじょうに不愉快だった。
銀行で腹の立った記憶といえば、6年前にも忘れられないことがあった。15年を越えるサラリーマン生活にピリオドを打ち、株式会社 旅籠屋本店を設立しようとしていた時のことだ。資本金として集めた現金をどこかの銀行に振り込み「保管証明書」を発行してもらい登記所に提出する必要があるのだが、サラリーマン時代一貫して給与振り込み先にしていた銀行で門前払いをくらってしまった。
担当者いわく「個人事業から法人なりする場合なら可能なのですが・・・」。「宿泊事業のように、初期の設備投資の必要な事業の場合、個人事業を経由して法人設立という方が不自然ではないか。そもそも、借入れの申込みではなく、預けたお金の保管照明を求めているだけなのだから貴行には何のリスクもないではないか」と主張したが、再検討の機会は与えられなかった。
前者は三和銀行・浅草支店、後者は第一勧業銀行・西麻布支店でのことである。
ベンチャー企業の経営者なら誰しも銀行であれ、取引先であれ、顧客であれ、周囲に軽んじられ信じてもらえない悔しさを経験している。そういう時に門前払いにせず真摯に対応してくれる相手の存在はほんとうに嬉しいものだ。そういう企業や個人とともに成長していきたい、いつか恩返しをしたいというのは自然な感情だ。
企業の経営者として、判断は冷静かつ合理的でなければならない。感情に流されるのは好ましいことではない。それを承知で言うが、少なくとも私は一定の合理性を逸脱しない範囲内で、そういう人たちと仕事をしていきたい。それが、損得では計れないベンチャースピリットではないのか。そして、こうしたマインドが企業の発展と矛盾するようになった時、それが起業家の引き時なのだと考えている。興すことと育てることは、モチベーションの異なることだ。
いずれにせよ、私はふたつの苦い経験を忘れることはない。仕方のないことだと水に流すほどお人好しでもクールでもない。必要最小限のつきあい以上の関係は、将来にわたってない。
- 2000.06.13 アメリカ
-
アメリカの大学に進んだ息子が1年目を終えて戻ってきている。大学生たちの無軌道ぶりなど、ともに生活してみなければわからない話しをたくさん聞いた。
そうか、そんなに無茶苦茶なのか・・・
私が子どもの頃、ようやく普及し始めた白黒テレビの中には、大きなソファでくつろいでいる上品なパパと、ハイヒールで料理するママと、土曜の夜にボーイフレンドの車でデートに出かけるブロンドの髪の女の子たちがいた。50年代から60年代にかけてのアメリカ、あのホームドラマのイメージは、甘酸っぱい音楽と一緒になって、私のアメリカ観の原点になっている。
その後、ケネディ暗殺があり、ベトナム戦争やヒッピーやウッドストックがあり、その印象はどんどん変っていった。私自身も「おとな」になり、政治や経済のリアルな面でアメリカを見るようになった。音楽の面ではブルースと出会い、夢見るような甘いポップスは、幼稚なものにしか聞こえなくなった。
そんなアメリカに行ったのは、30歳近くになってからのこと。憧れなど失っていたはずなのに、初めての海外旅行だったせいか、まじかに見る異人さんは香水の匂いがして、体型が別の生き物のようで、そばにいるだけで緊張してしまった。町に漂っている雰囲気も日本とは随分違っていた。何もかもが新鮮で、刺激に満ちていて、自由でパワフルで躍動的な印象を受けた。子どもの頃とは別の意味で、また私はアメリカに惹きつけられた。
それから20年近く、仕事を含め、何度もアメリカに行った。モーテルをお手本にしたロードサイドホテル事業を手がけるようにもなった。合理的だけど不合理。新しいけれど保守的。親切だけれど不親切。豊かだけれど貧しい。少しずつ多様なアメリカを知るようになった。
この1週間、車で「鬼怒川店」「那須店」「秋田六郷店」を泊まり歩いた。その道中、ずっと山下達郎や竹内まりあの曲を聞いていたのだが、彼らの曲はずっと昔の夢のアメリカの音に聞こえる。忘れていた懐かしさがこみ上げてくる。しかし、その気持ちが収まる場所を見つけられない。
あのホームドラマは一時期だけの蜃気楼だったのか。いや、そもそもブラウン管の中の幻想だったのか。甘いポップスもCMソングのようなものだったのかもしれない。もちろん、私の10代や20代はあの世界とは無縁なままに過ぎた。
しかし、豊かで、美しくて、楽天的で、みんなが未来への希望を共有している雰囲気。それは、かけがえのない「若さ」や「青春」のイメージと重なって、「いつか行けたかもしれない場所」として心の拠り所になっていた気がする。
息子から聞いた粗野で、傲慢で、自堕落な若者たちの実態。結局はすべて「あらかじめ失われた恋人たち」だったのか?
なんとなくつまらないぞ。夢を見させてくれないアメリカなんてつまらないぞ。
- 2000.05.02 ベンチャーの真実
-
先日、ある人に「ゴールデンウィークはいつからお休みですか?」と尋ねられた。なんとなくムッとしてしまい「休みなんか、ありませんよ」と答えた。「那須店」のオープン準備やら何やらで、フラストレーションがたまっていたのだ。簡潔すぎる答えを半ば冗談ととられたようだ。似たような質問を繰り返されたので、さらに語気強く言ってしまった。「自分で商売をやっているんですから、24時間、365日、休みなんてないですよ」。
言う必要のないこと、言っても理解してもらえないことを口に出してしまった。時候の挨拶程度の問いかけに、こんな過剰反応をしてしまうこと、それこそがここ数ヶ月の疲労の蓄積の証しだ。
最近、上も下も「ベンチャー、ベンチャー」と騒いでいる。新しいアイデアやビジネスが生れることは、世の中に活力を与えることだから、もちろん良い。既成の組織や生き方に安住せず自己責任で自分の世界を開拓していこうとするベンチャースピリットも素晴らしい。とくにこの日本においては。
しかし、これは総体的なマクロの話しであり、個別のミクロの場面を見れば、ベンチャーなんてけっして夢のような世界ではない。これらがゴチャゴチャになり、無数のバブルを生んでいるように感じられる。
そのことを詳しく述べる時間の余裕はまだないので、端的な言い方しかできないが、ベンチャービジネスを興す当人は孤独である。強制されなくても、睡魔に負けるまでは仕事をしてしまう。食事中も、入浴中も、いつも心のどこかで仕事の段取りのチェックをしている。
だから、「ベンチャー」に憧れ自己目的化しているような人は、おそらく挫折するだろうと思う。当然の困難に直面したとき、その困難そのものよりも、ちっとも幸せな気分になれないことに気づいて、意欲を失ってしまうだろう。悪魔との取り引き。心安らかな時間を売って得られたものの頼りなさに愕然とするだろう。
ベンチャースピリットにも耐久力の強弱がある。モチベーションの強弱と言ってもよい。既存のルールや仕組みの中で悪戦苦闘した結果としての起業なら、単なる憧れではない。世の中の現実にも無知ではないし、困難を乗り越える知恵や道具も携えているだろう。何より、バラ色の成功なんて夢見ていないから、自分なりの充足感をステップにして歩き続けていける。
ベンチャーなんて甘くない、なんて、どこにでもいるようなオヤジみたいな言い方はしたくない。世の中甘くないなんて言い方もしたくない。何もしないで愚痴だけこぼしているような連中よりは、ずっと人生に対して誠実な生き方だと思うからだ。
会社を設立して6年、ようやく「旅籠屋」が事業として成立する見通しが見えてきたに過ぎない私が偉そうに言うのも気が引けるが、20代のアントレプレナー達に言いたい。自分の本音を聞け、自分の本性を見よ、と。潰れて欲しくない。
「那須店」がオープンして早1週間。ゴールデンウィークはほぼ満室。ほんとうに忙しかったが、今つかの間の安堵感を味わっている。世の中はオフモード。電話も来客も減り、ようやく溜まる一方だった仕事の山に取り掛かれる。ゆっくり仕事ができる。心安らか、と言っても仕事に集中できる幸せだ。でも、けっして苦痛じゃない。苦痛じゃないから、私には出来る。
- 2000.04.15 はもらん浅草「発表会」
-
1月から本社オフィスでスタートした「はもにかラウンジ浅草」。きょうは3ケ月に1度の発表会だった。


講師の松田幸一さん、ゲストのヒロ西村さん、受講生の皆さんなど約40人。飲み食いしながらおおいに盛り上がった。皆さん楽しそうで、それが何よりだった。
今年に入ってからというもの、「那須店」や「秋田六郷店」の開業準備などで多忙をきわめており、ほとんどハモニカの練習をする時間もなく、今回も私自身の演奏はまったくの不出来で口惜しい。
仕事がこんなに忙しいのに、ハモニカ教室の裏方や8耐プロジェクトまで抱えてしまい、欲張りすぎだった、見通しが甘かった、と思うことも確かにある。どちらも他の大勢の人たちに関係することだから手を抜けない。一日が40時間あれば、私のクローン人間が3人くらい居れば、と切実に思う。
しかし、人生なんてこんなもんだ。忙しさは重なるものだ。忙しいからといって、仕事だけにのめりこんでいるとどこかで心のバランスが崩れてくる。自分の好きなこと、意欲を感じられる世界を複数持っていることはとても良いことだと思う。ただ、こうした忙しさのしわ寄せは、結局私自身の睡眠時間に影響してくる。体調管理は間違いなく不十分だ。5月いっぱいで「秋田六郷店」が終われば6月には余裕ができるだろう。数年ぶりにゆっくり旅行でもして、心身ともにリフレッシュしようか。
- 2000.03.04 通信環境の整備
-
チェーン店が3軒に増える。そこで課題となるのが、事業所間の通信環境の整備だ。
3年前にオリジナルの運営ソフトを開発して利用していることは、このコーナーで詳しく書いた。予約の受付・部屋割り・チェックイン・チェックアウトなどのフロント業務に加え、顧客管理や会計までを一体化したソフトで、現物を見た人は一様にその使い勝手の良さと必要十分な機能に驚く。このシステムこそが、事業の計数管理の基礎になっており、支配人の運営業務を支えている。ソフトハウスに依頼して開発に1年を要したが、市販品にはないスグレモノができたと自負している。
これまでは「鬼怒川店」と「本社」の1対1の関係だったので、データベースのオリジナルを「鬼怒川店」のPCに置き、毎日そのデータをダイヤルアップで電話回線をとおして本社に送りバックアップをとる、という方法で対応できたが、店舗が複数になればそうはいかない。例えば顧客データひとつとっても、店舗ごとに持つのでは内容の整合性がとれない。同じ顧客のデータが複数の店舗で更新されることがあるからだ。
というわけで、さまざまなシステムを検討してきたが、本社にデータベースサーバーを置き、各店舗のフロントのPCをクライアントとする方式がもっともシンプルだ。問題は、こうしたシステムにするには全体を常時接続しておく通信線の費用と必要十分な通信速度の確保だ。
単独の専用開設で本社と各店舗間をつなぐ方法も検討したが、これは高い。それに店舗が増えるに伴い、本社側の回線もどんどん増えていくことになる。インターネット利用は経済的だが、セキュリティと通信速度の面で難しい。結果的に採用したのはフレームリレーというネットワークを利用したシステムだ。
詳しいことはよくわからないが、これだと通信費も割安でWAN環境が成立する。DDIに申込みを済ませ、電話屋さんで電話加入権を購入、手続き関係は終わった。続いて、信頼性の高いデータベースサーバーマシンとフレームリレー対応のルーターを購入して、「鬼怒川店」と「本社」間でのテスト運用という順番になる。
会社を設立したとき、PCは1台だけだった。「鬼怒川店」がオープンして、フロント用のPCを用意して2台の間でLANを組んだ。「本社」オフィスを構えた時、「鬼怒川店」との間でダイアルアップだがルーターを設置してWANの環境をつくった。そして、いよいよ本格的な広域のネットワークの構築だ。
ますます複雑になっていくし、お金もかかる。でも、便利な世の中になったものだ。
- 2000.02.13 五十肩、その後
-
昨年の春から右肩が五十肩になり、秋からは左肩も痛み始めて苦しんでいると書いた。嬉しいことに、その後全国各地から100通を超える励ましのメールをいただき、あらためてネットの持つ情報伝達力の大きさと広がりを感じている次第。
というのは、もちろん真っ赤なうそで、友人知人さえも誰一人気にしてくれない。当たり前だ。私が五十肩のせいで、ワイシャツを着られないとか、風呂で背中を洗えないなんてことは、どうでも良い他人事なのである。だから「五十肩、その後」なんて誰の興味も引かないことだけど、ここは「日記」なのだから、自分のために書けばいいのだ。
結果だけ書くと、ずきずきぴりぴりと痛んでいた右肩も、発症から4ケ月が過ぎた今年1月をピークに痛みがどんどん治まってきている。右肩は昨秋から快方に向かいつつあるので、半年前と比べると大幅な改善である。
もちろん、まだ全快にはほど遠く、今でもひとりでワイシャツを着ることができないのは相変わらずだが、でも激痛で目覚めることはなくなったし、重症の肩こりからも解放された。
というわけで、きのう久しぶりにバイクで都内を走り回ったのだが、何のストレスも感じなかった。そのことだけで私は十分に幸せな気分になり、痛みのない暮らしに感謝した。
「健康がなにより」。ほんと、そうなんです。
- 2000.01.30 はもにかラウンジ浅草
-
この日記に何回も書いているが、私は、高校生の頃からブルースが好きで、とくにそこで演奏されるハモニカの音色がほんとに大好きだ。
ハーモニカにも実にいろいろな種類があって、ブルースでは単音10穴(10 Holes)と呼ばれるもっともシンプルなタイプのものが多く使われるのだが、これは1本3000円前後で気楽に買えるし、小さくて軽いから誰でもどこでも楽しむことが出来る。
私も、20歳の頃、なんとなく1本買って我流で見様見真似で吹いてみたのだが、普通のフォークソングのような曲ならそう難しくはないけれど、これでブルースを演ろうとすると独特のテクニックや感性が必要で、それらしく吹けるようになるのは容易なことじゃない。
というわけで、買ってはみたもののすぐに挫折、それからは聴いて楽しむだけになっていた。ところが、なぜかある頃から、やっぱり自分でも演奏できたらなーという思いが強くなり、思い切って日本の10 Holesの草分けで第一人者である松田幸一さんの教室に通ってみることにした。何か、毎日の生活に変化や刺激を求める気持ちがあったのかもしれない。7年くらい前のことである。
私は自意識が強いのか、情けないほどの上がり性で、わずか数人のレッスンなのに、はじめの頃はブルブル手が震えるみたいなこともあった。それでも1年くらい通ううちに少しはブルースらしい雰囲気が出せるようになった。しかし、その後「旅籠屋・鬼怒川店」のオープンにともなって東京を離れてしまい、教室に通うことも困難になり、またハモニカを手にすることもなくなってしまった。
そして、1年半前。3年ぶりに東京に戻って、数ヶ月、吉田ユーシンさん教室に通って勘を取り戻そうとしたりしたのだが長続きしない。好きなのにひとりで練習する気分になかなかなれないのだ。職住一致だし、気分転換が難しいということもある。そんな煮え切らない状態が続いていたが、昨年、たまたま現在住んでいる台東区の主催で松田さんの「ブルースハープ教室」が開催されることを知り、懐かしさもあって即座に申し込むことにした。
教室といっても、全6回の短期講座。最後に浅草公会堂で河島英吾のコンサートの前座として発表会を行うというユニークな企画だった。台東区在住・在勤者対象の教室で約100人の受講生が集まったのだが、年配者が多く、大部分はハモニカ初心者、おそらくはブルースなんて聞いたこともない人も多かったと思う。そんなわけで、多少の経験がある私が発表会の中でのソロ演奏を指名され、わたし的には「とんでもない」ことになってしまった。
結果だけ言うと、異常な上がり性の私なのに、まぁまぁ何とかコンサートをぶち壊さない程度に演奏できた。みんなが励ましてくれたし、何より自分が長年重荷に感じていた不自由な性格から少し解放されたような気がして、とても嬉しかった。
こうして、昨年末、教室は終わってしまったが、なんとかこうした気分を持続できないか、人前でハモニカを吹いてみんなで楽しめるようになれないものか、そんなことを考えて、松田さんに「引き続きハモニカを教えてほしいという人も多いようですし、場所はウチのオフィスを使って、月に1度くらいのペースで教室をやってもらえませんか」と提案してみた。なぜか、ブルースのライブハウスは新宿・杉並・中野・世田谷など「山の手」に集中しており、ハモニカの教室も「下町」には皆無なのだ。私の実感として、ブルースには下町のほうが雰囲気としてマッチしていると思うのだが。
それはともかくとして、松田さんは私の提案に快諾くださり、その100名の方々に案内状を送ったのだが、なんと30名以上から申込みがあり、この狭いオフィスで2クラスに分けて「はもにかラウンジ浅草」がスタートすることになった。
毎月1回、3回レッスンして1回はウチのビルにあるドイツ風居酒屋で飲み食いしながら発表会をしようという企画なのだが、1/28、無事に第1回目が終わった。
今後の様子は、また、このサイトのどこかで紹介しようと思う。
- 2000.01.02 ぶち壊された下町情緒
-
元日、浅草寺に初詣に出かけた。晴天無風、混雑もさほどではなく、気持ちのよい散歩を楽しんだが、ひとつだけ不愉快なことがあった。
雷門の前で、どこかのキリスト教の団体の街宣車ががなりたてていたからである。渋谷などの繁華街に行くといつものように出会う「神を信ずるものは救われます。悔い改めなさい・・・」という例のヤツである。
私は、無宗教というより反宗教という立場なので、宗教的信条で反発しているわけではないし、人の信仰をとやかく言うつもりもない。
しかし、元日、日本人がひとつの文化的習慣として初詣している神社や寺の門前で大音響で布教活動を行うのはいかがなものか。
例えば、クリスマスイブのミサが行われているヨーロッパかどこかの教会の前で、仏教徒が拡声器を使って読経するなどという場面を想像してほしい。
これは、宗教以前にその国や地域の人々の文化や暮らしに対する無神経で傲慢な振る舞いではないか。
あーうるせー。余計なお世話だ。よほど、中心にいる西洋人に近寄って苦情を言おうと思ったが、盲信している連中との議論で消耗するのはわかりきっているし、足早にその場を離れてしまった。あー、何も言わずに帰ってきた自分にも腹が立つ。
なんて、人の良い日本人。なんて、従順な日本人。すっかりぶち壊されてしまった浅草の下町情緒。来年は、ケンカする。
- 1999.12.31 クラプトンとベック
-
昨夜、BSでエリック・クラプトンとジェフ・ベックの来日コンサートの映像が続けて放映された。クラプトンは武道館に見に行ったし、ベックのは再放送で見るのは2回目だったけれど、やっぱり最高で興奮してしまった。
歳がばれるが、2人の音楽を聴き始めて、もう30年近くになる。ヤードバーズからブルースブレイカーズを経てクリームを結成していたクラプトン。ヤードバーズを脱けてロッド・スチュアートとグループを結成していたベック。彼らは高校生だった私にとって文字通りのスーパースターだった。
そんな彼らも、もう50代半ば。いろんなことがあったようだが、いまだにバリバリの現役で、しかもパワフルで緊張感あふれるロックやブルースを聞かせてくれる。昔の名声などととは関係ない、今この時点でも最高のプレイを聞かせてくれる。素晴らしい。そして、彼らの音楽に素直に感動できる自分であることも、嬉しい。
あと、20時間あまりで今年も終わる。普通なら、この1年を振り返り、来年に向けて事業の発展を期す、というところなのだろうが、ひとりの人間としての私にとっては、ブルースやバイクといった30年変わらずに自分の一部であった世界も生きていくのに必要不可欠のものだ。自己実現・・・語弊を恐れずに言えば、3つとも大切だし、これらが複合的にからみあう生き方をしたいと思う。説明は難しいが、これらが共通のイメージで結ばれていることが、私にはわかっているからだ。
しかし、こんな発言、日本では否定的に受け取る人が少なくないんだろうな。
好きなものは好き。少なくともベンチャー企業にとって、事業のポリシーとか理念とか哲学というものは、個人のセンスに依拠しているのが当然だし、必要なことだと思うのだが、いかが?
- 1999.11.19 増資
-
トップページでもご案内しているとおり、当社は11/15にVIMEXに登録して、現在、公募増資中である。
設立6年目ということはともかく、日本に前例のない事業を行っている赤字企業が広く投資を求めて資金を調達できる機会を得られるなど、ほんの数ヶ月前までは想像もしなかったことである。夢のようだ。
A火災保険・Mさんの紹介で知遇を得たN生命・Kさんに連れられてディーブレイン証券を訪ねたのが9月末。おそらくは「面白そうな事業ですね。いつか、機会があったら検討してみましょう」というくらいの反応を予想していたのが、とんとん拍子に話しが進み、わずか1ケ月半で公募開始である。
公認会計士による会計監査、ディスクロージャ資料の作成、証券業協会や財務局への届け出。おそらくは一般の株式公開とほぼ同様の作業と手続きを経て、未知のステージの入口に立っている自分がいる。
限られた自己資金と、残念ながら乏しい信用力に歯軋りしながら、2ケ月前までの私は、「焦っても仕方がない。1軒1軒コツコツと店を増やしていこう。そして、いつかは株式公開できるような企業に育てていこう」と考えていた。だから、ナスダック・ジャパンや東証マザーズなどの華々しい話しも、当面は自分とは無縁の世界の話しだと、ただ憧れているしかできなかった。それが、こうした公開市場への前段階とはいえ、一般投資家の前で事業計画を発表して1億円近くもの出資を募るなんて・・・繰り返し言うが、ほんと夢のような話しである。
この1ケ月半、知らなかった世界に触れ、学んだこと、刺激を受けたことは実に大きい。
多くの人から「株」という形で資金提供を受けて事業を具体化していく、株式会社本来のシステムを再認識できたこと。会社は経営者のものではなく、本質的にはオーナーである株主のものであると諭されたこと。事業の将来性を明示できればこれを評価して投資いただける場が日本にも存在していることを実感したこと。どれも大いに私の意識を揺さぶることばかりだった。
15日に新株式購入の申込み受付開始、そして17日ときょう19日の投資家向けのプレゼンテーションを終え、無茶苦茶に忙しかった準備作業も一段落した。あとは12月13日の締め切りまでにどれだけの申込みをいただけるか、ドキドキしながら反響を待つしかない。
精一杯、そして正直に「旅籠屋」の事業のコンセプトと将来性を訴えたつもりだが、基本的にローテクビジネスであり、1年や2年で爆発的な利益を得られるという計画にはならないため、投資家の皆さんにどれほど魅力を感じていただけるか、一抹の不安はある。でも、それは仕方のないことだ。逆に会社の過去と現在を丸裸にし、しかも将来への不安要素もすべて明らかにしたわけだから、私自身は妙にすがすがしい気分だ。
こうした場を創設したディーブレインの出縄社長の志にエールを送るとともに、毎日深夜までサポートいただいた同社のスタッフに素直に感謝したい。そして、こうした場が着実に成長し、多くの起業家に力を与える存在でありつづけて欲しいと願う。
当社、そして私に課せられた責任を痛感する次第だ。
- 1999.10.31 五十肩
-
なんとも冴えない話題だが、目下、私の最大の悩みは日本経済の低迷でも、「秋田六郷店」の集客でも、浦和レッズのJ2降格でもなく、今年の4月から続いている五十肩だ。
突然、右肩に痛みを覚えるようになり、マッサージに通ったり、整形外科の診察と治療を受けたが、症状は重くなるばかり、腕を上に上げたり後ろに回すことも出来なくなってしまった。本を読み漁り、ネットで情報を収集したが、結論は整形外科医の診断のとおり「典型的な五十肩」とのことで、通常半年から1年かかる自然治癒を待つしかないとのこと。
この痛みは、なんの病気でもそうだが、経験した者にしかわからないが、腕の動きが極端に制約されるだけでなく、ちょっと許容範囲を超えて力を入れると激痛が走り、就寝中に痛みのショックで目覚めることもしばしば。起きている間もズキズキと肩関節がうずき、重症の肩こりが何ヶ月も続く。
さわやかなはずの朝の目覚めを失い、起きていれば四六時中の不快感にさいなまされ、仕事への集中力が阻害されることはなはだしい。
原因は「老化と運動不足」とのことで、誰を恨むことも出来ず、また経験のない人からの理解や同情も得られず、いまだ抜本的な治療方法も発見できない現代医療の無力を嘆きながら、ひたすら与えられた運命を甘受するしかないという次第。
以前、手首の腱鞘炎を患ったことがあり、その時も半ば回復を諦めた頃に痛みが和らいでいったことを思い出し、このまま痛みとともに生きていくしかないと、ようやく諦観の境地に近づいたと思ったところ、なんと9月に入って、頼みの左肩にも同様の症状が発生。医学書には、左右同時の発症は稀、とあったのにと、自分が常に「一般的なマジョリティ」に属しているはずと疑わなかった不覚を思い知り、やっとつかみかけた「病とともに生きよう」という殊勝な心もズタズタに引き裂かれる。
しかし、まぁ、気がついてみれば、右肩は発症から半年、医者の予告どおり、左肩の悪化と反比例して痛みは峠を越し、かすかに快方の兆しが見えつつある。
このまま行けば、来春には右肩がほぼ治癒し、左肩も快方に向かい始め、来秋には痛みから解放され、自分ひとりでストレスなくワイシャツを着たり、風呂で背中を洗えたりするようになると予定しているが、さてことは計画どおり進むのかどうか。
それにしても、仕事がようやく軌道に乗り始め、もっとも気力体力が要求されるこの時期に、なんと1年半もの間、わが身の内からの反乱に遭遇するとは・・・
40代を迎えたみなさん、日ごろから運動不足には注意しましょう。
いつまでも、ぐるぐる回ると思うな、肩と金。オソマツ
- 1999.10.10 9ケ月ぶり
-
なんと、この日記も9ケ月も空白になってしまった。
ホームページを大改築したのを機に、また、少しずつ考えていることや感じたことなどを書いていこうと思う。
チェーン展開を具体化しようと動き回っているうちに、接する世界が広がり、また変化している。ベンチャー企業を取り巻く環境について、ユニークなレポートが書けるかもしれない。
しかし、いつものことながら、ホームページの改築はたいへん。昨夜、とりあえず全ページ更新したものの、あちこちに変な所が出ている。片っ端から直しているところですが、しばらくはおかしな部分が残ると思います。ご容赦ください。
- 1999.01.31 ワクチン教育
-
子供たちが中学や高校を卒業する年頃になり、「進路」について話しをする機会が増えた。夢がない、問題意識が低い、現実的なイメージを持っていない。ついつい「お父さんの若い頃は違った」なんて上から説教するような口調になる。
しかし、青年だった頃の自分を冷静に思い返してみると、問題意識だけは旺盛だったが、同じように世間知らずだったし、先のイメージを描きかねていた。そして、その後実際にたどってきた道のりも偶然に支配され、試行錯誤の繰り返しだったようなのだ。人生に計画的な意思を持ちこむこと自体、必ず意味のあることかどうか怪しくなってくる。
水場のそばまで行っても、水を飲むかどうかはその時点での意欲や好みの問題であり、結局人生はその連続に過ぎないかもしれないからだ。
ただ、ひとつだけ強く願うのは、喜怒哀楽の色の薄い退屈な人生に埋もれて欲しくないということ。外から平凡に見えるかどうかではなく、心のうちで確かな手応えを感じる日々を生きてほしい。何もしたくない、何も欲しくない、誰にも会いたくない、という鬱に囚われる人生はつらいだろうと思う。
今の社会、とりあえずは戦争や飢餓や貧困といったリアリズムから遠ざかり、子供たちはその社会からも隔離されている。意欲を持つことも、反発することも、目標を持つことも難しいに違いない。「求める」という意識の結果として「手応え」があるのだとすれば、子供たちの置かれている環境はつまらない人生をおくるためにあるようにさえ思えてくる。
そこでひとつ提案。子供たちがもっといろいろな実体験をできる、「現実の試体験」とでも言うべき機会を多く与えてみてはどうだろうか。教室を出て、いろいろな仕事の現場で、見学ではなく一定期間お手伝いをする。言葉による説教ではなく、物事の原因と結果を体で味わう。
例えば、高校生のバイク事故や暴走行為を減らすために行なわれている「免許を取らない、バイクを持たない、乗らない」という「3ない運動」。そのかわりに、校庭で実際にバイクに乗せ、転倒のショックや急ブレーキのパニックを経験させるというのはどうだろう。
少なくとも私の場合、安全運転や交通ルールの必要性は、自分がケガをした時の痛みや、事故の恐怖をとおして学んだ。生きていくことの大変さや自分という人間の自覚は一人暮しをしながらのプータロー生活の中で見つけた。経験をとおして「楽しさ」や「喜び」を感じて「意欲」が生まれることもあれば、逆に「痛み」や「苦しみ」の中でそこから逃れたいという「欲求」に動かされることもある。
わずか数十年前、私の両親達の世代はもじどおり「戦争と飢餓と貧困」の中で子供時代や青年時代をおくっていた。彼らの経験した現実が、彼らのパワーの源となり、その後の時代の活力となったと思う。かと言って「戦争と飢餓と貧困」の時代が良いはずはない。免疫力のない子供たちに過大な刺激を与えて、心身に壊滅的なダメージを生じさせては元も子もない。だから「ワクチン教育」。「現実」に触れることのプラスの面を生かすために、試体験の機会を増やしてはどうかと思うのだ。
人為的に仕組まれた人生経験、ある意味でこれはちょっと不自然なことかもしれない。しかし、歩く機会が減った大人達がスポーツジムに通うように、恵まれてしまった子供たちが「ワクチン教育」を受けることも認められてよいことなのではないか。無茶苦茶を承知で言えば、私は大学受験の受験資格として、1〜2年間の勤労経験を義務付けることさえ検討して欲しいと思う。
これらのこと、実は子供たちに限ったことではない。人間は40歳にして惑わず、なんてことはウソだ。いくつになっても生き生きとして生きていくために、つぶれない程度にいろいろな試行錯誤ができる「ワクチン」が用意されているような、フレキシブルで多様性に寛容な社会になって欲しいと思う。
- 1998.11.22 情報に追いつけない
-
久しぶりに「鬼怒川店」に行き、2日ほど店番を務めて帰ってきた。
いつものことだが、数日自宅を空けると、目を通していない新聞がたまってしまう。主なニュースはテレビで見ているし、そのまま古新聞入れに片付けてしまえばよさそうなものだが、几帳面というか貧乏性というか、日付を飛ばして読むのに抵抗があって、ひととおり目を通さないと「今日という日」にたどりつけない気がする。
私が定期購読している印刷媒体は、これ以外にも「日経パソコン」など3誌、Eメールで送られてくるメールマガジンが10近く、毎日巡回しているニフティサーブの会議室がこれまた10以上ある。さらにWOWWOWやCATVの番組ガイド、頼みもしないのに、クレジットカードやJAFのPR誌、通販カタログなども送られてくる。もちろん、こんなに読めるわけがない。それどころか、はっきり言ってほとんど読んでいない。新聞にこだわっているのも、せめてひとつくらいちゃんと読み通している実感が欲しいという気持ちからなのかもしれない。
そもそも、この程度の「定期購読」量は、人並みはずれて多いものなのだろうか。そんなことはないだろう。今の私の生活には通勤や昼休みなどの「なんとなく行動を制約された時間」というものがないので、意識的に努めないと雑誌を読んだりする機会がない。これがいけないのかもしれないと分析したりするが、時間や習慣というものは自分で作り出すものだ、という正論がすぐに浮かんできて、状況を正当化するわけにもいかない。
テレビだけでも地上波、BS、CATVとチャンネルは多くなるばかり。そこにEメールだ、インターネットだと、アクセスできる情報は増え続けるいっぽうだから、たいへんだ。
本来、情報はそれを自分なりに受け止め、自分なりに消化して、自分なりの判断や行動の材料にすべきものだと思うが、目の前にご馳走が並びすぎると食傷気味になって慢性的な消化不良。血にも肉にもなりゃしない。
どうしたものか。これは結構憂慮すべき事態かもしれない。
- 1998.11.04 トップがアホやから
-
久しぶりにバイクで、3泊のソロツーリングに行って来た。「旅籠屋」チェーン店の候補地を見て回りながら、1日に仙台郊外のスポーツランド菅生で開催された2輪の全日本選手権のレースを観戦してきた。今シーズンの最終戦ということで、主催者はMFJ。MFJというのは2輪のレース全体を統括する公益法人で、4輪のJAFに相当する組織だ。管轄は文部省なんだそうだ。
レースを見に行くたびに思うのは、もっともっと観客の立場に立ったサービスを心がけて欲しいということ。それは、レース自体の演出にも言えることだ。いつも型どおりの進行が繰り返されるばかりで能がない。アメリカのメジャースポーツのショーアップ精神に学んで欲しいと思う。だいたいMFJはいまだにウェブサイトすら開設していない。偏見かもしれないが、公益法人に心の通ったファンサービスなんて不可能じゃないかと思ったりする。
先日、Jリーグの横浜フリューゲルスがマリノスに吸収合併されることが報じられた。詳しいことは知らないけれど、経営者の無能が原因だったのではないかという疑念を抑えられない。
私はかつて、大会社の子会社で10年以上サラリーマンをしていたことがあるが、そこで痛感したのは経営者が天下りで派遣されてくるような企業はろくなもんじゃないということだ。官僚の天下り先である公益法人、親会社の中間管理職が出向してくるようなJリーグの経営会社、いずれも状況は似たようなものではないかと推測してしまう。
プロスポーツは興行ビジネスの世界だ。そこでは、時代の雰囲気を先取りして仕掛けていくような独特のセンスが求められると思う。役人のセンスや大企業のサラリーマンとは違った経営感覚が必要だと思う。鋭い感覚と自由なアイデア、大胆迅速な決断力と堅実なバランス感覚。これらがそろわないと夢のある世界なんて生まれない。
今の不況、集団に寄りかかってきたわれわれ日本人ひとりひとりの人間力が問われているように思えてならない。情熱と実行力を持った面白い人間たちがたくさん登場してきてほしいと思う。
評論家みたいに批判ばっかりしていちゃいけないのでした。これは、私自身の課題でもあります。
- 1998.10.11 官製の観光情報など無用だ!
-
運輸省は、「観光情報データベース」を構築するそうだ。概要を紹介する。
1.全国のホテル・旅館・観光スポット・飲食店などのサービス内容、料金、地図などを一元的に集約する
2.インターネットで誰でも自由に無料でアクセスできるようにする
3.日本語だけでなく、英語版・中国語版・韓国語版も用意し、外国人観光客の需要喚起を図る。
4.データの信頼性を維持するために、掲載施設にアンケート用紙の設置を義務付け、クレームが多い場合は改善を求めるなどの処置も検討する。
5.データベース自体は外郭団体である「国際観光振興会」に設置する。
6.新規事業の柱のひとつとして位置付け、来年度予算の概算要求に整備費として10億円を盛り込む。
このニュースはプライベートな業界情報サイトや業界新聞(日本海事新聞)などに発表されたのだが、不思議なことに肝心の運輸省や実際にこのシステムの管理運用を行なう国際観光振興会のサイトにリリース内容の記載はない。どこで原文が見られるのだろう。
それはともかく、私はこのニュースを読んでひじょうに不愉快な印象を持った。はっきり言って大反対である。余計なお世話だ。金の無駄だ。
断言しよう。よしんば10億円の予算がついたとしても来年度中の構築は不可能だし、スタートした後も使い物になど決してならないし、廃墟のようなサイトになるだろう。私の意見は以下のとおりだ。
1.自由な市場に任せれば良い。今は、役所の関与ではなく、関与の撤廃こそ必要。発想を変えろ。
ニュース記事のなかには、データベース構築の目的が明確に記されていないが、表向きの目的は、一元的に管理された「公正な」情報を利用者に提供することによって、その利便性を図り、観光業界の健全な発展と近代化を促す、というあたりだろう。
冗談じゃない。私のような新参者であっても観光業界の抱える構造的な問題を実感するが、その結果は何より利用者の減少による経営破綻という形ですでに淘汰が進んでいるのだ。役人が「公正な」情報をまとめなければ業界の健全な進歩がないという発想そのものが利用者や企業家をバカにしている。少なくとも当面は、市場のメカニズムに委ねておけば良いのだ。
いっぽうで会計検査院の発表によれば、厚生省・社会保険庁、郵政省、雇用促進事業団、簡易保険福祉事業団、年金福祉事業団が設置し、宿泊設備を持った三百七十施設のうち半数以上が赤字経営に陥っているそうだ。公的機関だからこそ、安価で質の高い施設が提供できるということで作られたのだろうが、これも役所が民間を見下し、不信感を持っているという意味で同じ発想にもとづくものだ。
直接間接に多額の公的資金をつぎ込み、しかも周辺の民間の宿泊施設の営業を妨げている。コスト意識の欠落した放漫経営、または補助金の額を確保するための粉飾経理。公然の秘密だ。
東京オリンピックを契機として、ガイドラインという名のさまざまな規制を業界団体の整備とあわせて築き上げてきたことが今や構造的な問題の解決を困難にしている。ある時代において合理性のあった政策や法律がその後の業界の発展と新陳代謝を妨げている。
業界団体への加盟と推薦がなければ公的融資の申請ができない仕組み。。ガソリンスタンドやレストランは建てられても宿泊施設は限られた地域にしか建てさせない法律。それだけで分厚い1冊の本ができているほどの行政指導。既得権と硬直化した業界秩序から手を引け。今はそのことが利用者の利益につながる。
2.官製のデータベースに生きた情報は集まらない。金の無駄だ。
今ごろ運輸省が言わなくても、観光情報がインターネットに適した、利用者のニーズの高い情報であることなど、誰もが知っている。会員登録が不要で誰もがアクセスできるデータベースは、いくつもある。例えば
やど上手、やどかり、全国旅行・観光情報、ホームページを持っているペンション一覧、みんなのペンション広場、宿泊施設一覧、日本の宿
いずれも、会員登録不要で自由にアクセスできるサイトばかりだ。宿のほうでの登録ももちろん無料だ。
こうしたサイトの多くは、有用な情報を集めてアクセスを増やし、バナー広告を勧誘することによって維持費をまかない、収益をあげようとしている。だから、情報が少なかったり、鮮度や精度が低くなればアクセスが減り、淘汰されるリスクを背負っている。お役人は、運輸省が号令するのだから黙っていても情報は集まるだろうとタカをくくっているのだろうが、私は上に挙げた民間サイトの担当者がひとつひとつの観光地をまわりながら情報の提供を頼んで回っていた努力と苦労を知っている。掲載無料であっても、データベースと呼べるほどの情報を集めるのは容易なことではないのだ。
そもそも運輸省のサイトに広告なんか載せられるの?聞こえの良いお題目だけでサイトの構築やメンテなんてできるわけがないのだ。ウェブサイトのメンテや情報の収集を甘く見てるんじゃないの。
だいたいどこから10億円なんていう数字が出てくるんだろう。天下り先の外郭団体に仕事を世話して予算をつけようというのが本音なのだろうが、子供だましは止めにしてほしい。だいたいこういうニュースを無批判に掲載するマスコミも情けない。今のうちに計画をつぶしておかないと予算がつくと既成事実になってしまうのだ。
3.生であること、多様であることが情報の値打ち。情報の一元化やアンケートの効果なんて幻想だ。
上に挙げた民間のデータベースの多くに「旅籠屋」も情報を登録している。その時に困るのが、指定された定型のフォーマットを求められることだ。例えば、料金の欄は「1泊2食付きの1人料金」、宿の種別は「旅館・ホテル・ペンションの中からの選択」だったりする。「旅籠屋」にはなじまないのだ。
記事によれば、運輸省の計画するデータベースでは希望の料金を入れると検索結果がでるような仕掛けを作りたいらしい。一見便利そうだが、それはサービスの形態や料金システムが共通している場合にしか成り立たないことを見落としている。これでは新しい業態やサービスを提供しようとする施設をはじき出すことになる。テーマパークにおける入場料と施設ごとの料金の組み合わせ方もいろいろでしょうに。
およそサービス業というものは、無形のものを提供している部分が大きく、料金という項目で一律に検索することが難しい場合が多い。飲食施設であれ、宿泊施設であれ、断片的な情報では判断できないものだ。そういう中にあって、インターネットというものはその施設の発信する生の情報に直接触れることがことができるという意味で、とても貴重なものだと思う。「旅籠屋」のような新しいスタイルの施設がホームページを持つことの意味はそこにある。
情報の一元化だ、アンケートの設置義務だ、どれも役人が机の上で考えたアイデアなのだ。自分勝手な客が実情を知らない相手に書き送ったクレームなんて、誠実で的確な改善の邪魔になるだけだ。
めずらしく、長々と書いてしまった。かなり感情的になってしまったので論理的でないところ、説明不充分な所もあるが、言いたいポイントは書いたつもり。「ゲストブック」へご意見をお寄せいただければ幸いです。
- 1998.10.03 不景気な話しはもうやめてよ
-
寝ても覚めても、猫も杓子も、不景気な話しばっかり。もういい加減にしてほしい。
円安の影響を受けて輸出で大もうけしている会社もあるだろうし、バブルに乗り遅れたことが幸いして堅実に業績を伸ばしている企業もあるだろう。なのに、そんな話しがちっとも聞こえてこない。
等しからざるを憂う、という感じ方もわかるけど、不況の時代に儲かっているなんて不謹慎、そんなニュースは反感を買うだけだ、というような風潮があるとしたら、それは1億総不動産屋、1億総株屋と言われた10年前の裏返しじゃないか。
このタイミングをとらえ、長年蓄積されてきた構造的な問題点を暴きたて改革を迫る旗手になろうという心意気は良いが、マスコミが状況を増幅し続け、結果として時代を一色に染め上げてしまっているとしたら大問題だ。昨今の消費や設備投資の低迷には「マスコミ不況」っていう面もあるんじゃないの。
こんな時こそ、成功している話し、儲けている話し、明るい話題にスポットを当てて我々を励ましてほしい。批判して、減点するのは得意なくせに、プラスを評価し建設的な行動を起こすことには臆病、お役所の官僚たちと同じじゃないか。
鬼怒川温泉周辺に限らず、全国の観光地で旅行者が減りつづけているらしい。旅館やホテルも生き残りをかけてリストラやコストダウンに励み、宿泊料金も下がりつづけている。こういう時こそ格安に旅行するチャンスなのだが、毎日毎日マインドを冷やされて消費者はお金を使う気を無くしている。これじゃ悪循環だ。
ほんと、景気のいい話しを待ってるよ。
- 1998.09.21 本社オフィス、いよいよオープン!
-
きょう、また鬼怒川に来ている。
この夏、雨が多かったせいか、壁に水垂れの跡などが目立ってきたので掃除の加勢に来たのだが、着いたらまた雨。でも、東京と違い、木々を濡らし、地面に染み込んでいく雨だれの音は悪くない。明日も天気は回復しないようだが、合羽を着てゴシゴシやるつもり。
私個人は、都会よりも自然に恵まれた場所での生活の方が性に合っている。
ところで、東京の本社オフィスの準備がようやく整った。
1.物理的な荷物の整理・・・改装工事と並行してなので、極端に効率が悪い。
2.資料の整理・・・数年の間にたまった書類を整理しながら、取り組むべき課題をあぶり出すのだ。
3.社会保険などの手続き・・・健康保険・厚生年金・労働保険・雇用保険。小なりといえ、企業ですから。
4.本社ビルの管理業務・・・これも仕事のうち。契約書類やらなんやら、手の抜けない仕事。
5.鬼怒川店のマニュアル作成・・・3年間のノウハウの集大成。これが店舗運営のバイブルになるのだ。
6.決算準備・・・当社の決算日は6月末。システムのチェックを含め、事務処理はけっこう煩雑。
7.パソコンシステムの改良・・・本部のLAN、INETとの接続、鬼怒川店とのWAN。苦闘の毎日。
8.チェーン展開のプレゼン資料作成・・・これこそが本業へ直接つながる作業。いい加減にはできない。
9.本部開設の通知・・・その前に住所録の整理。根気のいる作業だが、これこそ企業活動のベース。
以上、8月9日にまとめた作業項目なのだが、8以外は大部分やり終えた。予定より1ケ月も遅れてしまったが、あす戻ったらいよいよ前向きの仕事に取り掛かれる。
5年前、旅籠屋の誕生を目指し、企画書を携えてあちこち歩き回った頃の気分がよみがえってくる。かすかな高揚感と不安。でも、すべてが机上の計画だったあの頃とは違い、今は過去3年間の体験と実績が財産になっている。
しかし、世の中不景気風が吹きまくっている。突破口を見つけるのは容易ではないだろう。楽観できる状況じゃない。でも、難しいから切り開く値打ちも高まるというものだ。
中田を見習い、自分を信じて、チャレンジするのだ。
と、これを客室のテーブルの上にノートパソコンを置いて書いている。じつは、私自身が客室に泊まるのは今夜が初めてなのだ。うーん、部屋も広いし、落ち着けて悪くない。自画自賛。いけるよ、旅籠屋!
- 1998.09.13 自分の頭で考えるのは難しい
-
1週間分の新聞をまとめて読んだ。「未知しるべ」(9/5 朝日新聞夕刊 内藤 廣)というテーマで書かれた興味深いエッセイをみつけた。その中で引用されている植物学者Kさんの発言に目が止まった。
「どうして日本人は、ヨーロッパの田園地帯の風景にあこがれるんでしょうねえ。植生的にはあれほど貧しい風景はないのに」
私自身、以前車窓に見たパリ郊外の田舎町の風景に心引かれていたから、「美意識を疑ってみよう」という副題は目に痛かった。雑木林と雑草が繁茂する日本の自然の方がずっと豊かだというのだ。
自然とは違うが、私の中には伝統的な文化や景色との調和など考えもせず、無秩序な破壊と増殖を続けているような日本の街並みに対する嫌悪感がある。しかし、これも混沌とした多様性という目で見れば、ずっと豊かな風景ということになるのだろうか。
新聞紙上では、相変わらず金融不安の記事が騒がしい。不透明で曖昧な日本の社会。それに比べ、オープンでフェアなアメリカがすがすがしく、潔い社会のように見えてくる。多様な人種、多様な文化の中で磨き上げられてきた、自由市場という合理的な価値交換のシステム。基本的に日本もこういう方向に進むべきだと私は感じていた。
しかし、フランス人やドイツ人の多くは市場のメカニズムにすべてをゆだねることに懐疑的らしい。人々の尊厳や文化を守っていくためには人為的な調整が不可欠という考え方らしい。
今までなんとなく信じていたことに寄りかかれなくなるのはつらい。人と「そうだよねー」と安易にうなずきあえなくなるのもつらい。経済システムなんて、私のような素人がいまさら自分なりの意見を持つには難しすぎるテーマのように見えて、無力感にとらわれそうになる。でも、この問題抜きに21世紀の世界観や価値観を語るわけにはいかないようだ。
「旅籠屋チェーン」も、そろそろ核心に迫る仕事に取り掛かる段階に来た。海図なき航海への船出は無上の喜びでもあるが、いろんなことを自分の頭で考えなければならないのは骨の折れることだ。
- 1998.08.16 世代ギャップのマクロとミクロ
-
2週間前、海外における日本人旅行者の生態について書いた。友人は日本人の女性たちの貞操観念の喪失を嘆いていたが、私も大きなショックを受けた。しかし、そのことを書きながら、私は自分自身のリアクションに苦笑していた。
近頃の若い娘はどーのこーの。こういう話題になると急に感情的なモラリストになる、これは間違いなく典型的なオヤジの兆候だ。そのせいか、書きなぐった後、どうも後味が悪い。なにか違う、という気分が残った。少し考えてみた。
自分の息子を含め、ハイティーンの連中と接していると対話のベースが成り立ちにくいことを強く感じることがある。議論しようにも、同じ舞台に立てないようなもどかしさがある。
たとえば、世の中の矛盾に対して問題意識を持ち、これをなんとかするために現状に抗おうとする情熱、その志を共有できる仲間を求める欲求。そういうパッションが希薄なのに驚かされ、言葉を失ってしまう。
社会の中での個人をとらえようとする空間軸のイメージや、過去から現在・未来へと考えを組み立てていく時間軸が曖昧になっていると、意見交換はすれ違いばかりになる。きわめて個人的で感覚的な快さだけが判断の基準になるのでは、コミュニケーションはむずかしい。
目標と方法論を明確にして未来への夢を描き、そのために不断の努力を続けることの大切さを語っても届かないし、自立した人間になることの価値を説いても通じない。いいんじゃないのとかうざったいよという言葉を返された瞬間、人間の価値とか生きていくことの意味に向って語り合う意欲が萎えてしまう。
1960年代の後半にハイティーンであった私には、主義主張は別として、社会を考え、未来を考え、自分を考えることこそが自分の存在そのものを意味のあるものにしてくれるという意識があり、この感覚を多くの人と共有できることを信じているところがある。この確信に安住しているのは単純に過ぎることかもしれないが、信じていられるのは幸せなことだ。
時代は違っても、人間が社会的な存在であるという点において、今のハイティーンたちも客観的にはまったく同じ空間と時間の中に生きているのだと私は思っている。違っているのは、彼らが、そのリアリティを実感する機会を徹底的に失っている点なのではないか。そんな状況は、世界的に見て、きわめて特異な状況に違いないし、ある意味でとても不幸なことだと、私には思える。
海外を放浪する日本人、とくに女性達が増えているらしい。日本や日本人に対する生理的な嫌悪感。自分の居場所がないような疎外感。既存の倫理観から跳ぼうとする欲求。マクロ的に見れば、彼女たちの生態を「孤独な反乱」と呼ぶ見方は正しいし、健康的な反応であると思う。。しかし、ミクロ的に見れば、あまりに幼稚で、無防備で、不勉強で、傲慢で、無自覚に過ぎる。例えば、イスラムの国の彼と結ばれ、子供をなし、結婚し、かの国に暮らしている女性達の多くがどういう状況で毎日をおくっているかという情報は少しも伝わっていない。大使館の落書き帳には彼女たちの助けを求める叫びがあふれているそうだ。
感覚に流されていった挙げ句に現実に捕らえられてしまう、マクロ的に見れば、それは日本という社会の罪だが、ミクロ的に言えば、見えない現実をバカにし、見ようとしなかった者の罪なのだ。
時代が教師という言葉がある。世の中、不況、不況と騒がしいが、金にあかせて空いっぱいに書き割りの青空を描いてしまった時代こそ異常なのだ。時代の雰囲気が変われば、人間たちの在り様も一変する。悩み、考え、努力することが肯定的に語れる時代になってほしいと思う。
- 1998.08.09 1ケ月以上もなにやってんの?
-
引っ越して1ケ月が過ぎ、ようやく前向きの仕事にとりかかれそうな状況になってきた。ビルの改装も来週にはほぼ完了し、今月下旬には来客をオフィスへ迎えられるようになると思う。
面倒くさがりのくせに、完全主義。人と違うことをやりたいくせに、心配性。
チェーン展開に関心を寄せていただいている方、協力していただいている方々をお待たせし、焦る気持ちは募るばかりだが、走り始めてから足がもつれるのもイヤなので、準備運動は念入りにしたい。
それにしても、1ケ月以上もなにやってんの?というご批判(誰も、そんなこと言ってない?)に対し、自分自身への弁解ということで、準備体操の実態をちょっと確認しておこう。
1.物理的な荷物の整理・・・改装工事と並行してなので、極端に効率が悪い。
2.資料の整理・・・数年の間にたまった書類を整理しながら、取り組むべき課題をあぶり出すのだ。
3.社会保険などの手続き・・・健康保険・厚生年金・労働保険・雇用保険。小なりといえ、企業ですから。
4.本社ビルの管理業務・・・これも仕事のうち。契約書類やらなんやら、手の抜けない仕事。
5.鬼怒川店のマニュアル作成・・・3年間のノウハウの集大成。これが店舗運営のバイブルになるのだ。
6.決算準備・・・当社の決算日は6月末。システムのチェックを含め、事務処理はけっこう煩雑。
7.パソコンシステムの改良・・・本部のLAN、INETとの接続、鬼怒川店とのWAN。苦闘の毎日。
8.チェーン展開のプレゼン資料作成・・・これこそが本業へ直接つながる作業。いい加減にはできない。
9.本部開設の通知・・・その前に住所録の整理。根気のいる作業だが、これこそ企業活動のベース。
現時点で、以上の1/3くらいが終わった感じだ。誰からも強制されない反面、どれも人任せにできない仕事ばかり。
さぁ集中力を高めて、階段を登っていくぞ!
- 1998.08.02 海外における日本人旅行者の生態
-
ここ10年ほど、断続的に放浪旅行を続けていた友人が訪ねてきた。5年ぶりの再会だ。
4年前の春、「今回はもう戻ってこないかもしれない」と言い残しての旅立ちだっただけに、心身ともに元気な様子を見て、正直とても嬉しかった。彼ももう40代後半なのだ。
東南アジアとインドを拠点に、チベットから中国、中東から中央アフリカ、南アフリカにまで足を伸ばした壮大な旅。1ケ所に1年近く暮らすこともあったようだから、これはもう物見遊山の観光旅行などというものではない。猿岩石のことを話題にしてみたが、静かに微笑んでいるだけだった。
夜遅くまで、時間を忘れて彼の土産話しに聞き入った。いずれ、彼のコーナーをつくるなどして、何らかの形でじっくりと紹介してみたいと思っている。ナマの体験にもとづく彼の話しは、それほど貴重なスナップであり、示唆に富んだ心のスケッチだったからである。
とりあえず、印象に残った話しをひとつ。
あてがいぶちのパック旅行や団体旅行ではなく、荷物を背に旅して回るような旅行者をバックパッカーと呼び、アジアにもアフリカにもそういう連中が世界中から集まっているが、
日本人旅行者の生態はどんなものか。他の国の人々にどう映っているのか。
彼の表現は明快だった。
日本人の女は世界一もてる。
日本人の男は世界一もてない。
その理由は簡単だ。
日本人の女は、簡単に寝るし、簡単に金をくれる。
日本人の男は、女にアピールする表現力も気合いもない。
誤解を招かないように言い添えておこう。彼は日本でも海外でも、人種を問わず女性にもてる男である。中年男のひがみなんかではまったくないのである。
それにしても、久しぶりの日本の街を歩きながら、彼は驚いていた。
若い女の子のファッション、他の国なら、みんな娼婦に見られるだろうね。
- 1998.07.19 パソコン貧乏
-
チェーン展開に本腰を入れるに先立ち、いくつかの準備を行なってきた。そのひとつが、誰もが手間をかけずに運営業務を行なえる独自システムの開発。「旅籠屋マネージメントシステム」と命名したのだが、予約から、部屋割り、チェックイン・アウト、顧客管理、会計までをパソコン上で一元的に管理できる。この日記でも経過を書いたが、半年以上の試行錯誤を経て、昨秋から本格稼動、とても便利なシステムが出来上がったと自負している。
ところが、今回、本社オフイスを開設するにあたり、データベースを本社と鬼怒川店のどちらで持つか、リアルタイムなアクセスをどうするかが問題になった。高速な専用回線の確保、高速の検索と転送が可能なデータベースの構築など理想的な方法はあるらしいが、とてもそんなコストはかけられない。結論として、チェーン店がたくさん出来るまでは、過渡的な方法で行くことにした。
詳しくは書かないが、これに伴い、本社のパソコン(現在2台)の1台をデータサーバー専用機とし、私とスタッフがそれぞれクライアント機を持つことにした。当初は、サーバーパソコンとして販売されている機種の購入を検討したが、現状では必要性が低いことがわかり、これまで私が使っていた機械をサーバー機として転用することになった。
サラリーマンだった頃から仕事でパソコンを使うことが多かったが、自分用のパソコンを購入したのは5年くらい前だ。1台目は親指シフトが使えるということで選んだ富士通のFMタウンズ。2台目は、鬼怒川店のオープン前に購入した東芝のBREZZA。3台目は、鬼怒川店のフロント用に用意したコンパック。そして、昨夏に現在愛用しているGATEWAYのG6−300という当時最新鋭のパソコンを買って現在に至っている。これは、なかなか高性能で、今回これをサーバー機にしようというわけだ。OSも95からNTに入れ替えるつもりだ。
というわけで、私専用のマシンが必要になるわけだが、今後地方に出かけたりする機会も増えるだろうし、モバイル機としての利用もしたいので、ノートパソコンにしようと考えている。Windows98のプレインストール機の発売を待って買おうと思うが、どうしても30万円くらいはするようで頭が痛い。
「旅籠屋」はちっぽけな会社だ。チェーン店がアチコチに出来てくるまでは、本社はとくに穀潰しみたいな存在だ。だから、パソコンのハードやソフトにかかる費用はけっしてばかにならない。これまで、自分なりに活用し、その恩恵にあずかってきたことは間違いないが、投資した費用を回収できるかどうか今後にかかっている。パソコン貧乏にはならないぞ。
- 1998.07.12 CATVでインターネット
-
台東区にオフィス兼自宅を移すことになってすぐに考えたのは、通信環境をどうするか、ということだった。オフィス内のLAN、鬼怒川店とのデータのやりとり、インターネットへの接続など、ローコストで安定してシステムにするよう考えなくてはならない。インターネットに関して選択した結論は、CATVのINETサービスを受けることだ。
都心部のようにビルが立ち並ぶ地域ではTV電波が乱れることが多いらしく、CATVが普及しているのだが、具体的には局から各家庭やオフィスに光ケーブルや同軸ケーブルをつないで有線で番組を配信している。結果として映像情報を送れる高速大容量の通信線網が整備されているわけで、これをインターネットにも活用しようというアイデアは当然かつ合理的だ。CATV事業者などを中心とする「地域マルチメディア・ハイウェイ実験協議会」で実験と事業化が進められ、昨年あたりから全国のCATVが続々とサービスを開始している。
問い合わせてみたら、台東ケーブルテレビでもこの4月からサービスを始めたということで、さっそく資料を取り寄せ、検討の結果、これを利用することにした。電話線を使わないから電話代ゼロ、24時間つながりっぱなし、高速(最大で上りが2Mbps、下りが8Mbps)というのだから魅力的だ。CATVのサービスエリアは意外と広いので、地域内か、INETサービスは行なわれているか、こちらで調べてみてはいかがでしょう(この表では台東ケーブルテレビは7月から事業化予定となっているが、実際は4月から開始されている。それぞれのCATV会社に問い合わせてみる方が良い)。
さて、具体的な費用だが、これはCATV会社によって料金体系が異なる。ここの場合、オフィスと自宅で計4台のPCに接続することにしたので、月々の料金は7500円(固定)。工事費はハブやLAN配線を含め6万円くらいになった。PCが1台で良いのなら、それぞれ4700円/月、工事費2〜3万円ということになる。高速の常時接続、電話代不要、ISDNを利用する場合のTAの費用などを考えると十分割安ではないだろうか。
肝心の使用実感だが、常時接続なのでダイアルアップの手間と時間がかからない。ブラウザを起動させるとすぐにホームページが立ち現れる。スピードは、スペック上は最大でINS64の100倍くらいになるはずだが、実感としては数倍というところだろうか。でもメガ単位のファイルが数十秒でダウンロードできるから待ち時間のストレスはほとんど解消された。なんといっても電話を使っていないから、テレホーダイタイムを気にする必要もなく、開きっぱなしにして席を離れても構わない自由な気分が嬉しい。
良いことばかり書いてきたが、問題点や注意すべき点ももちろんある。ひとつ、これは導入コストにも影響することだが、電話回線用のモデムやTAのかわりにケーブルモデムを利用する(その使用料は月々の料金に含まれている)が、これとPCはLANケーブルでつなぐためPC側にLAN(ネットワーク)ボードが必要になる。これ自体は1万円以下で購入できるので大きな負担ではないが、CATV側との相性があるようだ。実際、私の場合、今まで使っていたLANボードがうまく機能しなかったのでCATV会社にもう1枚推奨ボードを追加してセッティングしてもらった。
ふたつめは、セキュリティの問題。難しいことはよくわからないが、CATVというのは、局がプロバイダーのような役目を果たし、そこから加入者に対しては大きなLANのような環境になるので、その中に自分のPCが無防備な状況に置かれることになるらしい。うちのように小規模といえ社内LANを張っている場合、最低そのLANとINETの系統は分けたほうが良いらしい。具体的にはLANボードや配線を分けるということだ。というわけで、前記のようにLANボードを2枚ずつ用意することはこの意味でも望ましい。
ちなみに、常時接続といっても、固有のアドレスが与えられるわけではない(6時間毎に変わるそうだ)ので、ウェブサーバーを自分で持つ場合には使えない。また、接続が物理的に固定されている(私の場合、台東区のこの建物内のPCを離れるとつなぐ方法がない)ので、出先でアクセスするようなモバイルコンピューティングにも使えない。必要なら、プロバイダを使ったダイアルアップ接続できる環境を維持しておかなければならない。
長々と書いたが、現時点ではひじょうに合理的な選択だったと考えている。検討をお勧めします。
- 1998.07.07 12回目のお引っ越し
-
6月末、予定どおり、鬼怒川を離れ、東京に引っ越してきた。地縁も人縁もない3年間の鬼怒川での暮らしだったが、忘れられない思い出がたくさんあり、感傷的な気分になってしまった。安心してお店をお任せできる素晴らしいご夫婦と出会い、念願のチェーン展開に専念できる前向きの転身なのだから、とても幸せなことなのだが、住み慣れた場所や家を離れるのは、いつもさびしい。
考えてみたら、私の引越しはこれで12回目になる。生まれた北九州市内で3回、その後東京(杉並)・大阪(堺)・東京(練馬)・埼玉(川口)・千葉(木更津・稲毛)・東京(足立)と移り、鬼怒川そして今回だ。社会人になってから転勤でもないのに5回だから、これは多いほうなのかもしれない。
しかし、私はけっして引っ越しが好きなわけじゃない。ある程度の年齢になれば捨てられない物も増え、その荷造りや片付けが大変だからだ。あちこちへの届けや連絡も面倒くさい。とくに最近2回の引っ越しは仕事場も同時に移るわけだから尚更だ。
というわけで、このホームページの更新も思うに任せない状況が続いていたが、LANの構築やパソコンの設定も終わり、少しずつ態勢が整いつつある。なんと言っても、こちらに来てCATVのINETサービスに加入したので、常時接続の環境になったのだ。料金も月数千円(電話代不要)、しかもスピードも実感でINS64の倍は速い。次回は、その体験レポートでもしよう。
今夜は早めに寝て、明朝4時からプラジル・オランダ戦をハイビジョンで観るのだ。
- 1998.07.07 悔しくないのか
-
またまたサッカー。また負けた。
なんだかんだと半分くらいの試合は見ているせいか、なんとなくサッカーの見方が少し深くなったような気がする。世界各地からいろんな国の、いろんな人種の人たちが集まってくるわけで、自然といろんなことを感じ、考えさせられてしまう。これがW杯の素晴らしいところかもしれない。
それにしても日本の試合は面白くない。初戦のアルゼンチン戦は伸び切ったゴムのようだったし、昨夜のクロアチア戦も暑さのせいか全体的に重かった。勝ち負けは別にして、キレのある動き、センスあふれるプレイを見たいのだ。
しかし、この2戦を通じて痛感したのは、日本人って図抜けて甘い集団なんだなーということ。
敗戦後のインタビューでどうして誰も「悔しい」とうめかないんだろう。どうして、評論家のような醒めた言い方をしてしまうんだろう。
サポーター連中も、どうしてVサインなんか作ってカメラの前ではしゃげるのだろう。負けた試合のあとであんなに無邪気に幼稚に騒ぐ国って他にあるの?
選手に、国民の期待に応えたいとか負けて申し訳ないって言って欲しいわけじゃない。「君が代」なんて歌わなくてもいい。サポーターにも、国の威信をかけてなんて発想で応援して欲しくない。ただ、人間としての誇りや懸命さから生まれる清々しさや力を確認したいのだ。一途に求め続けた者にだけが表現できる歓喜と失意の純粋な激情を。NHKのBSの中継の冒頭のフレーズ「夢をあきらめなかった子供達」に出会いたいのだ。
NHKで解説者を務めていたラモスの言葉に共感するところが多かった。「みんな逃げ道作ってる。W杯で次の試合につなげるなんて負け方はない。Jリーグの試合とは違うんだ・・・」。
柱谷やラモスやカズや北澤が居たらどうだったろう、と夢想してしまう。考えたら、今の日本代表メンバーってほんと子供に見える。人間力が感じられない。ピッチで味方選手を怒鳴り付けるようなタイプの人間が必要だよ。
井原よ、君はキャプテン向きじゃない。城よ、シュート外して笑顔をつくっているような選手は他の国にはほとんどいないよ。
ジャマイカ戦、大差でボロ負けしたほうが良いのではないか。半分は本気でそう思ってる。
あーくやしい。
- 1998.06.12 期待過剰なんじゃないの
-
今回もW杯について。
先日の日本vsユーゴの試合を見て、五分にプレイできているのはやはり中田のような印象を受けた。彼がボールを持つと安心して見ていられる。
「カズを外すなら、あえて中田を外して欲しかった」と書いた手前、彼がどんな人間で何を考えているのか気になる。さっそく、中田や城のコメントが掲載されているホームページを見て回った。
ふたりの表現スタイルはじつに対照的だ。中田は自前のオフィシャルサイト(専門のスタッフがサポート、飲料メーカーがスポンサー)のに対し、城は朝日新聞のサイトに間借りしている、このこと自体がすでに象徴的だ。中田は「プロ」らしく独自のパフォーマンスをしようとしているのに対し、城は「アマチュア」的だ。発言内容も前者は若手タレント的なノリであり、後者は学生のように素人っぽい。
しかし、発言内容はいずれもどうということはない。中田にしたところで、要するにマスコミは発言内容を歪曲して伝えるから何も話したくないんだ、というのが真意のようで、それ以上でも以下でもないようなのだ。考えてみれば、彼らはまだ21歳と22歳、ハタチそこそこの若者なのだ。30歳を越え、社会人としてそれなりの経験と修羅場をくぐってきたカズの発言とは背景がまるで異なる。
ちょっと語気荒く語ったしまった私としては、「なんだか期待過剰なんじゃないの」と自答したい感じ。スポーツ選手って異常にニュースになるから、こっちが何か勘違いしてしまうんですね。そう言えば、サッカーの世界に限っても、ジーコとか、ドゥンガとか、ストイコビッチのようにナショナルチームの中心選手の言動には人間としての迫力や説得力を感じるけど、それ以外の選手、とくに若手選手のコメントに心動かされるということは滅多にないような気がする。彼らに「日本の伝統と体験をもとに独自のモデルを提示して」欲しいなんて望むのは筋違いでした。
ただ、岡田監督や長沼会長、あなたたちは別ですよ。
- 1998.06.07 カズ落選
-
カズ落選のニュースが流れて数日が過ぎた。私はこの決定に憤慨し、釈然としない気持ちがおさまらない。しかし、当人達はどう思っているのだろうと、カズや北澤のサイトを訪ねた。無念の思いを抑えて残ったメンバーにエールを送る気丈な発言がそこにはあった。成田での帰国会見も感情を殺したものだった。サポーター達の掲示板での発言も読み漁った。岡田監督批判が多いようだが、周囲の方が動揺を隠せないでいる。
体力や技術の衰えとか、監督の戦術構想との不調和などについての分析は私にはわからない。以前、カズや北澤が岡田監督へ無礼な態度をとった(頭を蹴った?わざとぶつかった?)ことへの復讐だ、などという情報もあったが真偽のほどは不明。事実としても、子供のケンカじゃあるまいし、そんなことが決定に影響を与えているなとどとは信じがたい。要は、チーム首脳がW杯で「勝ちに行く」ことにこだわった結果の判断だったのだろう。
もともと私は読売カラーが生理的に嫌いで、ナベツネが嫌いで、巨人が大嫌いで、ベルディが嫌いな人間だ。無意識のうちに垣間見える選民意識と無神経さに一貫して腹を立てている。だから、カズが不動のレギュラーメンバーであることを前提にしたような選手起用に「政治的な匂い」や「実力者への配慮」を感じて腹立たしく思ったこともある。だから、カズのファンではもちろんない。しかし、今回の選考には納得できない。
以前、この日記で「中田を外せ」と書いたら非難のメールが殺到した!というのはウソだが、中田を選ぶことと、カズを外すということには、共通の思考基準があるように思う。すなわち、勝負にこだわるための合理性に従おうするか、儒教的なメンタリティとの調和を重んじるか、ということである。多分、前者はグローバルスタンダードの厳しさであり、後者は「日本的な甘さ」なのだろう。今回の決定の当事者である大仁強化委員長もこの点をわきまえており、「弱肉強食は世界の常識でも、日本では違う状況もある」という発言に迷いの深さが表れている。
スポーツの世界に限らず、日本人が世界の舞台で生きていかざるを得ない現在、その特殊性や未熟さを指摘されることが多い。私も日本や日本人の曖昧さや理念の欠落に苛立つことが多いのは、この日記に繰り返し書いているとおりである。しかし、ここで忘れてならないのは、グローバルスタンダードに同化すること自体を目的とするのなら、いつまで経っても亀を追うアキレスに過ぎないということである。アメリカ的な合理性が唯一の基準ではないし、ヨーロッパ的なマキャベリズムが成熟の証しでもない。我々は日本の伝統と体験をもとに独自のモデルを提示していくことが大切なのだと思う。それはもちろん、かつての矮小化された民族思想に回帰しようなどというものではない。
話しが大袈裟になったが、私個人はW杯において、勝利という結果よりも、記憶に残るパフォーマンスを日本代表に期待している。それは外国に対してだけでなく国内に対してもそうだ。カズの言葉にあった「誇りや魂」を重んじる「美学」を体言してみせて欲しいと願っている。その意味で、カズを外すなら、あえて中田を外して欲しかった。このままミニ・ブラジルやミニ・ドイツを目指してどうなるというのだ。
- 1998.05.17 サッカーTV観戦
-
あと1ケ月足らずで、待望のワールドカップが始まる。日本代表が出場するのだから、TV観戦にも力が入る。幸い(?)6月は「旅籠屋」のオフシーズン、ぜんぶみる勢いで臨みたい。常々、年中無休の軟禁状態を嘆いている私だが、こういう時ばかりは一日中TVの近くにいられる境遇がありがたい。サラリーマンではこうはいかない。しかし、放映時間って深夜が多いのだろうか。
我が家には分不相応にもハイビジョンTVがある。5年ほど前、当時100万円以上もした頃に衝動買いしたものだが、9チャンネルを見ることは多くない。宝の持ち腐れなのだが、その一因は番組情報の入手が困難なところにある。数ある番組ガイドでハイビジョンのを掲載しているのはごく一部、それもタイトルの羅列のみだ。ウェブサイトを探してみても、かろうじてNHKが簡単に紹介しているだけ。試験放送を行なっているハイビジョン推進協議会が情報を提供していないのは理解しがたいことだ。公益法人のやる気のなさはほんとうに救いがたい。いまどき、FAXや郵送(有料)で番組表を取り寄せなきゃならないなんて情けなくて視聴意欲が萎える。
それはともかく、ハイビジョンは画角が広く、ロングでも解像度が高いから、サッカーやラグビー中継には最適だ。オフサイドトラップなんてのもよくわかる。しかし、オリンピックの時のように実況や解説を独自に行なうのはやめて、BSと共通にしてほしい。控えのスタッフみたいで盛り上がりに欠けるからだ。
ところで、サッカーの日本代表メンバー、中田はどうなるのだろう。個人的には彼を代表から外して欲しい。私が監督なら、「呼ばれたから行くだけだ」などという一言で選考対象から除外する。最近の名波のふてくされぶりも不愉快だ。マスコミを含め、無責任かつ不誠実な「世論」への怨念もあるだろう。発言ではなくプレイで自分を表現したいというのも潔いことかもしれない。しかし、斜に構えるのではなく、正面を向いて語れる強さを身付けてほしいと思う。
2輪レース大好きの知人S君が、最近活躍目覚しい日本人ライダーについて苦言を呈している(4/24)。同感だ。たとえ戦力が落ちても、世界に向って語れる人間にこそ、世界の舞台に立って欲しい。
さて、そろそろキリンカップ「パラグアイ戦」が始まる。夜は2輪ロードレース「イタリアGP」だ。
- 1998.05.13 ビート感覚
-
小錦が出ているウィスキーのCMが流れている(※)。なかなかイイ感じなのだが、前半と後半で指のならし方が逆なのが気になる。前半はオンビート、後半はオフビート。4ビートジャズっぽい曲調だから、1拍目と3拍目に指を鳴らすオンビートは明らかにおかしい。このことに気づいて、明らかに違和感を感じる人は意外と少ないかもしれない。というのも、ここ10年くらいでビート感覚に大きな変化というか、私に言わせれば退化が進んでいるように思えるからだ。
(※)5月下旬頃からCFが新バージョン(小錦は踊るだけで歌はバックで流れている)に代わっており、ここでは全編オフビート。クレームがついたのか?それにしても、ディレクターが知らずに犯したミスだったのなら、ちょっと悲しいね。CFディレクターのビート感覚がその程度?チェックも素通り?みんなビート音痴?
前にも書いたが、私のお気に入りの音楽はブルースだ。日本を含め、世界中の音楽の多くがロックの洗礼を受け、そのビート感覚をベースにするようになって久しいが、その直接の産みの親はブルースである。ブルースそのものを知らない、または誤解している人が多いからピンとこないむきもあるだろうが、ロックの基本はクラシックでいう強拍をはずした所にビートを打つオフビートと、3度と7度がフラットするブルーノート音階であり、これこそ、まぎれもなく今世紀初頭以来のアメリカの黒人音楽に由来するものだ。もちろん、ジャズやR&Bなどその後の黒人音楽のすべてもブルースの子孫である。
オフビートもブルーノートスケールもアメリカの黒人にとっては体にしみついた自然な感覚なのだろうが、白人およびその音楽世界に慣らされてきた我々の耳にはある種の「はずれた音楽」に聞こえるところがあり、そこがカウンターミュージックとしての刺激的な魅力の源泉になっている。
オフビートに話しを絞ってみると、おもしろいことに気づく。60年代から70年代にかけての欧米のTVの音楽番組を見ていると、聴衆の手拍子がオンビートからオフビートに移っていくのがわかる。日本でも年配の人だと今でも圧倒的にオンビート、わかりやすくいえば民謡の手拍子だが、さすがにロックバンドのコンサートでそんな間抜けなことをするヤツはいない。
ところが、10年くらい前からどうも様子がおかしい。タテノリという平板で機械的な乗りが蔓延するようになって以来、明らかにオンビートで手を打つ連中が増えてきた。昨年、ジェームズ・コットンというブルースハーピストが来日した際、あるライブハウスに駆けつけたのだが、聴衆の多くは20歳前後の連中で彼らのノリが1拍ごとに体を上下させるタテノリなどのオンビートであるのに愕然とした。これでは私は乗れない。ブルースのグルーブ感は感じ取れない。だからひとりオフビートで手を打っていたのだが、さすがにステージ上のブルースマンも気持ち悪かったのだろう。演奏の手を休めて手拍子を催促し始めたが、それは私と同じだった。
ブルースを多少聞いたことがある人ならシカゴ・ブルースの巨人マディ・ウォーターズの「モジョ・ワーキン」という曲を知っているだろう。先日、彼をしのんで現代のブルースマン達が集まったコンサートを放映していたが、驚いたことにプレイヤーや聴衆の過半がオンビートで手を打っていた。この曲を知っている人なら試して欲しい。ビートの打ち方でまったく違うノリになってしまうのに気づくはずだ。クリームがカバーしてヒットしたブルースの名曲「クロスロード」でも同じことが試せる。
音楽は理屈じゃない。ある曲にどう乗っていこうがひとりひとりの自由だ。だから私の感覚が正しいなんてことを言うつもりはない。ただ「正統的な」ビートをあえてはずすことによって生み出される緊張感やドライブ感が生命線であったはずのかつてのロックの本質が変質しつつあることは確かなようだ。あえて逆らおうとする意志を捨て、機械的なリズムに埋没して集団で忘我の境地に至ろうとする単純さ。時代は、カウンタービートを失ってしまったのか!なーんちて。
- 1998.05.03 人生の節目
-
4月は1回しか書き込めなかった。これでは「日記」などとは言えない。アメリカ旅行記も手をつけていない。
というのも、3月〜4月と利用者が多かったのに加え、頻繁に東京へ出かけていたからなのだ。いずれ詳しく書くつもりだが、「旅籠屋チェーン」の具体化にいよいよ本腰を入れることになり、そのための本部オフィスの場所探しと2号店以降の計画づくりに忙しく、精神的に余裕がなかった。
しかし、ようやく本部オフィスの開設場所も本決まりになり、今後のスケジュールが見えてきて、少し気持ちにゆとりが出てきた。6月末には「鬼怒川店」の運営をあるご夫婦に委ね、私は本部オフイスに引っ越して「チェーン展開」の仕事に専念する予定だ。
「旅籠屋」のようなスタイルの宿は、全国の街道沿いに無数に点在するようになってこそ、本来の役割を果たすことができるし、新しい旅のスタイルをサポートできるようになる。だから、「旅籠屋」を構想した当初からチェーン展開を目指していたのだが、「鬼怒川店」の運営に手いっぱいで、3年近くが過ぎてしまった。だが、この3年という歳月は、こうした宿のマーケットをじっくりと確認し、宿の運営ノウハウを蓄積するのに必要な時間だったと思う。
というわけで、来月、私はちょうど3年ぶりに東京へ戻ることになった。仕事の内容も変わり、日常生活も一変することになる。前にも書いたとおり、私は唯物論の信奉者だから、神も仏も信じないし、もちろん運命論者でもない。だが、過去を振り返ってみると、10年前、20年前と10年ごとに大きな転機が訪れている。偶然とはいえ、今年もそういう節目の年になりそうだ。再び海図なき航海に漕ぎ出すわけだが、悔いのない10年間にしたいものだ。
あー、それにしてもきょうは異常だ。例年5月3日・4日だけのことだが、今こうして日記を書いている1時間の間に「今夜、部屋は空いてませんか?」という問合せが50件近くもある。1分に1件というと誇張のように思われるかもしれないが、本当のことだ。すでにお断りした総数は優に500は越えるだろう。ゴールデンウィークだけ、20階建ての大規模ホテルにしたいところだ。冗談はともかく、職場にせよ、学校にせよ、みんな一斉に働かせ休ませるという状況を何とかできないものか。
なんとかしないものか!
- 1998.04.10 DHEA
-
アメリカ旅行・GP観戦(鈴鹿)と、春休みの忙しい時期に10日間も宿を空けてしまった。旅籠屋日記も3週間ぶりだ。記憶が色褪せないうちに4年ぶりのアメリカ旅行のレポートをまとめる予定だが、今回はちょっと怪しげなドラッグについての話しを先行してご紹介したい。
もう半年以上も前になるが、NHKで最近アメリカで話題になっている向精神薬(?)についてのドキュメントが放映されたことがある。人間の精神状態を左右する脳内の化学反応のメカニズムが明らかになるにつれ、その化学物質そのものの投与による直接のコントロールが可能になり、プロザックをはじめとするいくつかの薬剤が市販され、これらを服用するアメリカ人が激増しているという話しだった。内臓疾患と同様、脳内物質の過不足を調整することは当然の医療行為だという意見がある反面、個人の感情や性格そのものを人為的かつ他動的に変化させてしまうことに強い抵抗感を感じたものだ。
現に、極度に非社交的でネクラな人間が別人のように陽気で積極的になり、落ち着きがなく何事にも集中できない子供が人の話しに耳を傾けられるようになる、こういう劇的な変化を見せられると、地道な努力とか意志の力とか人間としての成長などと自らを叱咤激励していることの意味がわからなくなり愕然としてしまうのだ。個性とか人格ってなんなんだ。
しかし、好奇心というものはおそろしい。たまたまワシントンの町角でジュースを買いに立寄ったドラッグストアで市販薬の棚が目に入った瞬間、もろもろの不安は消し飛び、なにかひとつアメリカでしか手に入らないような薬を買って帰ろうという誘惑にとりつかれてしまった。きっとある種の物質が私の脳の中で分泌されたに違いない。そして、風邪薬でも下痢止めでもなさそうな正体不明の薬を7ドル99セントで買ってしまったわけなのだ。値段も安いし、やばかったら捨ててしまっても惜しくない、と私の脳は判断したわけだ。
さて、帰国後2日目。さっそくラベルに書かれている名前DHEA(Dehydroepiandrosterone)や注意書きの解読にとりかかったのだが、英和大辞典を引いてもこんな単語は出てこない。注意書きにも18歳未満は服用禁止、妊婦は事前に医師に相談を、と書かれているだけで効能書きは見当たらない。ビタミン剤と並んで気楽に売られていたからといって、いくらなんでもこれじゃ飲んでみるわけにもいかない。健康食品や薬に詳しい知人に聞いても正体がわからない。しかし、世の中便利になったもんだ。そう、サーチエンジンを使ってホームページを調べてみれば良いのだ。そしたら、山のようにDHEAの関連ページがでてきた。その中のいくつかをご紹介する。
るみちゃんの精神神経科あれこれ・・・神経症を患うRUMIKOさんのホームページ
フラワーエッセンス・・・アメリカ在住の漢方医師による健康指南のホームページ
That's 健康「USA健康フロンティア」・・・サンケイ新聞グループのニュースページの一部にあるアメリカ発の健康情報コーナー。DHEAの様々の効能が8編にわたって詳しく書かれており、現在アメリカで爆発的な売れ行きを示していることが紹介されている。
というわけで、ついにDHEAなる薬の正体が判明。知れば知るほど、これは慢性的な疲労を感じつつ、意欲的に新しい仕事にチャレンジしなければならないような中年男性、つまり私のためにあるような薬であることを確信するに至り、ついに毎朝1錠25mgの服用を開始したわけだ。
それにしても、通販のページなどを見ると40〜50ドルの値段がついている。現地で8ドル足らずで買えたものが、こりゃちょっとボリすぎじゃないか。日本とアメリカの規制と情報の格差が生み出す飢餓感が悲しい。
今回は、どうにもまとまりのない内容になってしまいました。偶然、ちょっと面白い経験をしました(している)ので、ご紹介させていただきました。肝心の薬効ですが、副作用的なマイナスの効果も含め、数日経過した現時点では何もないようです。曖昧な言い方ですが、気力の充実なんて薬のせいかどうか判断しにくいものです。何か自覚できる変化がありましたら、またレポートさせていただきます。
- 1998.03.19 たかが照明、されど照明
-
宿の客室の照明は明るいほうが良いかというテーマで議論したことがある。私は10年以上住宅メーカーに勤めていたため、照明計画にはこだわりがある。それに従い、旅籠屋の照明は原則としてすべて白熱電球色に統一、客室内の照明も部分照明だけにしているのだが、たまに客室の照明が暗いという指摘を受けることがある。明るいほうが良い、という意見には大別してふたつの理由がある。
第一は、部屋の中で手紙を書いたり、荷物の整理をしたりする時、充分な照度が必要というもの。これは照明の持つ基本的な機能であり、軽視することはもちろんできない。しかし、ここで忘れてならないのは、明るさが必要だからといって部屋中を照らす必要はないということではないかということだ。必要な場所に必要な量と質の照明が確保されていればよいのであり、部分照明でよいのではないかと思う。
もうひとつの理由、それは心理的な問題。これは多くの日本人が慣れきってしまっている住宅の照明との違和感に由来する。部屋が薄暗いとなんとなく落ち着かず、不安になるという指摘だ。かつて書き連ねたことを以下に転記する。
・・・この感じ、よくわかります。部屋全体が暗いと閉所恐怖症ではありませんが、なんとなく圧迫感を感じます。 外国のホテルは総じて部屋のスペースは広いのですが、照明が暗いためになんか息苦しくて気力が吸い取られていくような感じがします。しかし、あえて言いたいのですが、隅から隅まで明るくないと落ち着けないという我々現代日本人の感性や習性もこれで良いのか、と疑問に思ったりしませんか。欧米の住宅に行ったり、映画なんかを注意深く見ていると、部屋全体を照らす照明はほとんどなくて、ダウンライトもない場合が多いのです。 そのかわり、リビングにもパーソナルな大きなイスがあって、その傍には必ずフロアスタンドが置いてある。つまり自分の空間は与えられるものではなく、自分の力で作り出すわけですね。おおげさな言い方と思われるかもしれませんが、 ひとりひとりが自分で自分の場をつくりだしていく強さのようなものを感じるのです。人間関係や、社会と個人の関わり方にも通じるような気がしませんか・・・
ここ数十年、日本の住宅では部屋全体の明るさを求めるために、天井に蛍光灯を並べることが多い。作業空間を除き、あの白い光は居住空間には適当ではないと私は感じている。白熱色と蛍光色の光源を混在させるのは論外だ。これは光の質の問題だ。
・・・私が住宅メーカーのモデルハウスを見たり、お住まい拝見などのグラビアを見て、そのセンスを判断する材料のひとつは、照明の質の統一を意識しているかどうかです。たとえば、和室の床の間に蛍光灯を使っている家、居室の天井に白熱球のダウンライト(天井埋め込み照明)と蛍光灯のシーリングライト(天井付け照明)を混在させているような家は、はっきり言っていただけません。どうしても用途に応じて光の質を変えたいのなら、コードペンダントやスタンドなど、常時点灯しない部分照明に限って組み合わせるべきです。
私は、宿の照明について、絶対的な照度だけでなく、光のメリハリ、光の質、そして照明器具のデザインなどを考えたいのです。谷崎潤一郎の「陰翳礼賛」でもありませんが、日本人は少し光に対するデリカシーを失っているように思いませんか。駐車場の水銀灯など「光害」の最たるものです。
昔から不思議なのですが、本格的な書院づくりの和室などと謳い、庭や建築にお金をかけた割に、照明といえばせいぜい表に障子をはめ込んだ蛍光灯のシーリングライトだったりするケースを多く目にします。ホントの和室なら、昔はローソクや油による行灯の光に頼っていたわけで、闇がたたずんでいるような中を赤く揺らめく光が一隅だけを照らす、そんな雰囲気だったわけでしょ?そういう日本人の夜の過ごし方を意識したデリケートな照明計画があっても良いはずなのです。
旅館の客室の照明、無神経だと感じたことはありませんか。かすかな湯の香り、川のせせらぎ、そして窓越しの月明かりを感じながら過ごすような風流を、背伸びしてでも私は感じてみたいものです・・・
しかし、宿の側が宿泊客の意見を無視してひとりよがりになるわけにはいかない。ホテルや旅館に宿泊するのは白く明るく照らされた家の中で暮らしている人たちなのだ。難しい。だが、そもそも日本には先例のないスタイルの宿を目指して「旅籠屋」をスタートさせたのだ。従来の最大公約数に無条件に流されるのは性にあわない。
・・・私も、初めて外国でホテルやレストランに行った時は「暗いなー」とイライラしました。ただ、前にも言ったとおり、そういう風に感じている自分は、今の日本の照明習慣に慣らされてしまっている自分であって、一歩踏み込んで、「それじゃ外国の人はこれで不満を持たないのだろうか。明るくないとイライラする日本人の方が少数派なのかもしれない」なんて考えてみたいのです。
繰り返しになりますが、天井に蛍光灯をベタベタつけて部屋中を明るくして(最近は廊下を含めて家中かもしれない)暮らしてるなんて、せいぜいここ3〜40年間のことでしょう。それも日本に特殊なことかもしれない。暖炉や囲炉裏の火、ひとつだけぶら下がった電灯が持っていた求心力、空間のメリハリ。機能だけで測れない照明の意味をもう少し考えてみませんか。
私は、ローソクや油の光に頼っていた昔に戻れとか、欧米人の習慣や文化を真似ろ、と言うつもりはもちろんありません。昔はそういう明かりの取り方しかできなかったのかもしれないし、外国の習慣も合理性を欠いているかもしれないからです。ただ、情報社会の中で、多くの情報を得ることより、自分の判断で選んでいくことが重要であるように、自分の第一感にひと鍬(クワ)入れてみる「こだわり」がなければコミュニケーションなんて不毛だと思うのです・・・
家中を光で充たすような暮らしは高度成長期以後のことではないか。そもそもこういう照明を当たり前にしてしまったのは誰だろう。かつての住宅公団の設計者たちだろうか。戦争中の記憶も含め、暗く貧しい灯かりに息を殺して育った人達が、高度成長の時代の中で昼間のような白色の明るさに憧れ、それを豊かさの象徴のように追い求めたのだろうか。貧しさからの脱却、もっと光あふれる未来を!そこまでは良しとしよう。しかし、なぜ1億の人間が皆そろって「明るさ」礼賛に走っていったのか。住宅メーカーの設計者や建築家や街や村の大工さんたちに「後ろめたさ」はなかったのか。時は移ってインテリアコーディネーチャンやグリーンアドバーチャンが氾濫するご時勢、私はまず灯かりを消して目を閉じよと言いたい。貪欲な量への欲望、高機能への崇拝、成り金集団の醜悪ではないか。
アジアの混沌、無秩序な熱気、それもわかる。確かにここはヨーロッパじゃない。しかし、上海でも香港でもない。蛍の光、窓の雪と歌って来た国ではないか。万事において「一灯の光明、一隅を照らす」的な生き方を貫こうとする「変人」の方に私は一票を投じたい。
- 1998.03.08 稚気、愛すべし
-
人間、歳を重ねていくうちに、恋に恋するような、小犬が用もないのに走り回るような、そんな無邪気さから遠ざかっていく。想像の世界に遊び、初体験の連続にときめく時期を過ぎれば、埋め尽くされた日常は果てることなく流れ、増え続ける人間関係は複雑な約束事をともなって隙間を埋めていく。大抵のことは先が見えるようになってきて、気がつくとすっかり用心深くなり、重たくなってしまった自分がそこにいる。かつてあれほど感動したことの多くに、今はもう心が弾まない。それが自立した大人の分別かもしれないし、感受性の老化なのかもしれない。
涙の本質がじつは誰よりも自分自身に対するあわれみであるのと同じように、声高に言う憧れも未熟な自分を補うためのディスプレイ行動に過ぎないと、私は自分の体験からそう思う。だからと言って、ひいきのアイドルに嬌声をあげて涙するローティーンたちに、「自分の幼さを補完しているだけさ」と皮肉るのはやめておこう。それぞれの時点で切実な感情なのであれば、それで良い。
しかし、個人のアイデンティティの重要な部分は、何が好きで何が嫌いかということについての一貫性が支えている。だから、自分の好みが変わったことに気づくのは快いことではない。他人から変節を咎められることを恐れているだけではない。自分自身がわからなくなることにショックを受けるのだ。そして、往々にして人は自分の感性の変質を認めようとせず、かつての自分を演じつづけようとする。
と、偉そうに一般論を書いてきたが、私はどうなのか。
いくつかの波はあったが、かれこれ30年、ブルースハープのあの音色には変わらず心がざわめき立つし、オートバイには心が弾む。たぶん大丈夫、きっとこの先もずっと好きでいられるだろう。こうした世界に出会えたことに感謝し、惚れ続けていられるアレコレに囲まれていることをつくづく幸せに思う。
というわけで、もうすぐF1のスタート。ドキドキしてきた。4月からは2輪のGPも始まるし、6月にはサッカーのW杯もある。そう、私はコドモなんです。自分のために言おう、稚気、愛すべし。
- 1998.02.28 ホテルという名の猿芝居
-
ホテル業界の人たちのネット上での会話を読んでいて、そこに独特の匂いがあることに気づいた。それは「ホテルマン」という言葉のニュアンスに通じるもので、ちょっと「文化的」で、オシャレで、育ちが良さそうで、インテリぽくって、そのくせ職人的で、プライドが高そうな匂いだ。
私は、正直言って、その匂いにどうも馴染めない。蝶ネクタイや奇妙な制服に対する違和感、高級レストランで感じる居心地の悪さとも共通する感覚だ。理由は簡単。私の生活感覚からするとそれらは借り物であり、私が私で居られる場所ではないからなのだ。ドアマンであれベルボーイであれ、そこで働く人たちは、端的にあの衣装を受け入れているわけだから、そういうホテル文化に同化し、あるいは積極的に肯定しているわけなのだろう。しかし、明治時代、西洋人から鹿鳴館の舞踏会を「猿真似」と冷笑されたようないたたまれない思いを、彼らは感じないのだろうか。東京ディズニーランドでブロンドの白雪姫のまわりを金髪のカツラを付けて踊るような恥ずかしさを感じないのだろうか。
日本は明治維新や太平洋戦争などを契機に上流階級なるものがほとんど実態を失っている世界でも珍しい国だと思う。なのに欧米のグランドホテルのスタイルを忠実に再現しようとするのは、どこか不自然で滑稽ではないか。召し使いや執事やお抱え運転手などにかしづかれることを当たり前の暮らしとし、いっぽうで古今東西の文化芸術への理解と高貴な義務とやらにモチベーションを感じるような人種が今の日本にどれだけいるというのだろう。どうしてあの猿真似のバカバカしさから抜けようとしないんだろう。サーバントやクラークの職業意識なんて、ありがたがって学ぶべきことなの?
ビジネス誌では「ホテルランキング」なんていう記事が定例企画になっている。田中康夫みたいな若い「文化人」が大まじめに「ホテル」の評価記事を書いてる。グルメ評論家なんてのも同類だ。ムズムズしてくる。アナクロで、ブルブルッと震えてしまう。言うまでもなく、彼らはグランドホテルのカスタマーを演じる我々のガイド役を自任しているわけだ。揃いも揃って、あーなんという猿芝居。
お叱りを受ける前にことわっておくが、私のこういう感覚を他の人に押し付けるつもりはない。一等国の仲間入りを果たそうと必死に走り続ける空気の中で育ち、タイミングよく労せずしてランナーズハイを体験させてもらった、そんな世代に特有な感受性かもしれないと思うからだ。
必死に追い掛けた人たちにとってホテルは憧れの実現だろうし、東京オリンピックや大阪万博を知らない世代には最初からそこにあった風景かもしれない。しょせん人間の感覚は時代の産物だ。
それを承知の上で、やっぱり私はチップや心づけがマナーとされるような宿に馴染めず、MOTELの没交渉にほっとする。私はそれで良い。
- 1998.02.21 弁解、あるいはネットコミュニケーションについて
-
ウェブサイト(ホームページ)というのは、個人や零細企業であっても、ホワイトハウスや朝日新聞やマイクロソフトと同じように情報を発信できる存在だ。直接に不特定多数の人々に伝えることができ、そのリアクションを受け取ることも可能だ。このホームページも、先日の改造以来、ゲストブックやメールでたくさんのご意見を頂戴している。
茨城の高松さんからは、画像ファイルの軽量化について貴重なアドバイスをいただき、奈良の二宮さんからは2バイト文字や半角カタカナを使うとバグが起き、端的にUNIXマシンではファイルが読み込まれなくなることを教えていただいた。まったくの我流でホームページをつくっている私にとって、こうしたアドバイスはほんとうにありがたい。
しかし、当然のことながら、すべてのメッセージが快いものばかりであるとは限らない。良薬は口に苦しということだってある。数日前、プレゼントクイズにご応募いただいた方から次のようなメッセージをいただいた。
「パブリシティ実績のページが見つからないし、又、本気で見つけようという気も起きない。WebページはRPGゲームではなく、高い通信費や、アクセス料金を気にしながらアクセスしているのだから、情報を探し易いことが大事なことだと思う。今後は自画自賛でなく、情報検索者の立場に立ったページ作りを望みます。」
このクイズを始めて1年以上になるが、宿泊料金の計算自体を問題にすることに私自身なんとなくしっくりこない気分を感じたことがある。そのうち、頭の体操として楽しんでおられるような常連の方も増え、その違和感は次第に薄らいでいた。いつのまにか人間は現状に慣れてしまうものだ。上のお叱りを読んで、もう一度考えてみようと思った。
まず、このホームページは「旅籠屋」という新しいスタイルの宿の存在を広くPRし、一人でも多くの方に利用していただけることを基本的な目的にしている。だから、「旅籠屋」に興味を持っていただいた方が必要な情報を得るのに不便な点があれば、それは改善しなければならないことだ。
では、プレゼントクイズはどうか。これは、もちろん私の道楽などではなく、懸賞サイトなどで紹介いただくことによってこのホームページの存在を少しでも多く知っていただき、クイズを解いていただく過程で「旅籠屋」の内容や特徴に触れていただくことを願って始めたことだ。だから、ホームページの中身を見なくてもわかるのでは意味が無い。
とはいえ、今回の場合、正解の記された場所はトップページにも目次にも明らかにされておらず、もっとも遠回りした場合すべてのページを開けていかないと見つからない仕掛けになっていたから、こちらの狙いには適っていても、逆の立場だったら、私だってかなりイラついたかもしれない。ちっぽけな安宿が「無料宿泊券プレゼント」など偉そうに俺を引きずり回すのか、そういう不快感を微かに感じたかもしれない。
しかし、ではどうしたら良いのだろう。人をバカにしたような簡単な問題ではかえって失礼に当たるような気もするし、あまりにあさましい関係になってしまわないだろうか。かといって不快に思われるようでは逆効果だし・・・
いっぽう通信費やアクセス料金云々の件について、これはまったくの筋違いだと思う。短時間で正解が得られるようにする義務はこちらにはない。パソコン通信の世界でもこのフレーズを愛用する人が少なくないのだが、すべてはアクセスする人の意志と選択の問題であって、妙な被害者意識は好きになれない。
もうひとつ自画自賛ということについて。「こんなにいろいろな雑誌で紹介されましたよ」と自慢していると受け取られたのだろうか。「安かろう悪かろうの宿ではありませんよ。雑誌でも紹介されてますから」というメディアのプレステージに頼る思いがなかったと言えば嘘になるが、マスコミとのコネもない中で地道に自己紹介文を送って関心を持っていただき、フェアに取材していただいたわけで、その成果を自画自賛と受け取られてはつらい。機会があったらその記事を読んでください、そういうことだけれど。
経験者には分かっていただけると思うが、ネット上で見ず知らずの相手とコミュニケーションするのはとても難しい。パソコン通信でシスオペの管理的なやり方に反発して発言削除になったこと、パティオの仲間とケンカみたいになったこと、深夜モードの感情に酔って書き込み後悔したこと、気持ちをこめて書いても反応がなくむなしかったこと。人並みに高揚と反発と自己嫌悪と倦怠の道のりを歩んできたように思う。インターラクティブというのは、バラ色じゃない。
ホームページでもあえてゲストブックや掲示板を設けないケースがある。大企業のサイトなら当たり前のことだ。メールアドレスさえ載せてないサイトも珍しくない。賢明なことかもしれないと思う。でも、それじゃつまんないじゃないの!
頂戴したひとつのメッセージをもとに、考えたこと感じたことを率直に書いてみました。このこと自体へのご批判もあるに違いありません。やっぱり私の考え違いもあるかもしれません。どうぞ、ゲストブックへご意見をお寄せください。
- 1998.02.15 頑張れ?
-
長野オリンピックが盛り上がっている。頑張れ、頑張れの大合唱だ。しかし、この頑張れという言葉、どうも耳あたりがよくない。英語では ”Do your best!” と訳すしかないらしいのだが、ちょっとニュアンスが違う。頑張れには合理性や現実性の欠如と個人の人格を超えた精神主義的な匂いが色濃く漂っていて、そこがどうも生理的に抵抗を感じるところなのだ。
以前、FIのトップドライバーがインタビューの中で頻繁にモチベーションという言葉を使うことに驚いたことを覚えている。直訳すれば動機づけ、意訳すればやる気という意味だと思うがやる気を出せるかどうかが問題だという言い方が頑張れの国の私には随分と軟弱で甘えた物言いに聞こえたわけだ。日本で、スポーツ選手がそんなことを言ったらマスコミやファンはとんでもないヤツだと非難するだろう。
そもそも、トップレベルで争うような選手達のパフォーマンスを支えているものは、地味で苦しい日々の練習の繰り返しと人並みはずれた集中力であるに違いない。とすれば、そんな日常や瞬間は頑張れなどという曖昧な言葉でどうにかなるもんじゃないだろう。凡人のジョギングとは訳が違うのだ。プロ野球選手の怠慢プレイがとやかく言われることがあるが、考えてみたら135試合いつも体調がベストでやる気満々なんていう方が不自然じゃないか。
楽したい、遊びたい、ゴロゴロしていたい、という人間的な欲望を抑え続け、失敗し負けることへの不安、名声・地位・収入を失うことへの恐怖を超越するまで集中するには、それに釣り合うだけの何かがなければならないのは当然だ。多分その第一は人並みはずれた負けず嫌いの性格、言い換えれば誰もが評価するほどの優越感を得なければ自分が安定しないという不安定な精神構造と異常なまでの欲望が渦巻いているのではないか。そうした自らの「狂気」をコントロールし、能力アップの一点にエネルギーを集約させていくには、なるほどモチペーションという言葉で自分を客観視していく理性が不可欠なのだろう。
語弊を恐れずに言えば、世界一になるような人間を家族や友人に持ちたいとはまったく思わない。例外のあることを否定はしないが、最高峰にメダカの学校はないのだ。マスコミは、すぐに勝者を「いい人」に仕立て上げようとするが、それは頑張れという言葉と同じく幼稚な幻想だと私は言いたい。
とはいえ、テレビの前で応援するだけの私は能天気でよいのだ。「頑張れ、頑張れ」と叫び、勝利を見ることなく父親が逝ってしまった話しに単純に涙する。でもマスコミの人間が日本国中に幼稚で無責任な幻想をふりまくのはいい加減やめにして欲しい。アホは感染する。
蛇足になるが、この話しはスポーツの世界に限らない。政治家に徳を求めるのは八百屋で魚を求めるようなもの(でしたっけ?)という喩えどおり(でもないが)、強力なリーダーは半ば狂人であり、絶大なリーダーシップはほとんど狂気に近いことに、我々は不断に思いを致すべきだと思う。少し大袈裟な言い方ではあるが、私はそういう人間をふたり、間近に見続けたことがある。
輝きの裏には闇がある。
- 1998.02.08 原田と片山
-
かつてのようなブームは去ったが、4輪のF1はすでにマイナーな存在ではなくなっている。全戦中継を続けているフジテレビの功績だ。
いっぽう2輪の世界はどうだろう。イタリアの街頭で調査した「知っている日本人」の上位に原田哲也の名前があったそうだが、日本人の多くは「それって誰?ジャンプで失敗する人?」って言うかもしれない。日本で無名の彼がヨーロッパでは広く知られる人物であることに私はニヤリとしてしまった。片山と聞いて片山右京ではなく、片山敬済の名をあげるイギリス人もいるかもしれない。なんと言っても右京は「いつもビリを走っていた人だね」なのに対し、敬済は350ccクラスの世界チャンピオン(1977年)だった人なのだから。ちなみに原田哲也は16年後の1993年、250ccクラスの世界チャンピオンだ。
しかし、私はここで日本における2輪スポーツの認知度の低さを嘆こうというのではない。わかりにくいたとえだが、大企業を批判しながら町の議員と飲み歩くような工務店のオヤジは嫌いだ。大きいこと、有名なことに憧れるだけのムジナのミニチュアにはなりたくない。
きのう開幕したオリンピックを見ていて、競技種目の多さに驚く。初めて見るような競技もあり、「これじゃオリンピックも水脹れ、メダリストのステータスも低下する一方だ」という批判もあるだろう。しかし、種目が異なれば、競う体力も技術も違うわけで、人間の持つさまざまな能力や表現力に感動することができる。
4月5日の鈴鹿を皮切りに1998年のロードレース世界選手権がスタートする。そして今年はNHK−BSが全戦フル中継するのだそうだ。欧米並みのメジャーな存在になって欲しいという発想には抵抗があるが、2輪レース独特の素晴らしさに触れる機会が飛躍的に拡大するのは嬉しいことだ。信じられないようなスピードで斜面に飛び込んでいくスキーヤーに通じるような、神々しいオーラをたくさんの人に感じてほしいと思う。
それにつけてもNHKのスタッフがこうした感性や感動体験を持った人々であることを祈りたい。片山敬済の名前を聞いて心が震えないような人にレースを実況する資格はない。まさか8耐中継のあのアナウンサーを起用するつもりではないでしょうね。
4月5日、私はもちろん鈴鹿にいます。ほんとうは、あのオーラは電波には乗らないんです。
- 1998.02.02 インターネットは世界を変える?
-
あらためて考えてみたら、初めてWWWにアクセスしたのは1年半前のことに過ぎない。
パソコンもそうだが、これを知らなきゃ時代に遅れるみたいな話しが聞こえてきて、新しもの好きでありながらアマノジャクな私はそんなもの必要ないよと手を染めずにいた。それがいったん始めてみたら、半年後には自分でホームページを開くようになり、今や、インターネットはすっかり生活の重要部分になっている。
すでにパソコン通信に親しんでいたから、見ず知らずの人と会話することの不思議さ、面白さについての驚きはなかったが、果てのない広がりと管理されない自由さはならではのもので、少なからずカルチャーショックを受け、それは今でも続いている。
インターネットの普及により、本質的に情報の運び手である営業マンが存在価値を失っていくだろうという言われるが、店で物を売る商売も先細りとなるかもしれない。いずれにせよ、社会を世界を基本から変えていくかもしれないことを、今や私は否定しない。
かつて、農業革命、産業革命、そして20世紀は情報革命だ!なんてことが語られ始めた時、私はお調子者の戯れ言と聞き流していた。人間の意識や社会構造を規定する基本は生産活動にある、という唯物史観の信奉者としてみれば、まじめにとりあうに値しない見解に思われたのだ。
しかし、どうも様子が違う。昨今の金融情勢などを見ていると、情報というものが経済活動を左右する重要な要素となっている。付随的に派生する存在であったはずの無形の情報が実体経済の流れを引き回しているようにさえ見える。
同様に、インターネットなどのバーチャル空間が我々の意識に直接の影響を与え始めている。実生活空間を経ることのないコミュニケーションの拡大が、価値観や世界観や人生観を、とてもパーソナルな次元で変えている。意識が変われば、ある程度は生き方も変わる。生き方が変わればひとりひとりの経済活動も変わってくる。なんだ流れが逆じゃないか。
こうした見方は、飽食の民が描くうたかたの幻想なのか。情報のまだら模様につけ込める間だけのゲームの理論なのか。私にはわからない。いろいろな解釈を知ってみたい気がする。
- 1998.01.30 1998年1月30日(金)
-
この10日ばかり、朝から晩までホームページの改造と引っ越し準備にかかりっきりだ。その目的や主旨をまとめておこう。
●引越しの目的
1.スペースの大幅な拡大(6MB→50MB)・・・今後、チェーン店が増えていくことを考え、大きな容量を確保。
2.独自のドメインネームの確保・・・HATAGOYAの名前を使った簡潔なURLにし、覚えやすくアクセスしやすい状態に。
3.CGIなどの活用・・・必要に応じ、使いやすく管理しやすい機能をホームページに盛り込めるように。
4.内容別メールアカウントの取得・・・予約、クイス応募など、内容に応じてメールを分けて受け取れるように。
●改造の主旨
1.「旅籠屋」全体と「鬼怒川店」関連のページを分割・・・チェーン展開に向け、性格の違う内容を区分・整理。
2.「予約申込み」「プレゼント応募」処理の簡便化・・・直接メールで受け取れるようにし、ダウンロードと対応の手間を省く。
3.「ゲストブック」などインターラクティブ機能の強化・・・「リンク登録」を含め、気軽に意見や情報を寄せていただけるように。
4.「リンク登録検索」システムの設置・・・リンク情報の充実と利用を容易にし、来訪者からの情報も蓄積。
5.古くなった情報の見直し・・・周辺の旅行ガイドなどを更新し、より実用的で新しい内容に。
6.新しいコーナーの開設・・・スタッフのコラム、チェーン店募集の内容などを漸次強化。
7.カウンターの複数設置やアクセス分析・・・内容やリンク先などを客観的に効率的に選別。
それぞれのページの内容の更新や補充は不断に行っていくべきことでもあり、今回は基本的な編成を変え、いくつかの機能を付加することを中心に作業を進めている。といっても各ページを見ていると情報が古かったり、足りなかったりで不満がつのるが、2月の宿題にしよう。
- 1998.01.25 1998年1月25日(日)
-
昨夜は久しぶりに満室だった。年末年始の休みが去ってからというもの、常連のお客様中心の静かな毎日が続いていたので少々緊張してしまった。ほとんどはご家族でのスキー旅行での利用なのだが、今年は若いボーダーの姿をほとんど見かけない。なぜなのだろう。
さて、ホームページの改造と引越しの件だが、ようやく先週から本腰を入れて取り組んでいる。すべてのページに手を入れ、情報の充実を図りたいところだが、現状でもかなりのページ数になっており際限がないので、とりあえず全体の構成を変え、個々のページのリニューアルは引越し後に継続して行うことにした。アクセスする立場に立てば、ある意味で常に未完成で頻繁に更新され変化していくサイトの方が生き生きと感じられるし訪ね甲斐があると思うのだ。
とはいえ、インターラクティブな部分については、引越しを機にシステムを変えるのが合理的であり、とくにCGIの活用にこだわっている。引越し先は広いし、CGIの使用も制約がないので便利な仕組みを自由に作り込むことが出来るのだ。あちこちのサイトで無料で使えるCGIが公開されているし、自由に使えるCGIの解説書もかなり並んでいる。だから作業は容易だろうと考えていたのだが、実際やり始めてみて、考えの甘さを痛感させられた。Telnetとか、UNIXとか、Perlとか、パーミッションとか、Sendmailとか、得体の知れない言葉が並び、自分なりにアレンジしようとしてもどこから手を付けて良いのかわからない。仕方なくPerl言語によるCGIスクリプト入門の本を買い、基礎の基礎だけ読んでみた。実際のサンプルプログラムが出てくる段になると、読み流して理解できるものではなく、かといってじっくり解読する気力もなく、結局ほんとうの理解には程遠いのだが、それでも多少のアレンジを施して利用するハウツー解説の意味くらいは理解できるようになってきた。
こうして、ようやく「予約申込み」や「プレゼントクイズ応募」のフォームメイルの仕掛けが動くようになり(引越し時に切り替える)、今は自分のサイト内で動くアクセスカウンターに取り組んでいる(これが難航している)。そして、これも今は外部のサイトに間借りしている「ゲストブック」をオリジナルのものにし、アクセス分析の仕組みを仕込もうと考えている。しかし、順調にいくのだろうか。
約1年前、まったくの独力でホームページの開設に取り組んだ時、HTMLを書いてはブラウザで確認して一喜一憂したのと同じく、今も少しいじっては「神様!うまく動きますように」って祈ってばかりいる。そんな願いがすんなり聞きいれられることは皆無なのだが・・・
- 1998.01.18 1998年1月18日(日)
-
先週、ようやく年賀状(寒中見舞い)を書き終えた。官製の年賀葉書なのだが、15日を過ぎてたからお年玉が当選していても無効なのだろうか。
それはともかく、これでようやくホームページの改造に専念できる。
- 1998.01.11 1998年1月11日(日)
-
やっと暇になったと思ったら、毎日ガラガラ状態。さすがに不況の影響か、全国的に観光地はお客さんが減っているようだ。鬼怒川も明らかに交通量が減少していて、「旅籠屋」も当日のウォークイン(予約無しの通り掛かり客)が少なくなっている。客室数が多く、しかも板前さんや仲居さんを多数抱えているような宿はほんとうに深刻な状況だろうと思う。
バブル期に社用の宴会客を当て込んで水脹れしたような宿はともかく、長い年数をかけて独特の味や雰囲気を醸し出してきたような宿が苦境に陥っているとしたら残念だ。こういう時こそ、目先の売上にこだわらず、頑固にそれぞれのスタイルを守って欲しいと思う。こうした「こだわり」に応えてくれる利用者がけっして少なくないことを信じたい。
- 1998.01.04 1998年1月4日(日)
-
昨年末までにホームページの改築と引越しを行おうと頑張ったが、間に合わなかった。年賀状も出していない。ズルズル遅れてしまい情けない限りだ。冬休みの繁忙期もあと2〜3日、来週中には集中して結果を出したい。
- 1997.12.21 1997年12月21日(日)
-
2ケ月前に加わった新人君は、パソコンでの分析を駆使する競馬のセミプロ。彼の影響もあって、有馬記念の馬券を買ってみた。ほとんど生まれて初めての経験。結果は、2万円投資して1万2千円の儲け!シルクジャスティスの単勝が当たったのだ。ビギナーズラックというやつだ。
来年も、GIレースには少し馬券を買ってみようか、などと調子に乗って考え始めている。
- 1997.12.13 1997年12月13日(土)
-
今夜は3週間ぶりに満室。小さなお子さん連れのご家族が多く、にぎやか。
この2週間、暇を見つけて庭の手入れに精をだした。氷点下の朝が来てようやく花が終わったマリーゴールドとコスモスの種を採り、雑草を取り、買ってあったパンジーの苗500個!をプランターや庭一面に植え込んだ。これでひととおり冬支度が終わった。
風が吹くたびに舞い落ちてきた無数の落ち葉も片っ端から燃やした。本当は穴でも掘って堆肥にすればよいのだが、とても処理しきれる量じゃない。次から次へと炎とともに消えていく落ち葉を見ながら、これは炭素と酸素で二酸化炭素が発生しているのだな、と思うが、その二酸化炭素はもともと植物が光合成で蓄積したもの、プラスマイナスゼロだから安心。
冬はこれからだが、もう春が待ち遠しい。
- 1997.12.07 1997年12月7日(日)
-
3ケ月も前から予告しているホームページの改築と引越しだが、作業が遅れている。
11月下旬からは利用者も減り、比較的時間に余裕のある時期なのだが、冬に向けての庭の手入れや「旅籠屋マネージメントシステム」の手直しやチェーン展開に向けての計画作りなどに追われてしまっているのだ。
経験のある人ならわかってもらえると思うが、すでにオープンし、ある程度のボリュームになっているサイトを再構築するのはけっこう神経を使う作業だ。アーもしたい、コーもしたいというアイデアの断片がいっぱいで整理するのがたいへん。でも、とりあえず構成だけ決めて、あとは少しずつ更新しながらふくらませていこうと思う。
- 1997.11.23 1997年11月23日(日)
-
サッカーついにやったぞ!勝ったのももちろん嬉しかったが、選手たちの動きがとても良かったので気持ちがよかった。それにしても延長戦は心臓に良くなかった。試合が終わった後も興奮して眠れず2時過ぎまでインタビューを見まくってしまった。これで来年のW杯が何倍も楽しみになった。出場枠が増えたから拾われたんだ、などという野暮は言わない。
それにしても、私を含めて、みんなリアルな共有体験に飢えているんだなと痛感した。冷静に考えるとつまらない時代なのかもしれない。
- 1997.11.12 1997年11月12日(水)
-
このホームページを開設したのが2月14日。その後3月から「スタツフ募集」の告知を載せ始めたのだが、先月ようやく待望の新戦力が「旅籠屋」に加わった。それまで、ここ「鬼怒川店」の日々の仕事をこなすだけで心身ともに手いっぱいだったが、これでようやくチェーン展開に向けて前向きに歩き始めることができる。今はまだ、HMS「旅籠屋マネージメントシステム」の試験運用に時間をとられているが、年内には大筋の計画を立て、年明けから具体的な活動に入れると思う。
- 1997.11.07 1997年11月7日(金)
-
去年の暮れに着手したHMS「旅籠屋マネージメントシステム」の運用をついに開始した。まだ、細かなバグやインターフェイスの改良などを続けているが、予約受付け、部屋割り、チェックイン・アウトなどのフロント業務から、顧客管理や会計システムまでを一元化したユニークなシステムに仕上がりつつある。日々のルーチンワークに追われ、チェック作業が大幅に遅れ、作成を依頼したソフトハウスの方には申し訳なかったが、宿泊に特化した小規模ホテル向けのシステムとしては類を見ないすぐれものが出来つつあると自負している。
基本的な部分については、一般販売も検討しているので、関心のある方はご連絡ください。このホームページを大改築した後、このソフトの紹介コーナーも設置したいと考えている。
- 1997.10.26 1997年10月26日(日)
-
この1週間、ほんとうに忙しい。当番にさせられてしまった町内の神社のお祭り(11月3日)の準備に加え、ようやく先日届いた新しいパソコンへの移動を行っているからだ。従来のパソコンとの間をケーブルでつなぎ(これも一苦労)、プログラムやデータを移し、これに伴ってブラウザ(IE4.0の製品版)やFTP転送ソフトなどを最新バージョンに変更。基本的に難しい作業ではないはずなのだが、モデムカードを移設したらリソースの競合などという訳の分からない事態が発生したり、突然ホームページの更新ができなくなったりで時間をとられてしまった。クイズのご応募や予約申し込みの内容も届かなくなり焦りまくってしまった。原因はトップのページに書いたとおりレンタルサーバーの契約容量(6MB)オーバーだったのだが、3日も穴を空けてしまった。来月には新しいサーバー(50MB!)に引っ越すからこんな心配はない。
- 1997.10.16 1997年10月16日(木)
-
今月に入って、さわやかな晴天が続いている。湿度が低く、空は青く、気持ちの良い気候だ。紅葉前線も中禅寺湖畔からいろは坂を下り始めた頃だろうか。
パソコンのCRTの突然の故障(何万円もかかるらしく買い換えることにした)、電話回線の不通(半日予約の電話が受けられなかった)など、頭の痛いことも多いが、天気が良いので救われている。
- 1997.10.11 1997年10月11日(土)
-
旅籠屋オリジナルマウスパッドの原稿が、ようやくまとまりつつある。最初につくった原稿が96dpiで仕上がりが粗くなってしまうため、250dpiで作り直したのだが、ロゴマークのオリジナルデータ(350dpi)をデザイナーからメールで送ってもらうのに手間取ってしまった。
bmp、pict、jpeg、gifといろいろなファイル形式を試みたがどうしても開くことができない。1週間以上試行錯誤してわかったことだが、先方がMac用のメーラーで変換方式がBinHex、これに私の使っているMSのOutlookExpressが対応していないのが原因だったようだ。定番メールソフトのひとつであるBeckyをダウンロードして届いたメールを自分宛てに転送してみたらようやく開くことができた。近々、すべてBeckyに乗り換えようと思う。
次にこれらの画像ファイルの加工を始めたのだが、ここでも素人の悲しさ、解像度や画像サイズの意味がのみこめずにまた数日。しかも愛用の画像処理ソフト「HappyPaint」が処理できるファイルのサイズに限度があるようで、ここでまた半日。
結局作業を始めてから1ケ月近くもかかってしまったことになる。一応、製作会社に送信したデータで印刷のサンプルをつくってもらい、その上がりを確認したら正式に発注ということになる。
パソコンのおかげで、自分の好きなようにいろんなことが出来るが、途中でつまづいてしまうことも多い。しかし、創造の喜びを味わえるのは楽しいことだ。
ところで、サッカーのW杯予選も今夜からは事実上トーナメント戦になる。先のカズフスタン戦は旅先の宿で観戦したが、韓国戦と同様最悪の気分になってしまった。理念先導の新しいムーブメントを開花させる責務を負わされていることを理解し体現できないような連中には失望を禁じ得ない。
- 1997.10.03 1997年10月3日(金)
-
予定どおり、今週はエアコンの大掃除と全館の大掃除を3日がかりで行った。これらの作業を横目で見ながら、先日購入した車(20年近く軽自動車を乗り継いでいたが、ついに大きな車=オデッセイにかえた。マギーを乗せての東京往復が楽になる)のためのガレージを組み立てた。車大好きのマギーが嬉しくて新車をガリガリやらないための自衛策なのだ。
ところで、29日のサッカーは大ショックだったが、日曜の夜の2輪世界GP500ccクラスでの岡田の初優勝は最高に嬉しかった。火曜日までビデオを見る暇がなく、それまではスポーツ新聞を見ないようにしていたのだが、その甲斐があった。これはたいへんな快挙なのだが、これを報じたメディアはどれほどだったろう。
さて、いよいよ明日から2泊の予定で仙台郊外のサーキット「スポーツランド菅生」へ「スーパーバイク世界選手権」の観戦ツーリングに出掛ける。雨よ、降るな!
- 1997.09.29 1997年9月29日(月)
-
きのうは朝から久しぶりに良い天気になった。「旅籠屋」の前の田んぼでも「こしひかり」の刈り入れが始まった。ゴールデンウィークの頃の田植えから毎日見てきた稲だし、なんだか嬉しくなってしまう。
おととし、お願いして新米を分けていただきお客様に販売したが、大好評だった。今年も精米が終わり次第届けていただき、3年連続で販売の予定。同じ田んぼでとれたまぜ物なしのとれたての新米、ほんとうに美味しい。
ところで、昨日のサッカーの日韓戦。悔しくて情けなくて夜まで何も手につかなかった。思わず、エムボマ帰化しろ!などという考えが頭をよぎってしまった。
- 1997.09.27 1997年9月27日(土)
-
先日、メールで、ホームページでMIDIを使うための無料セミナーの案内が届いた。この日記にも再三書いたとおり、MIDIでは苦労したので「行くっきゃない!」と思い、参加することにした。しかし、栃木在住者の悲しさ。会場は幕張国際会議場なので、昨夜遅く東京に出掛けて1泊、きょうも昼過ぎにセミナーが終わった後、隣りで「PC EXPO」をやっているというのに、素通りして帰ってこなければならなかった。うーん残念。
ところでセミナーだが、講師はMIDPLUGの解説ページでおなじみの吉田達矢さん。面白い実例紹介や業界の裏話しなど盛りだくさんであっという間の75分だったが、JavaとかActiveXなど、私のような素人には難解な部分もあった。しかし、「ここでいくつかのヒントや刺激を受け、あとは各自解説書を読んで理解すべし」という彼のやり方は正解だと思う。1ページのデータ量の上限を考えながらデザインすること、音はBGMに限らないことなど、貴重なアドバイスがあった。
最後に質問の時間があったが、あまりに初歩的な質問だったので、終了後直接聞きに行った。「音をつけるとどうしても重くなって、スクロールしたりする時、音が飛び飛びになったりします。改善策を教えてください!」
このページを実際に見た上で返事をします、という親切なお言葉をいただいたので、その時点で紹介させていただくつもりです。
- 1997.09.25 1997年9月25日(木)
-
それにしても毎日雨が降り続き、気分まで湿ってしまう。お客様の表情もなんとなくさえない。晴れてくれれば素晴らしい秋空になるだろうに。
ところで、来月からの紅葉シーズンを前に、あれこれのメンテを予定している。エアコン室内機すべてのクリーニング、ジュータンクリーニングを含めた全館の大掃除。あわせて50万円以上の出費だが、清潔がなにより。汚れが目立ってきたような部屋にお客様を迎えるストレスはゴメンだ。
加えて、来月からは正面の木をイルミネーションで飾る予定。毎年、秋から春の夜長を演出していたのだが、今年は本格的に電気設備工事を行って大幅にパワーアップする。誰よりも私自身が楽しみにしている。
- 1997.09.21 1997年9月21日(日)
-
夏休みの間、忙しくて進められなかったオリジナル・パソコンソフト「旅籠屋マメージメントシステム!」の最終チェックに取り組んでいる。これにともないハードも強化、最新鋭のパソコンを1台導入する。10月初めにはシステムを移行させる予定だが、これが完了すれば日々の管理業務は格段に効率的かつ合理的になる。これで、将来のフランチャイジーの方々にも容易に「旅籠屋」を経営していただける基盤が整う事になる。
そして、いよいよhatagoyaというドメインネームを使ったホームページの開設だ。10月末までには第2次大改装を行って「新規オープン」したいと考えている。周辺ガイドなどを強化するつもりなので乞うご期待!
URL変更のPRも兼ねて、これを機にオリジナルグッズ第2弾として「マウスパッド」を製作している。すでにサンプルは手元にあるのだが、とても使い勝手がよいので多くの方に使ってもらえたらと考えている。
- 1997.09.15 1997年9月15日(月)
-
昨晩、ある客室のエアコン室内機から水漏れがあった。1ケ月ほど前にも別の部屋で同じことがあり、業者に点検してもらったところ機械内部で結露した水滴を排出するドレンパイプに汚れが溜まってつまっているのが原因とのこと。フィルターは時々外して水洗いしているが、それでも熱交換用の細かなフィンにほこりがたまり、それが少しずつ流れ出していくのだそうだ。オープンして2年、そろそろ機械の大掃除が必要ということで、1台ずつかなりの費用をかけて作業を始めてもらっているところだった。
こうしたトラブルは、なぜか満室で他に部屋の余裕がない時、しかも業者の人がすぐに対応できない休日に発生する事が多い。お客様は室料の減額を主張し、これを拒絶する私との間で険悪なムードになる。これには、予約の時点からの見下したような横柄な態度と、これに対する不機嫌丸出しの私の対応という伏線がある。
サービス業にトラブルはつきもの。気持ちの余裕を失ってしまうと、収拾できない袋小路に入ってしまう。わがまま人間の私には難しい事ではあるが、少なくとも相手より先に感情的にならないこと。「反省すべし」と自分に言い聞かせる出来事となった。
- 1997.09.13 1997年9月13日(土)
-
今まで、ドリームネットのレンタルサーバー内にこのホームページスペースを置いていたが、先日アメリカのサーバーを借りてhatagoyaというドメインネームを取得した。月々2,000円ちょっとで50MBまで使える。もちろん今はそんなに必要ないのだが、将来を考えて踏み切った。これを機に第2次の大改造を実施しようと考えている。
- 1997.09.11 1997年9月11日(木)
-
きのう友人のS君と、8月にオープンした「ツインリンクもてぎ」を見に行ってきた。ここからは、121号・119号・宇都宮環状道路・123号を走って1時間半という距離だ。平日だったので問題なかったが、アクセス道路が1本しかないので大きなレース開催時の渋滞は深刻な問題ではないか。日帰りのミニツーリングだったが、写真も撮ってきたので近く「旅行記」のコーナーにレポートを載せたいと思う。
S君とは、4月の鈴鹿行きに続いて、10月5日仙台近郊の「菅生サーキット」で開催される「スーパーバイク選手権」を一緒に観に行くことになった。前後、宮城県の温泉旅館に泊まる予定だ。いずれもネットで知り合った知人の経営する宿だ。楽しみだ。
- 1997.09.05 1997年9月5日(金)
-
数日前、ブラウザをインターネット・エクスプローラー4.0にかえた。まだ正式版ではないので躊躇していたが、重大なトラブルもなさそうだし踏み切った。使いやすくなった点も多く気に入っているが、つなぎっぱなしにしていないと活きてこない機能も少なくない。やはりインターネットというものは常時接続が基本なのだ。でも、この近くにOCNのアクセスポイントが設置される予定はないそうで、専用線は遠い先の夢だ。
- 1997.08.31 1997年8月31日(日)
-
この3日間、恒例の「ハーレーフェスティバル」が鬼怒川温泉で開催された。全国から約2千台のハーレーが集まったようで、きのうきょうと独特のVツインサウンドが町中に響いていた。昨夜はウチの駐車場にも10台くらいのハーレーが並んだ。
私もバイクに乗るようになって25年、今も2台の所有者なのだが、正直言ってハーレーには馴染みがなかった。他のバイクでは味わえない独特のムードとイメージ、そしてステータスがあり、熱狂的なフリークがいることは知っているが、あのマッチョでデコラティブな雰囲気にスノッブな印象を受けてしまう。事実、昨夜お泊りのお客様達を見ていて、これは一種のコスプレの世界だな、と感じてしまった。
年に一度のハーレーだけでなく、もっとたくさんのライダーたちに気軽にさりげなく利用していただきたいものだ。
さてさて、今年もハーレーの排気音とともに、長く忙しかった夏休みが遠くへ走り去っていった。少し骨休めをさせてもらおう。
- 1997.08.24 1997年8月24日(日)
-
夏休みもあと1週間。1ケ月以上続いた満室状態も今夜まで。去年は31日の夜まで満室だったし、9月に入ってもほぼ満室の状況が続いたのに今年は明らかに予約が低調だ。再利用や利用者の紹介が着実に増えているのに対し、雑誌などでの紹介が半減しているのが原因だと思う。久しぶりに媒体各誌に「ニュースレター」を送ってみよう。
書き漏らしたが、10日ほど前からBGMを流すのをやめている。どうしても、表示速度が遅くなり、トータルに考えるとデメリットの方が大きいように考えたからだ。回線状況やハードの能力が向上するのを待って再開しようと思う。インターネットは、文字だけでなく画像や音声などを含めたマルチメディアであることが優れた点だと思うのだが、現状の平均的環境はまだまだそこまで整備されていない。残念。
- 1997.08.17 1997年8月17日(日)
-
猛暑と雷雨の毎日が終わったと思ったら、この数日冷夏といえる天候が続いている。今朝の最低気温は15℃、1週間前より10℃も下がってしまった。涼しいのは歓迎だが、農家の人には困った気候かもしれない。
ところで先日書いた雷によるISDN回線の不通の件だが、やはりTA(ターミナルアダプター)が壊れてしまっていた。修理が終わるまでということでNTTから代替品を借りているのだが、今後のこともあり、ホームセンターで雷ガードというプラグアダプターを買ってきた。
- 1997.08.13 1997年8月13日(水)
-
夏休みももう半分以上が過ぎた。連日満室が続いており、ありがたい限りなのだが、正直言って疲労はピークに達しつつある。慢性的な睡眠不足が何ヶ月も続き、体力的にもつらいが、精神的に疲れきっていて頭を使う仕事に取り組む気力がない。このホームページについても、新しいマップや観光ガイドづくり、そしてリンク先の追加が棚上げになったままだ。昨年末から続けてきたオリジナルのホテル運営システムの検証も進んでいない。いろいろな方面で不義理や迷惑をかけていることが申し訳なく歯がゆいが、しばらくはご容赦いただきたい。
- 1997.08.04 1997年8月4日(月)
-
大気が不安定な状態というのだろうか、最近毎日のように雷をともなう激しい夕立がある。昨夜の雷雨もかなりのもので、数時間にわたって夜空が明滅し、そのたびに部屋の灯りが揺れた。東京からこちらに引っ越してきて2年あまり。雷の多いのにもすっかり慣れてしまったので、あまり気にもせずにいたのだが、今朝にホームページにアクセスしようとしたら、TAのランプが点滅して回線が切れている。すぐにNTTに問い合わせたところ、ISDNの場合、雷の影響を受けやすく、TAが壊れているかもしれないとのこと。とにかく点検してくれるよう頼んだのだが、夜になっても来てくれない。そうこうしているうちにふとTAを見たらパイロットランプの点滅が消え、回線も復旧している。きっと知らないうちに点検に来てくれて、電話線の問題だということがわかって処置してくれたのだろう。よかった、よかった。
もし、TAが壊れていたら、宇都宮まで出かけて持ち込み修理を頼み、最悪1週間くらいホームページにアクセスできなくなるところだった。普段は意識しないが、インターネットも通信ネットワークの上に成り立っていることを再認識した次第。業務用にインターネットを活用することのリスクを痛感した。
- 1997.07.31 1997年7月31日(木)
-
日曜日の8耐、日本人ライダーペアの優勝で終わり、テレビの前で思わずもらい泣きしそうになった。
しかし、当初ほぼ完全フルタイムのTV中継の予定が、ヤンキース伊良部投手の登板が延びて野茂と同日になったため、午前中に2試合放送する事になり、その影響で急遽8耐の中継開始が午前11時20分(レーススタートは11時半)から午後2時に変更されてしまった。
長くなるが、これについての怒りのレポートをひとくさり・・・
前夜はもちろん満室、とにかく11時20分からはいっさい仕事しないと宣言し、それまでにすべての作業を終了させるべく、早めに客室の片づけに着手。急ぎのパンフ請求への対応に時間をとられ、10時半に買い物へ出発。途中ウェスタン村へ徒歩で向かう前夜の客(コリアンの若い女性グループ)を送って行った親切心が災いし、スーパーのレジの混雑でパニック。時速90キロで旅籠屋に戻ったが、すでに5分遅れ。テレビのスイッチ入れろーと叫びつつ、観戦席に飛び込んだところ・・・
久々に頭の中が真っ白になり、怒りを抑え切れない。無駄と知りつつ、黙っていては伝わらないと考え、NHKにTEL。
話し中。同様のクレームが殺到しているのかと、この時ばかりはリダイアルが苦にならない。10回目くらいでようやくつながる。
「番組編成のことで」と言うと、受付の女性が「8耐ですか?」と尋ねる。やはり抗議の電話が多いのだ。いいぞと思いながら、努めて冷静に「きわめて残念。年に1度、しかもライブであることが重要。来年はフル中継を!」と訴える。その後は、6時間テレビの前にいたわけだが、アナウンサーをはじめとするスタッフのレースのポイントをはずした画像やコメントには、わざと盛り下げようという邪悪な意図さえ感じるほど。これではレースにあまり関心のない人はすぐにチャンネルを変えてしまうに違いない。モータースポーツの素晴らしさが伝えられていないことに苛立つ。時々聞こえてくる「サーキットアナウンサー」みしなさんの的を射た場内放送にすがる思い。このアナウンスをそのまま流したら100倍おもしろいのにと思いながら、いつかその線での民放フル中継を夢想する。
他のスポーツにない、2輪スポーツの醍醐味と素晴らしさは、私のセンスで言えば、人類が到達しえたかけがえのない文化のピーク。これを的確に伝えていくことの意義と使命と栄光を自覚して欲しいところなのだ。オリンピックの一部(昨年はオリンピックのため、中継無し)や大リーグの1試合と同列に比較されるべきものじゃない。質的に違う意味を持つものだ。この点は、「BBCなら50年でも放送を続けるだろうに」といった知人の発言が核心をついている。
- 1997.07.26 1997年7月26日(土)
-
台風9号の影響で、久しぶりに雨がパラパラ降っていて、とても涼しい。庭の草花も、人間もほっと一息。
あすはいよいよ鈴鹿8耐の決勝だ。今年も観戦に行けないのは残念だが、BSで中継がある。申し訳ないが、あした私は11時から8時まで仕事しません。
- 1997.07.22 1997年7月22日(火)
-
この数日間、外国の方のご利用が続いている。旅行代理店を通した集客をまったくしていないのに、それでもこの2年間、ブラジル、韓国、スリランカ、ドイツ、フィリピン、アメリカ、タイ、中国、イラン、チリの方々にご宿泊いただいた。団体旅行でもパックツアーでもなく、欧米の金持ち観光でもないところが「旅籠屋」らしい。中で一番多いのは、韓国から留学や仕事で日本に来ている人たち。2回以上ご利用いただくケースも増えており、嬉しい限りだ。
それにしても、日本語を多少話せる方や日本人と一緒の場合は良いが、そうでない場合は片言の英語でのやりとりとなる。昨晩のアメリカ人のカップルも日本語がダメで、冷や汗をかいた。銀行でお金を引き出したいというので、ついでもあり車で案内する事になった。道中、「ブルースが好きだ」ということから話しが弾んだのはよいが、運転しながらのヒアリングはきびしい。その後、銀行の駐車場に車を停めてしばらく話したが、「ニューヨークに来たら連絡してよ。一緒にブルースを聴きに行こう!」なんて住所と電話番号を書いたメモをもらってしまった。この辺の気さくな感じはアメリカ人ならではだ。後で気がついたが、Eメールのアドレスを教えてもらっとけば良かった。
余談だが、このカップル、彼は白人で彼女は黒人。こういうカップルに出会ったのは初めてだったので、なんとなく嬉しくなった。
そろそろこのホームページも英語版をつくって海外にもPRしてみようか!
- 1997.07.20 1997年7月20日(日)
-
昨晩、Jリーグ中継に引き続いてBS討論「企業の責任・トップの責任」を見た。出席者の意見が明快かつ示唆に富んでおり、とてもおもしろかった。いつか「旅籠屋」もチェーン展開が軌道に乗り、名実ともに「企業統治=コーポレイト・ガバナンス」なんてことを意識するような時期が来るのだろうか。
いよいよ夏休みが始まった。コーヒーマシンを設置し、大掃除を済ませ、草取りも一応終わらせた。トラブルなく毎日が進んでいく事を祈るばかりだ。
- 1997.07.13 1997年7月13日(日)
-
10日の晩、テレビでガーデニングの番組を見た。プロのガーデナー達のアイデアと熱意に感心した。単純人間の私は、すぐその気になり、庭をアレコレいじってみたくなった。でもその前にものすごい勢いで伸びつつある雑草と格闘しなければならない。暑さが戻ってくると蚊の大軍に襲われて仕事にならないので、きのう雨の中合羽を着て一日草取りに専念した。それでも半分くらいしかできなかったので、きょうもこれから続けるつもり。
昨秋庭中にまいたマリーゴールドがどんどん花を付け始めている。もし、この夏に「旅籠屋」に来られる機会があったら、ぜひ見てください!
- 1997.07.06 1997年7月6日(日)
-
東京や埼玉と比べるといくらかましなのかもしれないが、とにかく暑い日が続いている。先週は2日がかりの大掃除を含め、掃除や庭の手入れに明け暮れた。お客さんも多く、さすがにバテ気味だ。でも、気になっていた汚れもなくなり精神的にはすっきりした。
それにしても、暑さのせいか蚊が多い。長袖長ズボンで草取りをしようとするが、あっという間に10ケ所以上刺されてしまう。でも今のうちに除草しておかないと、手遅れになる。自然に恵まれているのも、良いことばかりではない。
- 1997.06.30 1997年6月30日(月)
-
きのうときょう、2日がかりで1・2階のユーティリティやリネン室の掃除および大整理をした。台風一過、真夏の天気で日差しは強いが、湿度は比較的低くて掃除日和だ。あすからは、専門業者の方に来てもらい、2日がかりで客室のジュータンクリーニングなどの大掃除を行う。このような天気が続いてくれることを祈る。
- 1997.06.26 1997年6月26日(木)
-
1週間ほど前、待望のコーヒーマシンがラウンジに設置された。それまでは通常のコーヒーサーバーだったのだが、デカンタ内の残量を見ながら追加するのが手間だったし、何より抽出してから時間が経ってしまい味が落ちてしまうのが心苦しかった。新しい機械はボタンを押すたびに自動で豆が計量され、その時点で抽出されるからいつも新鮮なコーヒーを味わっていただける。「旅籠屋」の数少ないサービスだし、豆もちょっと高級なものを選んでいる。おおいに利用して欲しい!
- 1997.06.19 1997年6月19日(木)
-
このホームページを開設した直後から「平日無料宿泊券」プレゼントクイズを続けている。これまでの当選者17名のうち、すでに10名近くの方にお泊まりいただいた。ひとりでも多くの方にこのページを見て「旅籠屋」のことを知って欲しい、そして実際に利用いただいてその特徴を理解して欲しい、つまりPRの一環として始めたことだから当選者の方に恩着せがましい気持ちなどもちろんない。しかし、無表情に「招待券」を出され、帰りも何の会話も無く鍵だけ置いていかれる方も少なくない。せめて、客室に常備してあるアンケートに一言気のついたことなど書き残していただければ、と思う。
もちろん、そうでない方もいらっしゃるわけで、先日もメールをいただき、いくつかの不備をご指摘いただいた。ありがたい。こういう時は、プレゼントクイズを始めてよかったと思う。
- 1997.06.16 1997年6月16日(月)
-
このホームページを開いた目的のひとつは、スタッフの募集だった。求人誌だとお金がかかるし、何より求めていることをトータルに伝えることが難しい。私の片腕になってくれるような人を探しているわけだから、事務的な告知では意味が無い。
しかし、もう3ケ月経つというのに、1件の問い合わせもない。私がそうであったように、サラリーマン生活に限界を感じ、新天地を求めている人は少なくないと思うのだが、なぜなのだろう。
チェーン店はないのか? はやく作ってよ! という言われることは多いのに、ひとりでは動きがとれず、イライラが募る。しかし、焦っても仕方がない。そのうち、誰かの目に触れるだろう。
- 1997.06.10 1997年6月10日(火)
-
今朝は、雨も上がり素晴らしい天気だ。小さなお子さん連れのご家族がお泊りなのでよかった!でも暑くなるかもしれない。
ところで、日曜日とてもイヤなことがあった。昼過ぎ、20人くらいの家族連れのグループが「これから泊まりたいのだが・・・」と来られた。日曜の夜は予約も少ないし、こうしたウォークインはとても嬉しい。一応お部屋を見ていただき、ご家族別に5部屋ご利用いただくことに決め、掃除が終わった後にお出でくださいとお願いして近所の案内図などをお渡しした。雨も降っていたし、なるべく早く部屋に入りたいという風だったので急いで掃除を終わらせ、希望どおりエキストラベッドを用意し、明朝にお出しするパンやジュースを買い足しに出かけ、準備を済ませた。
しかし、結論を言うと、その約束は何の連絡もないまますっぽかされてしまった。他のお客様をお断りしたわけではないし、実害は使われないまま洗濯に出すエキストラベッドのシーツのクリーニング代くらいたが、夜の11時までじりじりしながら待ち続けるのはつらいことだ。
開業して2年、こういうことが何回かあった。その都度なんとも言えない情けない気持ちになる。ちょっとおおげさに聞こえるかもしれないが、人間不信というか、やりきれない気持ちになる。
- 1997.06.04 1997年6月4日(水)
-
とうとう梅雨入りしたような天気だ。憂鬱だ。気分転換にBGMを変えてみた。
来週、「BLUE NOTE TOKYO」に行くことになった。実家の近くなのでオープンした頃から前はよく通っていたのだが、入るのは初めて。大好きなブルースハーピスト「James Cotton」を聴きに行くのだ。最近、素晴らしく渋くなった彼のブルースを堪能したい!ブルースハープの好きな人、興味のある人、ぜったいのお薦めですよ。
- 1997.06.01 1997年6月1日(日)
-
ようやくBGMが本来の音で鳴るようになった。音楽CDに近い音質で感激!コントロールパネルからマルチメディアのオーディオ再生ドライバーの設定をYAMAHAのものに変更したらうまくいった。一応ここまでの手順をまとめてみたが、これが正しい設定方法なのか確信はない。
音は素晴らしくよくなったが、ページが表示されるまでやスクロールしたりしている時に音が乱れる。なにか設定に間違いがあるのだろうか。
あと、今BGMに使わせていただいているブギウギだが、それぞれの音がバラバラでグルーブ感が損なわれている。音質がよくなって気になり始めた。
- 1997.05.29 1997年5月29日(木)
-
BGMのことだが、なぜか今朝から音質も良くなりステレオで聞こえるようになった。おとといヤマハの「MIDI PLUG」をダウンロードしたのだが、音が変わらないので変だなーと思っていたのだが、どうして今ごろになって動き出したんだろう。きのう、IEを3.01から3.02にしたから?いまだに音が出ない人もいるみたいだし???曲は8ビートのアップテンポのブルース(ブギウギ)だけど、いつかオリジナルの迷演奏にしたい!
ところで、先日書いたツバメの巣作りだが、きのうから姿を見掛けない。残念だ。でも、工事を中止するなら、きれいに掃除していけよな。
- 1997.05.25 1997年5月25日(日)
-
毎日、梅雨のような天気が続いている。昨夜もずっとどしゃ降りだったが、朝起きたら晴れ間ものぞくさわやかな天気になっていた。
雨の中を来ていただいたお客様も、気持ち良く楽しい時間を過ごしていただけるだろう。よかった。
ところで、今朝気がついたのだが、車寄せの天井の隅にツバメが巣をつくるつもりのようだ。ひっきりなしに2羽が小枝のようなものを運んできてドロ?でくっつけている。建物が汚れてしまうが仕方ない。思い立って、巣作りの工程写真を撮ってみることにした。いずれ、「野鳥の部屋」というページをつくって、ココにやってくる鳥達を紹介してみようと考えている。
- 1997.05.24 1997年5月24日(土)
-
ホームページにBGMを流そうと思い立ち、数日前からアレコレ試行錯誤を繰り返した。いつものことながら、難しいことはさっぱりわからないから、音の出ているページのHTMLを拝見したり、フリーの音源素材を提供しているサイト(無償利用は個人サイトに限るという場所が多いので、見つけるのに一苦労)を探したり、気に入った曲を選んだり、前準備に時間がかかってしまった。BGMのせいで待たされたり、表示が重くなったりしないこと、ブラウザによって聞こえたり聞こえなかったりしないこと、などを考えた。
そして、いよいよ、きのう具体的に音が出る仕掛けづくりに着手したのだが、けっこう大変だった。元々NN専用の「EMBED」と、IE用の「BGSOUND」があって、それもバージョンによって対応が違う。JAVAスクリプトとやらを使うとブラウザの違いに対応できるらしく、これを借用させてもらったが、NNの場合エラーが出てしまう。また、これもNNの場合だが、フレームのページに書き込むと、フレームの機能自体がうまくいかなくなる。書き込む位置をあちこちに変えてみたり考え付くことをすべてやってみたが、うまくいかない。それに、自分のパソコンの中(ローカル)で確認している時と、レンタルサーバーにアップして見る時のトラブルの出方も違う。
結局、IEも3.0以降なら「EMBED」に対応しているらしいので「BGSOUND」での書き込みは無し。場所もフレームセットのページではなく目次のページにした。
今朝になってようやく作業を終え、一応確認してあるのだが、不具合があるようならぜひ指摘していただきたい。
それはともかく、オルゴールMIDI音源、軽いしさりげなくて、とても気に入っている。フリー素材として提供されているシノさんに感謝。
- 1997.05.22 1997年5月22日(木)
-
1ケ月も遅れ、すっかり鮮度が落ちてしまったが、ようやく「鈴鹿ツーリング」の旅行記を書き終えた。書き落としたことだが、自分が旅に出かけ宿の客になるとなんとも妙な気分になる。だいたい4年前まで、自分がこんな仕事を始めるなんて夢にも思っていなかった。人生の成り行きとは不思議なものだ。
- 1997.05.19 1997年5月19日(月)
-
インターネットの値打ちは、やはりインターラクティブなところにあると思う。実際ホームページを開いていても、一方的なPRや情報発信ではつまらない。
というわけで、以前から、訪ねていただいた人が自由に書き込んでいただける「ゲストブック」「掲示板」の設置を計画していたのだが、プロバイダの制約があり、自分のレンタルサイト上に用意することができない。そうこうしているうちに、レンタル掲示板というシステムがあることがわかり、この1週間検討を続けてきた。無料レンタルのサイトもあるのだが、どうしてもアクセスに時間がかかったり登録受付を中断していたりで、結局有料のスペースを借りることにした。
どれくらいの発言が寄せられるか不安だが、とりあえずスタートさせてみることにした。
- 1997.05.14 1997年5月14日(水)
-
きのう、きょうと雨模様だ。ひと雨ごとに緑が濃くなっていく。冬の間唯一花壇に飾ってくれたパンジーも少しずつ色褪せてきた。芝桜もピークを過ぎた。そろそろツツジが色とりどりの花を咲かせそうだ。去年の秋、わずか30cmばかりの苗木だったバラがつぼみをたくさんつけている。こんなに早く大きくなるとは思っていなかった。
先日も書いた巣箱のスズメだが、昼間は中からヒナの声がひっきりなしに聞こえてくる。親スズメはその声にせかされるように一日中エサを運んでいる。本能とはいえ、感心してしまう。
最近は、オナガやシジュウカラの姿をみかけない。どうしたのだろう。
- 1997.05.10 1997年5月10日(土)
-
3月28日に書いた巣箱だが、きのうトントンと指でたたいてみたら中からゴソゴソ音がする。なんと住人がいたのだ。びっくりしてしばらく家の中から双眼鏡で観察していたらスズメが出入りしている。やったー!
最近は、朝、前日の食べ残しのクラッカーなどを餌台に置くと、1分も待たずにヒヨドリやスズメが先を争うようについばみにやってくる。巣箱のスズメたちも頻繁に往復している。
先日テレビでアフリカのサファリパークでライオンの群れに出会い、感動して涙ぐんでいる女性レポーターがいたが、程度の差はあれ、野生の生き物には人間の心を動かす不思議な力が確かにある。以前は物好きな暇人と思っていたバードウォッチャーたちの気持ちが少し理解できるようになってきた。
- 1997.05.08 1997年5月8日(木)
-
ゴールデンウィークが終わり、この2〜3日、周辺の草むしりに汗を流している。あっという間に伸びてくる。隣りの林の木々もほんの1週間で森のようになり風景が一変してしまった。周囲の山から残雪の白が消えたと思ったら、白っぽい緑色の新芽の色が浮かび、日に日に緑が濃くなっていく。植林した針葉樹の濃緑と広葉樹の緑がまだら模様になっている。
チューリップの花が散り、山ツツジも色褪せ、かわって庭のツツジが少しずつ咲き始めた。
- 1997.05.04 1997年5月4日(日)
-
去年ほどではないが、きのうも1日で100件以上のお客様をお断りした。結局宿が見つからず、コンビニの駐車場に停めた車中で夜を明かしたご家族も少なくないらしい。2日後なら安い料金でのんびり泊まれるはずなのに・・・。どうしても学校や会社を休めないとしても、ウチのような時間の自由な宿なら、朝5時頃出発すれば間に合うと思うのだが。
ところで、こんな状況にもかかわらず、昨晩は久しぶりにNoShow客が1組あった。以前郵送しておいた予約確認状に「到着が夜8時を過ぎる場合は連絡してください。キャンセル扱いとさせていただく場合があります。」と明記してあるのだが、9時まで待っても現れない。電話もつながらず、こちらから連絡がとれない。仕方なくその後WalkInで来られたカップルにお泊りいただいたが、この数時間の心労は大きく、じつに情けない。
- 1997.05.01 1997年5月1日(木)
-
去年のはじめ頃だったろうか。偶然広告を見て注文した餌台を花壇の一角に設けてから、初めて野鳥に興味を持つようになった。
1週間ほどすると見たこともないキレイな鳥(図鑑で調べたらオナガという鳥だった)が来るようになり、なんだか無性に嬉しくなってしまった。以来確認できた種類は、スズメ、オナガ、ヒヨドリ、ムクドリ、ハクセキレイ、シジュウカラ、そしてキジ。こんな所にキジとは驚きだが、隣りの方が教えてくれたところでは、昔この辺に人家もまばらだった頃、猟友会の人が繁殖用に放したものがそのまま隣りの林に住み着いたのだそうだ。複数の雌のあとを5〜6羽のヒナがくっついて歩いているのを何度も見かけたが、ほんとうにこれがキジなのかは半信半疑だった。ところが半年ほど前に、あの尾の長いオスを見かけて、間違いなくキジであることが確認できた。
ちなみに餌は、朝ラウンジに用意しているパンやクラッカーの食べ残し。一度ヒマワリの種をしばらく置いてみたが、これは不評のようで、そのうち何と根が生えてきた(たくましい生命力)のですぐに庭に撒いてしまった。
最近は、もっぱらヒヨドリが群れでやってきて、1時間ほどできれいに食べていく。少しずつ慣れてきたようで、数メートルの距離から見ている前で、うるさく鳴きながら奪い合っている。建物のすぐ横なのだが、この光景に気づいている宿泊客はほとんどいないようだ。のんびり泊まって、まわりの草花や野鳥を見るのも一興と思うが、こういう心のゆとりを持った旅をする人は少ない。
- 1997.04.30 1997年4月30日(水)
-
デジカメは本当に便利。とにかくシャッターを押せば、明るさも、色バランスも、構図もあとで簡単に修正できる。目障りな電柱も消せる。以前、10年以上もある住宅メーカーで広告宣伝の仕事をしていたが、何万円もかけてポジのレタッチを頼んでいたのを考えると隔世の感がある。
こうして、建物や草花など画像でかなりの情報を盛り込めるようになったが、なかなか伝えられないものもある。それは、寄って撮れない野鳥達の姿や声、そして前の田んぼでうるさいほど鳴いているカエルたちの大合唱だ。
- 1997.04.30 1997年4月25日(金)
-
きょう待望の屎尿の汲み取り車が来た。頼んで10日待たされた。都会人は意識しなくなっているかもしれないが、下水道の整備されていない地域は今でも多いのだ。ここも大きな浄化槽(残念ながら合併処理にはできなかった)で3次処理したあと、地中に広く埋設したパイプを通して浸透させるようになっているのだが、どうしてもスカムが溜まり、年に数回は汲み取りを頼まなければならない。1回で10万円近くかかるのでバカにならない。くれぐれも異物を流さないで欲しいものだ。ゴミにせよ、排泄物にしろ、捨てたり流したりしたら消えてしまうと勘違いしてしまいがちだが、そんなことはない。黙々と後始末をしている人たちがいるのだ。
- 1997.04.24 1997年4月24日(木)
-
4日間の旅から帰ってもう3日が過ぎた。
18日(金)は、一緒に紹介されることが多かった伊豆の「旅籠・夢庵」に宿泊し、店長さんと情報交換。
19日(土)は、鈴鹿サーキットにたどりつき予選を観戦。夜は白子のなじみの宿「新みやこ」に宿泊。
20日(日)は、日本GPの決勝を観戦後、夜遅く富士山麓に住む山村夫妻(パリダカなどで有名)宅に到着し、歓談。
そして、21日(月)の夕方に1100kmのツーリングを終えて、旅籠屋へ帰還。
疲れたが、充実した4日間だった。忘れないうちに旅行記を書いておこうと思う。
- 1997.04.18 1997年4月18日(金)
-
この夏で、開業から満2年になるが、きょうから3泊で初めて自分自身が旅行に出かけられることになった。旅行と言っても、鈴鹿サーキットで開催される2輪の世界GPを観戦しにいくだけなのだが、ツーリングを兼ねて前後1泊することにしている。毎年通っていた鈴鹿も2年ぶり。今年は500ccクラスでも日本人ライダーの活躍が期待できるので、おおいに楽しみ。では、いってきまーす。
- 1997.04.17 1997年4月17日(木)
-
ネットスケープの2.0では、表の背景色が表示されない。640×480のディスプレイだと一番下の矢印のアイコンが上半分しか表示されない。フレームや画像の多いページは重たい(表示に時間がかかる)。目的のページに行くのに、3ステップもかかるのは面倒。
いろいろな方からご意見をいただいている。どのあたりを基準にデザインしたら良いのか悩ましい問題だ。
とりあえず、ひとつめの問題を解決すべく、カレンダーの表示方法を変更してみた。どしどしご意見をお寄せください。
- 1997.04.17 1997年4月15日(火)
-
トップのページでも紹介したが、FTP送信ソフトを「NextFTP」に変えた。これまで使っていた「小次郎」の簡便さと「CuteFTP」の機能を併せ持った優れモノ、しかも日本語だ。問題がなければこのまま使っていこうと思う。
- 1997.04.12 1997年4月12日(土)
-
きのう「Microsoft Site Builder Meeting 97」に行ってきた。ホームページ作成ソフトである「FrontPage97」(愛用中)や「Internet Explorer 4.0」の解説があるということで楽しみにしていたのだが、話の1割くらいしか理解できなかった。いわゆるハウツー講座ではなく、ソフトのコンセプトや今後の方向性などの概説が中心。それはそれで良いのだが、聞いたこともない専門用語の洪水(半分は同時通訳)で、私のような個人ユーザーにはレベルが高すぎ場違いな感じだった。1000人以上は集まっていたようだが、みんなどういう人たちなんだろう。
ま、しかし、わからないなりに、ウェブ(ホームページ)がどのように発展し、可能性豊かになっていくか、その雰囲気だけはなんとなく感じることができた。
講義終了後、「Internet Explorer 4.0β1」のCD-ROMをもらえるはずだったのだが、製作がまにあわず郵送になるとのこと。来週にはマイクロソフトのサイトからダウンロードできるようになるそうだし、これじゃ意味がない。それにしても、「Internet Explorer 4.0」はおもしろそうだ。
- 1997.04.08 1997年4月8日(火)
-
2日がかりで、リンク集の大幅拡充を行った。かなりの手間をかけて集めたし、役に立つ情報が得られると思う。活用していただけるとありがたい。事後報告になるが、リンク先に挨拶メールを送らなくては。
- 1997.04.07 1997年4月7日(月)
-
FTP送信ソフトの変更を検討している。今までは「CuteFTP」と「小次郎」を併用していたのだが、両方の機能を備えた「NextFTP」を使ってみようと考えている。「FTP Explorer」も検討したが、変更ファイルだけの自動送信が出来ないようだ。両方ともダウンロードして使い方などを勉強している。いずれにせよ、トラブルなく変更できると良いのだが。
- 1997.04.06 1997年4月6日(日)
-
ある方から、リンク先のページのフレーム内に開いているようだが、そのせいで表示速度が遅くなっているのではないかとの指摘をいただいた。その当否はわからないが、独立したページを自分のフレームの一部に表示すること自体失礼なことではないかと考えるようになった。自分自身がレイアウトに思い入れを込め、苦労したことを考えると、そのバランスを無視されるのはやはり嬉しいことではない。やはりオリジナルの姿で表示するのが礼儀と言えるかもしれない。というわけで、少しずつ、ターゲットを解除して全画面表示に変更することにした。
- 1997.04.03 1997年4月3日(木)
-
春休みもあとわずかになり、きのうあたりから部屋も空いてきた。結局3月は前年比で少しマイナスになってしまった。この先の予約も低調なので頭打ち傾向はしばらく続くかもしれない。
ところで、先日インストールしたOFFICE97だが、新機能にはまったくトライしていない。能力の1割も使っていないようで、使いこなしている実感が味わえない。なんだかもったいない。
- 1997.03.30 1997年3月30日(日)
-
ゴルフに来られたご夫婦がいらっしゃったが、昨夜は久しぶりに本格的な雨になった。しかし、早朝には雨も上がり、すばらしい晴天。良かった。
- 1997.03.28 1997年3月28日(金)
-
去年の夏、設置しておいた巣箱につがいらしき2羽の小鳥が来て、中を覗いたりしていた。スイートホームを探しているというところだろうか。そういう季節なんだ。ぜひ使って欲しい。ここでヒナが育つなんてことになったら素晴らしい。
- 1997.03.26 1997年3月26日(水)
-
珍しく泊りがけで東京へ出掛けていたため、3日ぶりの更新となってしまった。パソコンショップなどで、このホームページにアクセスしてみたところ、ネットスケープの旧いバージョンだと表の背景色を表示してくれない。とすると、予約カレンダーの表示が意味不明になってしまう。本来、旧バージョンでも判別できるような表示にすべきなのだが、合理的な方法を思い付かないので、3.0以上で見ていただくようお願いすることにした。他にも表示が変な箇所があるのだが、ブラウザの特性に対処するのは難しい。
- 1997.03.23 1997年3月23日(日)
-
昨夜遅く、ついに大改装工事を断行。なぜか「小次郎」が途中で止ってしまう。仕方なく「CuteFTP」で送る。ファイル名の大文字小文字に過敏になってエラーになったりしたが、まぁ大事にはいたらなかったようだ。やれやれ。
見やすくなるように工夫したし、内容もかなり増やしたので、来訪者に活用していただけると嬉しいのだが。
ところで、きょうの午後から3日間は東京に行くので更新出来なくなる。この2ケ月の間、受験生のような生活だったから、さすがに疲れた。少しのんびりしてこよう。
- 1997.03.22 1997年3月22日(土)
-
ようやく新規に入れ替えるホームページの中身ができあがった。これからFTPソフトの設定を変更し、サーバーに送り込むが、うまく行くだろうか。すでに開設しているページだけに失敗すると困る。もう一度手順をチェックしてみよう。
- 1997.03.21 1997年3月21日(金)
-
学校の終業式はいつなんだろう。もう3学期は終わったのだろうか。というのも、今夜はウォークインが何組もあり、久しぶりに満室に近い状態になったからだ。
- 1997.03.20 1997年3月20日(木)
-
ホームページ改造作業も大詰め。外部へのリンク設定をおこなっているが、事前承諾が必要かどうかについて迷ってしまう場合がある。「魅せるホームページ実践テクニックガイド(何冊も買ったホームページ作成のための解説書の中でもっともお薦めできる1冊)」には、『企業や団体が、広報や広告の目的で公開しているページは、許可を得ずにリンクしても問題ないでしょう』と書かれているが、判断の難しいケースもある。とりあえず、メールで問い合わせてからにしようと思う。
リンク集ついては、簡単な紹介文を付記したいのだが、ちょっと時間が足りない。スタート時は羅列になってしまい味気ないが、少しずつ書き込んでいこう。何といっても、ホームページの最大の特徴はハイパーリンクにあるのだし、的確で豊富なリンク先の選定が命だ。
- 1997.03.19 1997年3月19日(水)
-
春休みに入ろうとしているのに、相変わらず利用者が少ない。満室になっているのは22日だけだ。鬼怒川温泉の方も去年よりかなり悪いらしい。ちょっと心配。すっかり暖かくなってきて穏やかな天候が続いているし、家族でちょっと旅行すしたり、テニスやゴルフなどにも最適の季節なんだけどなー。
- 1997.03.18 1997年3月18日(火)
-
ホームページの改装作業も9割は終わった。今週の土曜日に一度に入れ替えることにした。文字のデザインをしたり、写真をいじったりして、期待した結果が得られるととても嬉しいのだが、 それ以前のソフトの勉強はカッタルイし、材料をそろえて内容を膨らませていくのはほとんど事務的で単調な作業だ。
- 1997.03.17 1997年3月17日(月)
-
きのうの昼頃のこと。男性ふたりが入ってきて「ここは、芸者とか呼べるの?」って言われた。誤解もここまで距離が開くと爽快だ。
- 1997.03.16 1997年3月16日(日)
-
予定よりだいぶ遅れたが、このホームページの大改造もようやく準備が整ってきた。かなり見やすくなると思うのだが、どうだろう。あともう一息、頑張れ。
- 1997.03.15 1997年3月15日(土)
-
昨夜から久しぶりに雨が降った。3日に1度は花壇に水撒きをしていたのだが、これでしばらくは手間が省ける。きのう、ようやく保管しておいた大量のマリーゴールドの種を蒔き終えたところだが、これで発芽が始まるかもしれない。冬の間、冷たく乾いていた土が、雨に濡れて生命力を蘇らせたようで、注意深く観察すると、あちこちに草が芽吹いている。チューリップもかなり大きくなった。新緑の季節はもうそこまで来ている。1年で一番劇的な変化が始まろうとしている。
- 1997.03.14 1997年3月14日(金)
-
去年紹介記事を載せてくれた「県別マップル栃木」の97年版が出ているようなので本屋に行って見てきた。
やはり記事は掲載されていない。パブリシティなのだから、仕方のないことだが、残念。 営業的には、記事体広告(ペイドパブ)による収入が欠かせないのはわかるし、こうした広告主とのバランスもあるだろう。しかし、マス媒体への広告出稿が難しい小規模な施設を拾い上げるのは、読者にとっても有用なことだと思う。
近隣のおすすめのレストランやレジャー施設の記事も抜けている。 旅行雑誌からもれている情報も多いのだ。まーだからこそ現地での発見があるとも言えるわけだが。
- 1997.03.13 1997年3月13日(木)
-
このホームページを開設してちょうど1ケ月が過ぎた。アクセス数は1000くらい。実質30/日というところだろうか。改造準備に追われていて、こちらの情報の拡充が進んでいない。あと数日で、改装オープンできると思うが、新鮮な情報を流し続けるというのはけっこうたいへんなことだ。
- 1997.03.12 1997年3月12日(水)
-
春休みの予約状況がかんばしくない。一昨年夏のオープン以来、ずっと前年同月比でプラスを続けていたが、今月は初めてマイナスになるかもしれない。去年は1月〜3月にかけていくつかの雑誌に紹介された効果が大きかったから、その反動だろう。平日もビジネス客などで半分近くは埋まっているのに、週末が満室にならない。リピーターは確実に増えているし、悲観的になる必要はないが、客室稼働率が5割を切るようだとつらい。
- 1997.03.11 1997年3月11日(火)
-
今夜初めて「このホームページを見て」というお客様が宿泊されている。こんな日記まで書いているから、なんとなく恥ずかしい。「もうすぐ、大改造しますから、また覗いてください」とお願いしてしまった。
- 1997.03.10 1997年3月10日(月)
-
ホームページの改造作業は、少しずつだが進んでいる。たんにレイアウトやデザインだけ変えるのでは実質的な意味がないので、情報の内容自体を増やそうと考えている。しかし、昨夜遅くまでF1を見ていてすっかり睡眠不足になってしまったので、能率が上がらなかった。
- 1997.03.09 1997年3月9日(日)
-
きのうの火事だが、結局人家などへの被害はなく、一件落着ということになったのだが、別の意味での火消しに神経を使った。というのも、ここでは私はよそ者だし、第一通報者として話しを聞かれている姿を近隣の人が見て、出火元は「旅籠屋」という誤解が延焼しそうな気配を感じたからだ。噂というものも初期消火に失敗したら手がつけられなくなる。幸いこちらの火事は燃え広がらずに消せたようだ。
- 1997.03.08 1997年3月8日(土)
-
今朝、いつものように駅まで従業員を迎えにいこうと駐車場に行ったら、なんと隣接している空き地で子供が火遊びをしていて枯れ草の地面が燃えている。すぐに散水用のホースを伸ばしたが届かない。瞬間的に「消せない」と判断、走ってフロントへ戻り生れて初めて119番通報した。1分くらいかかったのだろう、再び、引き返してみたら、火はさらに奥の薮に燃え移っており、すぐに消火機を使って、手間側の火だけは消したが、奥の方はもう手がつけられない。幸い風も弱く隣家へ燃え移る危険性は少ないが、いつ風向きが変わるかわからない。以前、防火管理責任者の資格講習会で習ったことを思い出し、「火事ですよー」と大声で叫び、届く範囲でこちら側へ続く薮に水を撒き続けた。火はさらに奥の「日光猿軍団」の駐車場へ続く雑木林に移りはじめ、物凄い炎と音をたてながら燃え広がっている。林全体が火に包まれたら大変なことになる。ようやく近所の人も集まり始めたが、何もできない。
10分ほどたったろうか、ようやく数台の消防車が到着、30分ほどの喧騒のうちに火はようやく鎮まった。続く・・・
- 1997.03.07 1997年3月7日(金)
-
好天が続いている。近所の白梅も咲き始めた。去年庭の一角で増えたマリーゴールドから洗面器いっぱいほどの種をとったのだが、これを今年は庭一面に撒いて黄色のじゅうたんのようにしようと考えている。春になり、針金のようだった木々の枝から若葉が「咲き」、乾いた薄茶色の地面が緑に変わっていく。自然からたくさんのエネルギーをもらえるシーズンだ。
- 1997.03.06 1997年3月6日(木)
-
きょうは、とても暖かい。このまま春になってほしい。昨秋、庭一面に植えたパンジーも嬉しそうだ。冬の間、葉を凍らせながらも花を咲かせ続けてくれた。ホームページの方も「FrontPage97」がうまく動くようになって表紙と目次のページが完成した。使えるようになってみると、このソフトは凄い!
- 1997.03.05 1997年3月5日(水)
-
グラフィック処理とデジタルカメラによる画像処理、2週間かかってようやく基本的なことができるようになった。残るはホームページ作成管理ソフトである「FrontPage97」。自分のパソコンの中にローカルのウェブサイトを作って作業するのだが、この手続きでひっかかっている。
- 1997.03.04 1997年3月4日(火)
-
朝は-3度とまだ寒いが、昼間はポカポカ陽気。やわらかな日差しはもう春だ、と感じたところで思い立ち先日購入したデジタルカメラに初挑戦。パシャパシャと外観を撮影し、パソコンにつなぐ。思ったよりずっときれい。それに付属ソフトである「Adobe Photo Deluxe」が素晴らしい。マニュアルが付いてなかったので不親切だと思ったが、ヘルブがとてもわかりやすく出来ていてこれだけで簡単に補正や加工ができる。サクサク動く。ここんとこソフトの難解さに悩まされ続けているのでとても嬉しい。兄弟ソフトのPhotoShopもこれくらい分かりやすかったら良いのに。これは推薦できるソフトだ!2~3時間楽しく作業して、改造ページに載せる外観写真が出来上がった。
- 1997.03.03 1997年3月3日(月)
-
ついに、グラフィック処理ソフトの使い方がのみこめてきた。昨夜は2時頃までかかって、ようやく新しい表紙デザインの一部が完成した。嬉しい。これで本格的に作業に入れる。
- 1997.03.02 1997年3月2日(日)
-
早朝から深夜までソフトと格闘している。まるで受験生のようだ。Photoshopは体験版なので中途半端な作業になる不安があり、同じく参考書の付属CD-ROMに完全版が入っていた HappyPaint を使うことにする。基本的な内容はとても似ているようだ。江戸時代の日本人が断片的な辞書だけを便りにオランダ語の技術書を読もうとしているような感じ。でも、少しずつわかってきた気がする。
- 1997.03.01 1997年3月1日(土)
-
きょうはウォークインもなく、結局ご利用はわずか4室。土曜日としてはきわめて異例、1年以上もなかったことだ。先週は何組もお断りしたのに・・・。こんな日に初めて宿泊された方は「なんてはやらないホテルなんだ」と思われるかもしれない。
- 1997.02.28 1997年2月28日(金)
-
きょうで2月も終わり。仕事で平日に連泊された方が多く、客室稼働率は昨年を大幅に上回り5割を超えた。ひとりで1室という利用が多いため、室料売上は200万円くらい。でもこのオフシーズンにこれだけ利用していただけるのはありがたい。しかし、今夜は1室のみ。9ケ月ぶりにゼロ日になるところだった。あしたも土曜だというのに、半分も埋まっていない。週末に空室があるの珍しい。どうしたのだろう。
- 1997.02.27 1997年2月27日(木)
-
きょうは風もなく、暖かく穏やかな日和だった。客室の清掃を終え、庭のベンチでマニュアルを読んだ。のどかな情景か想像されるかもしれないが、じつは何回読んでも理解できず煮詰まってしまっている。MSのサポートセンターに電話し、1時間以上あれこれ試行錯誤してみたがうまくいかない。あー空しく時間が流れていく。
- 1997.02.26 1997年2月26日(水)
-
原画の画像データが届いたので、 ロゴと交通案内図を交換。周辺案内のマップを追加した。いっぽう大改造に向け、ホームページ作成ソフトであるMSのFrontPage97のマニュアルと格闘している。今までは、Wordユーザーに無償配布されるInternet Assistant for Word を使っていたのだが、格段にいろいろなことが出来るようだ。そのかわり難解で苦しんでいる。
- 1997.02.25 1997年2月25日(火)
-
見栄えの良いグラフィック処理をしようとすると、やはり「Photoshop」が定番らしい。買うと高いし、手軽に似たようなことができる方法はないのかと思っていたら、なんと本の付属CD-ROMに体験版が入っていた。やったぜ! でも、これでまたもうひとつの苦行が始まる。自力でホームページを作ろうというのはたいへんだ。趣味と言えば楽しそうではあるが。
- 1997.02.24 1997年2月24日(月)
-
パンフレット用に作ってもらったマップなどの画像データが届いた。もともとマックで作ったデータなので、BMP形式に変換してもらったのだが、GixでもGVでもPaintshopでも読み出せない。うーん、パソコンってどうしてこう思いどおりにならないのか。
- 1997.02.23 1997年2月23日(日)
-
きのう秋葉原で増設メモリー(計96MBになった)とデジカメ(オリンパスのC-800L、81万画素!)を買った。これで不満だらけのホームページの改造に取り掛かれるが、ホームページ作成ソフトのマニュアルは200頁以上あるし、デジカメもパソコンとの接続キットを買い忘れている。焦るな、落ち着け!
- 1997.02.22 1997年2月22日(土)
-
朝起きたら、まだ雪が降り続いていた。ここから先に行くのならチェーンが必要だが、数キロ南に下がると雪はほとんど降っていない。日本海側と太平洋側のちょうど境目なのだ。それにしても車での東京往復は疲れる。
- 1997.02.21 1997年2月21日(金)
-
夕方から雪が降り始めた。気温も下がっているので、サラサラのパウダースノーだ。あすは車で東京に行く予定なので積もらなければよいのだが。
- 1997.02.20 1997年2月20日(木)
-
久しぶりにバイクで宇都宮まで出掛けた。TLRだが、何年も乗ってなかったので、サスが前後ともダメになってる。オイルがもれている。ただでさえ悪い乗り心地が尚更だった。宇都宮で、パソコンショップをまわり、ちゃんとしたホームページ作成ソフトと参考書を買い込んできた。 あさっては秋葉原に行って、ついにデジカメを買うつもり。
- 1997.02.19 1997年2月19日(水)
-
各種のカタログページ(検索エンジン)と懸賞ガイドページへの登録を済ませた。今月からテレホーダイに申込んではいるが、仕事柄あまり夜更かしも出来ず、昼間のアクセスも多い。今月は毎日3~4時間つなぎっぱなしという日も多いから来月の請求が恐ろしい。カウンターを見ると150くらいになっているが具体的な反応がないので、なんとなく頼りない。
- 1997.02.18 1997年2月18日(火)
-
オープンしてまだ4日というのに、不満がつのってきた。フレームの使い方や画像処理についてのアドバイスももらった。全面的に構成を変えてみようと思う。それにしても、プレゼントクイズの応募も予約申込みもまだゼロ。いくつかのカタログページに登録したが、もっともっとたくさんの人の目にふれるようにならなければ意味が無い。どうしたら良いのだろう。
- 1997.02.17 1997年2月17日(月)
-
お願いしてあった画像ファイルの入ったフロッピーが届いた。パンフレットの写真をスキャンしていただいたものだ。これで、工事中だった部分が作れる。ホームページ全体のデータ量は予想外に小さくてまだ500Kに満たない。10枚くらいの画像を追加しても何の心配も無い。
- 1997.02.16 1997年2月16日(日)
-
2人の方から、ホームページにメッセージをいただいた。さっそく返信を送ろうとしたのだが、 どこかで設定が変わってしまったのか「プロファイルの作成」という画面が出てくる。何のことやらさっぱりわからない。あーまた雑誌や本をひっくり返して勉強か〜、とウンザリする。一難去ってまた一難。パソコンは便利だけど、延々とこの繰り返し。もう少し流れがゆっくりになって欲しいと切実に思う。
- 1997.02.15 1997年2月15日(土)
-
とりあえず、ホームページがオープンし、ごく一部の人にだけ伝えた。カウンターは20を越えているが、そのほとんどは自分。プレゼントや予約の申込みもまだない。そろそろあちこちのカタログページに登録する予定。それにしても、一応出来上がってみるとフレーム機能の使い勝手やフロントページの印象など、気になる所がたくさんある。毎日少しずつ改良していこう。オープンしたからには情報は毎日更新していくつもりだ。
- 1997.02.14 1997年2月14日(金)
-
昨夜、内容をサーバーに転送してみたが、やっぱりてこづった。どうしてもカウンターと送信フォームが動かない。朝を待ち、何度もプロバイダーに電話をしてようやく解決。今までIEでしか見ていなかったので、念のためと思いネットスケープをダウンロードしてみたら、字の大きさが違う。読みにくい。仕方なく全面的に修正。やれやれ。でも人知れずオープンにはこぎつけた。
- 1997.02.13 1997年2月13日(木)
-
こホームページの中身がだいたい出来上がった。画像が間に合わなくて工事中の部分もあるが、とりあえずこれでスタートしてみようと思う。
2週間前まではまったくの素人だった人間が独力で作ったわりにはマァマァの出来ではないかと自己満足。たくさんの人に見て欲しいし、「旅籠屋」のことを知って欲しいから、いかにもではあるが、プレゼントクイズを載せてみた。
それにしても、ホームページづくりにかまけてパソコン通信のパティオにご無沙汰してしまっている。情報交換は継続することが大切なのに、これではイケナイとわかっているのだが、この2週間は余裕がなさすぎた。さぁ、うまくサーバーに送り込めるだろうか。
- 1997.02.12 1997年2月12日(水)
-
難解だった送信フォームを一日かけて作った。プロバイダで用意してくれているCGIを使うと、メールではなく、専用のファイルに受信内容がまとめられるらしい。ちょっとピンとこないが、とにかくやってみよう。まだ、ホームページの内容をサーバーに送って実際にアクセスして見ていないので不安。
- 1997.02.11 1997年2月11日(火)
-
鬼怒川の観光協会がホームページを開くそうで、その説明会のご案内があった。「インターネットって聞いたことあるでしょ?」だって。
予断は禁物だが、ただ会員旅館の名前を並べるだけだったら無駄な投資だと思う。形だけ真似る前に、インターネットがどういうものかを肌で感じとり、インターネットならではの活用法を検討して欲しい。それを省いて専門業者に原稿だけ渡すようなやり方なら情報発信なんてできっこない。
- 1997.02.10 1997年2月10日(月)
-
この連休、久しぶりに満室の日が続いた。でも、明日は祭日なのに、なぜか今夜は空室がある。こういう情報を伝えるのが、ホームページを開く目的のひとつだ。夏休みなどに満室でお断わりしたお客さんからは、どうせ休みの前日はダメだろう、と敬遠されているみたいなのだ。
- 1997.02.09 1997年2月9日(日)
-
ホームページ作成に取り組み始めて10日が過ぎた。
客室の掃除や買い物などを除き、朝から夜までかかりっきりだ。参考書や雑誌を見ながらの素人作業なので最初はとにかくたいへんだった。でも、難問だったフレームづくりの要領も飲み込めてきて少しずつ形が見えてきた。
- 1997.02.08 1997年2月8日(土)
-
11月下旬に紅葉狩りのシーズンが終わると、年末年始を除き春休みが始まるまでは1年で一番お客さんの少ないシーズン。
今年は雪が遅かったせいか、1月はスキー客も少なかった。だからこの機会を利用してホームページづくりにとりかかったわけだが、2月に入って、仕事でお泊まりの方が増えてきた。こういう平日の利用はほんとうにありがたい。
空室照会・宿泊予約
- 宿泊店舗
- チェックイン
- チェックアウト
- 宿泊人数


